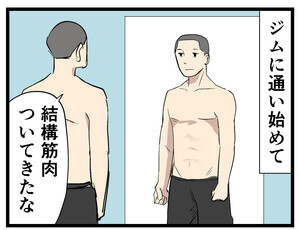9月のはじめ、経団連会長の中西宏明氏が「2020年度以降に就活ルールを廃止する」とコメントしたことが話題となった。この発言が社会にどのような影響をもたらすこととなるのか。大学にてキャリア教育および支援を担当する教員として、今回の出来事に関しての見解を述べたい。
ルールを守ると「優秀な人材」を採れない実情
そもそも、同氏がこのような発言をした背景には、「就活のルールを守った企業が損をする」という現状への危機感、および、経団連に所属している企業であっても「こっそりと就活ルールを破っていた」現状への罪悪感があったと考える。
もっとも、我々大学サイドとしても、これだけインターンシップ採用やリクルーター採用、つまり「リファラル採用」が一般化しているのに、○月より情報解禁、△月より試験・面接開始……といった就活ルールに基づき、学生の就職支援をするのは実情に合っていない、ということは身をもって感じている。
ではなぜ、現行の就活ルールのままではいけないのか? その理由の1つとして、就活ルールが、「優秀な人材」の輩出を阻害している点が挙げられる。
新卒の人材について、ここでは「優秀な人材」と「普通の人材」という2つのパターンに分けて考えたい。優秀、普通の定義については、仮に前者を"イノベーションを起こせるような人材"、後者を"従来の仕事(イノベーションというよりは、これまで多くの企業がやってきたような仕事)ができる人材"としよう。
一方、採用をする側をおおまかに「人気ベンチャー」「大企業」「中小企業」と分類し、それぞれの関係性をざっくりと図式化すると、以下のようになる。

この図で示す通り、就職活動(採用活動)には大雑把に2つの道があって、志望する企業によって就活は変わるし、採用する企業によって採用活動も変わる。それにも関わらず、かたくなに1つのルールのみで縛っていこうとすると、就活生、採用活動を行う企業のどちらにも不利益が生まれることは明らかだ。
変化が求められるナビサイト
今回の発言を受けて気になるのは、リクルートやマイナビ、キャリタスなどの就職情報サイトが、いつ会社説明会情報を解禁にするのか、ということだ。もし同社らがビジネスモデルを堅持するようであれば、ざっくりと「3年生の授業が終わる時期に合説がスタートし、4年生の春から面接・内々定」の流れは数年続くかもしれない。
しかしながら、それは会社の事情であって、学生には関係の無い話だ。例えばインターンシップを1・2年生でも体験できるのであれば、就職情報サイトを年度別に設計するのはすでに実情に合っていない。それぞれのサイトに一度登録すれば、4年間、キャリアに関する情報を収集できるようにするべきだろう。ひいては中途採用の就職情報サイトと統合すべきだ。
世界に遅れる日本、キャリア教育のアップデートを
こういう話をすると「インターンシップなどのキャリア形成のための活動が学業に影響を与えるのはおかしい」という議論があるが、それは間違っているように思う。
仮に欧米の大学生のように、長期休暇などに興味がある企業でインターンシップで働いて、納得できる採用先を早期に確保した方が、かえって卒論などに影響を与えない可能性があるためだ。
もちろん、欧米の場合、専門職採用が主体で学びと就職が一貫していること、長期休暇が取りやすいカリキュラムになっていて、有償のインターンシップを紹介してもらえるなど、日本とは状況が違うので、すぐには無理だろう。しかし、日本だけ異質なままではグローバルな視点からは取り残されてしまうこととなる。
今、大学側に求められるのは、年次に縛られず、自ら行動し、試行錯誤しながら、自らのキャリアを紡ぎだせる学生を育てることだろう。
中西氏の発言が今後、企業の採用活動、および学生の就活にどのような影響をもたらすかは断言できない。しかしこの出来事は、就職活動に歪みが出てきていることを示す顕著な例であることは確かだ。大学側には、これまで提供してきたキャリア教育の見直しの時期が強く求められている。
(見舘好隆)