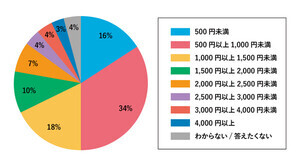「断捨離」を家計のやりくりに応用する
クラター(がらくた)コンサルタントのやましたひでこさんが提唱する、新しい片づけ法「断捨離」が話題を集めています。
一般に、片づけ法というと、たとえば、細かいモノは箱やカゴを使って小分けするとゴチャつかないとか、突っ張り棚やコの字ラックを使うと空間をムダなく使えて、収納スペースが増えるなど、「モノありき」の考え方が主流です。今、家にあるたくさんのモノたちをいかに使い勝手よく、さらに見た目よく収めるかに主眼が置かれています。
「断捨離」の片付け法は、こういった収納法や片づけテクとは、明らかに一線を画します。片づけを思い立って、まず一番にすべきことは、今あるモノの要・不要を見極め、必要なモノだけを残して、不要なモノを減らすこと。モノが少なくなれば、ややこしい収納や面倒な片づけから解放されるという発想です。つまり、「断捨離」すれば、片づけがラクチンになるというわけです。
「断捨離」やりくりでお金を使う生活とサヨナラする
この発想を家計のやりくりに当てはめたら、どうなるでしょうか? 「モノ=お金を使うこと、お金を使う機会」と考えます。
断:家の中に入ってくる不要なモノを断つ。
→必要のない出費を断つ。
どうしても欲しいわけでも、必要でもないモノを買う、安いからという理由で買う、退屈しのぎにネットショップ・サイトを開く、コンビ二、ドラッグストア、乗り換え途中の駅なかショップにフラリと寄る、あまり気がすすまないけど"付き合い"なのでご飯に行く……を止めます。
捨:不要なモノを捨てる。
→買ったのはいいけれど、使っていないモノ、この先も使わないモノを捨てる。
クロゼット、タンス、押入れ、靴箱、冷蔵庫の中、冷蔵庫の上、食器棚の中、食器棚の上、シンクの収納棚、テレビ台のラック、固定電話のまわりなどをチェックして、不要なモノ=ムダ使いの証拠を捨てます。捨てるときの「もったいない」「お金をムダにしてしまった」という罪悪感を体験することで、次から余計なモノを買うブレーキになります。
離:モノへの執着から離れる。
→お金を使う生活から離れ、モノを買わずに済ませるにはどうしたらいいかを考える。
手作りできるモノは作ってみる。ないモノは他のモノで代用してみる。なくても、なんとかならないか工夫してみるなど。
「無買デー」=買わない日を作る。「今日は、財布を開かない」と決め、まる1日お金を使わないようにします。通勤は定期券があれば、お財布を開くことはありません。ランチは手作り弁当にします。ペットボトル飲料は買わずに、水筒や空ボトルに水やお茶を入れて持参。仕事が終わったら、まっすぐ帰宅。目的なくコンビ二に寄るのはNG。帰宅後は、冷蔵庫の在庫整理のつもりであるモノで夕飯を作ります。
以上のような「断捨離」やりくりで、お金を使うこと自体を減らしていきます。お金を使わなければ、面倒な家計簿をつける必要もなく、家計管理がずっとラクになります。さらに、あれも欲しいし、これも買いたい……どっちにしよう?と迷うことも、給料日前のお金がないストレスからも解放されるはず。
お金を使わない生活のスッキリ感を体験する
「断捨離」の著者は、「『断捨離』の目的は、モノと自分との関係を見直すことにある」と述べています。「家の中が片づかないのは、やる気がないわけでも、片づけ方が下手なわけでもなく、自分にとって必要なモノと不要なモノを見極める感性が鈍っていることにある」と。「断捨離」でモノと自分との関係を見直すことで、その感性を取り戻すことができるというわけです。
同じように、やりくりに「断捨離」を実行すれば、自分のお金の使い方を見直すことになります。自分にとってお金を使う本当に価値のあることやモノが見極められれば、不要な出費は自然と減るはず。
また、お金を使うことは、判断を要することでもあります。買うか買わないか、どっちを選ぶか、いくらまでの出費なら許されるのか、今お金を使ったら今月の生活はどうなるのか……など。お金を使うたびに、こういった判断を強いられることは、知らず知らずのうちにストレスになっていることも。お金を使わないと決めれば、使うことに伴うストレスから解放されます。
さらに、お金を使う機会が減れば、ズルズルとお金を使っていたときよりも、はるかにお金を使うことを意識するようになるはず。そうなれば、本当に必要なことやモノにお金を使う=ムダ使いがなくなります。今まで買ってすませていたとこが、買わずになんとかなった。買わなくても、意外とへっちゃらな自分を発見したり。
家の中に不要なモノがない生活がスッキリ快適なように、ムダ使いのない生活も清々しいもの。「断捨離」やりくりは、試してみる」価値がありそうです。