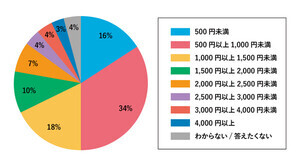先週は、どんなよい材料があっても、リスク回避の地合いにはわずかな時間の希望だけであっさりと逆戻りの展開となってしまいましたが、今週は山盛りの経済指標と金融政策イベントがあることから、ボラティリティーが上昇しやすい地合いになると思います。
まずは、今回のリスク最大要因を見ていきましょう。

|
HS株価指数チャート |
一つ目は、メディアでもどうにか話題になってきたギリシャのソブリンリスク(とはいっても市場関連で、一般メディアではアメリカの話題は多く取り上げるのになかなか取り上げられないのが現状)。中国やフランスなどの支援の憶測が出るも、メディアの先走りの記事の中での話。市場ではECBが最終的なサポート役として出てくるという見方がありますが、はたしてどうでしょうか。
もちろん、ユーロの崩壊という可能性はECB / EUとしても死守するはずですが、ポイントしてはギリシャ国民及び政府当局者などの意識の問題。ユーロの規律(まだ特別な流動性措置及び財政緩和が継続されますが)に戻すためには、それ相応の自己規律が必要になりますが、タガが外れたような今回の状態では決断しなくてはなりません。
ユーロ参加国という大きなメリットを失えば、税制・貿易などあらゆる面で弊害が出てきますし、これまでの恩恵はすべてなくなります。かなりギリシャ国内においても厳しい措置がなされるのではないかと思いますが、当のギリシャ国民からは警戒感している話題すら聞こえてきません。
ギリシャ国民の決断を待つわけにはいきませんし、市場参加者にとっては、リスクは回避しなくてはなりませんので、ユーロ圏内でも安全(比較的)といわれるドイツ及びフランス国債の方の資金が流れていきます。国債利回り格差も4%近くにまで上昇しており、金利面では魅力的かもしれませんが、その分のリスクは大きくCDS市場でも上昇。魅力的と感じている市場関係者も、まだ少数派です。この展開はギリシャだけではなく、他の南欧諸国においても同様な展開になっており、ECBとしてもかじ取りが難しくなってくるでしょう。
その意味では、今週のECB理事会において当然議題に上るでしょうし、記者会見でもトリシェECB総裁だけではなく、パパデモス副総裁(ギリシャ出身)にも質問が来るかもしれませんね。どのようなスタンスを示してくるのかに注目しておきたいですが、速報には注意しておきましょう。
そして、二つ目は中国とインドの引き締めスタンス。中国の話題はもうすでに日本企業でも影響が出てきているようですが、インドも引き締め気味に移行したことで、資源需要の後退観測が出ています。中国の2009年度GDPがかなり高かったことで、2010年夏には政策金利引き上げの可能性があるのではないかと市場では話題になっています。
インドも内需の伸びが高くなっていることから追随する可能性は高いでしょう。ただ、好景気というよりバブル的な面を抑制する意味での中国の指導によって、バブルに乗って走ってきた資源・エネルギー分野の調整が、今回の引き締めリスクのポイント。自然な需要と供給という流れであればよいのですが、ファンド筋などの投機筋の流入+過剰流動性が押し上げてきたことも背景にありますので、市場のポジションは偏っていたはず。
また、まだ内容が固まっていないとはいえ、オバマ大統領の金融機関へ規制、市場ではボルカールールと呼んでいますが、さらにポジション圧縮を後押しすることになりました。
こういった中、政治的な警戒感の影響も考えなくてはならないかも。
それはアメリカと中国、そして欧州。グーグルの中国事業撤退の可能性を示したことで、米政府側は懸念表明として同調しましたが、それ以外にアメリカの台湾に対する武器売却への反応。中国側としても意見はあると思いますが、中国側としても軍備増強をさらに進めている事実を考慮すれば、台湾側としても警戒するでしょう。もちろん、アメリカや欧州としても警戒を示しており、欧米企業のさらなる撤退の可能性が出てくるとなると、外資の資本だけではなく、ノウハウを吸収したい中国側としてどれだけ強行に出てくるかどうかで、アジアリスクという点が出てくるかもしれません。
また、以前からオバマ大統領のスタンスに対して、欧州側も不均衡是正という点で同調しており、これらの政治的な発言にも留意しておかなくてはならないかもしれません。一般教書演説において今後5年間輸出を倍増させるという意気込みは、輸出にかなり依存している国々に対してのメッセージとも受け止められます。どの程度経済政策に反映されるかは不透明ですが、中国がかたくな姿勢をとればとるほど、別の意味でリスク回避地合いが強くなるかもしれません。

|
EURチャート |
今週はこれらのリスク回避的な地合いの中、各国中央銀行イベント(オーストラリア、イギリス、ユーロ)に加え、先週金曜日に久しぶりの明るい材料となった米経済指標が今週もみられるのかどうか。RBAにおいては政策金利引き上げの可能性が高いものの、100%織り込まれていない状態。さらに、木曜日のECB理事会までは多少の期待感から買い戻しが入りやすいかもしれませんが、財政規律を重んじるECBの立場が確認されれば、再度リスク回避のクロス円売り・ユーロ売りの展開が再燃するかと思います。よって日々展開が変化しやすい(振幅しやすい)地合いになると思います。
また、オバマ大統領が一般教書演説で雇用に関してメッセージを出したものの、はたして金曜日の毎月の一大イベントである米雇用統計やそれ以前のいくつかの雇用関連指数で改善の基調を示してくれるかどうかが注目されます。
欧州時間やNY時間においてはこのように盛りだくさんのイベントがありますが、アジア時間ではどうでしょうか? 日本の株式市場は海外時間の流れを受けやすいのですが、気になるのはやはり中国の株式市場。新たに金融機関に対して窓口指導を行うのかどうかが市場では気になっているようです。
この場合には、市場のリスク回避に対してアジア通貨へのリスクという点で、円の立場はかなり微妙。ドルにおいては消去法的な(いわゆる不美人投票で比較的良い)買い戻しがある半面、人民元に対するスタンスであればドル安容認(黙認? )圧力になるかも知れず、金利面でも今週のイベント次第では上下動しやすく、ドルと円の双方の材料で板挟み状態になると思われます。
よって、あえて方向性を求めるのであれば、対ドルの動きで、ユーロ、AUDの方が取引しやすいかもしれません。米経済指標の内容とも合わせて、どの程度までの回復を見せるかどうか、先週までの下落幅で見た調整ポイントを把握しておいた方がよいかもしれません。
ちなみに、小沢幹事長の話題+日本の政局の影響に関しては、それほど市場の話題にあまりなっていないというよりも他のイベントへの注目度が高いので、あえて材料視することは避けたほうがよいかもしれません。

|
|
ドル円チャート |
今週の主なイベント
| 2月1日(月) |
| (NZ)休日 |
| (豪) 第4四半期住宅価格指数(前期比/前年比) |
| (欧-仏) 12月生産者物価指数(前月比/前年比) |
| (欧-仏) 1月 (確定値)PMI製造業 |
| (欧-独) 1月 (確定値)PMI製造業 |
| (欧) 1月 (確定値)PMI製造業 |
| (英) 12月消費者信用残高 |
| (英) 12月 (確定値)マネーサプライM4(前月比/前年比) |
| (英) 1月PMI製造業 |
| (米) 12月個人所得 |
| (米) 12月個人支出 |
| (米) 12月PCEデフレータ(前年比) |
| (米) 1月ISM製造業景況指数 |
| (米) 12月建設支出(前月比) |
| 2月2日(火) |
| (豪)RBAキャッシュターゲット(政策金利) |
| (欧)12月ユーロ圏 生産者物価指数(前月比/前年比) |
| (米)12月中古住宅販売 |
| 2月3日(水) |
| (英)1月ネーションワイド消費者信頼感 |
| (豪)12月貿易収支 |
| (欧-仏)1月 (確定値]PMIサービス業 |
| (欧-独)1月 (確定値]PMIサービス業 |
| (欧)1月 (確定値]PMIサービス業 |
| (英)1月PMIサービス業 |
| (欧)12月ユーロ圏 小売売上高(前月比/前年比) |
| (米)MBA住宅ローン申請指数 |
| (米)1月チャレンジャー人員削減数(前年比) |
| (米)1月ISM非製造業景況指数(総合) |
| 2月4日(木) |
| (NZ)第4四半期失業率 |
| (豪)12月住宅建設許可件数(前月比/前年比) |
| (欧-独)12月製造業受注(前月比-季調済/前年比-季調前) |
| (英)BOE 政策金利発表 |
| (欧)欧州中央銀行 政策金利発表 |
| (欧]トリシェECB総裁記者会見 |
| (加)12月住宅建設許可(前月比) |
| (米)第4四半期非農業部門労働生産性 (速報値) |
| (米)新規失業保険件数 |
| (加)1月Ivey購買部協会指数 |
| (米)12月製造業受注指数 |
| 2月5日(金) |
| (英)1月生産者物価指数(コア/季調前/前年比) |
| (欧-独)12月鉱工業生産(前月比/季調済) |
| (加)1月失業率 |
| (米)1月非農業部門雇用者数変化 |
| (米)1月失業率 |