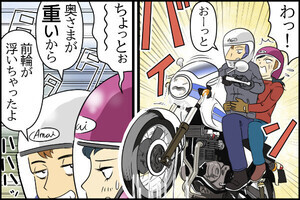スバルブース最大の注目車はSUBARU HYBRID TOURER CONCEPT(スバル ハイブリッド ツアラー コンセプト)

|

|
ガルウイングドアはスタイリッシュで注目度は高いが、コンセプトモデルのためのもので実現性は少ないだろう |
可動するのはメーターだけではない。インパネやコンソール、ペダル類が動いてドライビングポジションを合わせてくれる |
まさかスバルがまたもハイブリッドカーのコンセプトを出してくるとは思わなかった。過去にもハイブリッドカーのコンセプトモデルを発表していたが、トヨタと協力関係を構築した現在、独自開発のハイブリッドカーを出すとは考えていなかった。ハイブリッドを得意とするトヨタと協力関係にあるのだから、トヨタのFRベースのユニットを流用させてもらえばコストも開発期間も短縮できるはずだ。だが技術集団のスバルはそれを許さなかった。レガシィやエクシーガに採用したCVTを見ればそれも納得できる。コスト低減のためにミッションを外部から買ってくるというのは技術者魂が許さなかった。ハイブリッドも同様で、トヨタから調達するという考えはなかったのだろう。あくまで独自開発にこだわったわけだ。

|

|
ツアラーというネーミングからもわかるようにすばるらしいワゴンのハイブリッドカー。スポーティなスタイリングが印象的だ。レガシィは新型が登場したばかりだが、次世代はこのテイストがどこかに取り入れられるかも |
ユニークなのはドライバーに最適な運転環境を提供するというシステム。なんと走行状況や速度に合わせてディスプレイパネルが上下することで、ドライバーをサポートする |
ハイブリッドコンセプトモデル「スバル ハイブリッド ツアラー コンセプト」は走りのスバルのDNAを継承している。スバルは伝統のシンメトリカルAWDをハイブリッドカーでも守りとおすようで、フロントとリヤに駆動用モーターを配置した2モーターアシストを採用している。いわゆるシリーズ・パラレル式のハイブリッドで、EV走行であるモーター走行もできるしエンジンとモーターアシストで強力な加速性能も実現可能だ。フロントモーター・ジェネレーター(発電機)は、エンジンとミッションの間に置かれるタイプ。エンジンをクラッチで切り離せば、モーター駆動はもちろん、回生時もエンジンのフリクションロスをなくせるため、回生効率が高い。さらにスバルのシステムはリヤにモーターを配置。デフの直前に1つ付けられたモーターは駆動用として使われる。
2モーターのメリットはズバリ、前後駆動配分のコントロールだ。前後モーターの駆動配分を変えることで旋回性能を高めたり、姿勢を安定化させることも可能だ。もちろんエンジン車でも同様のことはすでに行われているが、モーターはクイックかつ制御が極めて正確。モーターだけの制御だけではなく、エンジンの動力をメインにしているときでもモーターアシストの配分を変化させることで、さまざまな制御が可能なはずだ。現段階ではコンセプトモデルということなので、エンジンとモーターを断続させるクラッチ位置などは公表されていない。このクラッチの位置と制御がEV走行や走行フィールを左右するポイント。スバルは現在研究を進めていて、既存のシステムとは違うものを追求するという。
燃費向上がハイブリッドのメインテーマの1つだが、ハイブリッドシステムだけで燃費を向上させているわけではない。注目はエンジンだ。スバルは新型レガシィの国内モデルを2.5L以上の排気量に格上げしたが、燃費向上には排気量のダウンサイジングが必要。新型レガシィでも欧州仕様は従来の2Lが残されている。国内でも2L待望論は根強いものがあるが、それに応えられそうなのがこのコンセプトモデルのエンジン。エンジンはもちろん水平対向4気筒の2L。それをターボ化して燃費向上と排ガスのクリーン化のために直噴化している。欧州車の例を見てもわかるようにターボ直噴は、エミッションとパワーを両立する。さらにミッションは新型レガシィから採用されたリニアトロニックCVTを組み合わせている。ハイブリッドカーのコンセプトとはいうものの、ハイブリッドシステムを外せば2L直噴ターボとしてリリースできるシステムといえる。もちろんハイブリッドシステムも将来の実用化を十分に期待できる。
ビームスとのコラボモデルが登場 - Plug-in STELLA feat.BEAMS(プラグイン ステラ フィーチャリング ビームス)
すでにインプレッサではビームスとのコラボは行われている。そこでEVであるプラグインステラにもセレクトショップとして有名なビームスの力を借りて、幅広い世代にアピールしようというねらいだ。とくに環境に優しいプラグ インステラとビームスがコラボすることで、若い世代のユーザーにEVを身近に感じてもらいたいわけだ。コラボはメカニカル面ではなく、ボディサイドとルーフ、ボンネットなどに施されたペイントなどのビジュアル面をビームスが担当。四つ葉のクローバと化学記号を組み合わせたデザインは、特別なメッセージが込められている。それはEVのような環境技術が「平和で楽しく暮らせる世の中への想い」につながることをイメージしているという。走行時にまったく排気ガスを出さないゼロエミッションのEVを、なんとか普及させたいという願いが込められている。ホイールをグリーンにペイントしているのは、さわやかな草原をイメージしたものだという。鳩山首相は二酸化炭素の削減25%を国際社会に約束したが、こうしたすでに商品化されているゼロエミッション車を広く普及させなければ25%の目標を達成することは難しいだろう。
なんとスバル製M3の登場!? - IMPREZA WRX STI CARBON(インプレッサ WRX STI カーボン)
こういうモデルが登場するからモーターショーは楽しい。何もコンセプトカーや未来のモデルばかりがモーターショーの華ではない。近い将来登場しそうなモデルをいち早く見られるのもショーのだいご味だ。それらのモデルが登場するようにと、メーカーに熱いラブコールを送れば市販化されることもある。それはメーカーがモーターショーを重要なマーケットリサーチの現場としてとらえているからだ。そうしたラブコールを送りたくなるのが、インプレッサ WRX STI カーボン。インプレッサWRX STIのエボリューションモデルと呼びたくなる。ネーミングからもわかるようにルーフにカーボンを使う贅沢なモデルなのだ。カーボンルーフと聞いてすぐに思いだすのは、やはりBMW M3だろう。スバルもM3と同様にルーフをカーボンによって軽量化することで運動性能向上を狙っている。
もちろんルーフ部分のカーボンはリアルカーボン。ルーフはカーボン化で4kgの軽量化だが、重心から高いところの軽量化だけに走行性能には大きな効果がある。スバルによると重心点を3mm下げることに成功しているという。ここまでやるモデルは、さぞかしスパルタンなクルマと想像するが、じつはWRX STI Aラインがベース車。2ペダルのAT車であるWRX STI Aラインは2.5Lターボエンジンで、気軽にスポーツ走行ができる。はっきり言ってWRX STIより軟派なクルマだ。せっかく高価なカーボン化をしているのにベース車にMTではなくAラインを選んだのか疑問の人も多いと思う。スバルの説明ではAラインの販売が好調なため、多くのユーザーが見込めるグレードに採用したのだという。もっともこれは市販が決まったわけではないので、MTとATの両方にカーボンルーフを設定する可能性もあるわけだ。限界性能を向上させるカーボンルーフだけに、走りを極めるWRX STIに採用してもらいたいと思う人は、スバルブースに足を運んでMTにもカーボンルーフを設定してほしいとお願いしよう。ユーザーが直接メーカーに意見を伝えられるのもモーターショーのいいところだ。