☆国家公務員試験の難易度を職種別で知りたい!
☆国家公務員試験の内容や合格ラインが知りたい!
☆国家公務員の年収ってどのくらい?
私たちの暮らしを支えて、更に豊かにするため毎日働いている国家公務員は、「収入が安定している」「生涯安泰」「信頼性があってローンも通りやすい」等の高評価を耳にする機会が頻繁にあります。
そのため、国家公務員を目指したいと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし国家公務員は職種が豊富で、試験が非常に難関ともいわれています。
本記事では以下4つの内容を紹介します。
また、当サイトでは国家公務員の通信講座について紹介している記事も公開しています。
国家公務員という資格について興味のある方はぜひこちらの記事もご覧ください。
国家公務員とは?
ここでは、そもそも国家公務員とはどのような資格なのか?という疑問を解消していきます。
国家公務員という資格の概要
国家公務員とは数ある公務員の職種のうち「国家機関や行政執行法人」等に勤務する方々で、公務員を大きく分けると、今回紹介している「国家公務員」と「地方公務員」の2つが皆さんもよく知っている公務員の職種となります。
この国家公務員と地方公務員の違いを簡単に説明すると、以下のようなイメージです。
国家公務員は誰かの指示で動くというよりは、自分で未来予想図を描いて動いていくイメージで、あくまで企画を立案し提案する役目です。
裏で企画や政策を支えて実行しようと動いている公務員が地方公務員となります。
国家公務員のメリット・デメリット
国家公務員を含む公務員のメリットは、以下のようなものが代表的です。
それに対し、公務員のデメリットは以下が代表的となります。
給与に関しては昇級すればアップしますが、基本的に何か成果を挙げたからと言ってすぐに給与に反映されるわけではないでしょう。
また仕事内容も国家一般職等の職種は決められた仕事をこなすのみで、国家総合職のように自分で全てを考え、提案して動く機会はないため自由度が低いと言えます。
加えてどの公務員も激務となっており、特に仕事内容にスピードと正確さを求められる傾向にあるでしょう。
国家公務員と地方公務員、どちらを選ぶ?
国家公務員と地方公務員では資格取得方法や試験難易度も違うため、「自分は日本や世界の未来を考えて働きたい」とスケールの大きい職種に就きたいのならば国家公務員資格取得を目指し、スケールよりも地域と深く関わりたいとお考えならば地方公務員資格取得をおすすめします。
理由として、国家公務員は地域よりも国、世界に目を向ける職種であり地方公務員は国や世界ではなく地域との関わりに目を向ける機会が大半です。
国家公務員試験の受験資格・合格ラインと倍率
| 受験資格 |
※中学卒業後2年以上5年未満の方も受験可
※高卒者試験の受験資格を有する方は除く
※必要に応じて年数の上乗せor短縮を行う可能性有/特定の資格を有すること等を要件とすることも有 |
| 合格ライン |
|
| 試験倍率データ | TAC「国家公務員の試験倍率データ」 |
国家公務員試験は毎年4月頃から秋までの期間で行われています。
職種によって日にちが変わるため、自分が気になっている職種はいつ試験が開催されるのかを予めチェックしておく必要があるでしょう。
次は国家公務員の試験科目を職種ごとにご紹介します。
国家公務員試験の試験科目一覧「国家総合職」
| 試験名 | 職種 | 試験科目 |
| 総合職試験(院卒者試験) |
|
|
| 総合職試験(大卒程度試験) |
|
|
| 院卒者試験(法律区分) | × |
|
| 大卒程度試験(教養区分) | × |
|
国家公務員試験の試験科目一覧「国家一般職」
| 試験名 | 職種 | 試験科目 |
| 一般職試験(大卒程度試験) |
|
☆行政本府省~行政沖縄地域
☆電気・電子・情報~林学
|
国家公務員試験の試験科目一覧「国家専門職」
| 試験名 | 職種 | 試験科目 | 特記事項 |
| 航空管制官 |
|
|
|
| 法務省専門職員(人間科学) |
|
|
× |
| 財務専門官 |
|
|
× |
| 国税専門官 |
|
|
× |
| 労働基準監督官 |
|
|
× |
| 労働基準監督官 |
|
|
× |
| 皇宮護衛官(大卒程度試験) |
|
|
× |
| 海上保安官 |
|
|
× |
| 食品衛生監視員 |
|
|
× |
| 外務省専門職員 |
|
|
× |
以上が受験資格・合格ラインと倍率(データ参照)、そして国家公務員試験の科目一覧表です。
今回は受験者が多いとされる「国家総合職」「国家一般職」「国家専門職」の科目に絞りましたが、この3つ以外にも「裁判職員」「衆議院・参議院」「自衛隊幹部候補生」等があります。
ここに記載している以外の科目が知りたい!という方は「国家公務員試験科目一覧」をご覧ください。
【ランク別】国家公務員試験の難易度と推移
国家公務員試験は職種ごとに難易度が違います。
ここではランクで難易度をご紹介し、合格者数や倍率から見る試験の推移も併せてご覧ください。
ランクS~A
| 職種名 | 難易度 |
| 国家公務員(国家総合職) | S |
| 外務省専門職 | S |
| 国会職員 | S |
| 労働基準監督官 | A |
| 航空管制官 | A |
| 東京都庁I類・都市圏県庁(上級)・政令指定都市職員(上級)・東京23区職員 | A |
数ある国家公務員の職種で試験が非常に難関とされている職種が以上の6種となります。
特に国家総合職や外務省専門、国会職員は「キャリア官僚」と呼ばれる方々がこぞって集結している職種で、人事院での高難易度の筆記試験に加えて面接試験や官庁訪問も難関です。
次は難易度がSランクとされている職種の難易度推移をご紹介します。
| 試験 | 年度 | 採用予定数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家総合職(法律) | 2021 | 145 | 6,383 | 406 | 15.7 |
| 2020 | 155 | 3,466 | 401 | 8.6 | |
| 2019 | 160 | 7,592 | 449 | 16.9 | |
| 国家総合職(経済) | 2021 | 60 | 1,003 | 168 | 6.0 |
| 2020 | 60 | 631 | 141 | 4.5 | |
| 2019 | 60 | 1,432 | 168 | 8.5 | |
| 国家総合職 (教養区分) |
2020 | - | 1,989 | 163 | 12.2 |
| 2019 | - | 1,944 | 148 | 13.1 | |
| 2018 | - | 1,863 | 145 | 12.8 | |
| 衆議院事務局総合職 | 2020 | 若干名 | 158 | 2 | 79 |
| 2019 | 若干名 | 176 | 2 | 88 | |
| 2018 | 若干名 | 218 | 2 | 109 | |
| 参議院事務局総合職 | 2020 | 15 | 526 | 9 | 58 |
| 2019 | 15 | 595 | 13 | 45.8 | |
| 2018 | 15 | 610 | 13 | 46.9 | |
| 外務省専門職員 | 2020 | 50 | 217 | 51 | 4.3 |
| 2019 | 50 | 253 | 48 | 5.3 | |
| 2018 | 50 | 316 | 49 | 6.4 |
引用:https://www.lec-jp.com/koumuin/about/difficulty.html
表をご覧いただくとわかるように、受験者数に対して採用予定数が非常に少なく、狭き門と言って過言ではないでしょう。
難易度の推移としてはそこまで大きい変化ありませんが、全体的に見てやはりSランクと呼ばれるだけの所以があると実感する数字と言えます。
ランクB~D
| 職種名 | 難易度 |
| 国家公務員(国家一般職)/大卒程度・高卒者 | B |
| 国税専門官 | B |
| 自衛官 | D |
| 刑務官 | D |
S~Aランクよりは難関ではないとされている4種です。
とはいえ、上でご紹介した職種よりは厳しい戦いではないというだけで難関に変わりはありません。
ランクB~Dが難関とするならば、S~Aランクは超難関と言って過言ではないでしょう。
次は受験者数が多いランクBの職種難易度推移を見ていきます。
| 職種 | 実施年/応募者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 国家公務員(国家一般職)/大卒程度・高卒者B |
|
|
|
| 国税専門官 |
|
|
|
こう見ると、Sランクと比較すれば超難関ではないと感じますが、推移を見ていくと合格率は最高でも31.9%となっており公務員資格以外の資格と比べるならば国家資格である「司法試験」が合格率約30%となっています。
司法試験と言えば超難関資格として有名です。
その司法試験と合格率がそう違いのない試験と考えると、Bランクだとしても難関であるかがよくわかります。
よくある質問「国家一般職編」
ここではネットでよく検索される「国家一般職」に関する質問をご紹介します。
Q.地域によって試験難易度は違うの?
A.国家一般職の試験問題自体は地域全て統一されているため、試験難易度自体はどの地域も同様です。
ただし地域ごとに合格のボーダーラインが違います。
全国地域別難易度
国家一般職「地域区分」は、以下9つです。
- 北海道
- 東北
- 関東甲信越
- 東海北陸
- 近畿
- 中国
- 四国
- 九州
- 沖縄
採用予定数が少ない地域かつ、受験者の多い地域ではボーダーラインが低い地域よりも5点高くなり、特に近年だと「近畿地方」「関東甲信越」「九州」の3地域でボーダーラインが高い傾向にあります。
その理由は上でもご紹介した内容プラス、以下の理由が考えられるでしょう。
特に、上の3つが揃っている近畿地方は「魔の近畿」と呼ばれる程の激戦区となっています。
Q.国家一般職が受かりやすい地域や官庁があるなら知りたい!
国家公務員試験や難易度に関する評判まとめ
ここまで国家公務員について、更に試験内容や難易度についてご紹介しましたがネットでよく見られる評判で一番多い口コミは「国家公務員試験は凄く難しい!」という内容です。
ではなぜ国家公務員試験は難関だと言われてしまうのか、それは以下の理由が挙げられます。
国家公務員試験の倍率は平均5~10%で、簡単に言えば「10人に1人が受かる」というイメージです。
倍率が高い=合格率が低いと考えられるため、難関と呼ばれる所以となっています。
また勉強範囲が広範囲で、難しい科目や問題があるという点も理由でしょう。
目安として公務員試験の勉強時間は平均1500時間前後と言われており、国家公務員となればそれ以上の時間が必要となります。
中には3000時間以上勉強しても受からなかった!という方もおり、国家公務員試験はただ時間をかければ受かるというわけではなく、必要な情報を選び抜いて学習するという大変さや官庁訪問等の面接対策も立てる必要がある点を含めて国家公務員試験が難関と言われる理由の一つです。
近年では筆記は合格しても面接で不合格になってしまうという方も多く、学習力は当然としてプラス人物性を重視していると考えられます。
「公務員試験にノー勉で受かった!」「意外と受かる!」という口コミの真相は?
ネットで国家公務員試験について調べていると、以下のような口コミがよく見かけられるでしょう。
この口コミに関しては「地方公務員試験」と「国家公務員試験」の違い、加えて公務員試験の職種によります。
公務員試験と一口に言っても地方公務員を目指す方や国家公務員を目指す方で試験内容は違う点や、加えて国家総合職ともなれば先ほどもご紹介したように合格率は非常に低い傾向にあるため、上の口コミを間に受けて「大丈夫だろう」という解釈はNGです。
以下は実際に国家公務員試験を受験した方々の口コミとなります。
国家公務員試験に合格する大半が、有名大学や専門学校に通っているという口コミです。
特に国家総合職はキャリアと呼ばれるにふさわしい難易度を誇っているという事実は変わりません。
公務員試験は難関ではなく「大変」と語る方も
国家公務員含む公務員試験は難関ではなく、単純に大変なのだと語る方の意見をご覧ください。
3つの意見をまとめると、公務員試験は難関ではないが暗記や面接の基本を押さえる等たゆまぬ努力が必要なのだと伝えたいと考えられます。
ですがこの方は以下のように、国家公務員試験に関しては確実に難関だと語り、最終的にどの職種で試験を受験するかが問題となるでしょう。
「国家公務員とは?」でお話ししたように、地域を対象として従事する地方公務員と違い、国や世界を対象として従事していく国家公務員は試験も桁違いの難関さとなります。
【職種&年代別】国家公務員の年収と初任給は?
国家公務員の年収モデル(令和2年度)
| 職種 | 年齢 | 年収 | 月収 |
| 係員 | 25歳 | 3,178,000円 | 193,900円 |
| 係長 | 35歳 | 4,544,000円 | 273,600円 |
| 地方機関課長 | 50歳 | 6,730,000円 | 413,200円 |
| 本府省課長補佐 | 35歳 | 7,314,000円 | 440,600円 |
| 本府省課長 | 50歳 | 12,659,000円 | 749,400円 |
| 本府省局長 | – | 17,804,000円 | 1,074,000円 |
| 事務次官 | – | 23,374,000円 | 1,410,000円 |
公務員と呼ばれる職種に従事する方々の年収中央値は「約580万円」です。
※男性サラリーマンの年収中央値は約470万円
もちろん役職や勤務年数、能力や手当によって差は発生します。
国家公務員のナンバー1と言われる事務次官の年収は2000万円を超え、同様の年収で有名な職業と言えば「独立コンサルタント」です。
「年代別」国家公務員の年収と日本の平均年収中央値/男女
年代別で年収を見ていくと、以下のように国家公務員は全体的に年代が上がれば上がる程、年収も高額になっていく傾向にあります。
| 年代 | 年収 | 日本の平均年収中央値/男女 |
| 20代 | 約300~450万円 | 約298~342万円 |
| 30代 | 約500~600万円 | 約390~431万円 |
| 40代 | 約650~800万円 | 約349~516万円 |
| 50代 | 約800~900万円 | 約335~556万円 |
表の金額プラス期末・勤勉手当(ボーナス)も年間で4か月分程度支給されるため、国家公務員になれば収入面は安定した生活が送れるでしょう。
ですがその分、年代が上がれば仕事量や責任を担う機会も多くなるため「確かに収入は安定するけれど自分の体力や精神面が心配」と語る方々もいます。
令和3年(4月1日現在)の初任給(行政職(-)本府省内部部局等配属の場合)
| 試験 | 学歴 | 級・号棒 | 月額 |
| 総合職 |
|
|
|
| 一般職 |
|
|
|
初任給を見ていると、一般職高卒者の場合は民間企業の初任給と大差はありません。
ですが上の年収表をご覧いただくとわかるように、ここから給与は上がっていくため、その点は民間企業との違いです。
「この会社に入ってからもう何十年も経つけど、そんなに収入が変わらない」というような悩みとは無縁と言えます。
よくある質問「国家公務員の年収編」
次は国家公務員の年収でよくある質問をご覧ください。
Q.俸給表って何?
A.俸給表「ほうきゅうひょう」とは国家公務員の給与を指しています。
国家公務員の給与に関しては法律でしっかり定められており、誰でも閲覧可能で俸給が記載されているものが俸給表です。2021年俸給表
俸給表は横軸の「級」と縦軸の「号棒」で構成されています。
民間企業での「基本給」と同様で、これ以外にも様々な諸手当があるため俸給表に記載されている以上の給与をもらっている国家公務員がほとんどです。
加えて、俸給表には11種17表に分類されており上の「2021年俸給表」は行政職の俸給表となります。
以下が俸給表の種類です。
- 専門行政職俸給表
- 税務職俸給表
- 公安職俸給表
- 海事職俸給表
- 教育職俸給表
- 研究職俸給表
- 医療職俸給表
- 福祉職俸給表
- 専門スタッフ職俸給表
- 指定職俸給表
- 行政職俸給表
Q.人事院勧告とは?
人事院勧告とは簡単に説明すると、国家公務員は給与や勤務条件を自らで決める等の関与が不可能なため、第三者機関である人事院が国会と内閣に「ここを見直して欲しい!」と声を挙げる制度で、原則毎年実施されています。
※2021年(令和3年)の人事院勧告は8/10日
人事院勧告は、公務員と民間企業に就職している従業員の給与水準を均衡させるという目的を果たすために大変必要な制度です。
令和3年の人事院勧告では、前年令和2年と同様の「ボーナスを引き下げ」が勧告されました。
それにより、もし実現すると勧告前と比べた国家公務員の平均年収は6万2,000円減の664万2,000円となります。
人事院勧告の詳細をもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
・人事院勧告(令和3年)
Q.号棒って何?どうしたら上がるの?
A.号棒とは先ほどご紹介した通り、国家公務員の給与を指しています。
この号棒ですが「勤務年数や能力・功績」が反映されるため、号棒を上げたいのならばこの3つを意識する必要があるでしょう。
ただし、級や号棒が上がればそれだけ仕事も大変になり忙しさも倍増するため、上げるという行為が良いものかと悩む国家公務員の先輩方も多数存在しています。
国家公務員の年収に関する評判まとめ
国家公務員の年収は民間企業と比べて高値であり、年代に比例して上がる傾向です。
また地域によって年収は上下し、キャリアともなれば高給取りと呼んで差し支えない年収となります。
ですが、中には「国家公務員の給与は安すぎる!」と訴える方々も。
一体どうして?理由をご覧ください。
激務に比例していない年収である
国家公務員を含む公務員は激務であると言われています。
確かに地域や国、世界と関わっていく職種のため、それだけ公務員を必要とする人々がいるでしょう。
特に国家公務員は国、世界がフィールドになるため様々な問題の解決や新たな政策の実施等、休む暇がないと答える方もいます。
事実、霞が関官僚の夫を持つ奥様が話していた内容を抜粋すると、
以上のように、激務さはブラック企業も驚く程です。
更に高給取りと言える1,000万円以上の年収をもらっている方はそこまで多くないとも言います。
その理由としては激務で体を壊して仕事を辞めてしまう方や、家族や医師からドクターストップを受けて戦線離脱する方も多いという理由も一理あるでしょう。
確かに倒産の心配もなく、民間企業から見れば安定した職種ですが、常に年収以上の働きをしていると考えれば国家公務員は給与が安い!と答える方がいるという事実も頷けます。
他にも国家公務員である自衛官は災害時等、自分達の命を犠牲にしてしまうかもしれないような状況で職務を全うするとなれば年収と働きが見合わないと考える方もいて当然でしょう。
またとあるサイトでは元公務員の方が以下のような口コミで国家公務員含む公務員のリアルを暴露していました。
年収が急激に下がるという不安も滅多にない安定性や、急に仕事もなくなってしまう等の可能性が低い国家公務員は誰もが憧れる職種かもしれませんが、このような意見も把握しておくべきでしょう。
国家公務員は独学で勉強できる?
結論から申し上げますと「国家公務員は独学で勉強可能」です。
ネットを見ていると独学で勉強して合格したよ!と報告している方を見かけます。
ですが、国家公務員試験は非常に範囲が広く、毎年難関を極めている試験です。
そのため、独学と言っても以下のような対策が必要となります。
ただやみくもに国家公務員試験に関する情報をネットで検索したり、参考書を購入したりして勉強を進める方法はNGです。
情報や参考書の中で試験に必要だと思われる情報だけを抜き出して勉強をしないと、時間がいくらあっても足りない!となってしまう可能性があります。
そこで国家公務員の知人や友人に「試験でこれは絶対押さえておくべきだ」というポイントを教えてもらい、それから勉強を開始する方が効率的です。
更に、試験をクリアしても官庁訪問等難関として立ちはだかる壁が多いため、通信講座を利用して官庁訪問の際に必要な面接対策や覚えておくべき基本的なマナーや時事情報もしっかり身に着けておく必要があります。
通信講座では面接対策だけでなく、知っておくべき時事情報等、独学では得られない経験や学習を提供してくれるでしょう。
現在では忙しい社会人の方も、オンライン講義をスマホで視聴しながら試験対策が行える通信講座が増えていたり、格安の通信講座も増えていたりと本気で国家公務員を目指す方々をサポートする場所が増えています。
もちろん独学ならばコスト的に負担がかかりませんが、国家公務員試験合格を最短かつ高確率で成功させたいのならば通信講座の利用を一度は検討すべきでしょう。
※受講前でも「お試しweb講義」や「国家公務員に関するガイド」を無料で配信している通信講座もあります。
また、独学での勉強をサポートするための手段として、通信講座などが挙げられます。
国家公務員の通信講座に関する内容はこちらの記事をご覧ください。
国家公務員を独学で勉強する際におすすめの参考書
国家公務員を独学で勉強する際にぜひおすすめしたい参考書は、まず自分がどの職種で合格したいのかによって変わります。
例えば、国家総合職を独学で勉強するならば「国家総合職 教養試験 過去問500 2021年度(公務員試験 合格の500シリーズ1)」がおすすめです。
過去問を徹底的に解いていき、そこから試験の傾向を導き出していきましょう。
「こんな過去問が多かったから予想ではこのような問題が出るだろう」等、予想問題集の役割も果たしてくれる優秀な参考書です。
国家総合職以外でも国家一般職の過去問シリーズや専門、文章理解や数的処理等国家公務員試験対策に必要な区分や分野ごとに参考書が販売されています。
ただし「この参考書は人気だからこの参考書にしよう」と選ぶのではなく、まずは自分がどの職種を目指すのか、全体的に国家公務員試験を見て自分にはどの部分の学習を重点的にすると良いのかを理解し、最終的な目標設定も済ませておく必要があるでしょう。
参考書を選ぶポイント
参考書を選ぶポイントとしては、問題数が多い科目や併用度の高い科目を意識することです。
例えば、出題されても1.2問しかない科目を徹底的にマークしても、試験で得点を取るためにはあまり効率的とは言えません。
また、同じ科目で何冊も参考書を買うよりも、科目ごとに1冊ずつと決めてその参考書を徹底的に解いて理解する勉強方法がおすすめです。
国家公務員試験は出題範囲が広いため、たくさんの情報を勉強する方が良いのではないかと考える方も多いと思いますが、何種類もの参考書を読み解き理解するのは、集中力の面や勉強面で相当体力と頭を使うため、せっかく頑張って学習をしても身に付きにくいでしょう。
国家公務員は独学で受験できる?
国家公務員試験は院卒~高卒ならば受験可能と、それ以外に厳しい受験資格が設定されているわけではないため、独学での受験が可能です。
ただし、基本的に国家公務員試験は最低でも高校卒業が前提となっているため、中卒で国家公務員を目指したい!という場合はまず高認試験を受ける必要があります。
とはいえ、いきなり予備校や学校に通うとなるとなかなか時間がない!という方もいるでしょう。
そんな方には通信講座の利用がおすすめです。
通信講座の中には「高卒認定試験通信講座」を開講している予備校兼通信講座もあります。
そのため、高卒認定に合格した後「国家公務員試験の受験資格取得」を目標としている通信講座を利用すれば最初の学歴が中卒でも受験可能です。
国家公務員の資格で就職可能な職種一覧表
次は国家公務員の資格で就職可能な職種を一覧表にしてご紹介します。
| 職種 | 職種内容 | 年収/月収 |
| 国家総合職/国家一般職 |
|
|
| 法務省専門職員(矯正心理専門職・法務教官・保護観察官) |
|
|
| 財務専門官 |
|
|
| ・国税専門官(国税調査官、国税徴収官、国税査察官)
・税務署職員 |
|
☆税務署職員
|
| 食品衛生監視員 |
|
|
| 労働基準監督官 |
|
|
| 航空管制官 |
|
|
| 裁判官 |
|
|
| 裁判所事務官 |
|
|
| 家庭裁判所調査官 |
|
|
| 検察官 |
|
|
| 警察官 |
|
|
| 外交官 |
|
|
| 国会議員 |
|
|
| 国会職員(衛視のみ高卒) |
|
|
| 特定独立行政法人職員 |
|
|
| 皇宮護衛官 |
|
|
| 検察事務官 |
|
|
| 自衛官 |
|
|
| 海上保安官 |
|
|
| 刑務官 |
|
|
| 入国警備官(これから日本へ入国する外国人が対象) |
|
|
| 入国審査官(すでに日本国内に不法滞在・不法就労をしている外国人が対象) |
|
|
以上が国家公務員資格を取得後、就職可能な職種一覧です。
一つの資格でも就職可能な職種が多岐にわたっています。
また警察官をご覧いただくとわかるように、全ての警察官が国家公務員ではなく「警視正未満」は地方公務員と呼ばれ、「警視正以上」からが国家公務員です。
警察官以外でも、消防士も地方公務員ですが消防庁で働く方々は国家公務員と少々紛らわしいところがあるため注意しましょう。
国家公務員試験の難易度:まとめ
今回は国家公務員に関する情報をご紹介しました。
本記事を読んでいて初めて知ることがあった方もいるでしょう。
「国家公務員=生涯安定」というイメージは誰しもが持つかもしれませんが、そこに行きつくまでの道のりも困難です。
国家公務員を目指そうと考えている方々はぜひ今一度、国家公務員についてお考えいただき、いつか「国家公務員の年収に見合わない激務」等の問題を含めて、国や世界を良くしていく国家公務員の一人として活躍していけるよう、難関を乗り越えていきましょう!
また、当サイトでは国家公務員の通信講座について紹介している記事も公開しています。
学習を始めるにあたって、ぜひこちらの記事もご覧ください。


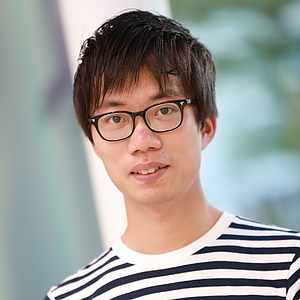








現在、国家一般職が受かりやすい地域として挙げられるのは「北海道地域」(平成28年度)です。※受験者数が少ない、国家公務員に特化した大学が少ない、人手不足等の理由が考えられる
また受かりやすい官庁等は、はっきりとしたデータはありません。
理由としては「最終的に自分次第」となるため、受かりやすい官庁を選ぶよりも「受かりたい官庁」を選び、徹底的に戦略を立てる対策が必要です。
ですが、仮に合格しやすい地域や官庁を選んで受験し合格したとしても、自分の住んでいる地域から離れている場合は引っ越しを考えたり、長期間そこで働かなければならなかったりする点が懸念されます。
また国家一般職本省の採用難易度はS~Dで示すと「B」程度です。
本省の採用難易度は厳しいとされていますが、同じ国家公務員の職種である国家総合職の難易度はSとなっており、その点を踏まえると「非常に厳しい難易度」と言うわけではありません。