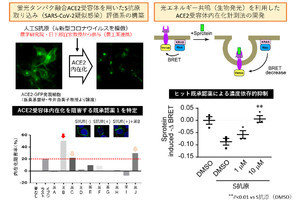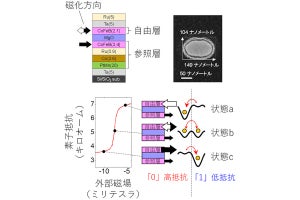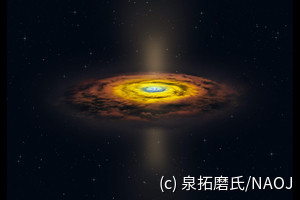理化学研究所(理研)ならびに東京工業大学(東工大)は3月18日、生体内に導入できる「人工金属酵素」によって薬剤の骨格を構築できる遷移金属触媒反応を開発したと発表した。
同成果は、理研 開拓研究本部 田中生体機能合成化学研究室の田中克典主任研究員(東工大 物質理工学院 応用化学系教授兼任)、チャン・ツンチェ特別研究員、ケンワード・ヴォン研究員、山本智也特別研究員らの研究チームによるもの。詳細は、科学雑誌「Angewandte Chemie, International Edition」に掲載された。
薬剤を用いた治療では、薬剤が疾病部位以外の場所に作用してしまうと、副作用を起こしてしまう可能性が出てくる。そうした副作用を防ぐ手法として、近年注目されているのが、「プロドラッグ」戦略だ。プロドラッグとは、標的となる生体内の疾病部位に届いてから、化学反応によって薬効を示す分子に変換されるようにデザインされた薬剤のことである。
疾病部位まで確実に薬剤を届ける仕組みとして「ドラッグデリバリー」が研究されているが、プロドラッグはさらにそれが進んだものともいえる。疾病部位まで届けられるうえに、その場に至ってはじめて薬剤に化学変化して活性を示すので、二重に副作用の軽減を期待できる仕組みを持つ。
これまでのプロドラッグでは、反応性を低下させられる「保護基」と呼ばれる官能基を、反応性の高い官能基に導入して活性を低下させた薬剤を生体内に投与してきた。疾病部位における生体内反応によって保護基を除去することで、薬剤の活性を復活させる戦略が取られていたのである。
-
従来のプロドラッグ戦略と新たなプロドラッグ戦略。(A)これまでのプロドラッグの活性化の模式図。保護基の脱離反応を用いる仕組みだ。(B)今回新たに考案されたプロドラッグの活性化の模式図。薬剤分子の骨格構築により、保護基を導入する官能基がなくてもプロドラッグを活性化することが可能となる (出所:理研Webサイト)
しかしこの戦略は、アミノ基やヒドロキシ基といった保護基を導入できる官能基を持つ薬剤にしか利用できないことが大きな課題だった。多くの薬剤は、これらの官能基を持っていないため、導入できなかったのである。そのため、プロドラッグの適用範囲を広げるには、薬剤の新たな活性化手法を開発する必要があった。
そこで研究チームは今回、「生体内金属触媒によって薬剤の骨格を構築させることで、活性を制御する」という新たなプロドラッグ活性化を実現することに挑戦することにしたのだという。
「フェナントリジニウム構造」を持つ化合物は、細胞のDNAに結合することで細胞増殖を抑制することが知られている。そこで今回は、三重結合を持つ化合物「アルキン」と、アンモニアの水素を炭化水素基などで置換した化合物である「アミン」を持った前駆体構造を、金触媒によってヒドロアミノ化反応を起こさせ、がん細胞上でフェナントリジニウム構造を合成する戦略が考案された。
さまざまな前駆体を用いた分析が続けられた結果、生体内と似た環境である緩衝液中や細胞培養液中において、さまざまな金触媒を加えた条件でヒドロアミノ化反応が速やかに進行することが確認された。また細胞毒性を示す薬剤2を、毒性を示さないプロドラッグ1から合成することにも成功したという。
-
金触媒によるフェナントリジニウム構造の構築。(A)緩衝液中で進行したヒドロアミノ化反応。(B)緩衝液中において一般的な金触媒(Au-b)を用いると、三重結合を持つプロドラッグ1がヒドロアミノ化反応によりフェナントリジニウム構造を持つ薬剤2へ変換されることが確認された (出所:理研Webサイト)
実際にこの化学反応によって、がん細胞のモデル株として実験で利用されている「A549細胞」(ヒト肺胞基底上皮腺がん細胞)に対し、プロドラッグ1と金触媒(Au-1)を作用させる実験が行われた。その結果、プロドラッグ1のみを作用させたがん細胞やAu-1のみを作用させたがん細胞では、細胞の増殖が阻害されなかったのに対し、プロドラッグ1とAu-1の両方を作用させたがん細胞では細胞増殖が抑制されることが確認された。これは、がん細胞存在下においても、Au-1によってプロドラッグ1が薬剤2に変換されたためと考察された。
-
がん細胞存在下でのプロドラッグから薬剤への変換。プロドラッグ1のみを作用させたがん細胞(白)や金触媒(Au-1)のみを作用させたがん細胞(オレンジ)は増殖が阻害されなかった。一方、プロドラッグ1とAu-1の両方を作用させたがん細胞(青)は増殖が抑制された (出所:理研Webサイト)
しかし、これまでの実験で用いられてきた金触媒は、「グルタチオン」などの生体内分子とも反応するため、生体内では触媒活性が低下するという課題を抱えている。今回の実験でも、がん細胞で薬剤を合成するためには、プロドラッグ1の50%以上の濃度の金触媒(Au-1)を細胞に作用させる必要があったという。
そこで研究チームが注目したのが、これまでの研究において開発に成功していた人工金属酵素だ。その人工金属酵素は、可溶性タンパク質の「アルブミン」とルテニウム触媒を複合化したものであり、グルタチオンなどが多く存在する生体内に似た環境でも触媒活性を保つことは確認済みだった。そこでこの手法が応用され、Au-1を導入した人工金属酵素が開発されることとなった。
Au-1は疎水性リガンド(特定の生体分子と結合することで、生理的な作用を発揮する物質のこと)である「N-ジエチルアミノクマリン構造」を持つことから、アルブミンの疎水性ポケットに配位し、アルブミンと金の複合体の開発に成功。同複合体はヒドロアミノ化反応を触媒したことから、Au-1を活性中心に持つ人工金属酵素「albumin-Au-1」と命名された。
-
金触媒を用いたアルブミン人工金属酵素の開発。(A)albumin-Au-1は、グルタチオンなどの生体内低分子の影響を受けず、アミノヒドロ化反応を起こす。(B)生体内低分子の金触媒反応への影響。一般的な金触媒(Au-b)では、アルギニンやグルタチオンや細胞溶解液によって触媒活性が低下。しかし、albumin-Au-1を用いた条件では、触媒活性が低下しないことが確認された (出所:理研Webサイト)
さらに、albumin-Au-1についてその性能や特性が詳細に調べられた。グルタチオンやアルギニンなどの生体内低分子や細胞溶解液は、一般的な金触媒(Au-b)の触媒活性を低下させてしまう。しかし、これらの生体内低分子や細胞溶解液を加えても、albumin-Au-1の触媒活性が低下しないことが確認された。つまり、albumin-Au-1は、生体内や細胞内においても触媒活性を保つ可能性が示唆されたのである。
albumin-Au-1ではAu-1の活性中心が疎水性ポケットに保護されているため、親水性の生体内低分子が反応できない。一方、疎水性の基質はalbumin-Au-1と反応できるため、生体内低分子の存在下でも化学反応が進行すると考えられるという。
最後に、albumin-Au-1をプロドラッグ1とともにA549がん細胞に作用させたところ、albumin-Au-1のみを用いた条件よりも低濃度でプロドラッグ1を活性化し、細胞増殖を抑制できることが明らかとなった。
-
人工金属酵素を用いたがん細胞での薬剤合成。プロドラッグ1のみを作用させた細胞(白)や人工金属酵素(albumin-Au-1)のみを作用させたがん細胞(オレンジ)では、細胞の増殖が阻害されなかったのに対し、albumin-Au-1とプロドラッグ1の両方を作用させたがん細胞(青)では、細胞増殖が抑制されることが確認された (出所:理研Webサイト)
研究チームでは、今回開発したalbumin-Au-1は保護基を導入する官能基がなくても、薬剤の骨格を直接構築することで薬効を制御できるため、プロドラッグ戦略の適用範囲を広げることができるとする。
さらに、生体内に導入可能な人工金属酵素によっても、このプロドラッグの活性化が行えることが今回の研究で示された。アルブミンを用いた人工金属酵素は、酵素の表面を糖鎖修飾することで標的細胞に選択的に輸送されることが、これまでの研究で確認されている。今後、生体内の標的細胞に輸送された人工金属酵素で今回の化学反応を行うことができれば、生体内のがん細胞で薬剤を合成することも可能になると考えられるとしている。