長期譲渡所得という言葉はご存知でしょうか?個人の土地や建物、株式など資産となるものを譲渡することによって得る所得を「譲渡所得」といい、所有期間の長さによって、税率が変わります。
短期譲渡と長期譲渡では税率が大きく変わり、受けられる特別控除の種類が異なったりするため、この所得税について知らなければ税金で損をしてしまう可能性があります。
この記事では譲渡所得の種類や税率、それに伴う特別控除についても解説します。税金で損をしないためにも是非、この機会に長期譲渡になるような不動産売却のタイミングを考えてみましょう。
- 譲渡所得には、保有期間が5年を超える長期譲渡所得と5年以内の短期譲渡所得があります。課税率は長期譲渡所得の方が短期譲渡所得よりも低いです。
- 譲渡所得の金額は、資産の売却金額から取得費や譲渡費用、特別控除を差し引くと算出できます。この金額をもとに、所得税や住民税、復興特別所得税が決定されるのです。
- 譲渡所得の金額によっては所得税だけで数百万円かかることもあります。特別控除で譲渡所得の金額を抑えられればその分の税金も抑えられるので、活用できる特別控除がないか調べておきましょう。
譲渡所得の種類

譲渡所得は不動産の保有期間によって、長期譲渡と短期譲渡に分かれます。ここでは、それぞれの保有期間や税率を解説します。
課税率の低い長期譲渡所得
不動産の保有期間が5年を超えた場合、長期譲渡所得として扱われ課税率が低くなります。保有期間は、不動産を売却した年の1月1日時点で計算することに注意しましょう。例えば、6月1日に不動産を売却しても、保有期間は売却した年の1月1日までです。
具体的な税金の種類と税率を表にまとめました。
| 税金の種類 | 税率 |
| 所得税 | 15.315% |
| 住民税 | 5% |
| 復興特別所得税 | 2.1% |
課税率の高い短期譲渡所得
不動産の保有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得となります。この場合も、不動産を購入してから売却した1月1日時点までが保有期間として扱われます。短期譲渡所得に課税される税金と税率も表にまとめました。長期譲渡所得と比べて、課税率は高くなります。
| 税金の種類 | 税率 |
| 所得税 | 30.63% |
| 住民税 | 9% |
| 復興特別所得税 | 2.1% |
長期譲渡と短期譲渡の比較について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

譲渡所得の計算方法
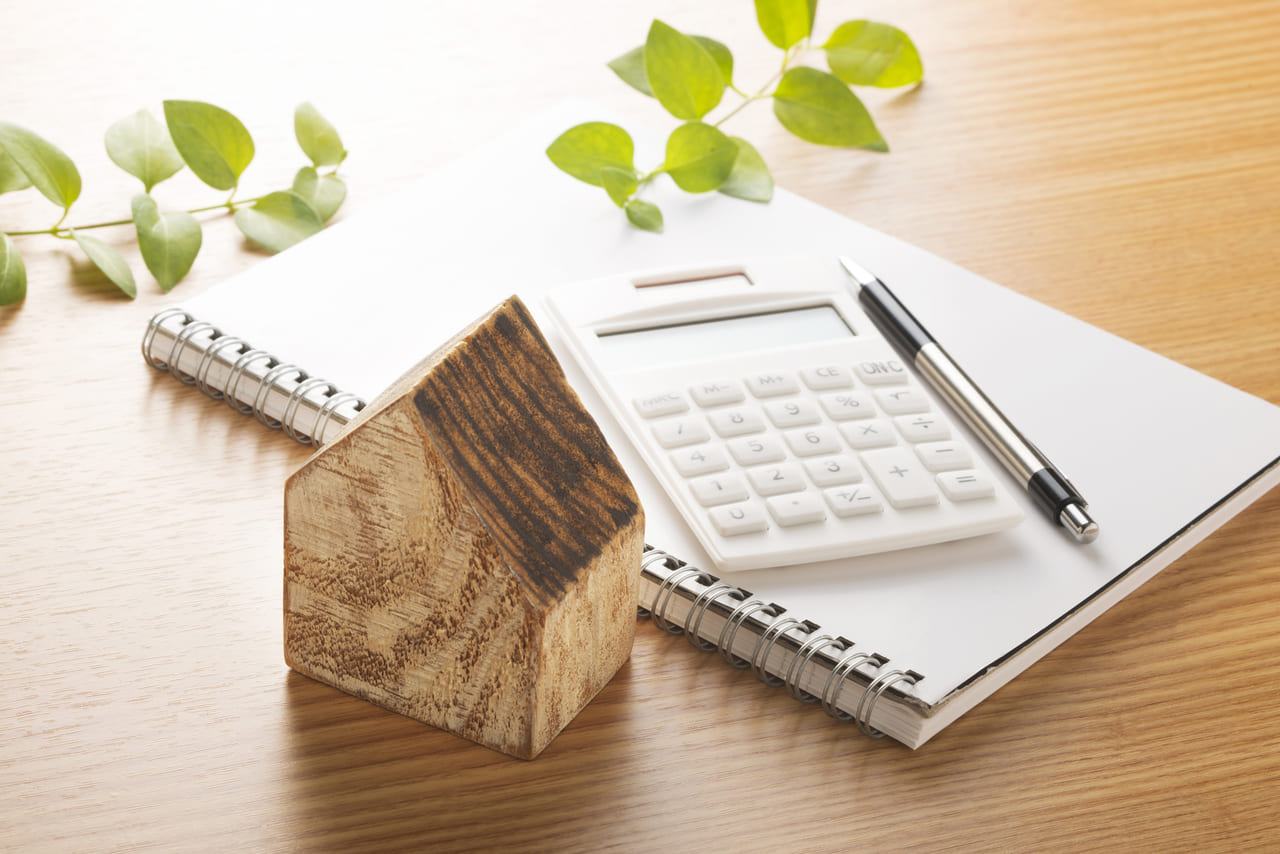
譲渡所得の計算式は下記のとおりです。
売却代金が3,000万円、取得費が1,000万円で譲渡費用が200万円とした場合で計算してみます。この場合の譲渡所得は3,000万円-(1,000万円+200万円)=1,800万円となります。
譲渡所得の計算方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

分離課税の計算方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

譲渡所得に関する用語の解説

譲渡所得に関する用語を紹介します。ここで紹介する用語を覚えて、理解をさらに深めましょう。
不動産購入費用である取得費
不動産購入費用である取得費ですが、以下のようなものも含まれます。
- 土地や建物を購入した際に発生した登記費用を含む登録免許税
- 不動産取得税
- 取得分の特別土地保有税
- 印紙税
なお、建物の取得費は購入代金又は建築代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となることに注意しましょう。
不動産売却の減価償却について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

不動産売却の所得費について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

不動産売却費用である譲渡費用
不動産売却費用である譲渡費用ですが、以下のようなものも含まれます。
- 仲介手数料
- 売主が支払った印紙税
- 立ち退き料
- 不動産を売却するために生じた取り壊し費用とその不動産の損失金額
- 売買契約締結済みの資産を更に良い条件で売却するために生じた違約金
- 地主に対して支払った名義書換料など
注意点として、修繕費や固定資産税、維持や管理のためにかかった費用は譲渡費用に含まれません。譲渡費用は売却するために直接かかった費用です。そのため、売却するために行なった取り立てなどで生じた費用も譲渡費用として扱うことはできません。
長期譲渡所得に適用される特別控除

長期譲渡所得に適用される特別控除の概要や、適用されるための条件について解説します。長期譲渡で節税するのであれば、ここで紹介する特別控除はぜひ受けたいところです。受けるために必要な条件を、しっかり把握しておきましょう。
マイホーム売却の際の特別控除
自宅として住んでいた家を売却した場合、条件を満たせば最高3,000万円の特別控除が受けられます。最高3,000万円であることから、そのまま「3,000万円の特別控除」と言われることも多いようです。この「3,000万円の特別控除」を受けるための条件は、売却する家の状況によって異なるため注意が必要です。
相続で空き家になっている家を取得して、その家を売却する場合は下記の条件を満たす必要があります。
- 昭和56年3月31日以前に建築された建物である
- 区分所有建物登記がされてい建物である
- 相続する前に被相続人以外に住んでいた人がいない
過去に自身が住んでいて、現在は空き家状態になっている家を売却する場合は、居住しなくなってから3年が経過した日の年の12月31日までに売却することが条件となっています。現在も住んでいる家を売却する場合は、所有期間に関わらず最高で3,000万円の特別控除を受けられます。
自宅を売却する際には、ぜひこの特別控除を受けられるようにしましょう。
公共事業のため不動産を売った場合の控除
公共事業のために不動産を売却した際に受けられる控除は2種類あります。
公共事業のために不動産を売却して、そのお金で別の不動産を購入した場合は、買い替えによって譲渡はなかったものとして扱い、課税の対象にはならない特例が設けられています。この特例が適用されるためには下記の条件を満たしていなければなりません。
- 不動産を売却してから2年以内に売却する
- 売却した不動産が個人の所有する固定資産である
- 売却した不動産と同じ種類の不動産を購入する
もうひとつは、譲渡で得た所得から最高5,000万円の特別控除を受けられるというものです。この特別控除が適用されるのは1年だけとなっています。ある不動産を同じ公共事業に対して、2年に渡って売却した場合でも1年目しか控除は受けられません。
土地区画整理事業のため不動産を売った際の控除
土地区画整理事業とは、国や公共団体が公共施設の改築や整備を行う事業です。土地区画整理事業のために不動産を売った場合に適用される特別控除もあります。この場合、控除される金額は最高2,000万円です。
特定住宅地造成事業のため不動産を売った際の控除
特定住宅地造成事業とは、地方公共団体や独立行政法人中小企業基盤整備機構などが、住宅の建設や宅地の造成を目的として行う事業です。このために不動産を売却した場合も、控除の対象となります。特定住宅地造成事業で不動産を売却した場合の特別控除は最高で1,500万円です。
農地保有の合理化のため農地を譲渡した際の控除
農地保有合理化事業に伴い、自分が所有している農地を農業委員会の斡旋などで、その地域の担い手に売却した場合は売却所得から最高800万円の特別控除を受けられます。
農地保有合理化事業は、農地保有合理化法人が主体となって実施している事業です。酪農農家や規模の小さい農家などから農地を買い入れ、もしくは借り入れすることによって農地を効率的に利用できるように調整した上で、その農地を売却したり、貸付けしたりします。
農地を売却する方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

一定期間に取得した不動産を売った際の控除
一定期間に取得した不動産を売却した際に受けられる控除があります。取得した期間以外にも条件がありますが、それらを満たせば最高で1,000万円の特別控除を受けられます。この特別控除を受けるための条件は下記のとおりです。
- 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した不動産である
- 平成21年に取得した不動産は平成27年以降に譲渡している
- 平成22年に取得した不動産は平成28年以降に譲渡している
- 親子や夫婦、内縁関係など特別な間柄の人物から取得した不動産ではない
- 相続や贈与、交換、遺贈、代物弁済や所有権移転外リース取引で取得した不動産ではない
- 譲渡した不動産が他の譲渡所得の特例を受けていない
この特別控除ができた背景として、リーマンショックの影響による景気の低下、不動産取引の低迷があります。このような状況から、不動産取引を活発にして景気が上昇することを図って創設された制度です。
低未利用土地等を譲渡した際の控除
令和2年7月1日から令和4年12月31日の間に、個人が都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売却した場合、最高で100万円の控除を受けられます。低未利用土地等とは、居住用や事業用として利用していない土地や、利用の程度が著しく低い土地などのことです。
この特例を受けるための条件は下記のとおりです。
- 売却した不動産が都市計画区域内にある低未利用土地等である
- 売却した年の1月1日時点で保有期間が5年超
- 売却主と買い主が家族や生計を共にする者など特別な関係ではない
- 売却金額が低末利用土地等の上にある建造物等の対価を含めても500万円以下
- 売却後、その低末利用土地等が利用されている
- 対象となる低末利用土地等が、1年前もしくは2年前にこの特別控除を受けていない
- 売却した不動産が他の譲渡所得に関する課税の特例を受けていない
不動産売却の際に利用できる特別控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

譲渡所得の税金の計算方法
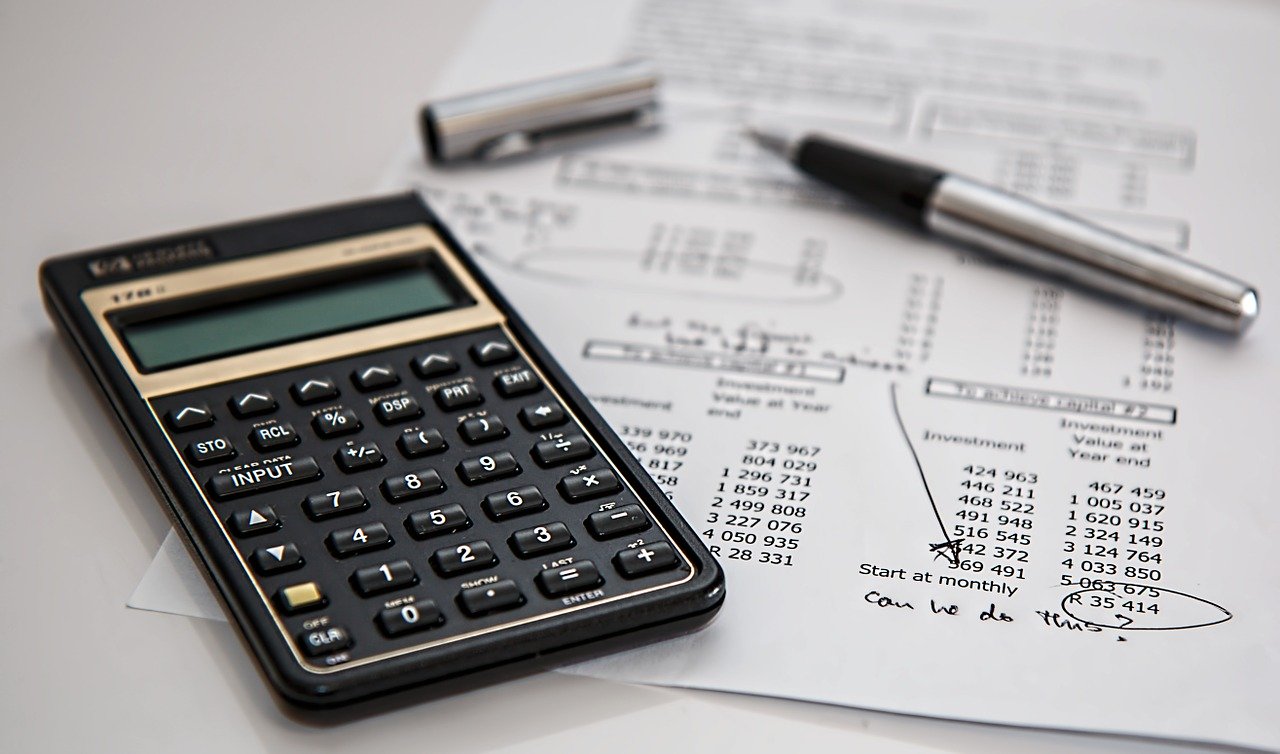
譲渡所得の税金の計算方法を紹介します。譲渡所得の種類や、不動産の保有期間が10年以上の場合で軽減税率の特例が適用された場合についてそれぞれ解説します。それぞれで税額が変わることを確認しておきましょう。
長期譲渡所得の場合
長期譲渡所得の税金計算方法は下記のとおりです。
例として、譲渡金額が5,000万円、取得費が2,000万円、譲渡費用が200万円だった場合、課税長期譲渡所得金額は5,000万円-(2,000万円+200万円)=2,800万円となります。長期譲渡所得の税率は15.315%であるため、所得税は2,800万円×15%=420万円です。
復興特別所得税の税率は2.1%であるため、2,800万円×2.1%=58万8,000円となります。住民税は、2,800万円×5%=140万円です。
短期譲渡所得の場合
短期譲渡所得の税額も、長期譲渡所得と同じ計算式で算出できます。しかし、所得税と住民税の税率は異なることに注意しましょう。短期譲渡所得は所得税の税率が30.63%、住民税の税率が9%です。
先ほどと同様に譲渡金額が5,000万円、取得費が2,000万円、譲渡費用が200万円だった場合で計算をしてみましょう。課税長期譲渡所得金額は5,000万円-(2,000万円+200万円)=2,800万円です。所得税は2,800万円×30%=840万円となります。
復興特別所得税の税率は2.1%で、2,800万円×2.1%=58万8,000円となります。住民税は、2,800万円×9%=252万円です。このような結果から、長期譲渡取得は所得税と住民税の面で節約できることがわかります。
不動産の保有期間が10年以上の場合
保有期間が10年以上の不動産は、軽減税率の特例によって長期譲渡所得よりも税率が低くなります。軽減税率の特例を受けるための条件は下記のとおりです。
- 居住用の不動産を売却した
- 居住用の不動産ではない場合は居住しなくなってから3年目の12月31日までに売却できる
- 売却した年の1月1日時点で所有していた期間が10年を超えている
- 過去2年間でこの特例を受けていない
- 自宅買い替え特例などを受けていない
- 家族など特別な関係の人との売買取引ではない
- 確定申告している
軽減税率の特例での税率下記のとおりです。課税譲渡所得が6,000万円以上の場合は、6,000万円以下の部分と以上の部分で税率が変わります。
| 6,000万円以下にかかる税率 | 6,000万円を超えた部分にかかる税率 | |
| 所得税 | 10.21% | 15.315% |
| 住民税 | 4% | 5% |
| 合計 | 14.21% | 20.315% |
課税譲渡所得が6,000万円以下で軽減税率の特例が適用された場合の税額を計算してみましょう。譲渡金額は5,000万円、取得費が2,000万円、譲渡費用は200万円として計算します。課税長期譲渡所得金額は5,000万円-(2,000万円+200万円)=2,800万円です。所得税は2,800万円×10%=280万円となります。
復興特別所得税は税率が2.1%であるため、2,800万円×2.1%=58万8,000円となります。住民税は、2,800万円×4%=112万円です。比較すると、長期譲渡所得よりもさらに所得税と住民税を低く抑えられることがわかります。
長期譲渡所得に関するよくある質問

長期譲渡所得に関することでよくある質問とその回答を紹介します。この機会に、長期譲渡所得に対しての知識を深めておきましょう。
相続した不動産の保有期間はどうなるのか
相続で取得した不動産の保有期間は、親がその住宅を取得した日から相続した子が売却した年の1月1日までです。相続した日にちからではありません。
相続した不動産の場合は、取得費も親が購入した時の金額をもとに計算します。子が相続した時に登記費用や不動産取得税が発生している場合は、それらの金額も取得費として含まれます。
また、支払った相続税のうち一定額を取得費に加算できる「取得費加算の特例」があります。この特例を受けるためには以下の条件を満たしている必要があります。
- 相続などで財産を取得していること
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること
- その財産を相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却していること
取得費が分からない場合はどうするのか
取得費とは、不動産の購入金額とその手数料の合計額です。先祖代々の不動産など、購入した時期がかなり昔で取得費が不明の場合がありますが、そのような場合は売却金額の5%相当額を取得費にできます。
例として不動産を5,000万円で売却したら、その5%にあたる250万円を取得費にできます。しかし、取得費を5%で計算した場合、損をすることも多いです。損をしないためにも、できる限り購入した時の契約書等はしっかり保存しておきましょう。
まとめ

本記事では、譲渡所得の種類や計算方法、そして長期譲渡所得に適用される特別控除の種類について詳しく説明してきました。
譲渡所得は、保有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。長期譲渡取得は、短期譲渡所得に比べて課税率が低いので、利益率が高いです。さらに条件によっては、受けられる特別控除も多数あるため、物件売却の前に自身の条件に合う控除のサービスをよくリサーチする必要があります。
長期譲渡所得と特別控除の詳細を理解した上で上手に節税することをお勧めします。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。


