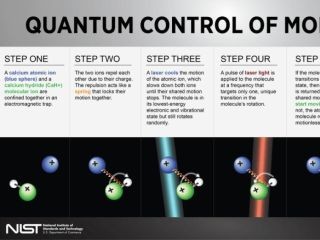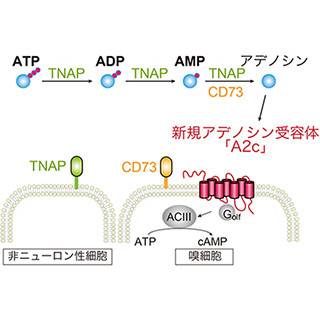理化学研究所(理研)は、同所仁科加速器研究センター櫻井RI物理研究室のピーター・ドーネンバル研究員、櫻井博儀主任研究員をはじめとした11カ国の研究者による国際共同研究グループが、重イオン加速器施設「RIビームファクトリー(RIBF)」を用いて中性子過剰なスズ-133(133Sn、陽子数50、中性子数83)原子核の励起準位を調べたところ、「非束縛状態」であるにも関わらずガンマ崩壊が起こる現象を発見したと発表した。この研究成果は5月18日、米国の科学雑誌「Physical Review Letters」オンライン版に掲載された。
自然界には、強い相互作用、電磁相互作用、弱い相互作用、重力相互作用という4つの相互作用があり、ミクロな原子核の世界では強い相互作用によって陽子や中性子(核子)が結び付いている。原子核を徐々に励起していくと、核子が束縛されるか・されないかの限界に達し、これを超えると「非束縛状態」になり、強い相互作用によって核子を放出して異なる原子核へと崩壊するという。
一方で、限界を超えない場合には核子は放出されず、電磁相互作用によってガンマ線を放出し基底状態に移る「ガンマ崩壊」が起こるという。この電磁相互作用の大きさは強い相互作用の1万分の1しかなく、非束縛状態にある原子核ではガンマ崩壊は起こらないと考えられていた。
今回、研究グループは、理研の重イオン加速器施設のRIビームファクトリー(RIBF)の大強度ウラン(238U)ビームを用いた核分裂反応で134Snビームを取り出し、それを炭素標的に照射することで133Snを生成。ここから放出されたガンマ線のエネルギーを測定したところ、束縛状態と非束縛状態の限界である2.4MeVよりも大きい3.6MeVであることがわかったという。
この発見は、これまでの常識を覆し、133Snが非束縛状態であるにも関わらず、強い相互作用と拮抗してガンマ崩壊を起こした稀な現象であることを示している。宇宙での重元素合成過程(r過程)の理論モデルには、中性子過剰な原子核の脱励起に関して、中性子放出による崩壊過程だけが含まれていたが、今回の成果によりガンマ崩壊も考慮する必要性が生まれたことになる。
今後は、133Snと同じ現象が他の原子核でも現れるかどうかが課題になる。RIBFで非束縛状態の研究が進むことで、非束縛状態の理論・実験研究がますます活発になり、新しい成果の創出が期待できると説明している。