「技術士の難易度は高い?」
「年収やおすすめの過去問が知りたい」
技術士になるためには、技術的な専門知識に加え、実務経験を有していなくてはなりません。
この記事では、技術士の難易度や年収、過去問についてご紹介します。
難易度や過去問を知ることで、具体的な学習計画を立てられるでしょう。
技術士として働くイメージを膨らませながら、年収を上げるコツも参考にしてみて下さい。
また、技術士の試験対策は通信講座の利用もおすすめです。
| 通信講座 | コース名/料金(税込) | 合格率/実績 |
| アガルート |
※SATがサービスを提供 |
|
| SAT | 【一括セット】
|
|
技術士 通信講座の詳細は以下の記事もあわせてご覧ください。
→技術士のおすすめ通信講座5選と失敗しない選び方!の記事はこちら
技術士の難易度について
技術士試験は一次試験と二次試験に分かれており、さらに4~7年の実務経験も必要なため、資格取得には長い時間を費やすことになるでしょう。
一次試験は受験資格がなく、過去問から出題されることも多いため、合格率は40~50%程度となっており、比較的合格しやすい試験と言えます。
一方で二次試験は、筆記試験のほかに口頭試験もある難関で、最終的な合格率は10%前後と狭き門です。
合格率から見る技術士の難易度
技術士を含む、各国家資格の合格率は以下の通りです。
| 資格名称 | 受験者数(人) | 合格率(%) |
| 司法書士 | 12,727 | 5.18 |
| 気象予報士 | 8,339 | 5.4 |
| 社労士 | 40,633 | 5.3 |
| 測量士 | 3,194 | 14.4 |
| 弁理士 | 3,177 | 6.1 |
| 土地家屋調査士 | 4,404 | 9.6 |
| 行政書士 | 47,850 | 12.13 |
| 技術士(二次) | 22,489 | 11.7 |
| 宅建士 | 226,048 | 17.0 |
| 税理士 | 28,853 | 19.5 |
| 中小企業診断士 | 17,345 | 5.4 |
技術士二次試験の合格率は11.7%と非常に低く、他資格と比較しても難易度の高さがうかがえます。
技術士試験に合格できるかどうかは、「二次試験に合格できるかどうか」と言っても過言ではありません。
二万人以上の受験者数を誇る技術士は、社労士や税理士に続き受験者数が多く、資格取得希望者が多い資格と言えるでしょう。
偏差値から見る技術士の難易度
技術士を含む、各国家資格の偏差値は以下の通りです。
| 偏差値 | 資格名称 | ジャンル |
| 77 | 公認会計士 | 法律 |
| 76 | 司法書士 | 法律 |
| 75 | 税理士 | 法律 |
| 75 | 弁理士 | 法律 |
| 70 | 技術士 | 工業 |
| 67 | 中小企業診断士 | 法律 |
| 66 | 一級建築士 | 建築・土木 |
| 65 | 社労士 | 法律 |
| 64 | 土地家屋調査士 | 不動産 |
| 62 | 行政書士 | 法律 |
| 60 | 技術士補 | 工業 |
| 59 | 測量士 | 建築・土木 |
| 57 | 社会福祉士 | 福祉 |
| 57 | 宅建士 | 不動産 |
技術士の一次試験は偏差値60、二次試験は偏差値70とさらに高く、税理士や弁理士に続く難易度の高さとなっています。
二次試験受験者10名のうち、合格できるのはたった1人と言われるのも納得できるでしょう。
技術士補は技術士と比べると合格しやすいと言われていますが、偏差値60という数字から見ると、決して安易な試験ではないことも分かります。
部門別◆難易度
技術士試験は、一次試験が建設部門や機械分野などの20部門、二次試験は総合技術監理部門を加えた21部門に分かれています。
部門によって合格率に差があり、難易度もまちまちです。
令和6年度の二次試験(筆記試験)における部門別合格率は以下のようになっています。
| 技術部門 | 合格率 |
| 機械 | 17.4 |
| 船舶・海洋 | 20.0 |
| 航空・宇宙 | 14.0 |
| 電気電子 | 9.1 |
| 化学 | 18.0 |
| 繊維 | 18.8 |
| 金属 | 18.8 |
| 資源工学 | 14.3 |
| 建設 | 8.7 |
| 上下水道 | 10.7 |
| 衛生工学 | 10.9 |
| 農業 | 11.8 |
| 森林 | 12.1 |
| 水産 | 15.2 |
| 経営工学 | 10.3 |
| 情報工学 | 7.0 |
| 応用理学 | 12.5 |
| 生物工学 | 17.5 |
| 環境 | 11.6 |
| 原子力・放射線 | 19.0 |
| 総合技術監理 | 15.2 |
| 全体 | 10.4 |
船舶・海洋部門の合格率は高めですが、電気電子や建設の合格率は共に10%を切っており、極めて難易度が高いと言えるでしょう。
情報工学部門の7.0%と船舶・海洋部門の20.0%を比較すると、合格率に3倍近くの差が開いています。
技術士試験の難易度が高いと言われるのは、「二次試験の合格率が低いから」と言えるでしょう。
さらに、部門によって合格率に差があり難易度も異なります。
自分が受ける部門の合格率・難易度を把握したうえで、試験対策を行いましょう。
建設部門◆難易度
建設部門を取得することで建設コンサルタントや官公庁への就職、技術士としての独立など仕事の幅が大きく広がるでしょう。
こうした需要の高さから受験者が多い建設部門ですが、合格率は各部門の中でも6~13%と低迷傾向にあります。
合格率が低い原因の1つに、会社から資格取得依頼を受ける受験者は多いものの、合格できる従業員はわずかである点が挙げられるでしょう。
建設部門の第二次試験では、以下の選択科目(専門分野)が規定されています。
- 土質および基礎
- 鋼構造およびコンクリート
- 都市および地方計画
- 河川・砂防および海岸・海洋
- 湾岸および空港
- 電力土木
- 道路
- 鉄道
- トンネル
- 施工計画・施工設備および生産
- 建設環境
選択科目(専門分野)を確認し、長期的かつ効率的な方法で技術領域と知識を保有していきましょう。
非常に難易度の高い分野ですが、過去問を中心とした学習サイクルを確立することで、合格できる力が身に付けられます。
総合技術監理部門◆難易度
総合技術監理部門は、さまざまな分野を総合的に監理する役割を担うため、常に需要の高い部門です。
総合技術部門とその他20の専門技術部門では、「全体を統括できるか」、「一部の部門に長けているか」という点で異なります。
このように、21の技術分野で最上位の部門であるため、社内外問わず評価は高く、企業によっては給与や待遇面での向上も期待できるでしょう。
総合技術管理部門の難易度は非常に高く、専門技術部門とは試験内容も異なります。
合格率は10%を下回る年もあるため、専門科目の技術士資格を取得したのち、総合技術管理部門に挑戦する方も多く見られるほどです。
総合技術監理部門では、多種多様なスキルが求められるため、幅広い分野を効率良く学習する必要があります。
計画的な学習方針を立て、資格取得までの間で必要な能力を身に付けていきましょう。
技術士の年収は?
「技術士の年収はいくら?」
「生涯安定して稼げる?」
など気になっている方も多いでしょう。
技術士の平均年収を基に年代別、地域別についてもご紹介します。
技術士の平均年収
技術士の平均年収は以下の通りです。
| 性別 | 平均月収 | 平均賞与 | 平均年収 |
| 男 | 44万3100円 | 141万6600円 | 673万3800円 |
| 女 | 38万5600円 | 110万5000円 | 573万2200円 |
| 合計 | 43万9400円 | 139万6500円 | 666万9300円 |
2019年の賃金構造基本統計調査によれば、技術士の平均年収は男性で673万円程度、女性で573万円程度となっています。
日本人の平均年収440万円と比較すると、技術士は高収入を得られる職業といえるでしょう。
男性の方が年収は高い傾向にありますが、男女問わず安定した収入が望めます。
しかし、実際の年収は年齢や経験、会社の規模や地域などによって異なるため、全員が600万円以上もらえるわけではありません。
年代別年収
年代別の平均年収は以下の通りです。
| 年齢 | 年収(男性) | 年収(女性) |
| 20~24歳 | 407万4300円 | データなし |
| 25~29歳 | 515万6300円 | 492万3400円 |
| 30~34歳 | 624万6300円 | 683万9200円 |
| 35~39歳 | 645万9900円 | 628万3900円 |
| 40~44歳 | 741万9000円 | 501万5000円 |
| 45~49歳 | 760万5700円 | 662万8000円 |
| 50~54歳 | 770万3100円 | 634万1100円 |
| 55~59歳 | 757万5200円 | 510万3500円 |
| 60~64歳 | 612万1600円 | 287万3100円 |
| 65~69歳 | 529万700円 | データなし |
男性技術士は50~54歳、女性技術士は45~49歳が年収のピークとなっており、男女いずれも高年収であることが分かります。
20~29歳で既に日本人の平均年収を上回っており、幅広い世代において高収入を得られる安定した職業であると言えるでしょう。
技術士は各業界から求められる需要の高い職業ですが、資格取得には難易度の高い試験を突破しなくてはなりません。
資格取得が叶えば20代の若い世代から60歳以上の年配層まで、幅広い年代で高収入を得ながら活躍できる点が技術士の魅力と言えるでしょう。
地域別の平均年収
地域別の平均年収は以下の通りです。
| 地域 | 平均年収 | 平均月収 |
| 北海道・東北 | 502万円 | 42万円 |
| 関東 | 478万円 | 40万円 |
| 甲信越・北陸 | 469万円 | 39万円 |
| 東海 | 419万円 | 35万円 |
| 関西 | 447万円 | 37万円 |
| 四国 | 454万円 | 38万円 |
| 中国 | 370万円 | 31万円 |
| 九州・沖縄 | 411万円 | 34万円 |
地域別で見てみると、北海道・東北地方が502万円と最も高い年収となっています。
関東地方に比べ、北海道や東北地方は豊かな自然に囲まれ、森林・水産・農業とさまざまな分野が盛んな地域です。
そのため、技術士として活躍できる場が多く需要も高いため、平均年収も多く得られるのかもしれません。
このように技術士は地方で幅広く活かせる資格であるとも考えられるでしょう。
部門別平均年収
同じ技術士であっても、勤める業界によって年収に差があります。
事業受注の優位性による関係から、建設業・製造業・情報通信業の技術士が多いとされ、産業別の賃金データによると、平均月給は建設業345,500円、製造業321,800円、情報通信業405,000円と、業界によってさまざまです。
部門別の平均年収を一部ご紹介します。
建設部門
厚生労働省が実施した2019年度の賃金構造基本統計調査では、技術士全部門の平均年収は669.3万円となっています。
試験合格者の4割程度が建設部門であることから、建設部門の平均年収も669万円に近いと言えるでしょう。
さらに、国税庁が公表した民間給与実態統計調査結果によると、国民全体の平均給与は433万円です。
技術士建設部門の平均年収と比較すると、200万円以上高いことがわかります。
電気電子部門
部門ごとの年収は公表されていないため一概には言えませんが、求人サイトを参考にすると、電気電子部門の年収は500~800万円と言われています。
勤続年数や実務経験の有無などによって異なりますが、管理職に就いた場合、年収1,000万円以上を目指せる可能性もあるかもしれません。
電気電子部門では、電気エネルギーや情報通信などに関する技術面のコンサル業務を行います。
このコンサルティング会社の規模が大きいほど年収が多い傾向です。
技術士の年収を上げるコツ
技術士の年収をアップさせる方法をいくつかご紹介します。
技術士資格は「業務独占資格ではない」というのが特徴です。
つまり、有資格者による市場の独占ができないため、技術士の資格を取得したからといって、年収や給料が大幅に増えることはありません。
そのため、技術士資格を活かせる企業探しは必要不可欠と言えるでしょう。
大手のコンサルティング会社に転職する
技術士の多くがコンサルティング会社で活躍しています。
下記の規模別年収データを見ると、企業規模が大きいほど収入が高い傾向です。
| 企業規模(合計) | 年収 | 月収 | ボーナス |
| 10人~99人 | 606万3300円 | 42万3700円 | 97万8900円 |
| 100人~999人 | 668万6000円 | 42万6200円 | 157万1600円 |
| 1000人以上 | 752万600円 | 47万4200円 | 183万200円 |
10人~99人規模の企業と1000人以上の企業を比べると、140万円以上の差が生じているのが分かります。
技術士として年収アップを目指すなら、大手企業に就職・転職するのも一つの方法です。
実務経験を積んで管理職に就けば、さらなる年収アップも見込めるでしょう。
資格手当が支給される会社に就職する
資格手当を多く支給している企業を探すのも年収アップに繋がるでしょう。
資格手当の相場は2万円ほどとされており、毎月の技術士手当を10万円としている地方企業もあります。
月々の手当支給額を年換算すればかなりの金額になるため、資格手当の有無を確認しておくと良いでしょう。
さらに会社に勤めながら技術士を取得すると、合格のお祝い金を出す企業も少なくありません。
技術コンサルタントとして独立する
技術コンサルタントとして独立するのも年収アップを狙える方法の一つです。
技術士を取得すると、多くの分野で「技術コンサルタント」として働けます。
多くのクライアントと信頼関係を築き、実績を積むことで、独立後も継続的に仕事を受注できるようになれば大幅な収入アップに繋がるかもしれません。
また、企業が技術コンサルタントを雇うと顧客からの信頼度が増します。
新規案件を獲得できるチャンスが生まれるため、企業にとっても大きなメリットです。
技術士を技術アドバイザーとして登録する企業も年々増えており、技術士は多くの企業から必要とされています。
技術コンサルタントは今後ますます求められる人材であり、さらなる年収アップも期待できるでしょう。
他の国家資格を取得する
技術士以外にも資格を取得することで資格手当が増え、年収アップに繋がる可能性があると言えるでしょう。
技術士資格を取得していると、国家試験において一部の科目が免除となる優遇制度が設けられています。
優遇の対象となる国家資格は、弁理士、労働安全コンサルタント、消防設備士、処理施設技術管理者などさまざまです。
技術士の資格を足がかりにして他の国家資格を取得し、さらなるキャリアアップを図り、年収アップへと繋げていきましょう。
技術士試験対策におすすめの過去問・テキスト
技術士試験対策におすすめの過去問やテキストをご紹介します。
出題傾向は最新の状況に合わせて変化するため、最低でも直近3年分の過去問をこなしましょう。
技術士第一次試験基礎・適性科目完全制覇【改訂2版】/オーム社

(引用元:amazon.co.jp)
本書は、基礎・適性科目に特化し、一部変更された基礎科目に完全対応しています。
過去問の傾向を分析し、出題頻度の高いキーワードを中心に解説しているのが特徴です。
学習のポイントや予想問題を混ぜながら幅広く載せているため、試験の概要や対策をしっかり把握できます。
過去問と併せて利用することで、さらなる理解力が身に付けられるでしょう。
技術士教科書技術士第一次試験問題集
基礎・適性科目パーフェクト2025年度版
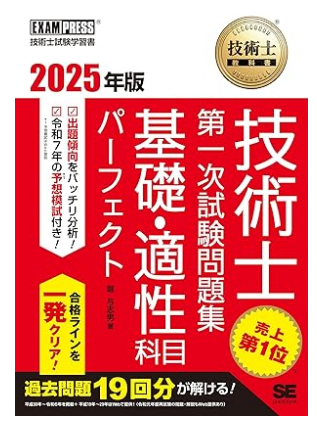
(引用元:amazon.co.jp)
本書は技術士第一次試験3科目のうち、基礎科目と適性科目に対応しており、平成19年度~令和6年度まで、計19回分の過去問題を提供しています。
近年の出題傾向をしっかり分析して作成した予想模試も、読者専用サイトからダウンロード可能です。
初めて技術士一次試験に挑戦する方や、効率的な学習方法を知りたい方、過去問題をたくさん解いて合格力をつけたい方におすすめします。
2023年版ユーキャンの技術士第一次試験
◆基礎・適性◆過去問完全解説&予想模試

(引用元:amazon.co.jp)
本書は、一次試験基礎科目・適性科目の令和~平成26年度までの過去問と、令和5年度の予想問題を収録しています。
過去7回分の出題傾向を年度と出題テーマを表にしており、各群の頻出事項を絞って解説しているため、本試験で役に立つ情報が満載です。
基礎科目は難問に対応した解くためのコツを、適性科目は技術士法第4章や製造物責任法など、問われやすいポイントを丁寧に解説しています。
技術士第二次試験◆合格する技術論文の書き方【第2版】

(引用元:amazon.co.jp)
本書は、二次試験の筆記試験に合格に必要な論文の書き方について説明しています。
試験問題からキーワードを抽出し、解答論文への絞り込みを行い、文章展開を具体的に示しているのが特徴です。
日々行っている業務の中でも使用できるよう、技術報告書や技術提案書、業務日誌など、技術論文の要点を示し、論文記述の共通点である「論文の書き方」を分かりやすく理解できます。
日本技術士会のホームページ

公益社団法人日本技術士会公式HPから、過去の試験問題がPDF形式でダウンロード可能です。
一次試験の問題が直近15年分、二次試験に関しては直近6年分が用意されています。
択一式問題の解答は一定期間分用意されていますが、論述式の解答は用意されていません。
また、解説はついていないため解答に至る過程が分からないため、別途問題集などで補う必要があります。
おすすめの勉強方法
技術士試験に合格するための勉強方法について見ていきましょう。
過去問を繰り返す
一次試験は過去問から多く出題されるため、何度も解いて慣れておきましょう。
繰り返し解くことで出題傾向も見えてきます。
問題の傾向を把握できれば、重点的に学習すべきポイントが分かるため、さらに学習が効率化できるでしょう。
また、過去問を繰り返す中で、時間配分を意識することが大切です。
どの問題から取り掛かると良いか、どのくらい時間を掛けられるか、など自身で基準を作っておけば、本試験も落ち着いて問題に取り組めるでしょう。
時間を費やす科目を見極める
技術士試験の範囲は非常に広いうえ、各科目の合格点が決められているため、苦手科目でいかに点数を落とさないかが重要です。
どの科目も万遍なくこなすことも大切ですが、合格点を確実に獲得することを意識しましょう。
たとえば、基礎科目や適性科目よりも専門科目が苦手であれば、専門科目に十分時間を掛け、合格ラインを落とさないよう努めるのが大切です。
時間を費やす科目を見極めることは、合格を勝ち取る最良方法と言えるでしょう。
模擬試験を受ける
筆記試験、口頭試験のどちらについても模擬試験を受けておくことをおすすめします。
実際の試験に近い体験をすることで、本番で発揮できる力を養えるでしょう。
模擬試験の実施機関は、関連する公益社団法人や民間会社です。
ただし、模擬試験はすべての部門で行われていないため、希望する部門の模擬試験を実施している機関を調べる必要があります。
通信講座を利用する
技術士を独学で合格するのは非常に困難であると言えるでしょう。
一次試験は、答えが一つである知識問題のため、過去問やテキストを使って学習すれば、合格できる可能性は十分にあります。
しかし二次試験は解答が一つとは限らず、解答者の数だけ無限に答えが存在するため、しっかりとした対策が必要です。
二次試験では、業務遂行上の課題について自身で考え決断し、行動できる力が問われます。
独学による暗記の知識だけでは、圧倒的に不利だと言えるでしょう。
通信講座なら内容説明の分かりやすさに加え、独学では難しいとされる二次試験の論文対策も万全に行ってくれるため、客観的な判断や視点も得られます。
また、受験申込書から口頭試験まで一貫して学習を進められるため、着実に合格を目指せるでしょう。
技術士の試験対策なら、スタディングの通信講座がおすすめです。
まとめ
技術士の平均年収は男性で673万円、女性で573万円と言われており、生涯を通して安定した収入を得られる職業といえます。
さらなる年収アップを狙うなら、大手コンサルティング会社への転職や他資格取得へのチャレンジ、技術コンサルタントとしての独立などを視野に入れると良いでしょう。
技術士の合格率は10%程度と、税理士や弁理士に続く難易度の高さとなっているため、通信講座やスクールなどを利用し、効率良く合格を目指すのがおすすめです。
これから技術士資格取得を目指す方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
また、技術士の試験対策は通信講座の利用もおすすめです。
技術士 通信講座の詳細は以下の記事もあわせてご覧ください。
→技術士のおすすめ通信講座5選と失敗しない選び方!の記事はこちら










