会社員が住宅購入のためにローンを組むことは一般的ですが、勤務年数や年収などの条件がそろえば借り入れできます。会社と直接雇用契約を結んで信用を得る会社員とは異なり、個人で事業を営む個人事業主の人は、住宅を購入するためのローンを組めるのでしょうか?
そこでこの記事では、個人事業主が住宅ローンを組みにくい理由や審査を通す際のポイント、会社員との審査基準の違い、おすすめの借り入れ先について解説していきます。ポイントや基準の違いを把握することで、審査に対して対策することも可能です。本記事を参考に、個人事業主が住宅ローンを借り入れするのに必要なことを学びましょう。
\\この記事は専門家監修のもと作成しています//
個人事業主が住宅ローンを組みにくい理由

会社員とは異なり、なぜ個人事業主は住宅ローンを組みにくいとされているのでしょう?その理由として、会社員は毎月安定した給料が収入として得られるので、継続した返済能力があると判断されます。対して、個人事業主は景気などの要因で変化が大きく、安定した収入が得られないかもしれません。
その他にも病気やけがなどの休業は、会社員のようには保障されないのでより不安定になりやすく、会社員とは住宅ローンの審査基準が違います。そのため細かく審査していく必要があり、個人事業主への融資は消極的になる金融機関は多いです。
住宅ローンで困ったときの相談先について詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。

個人事業主の住宅ローン審査ポイント8つ
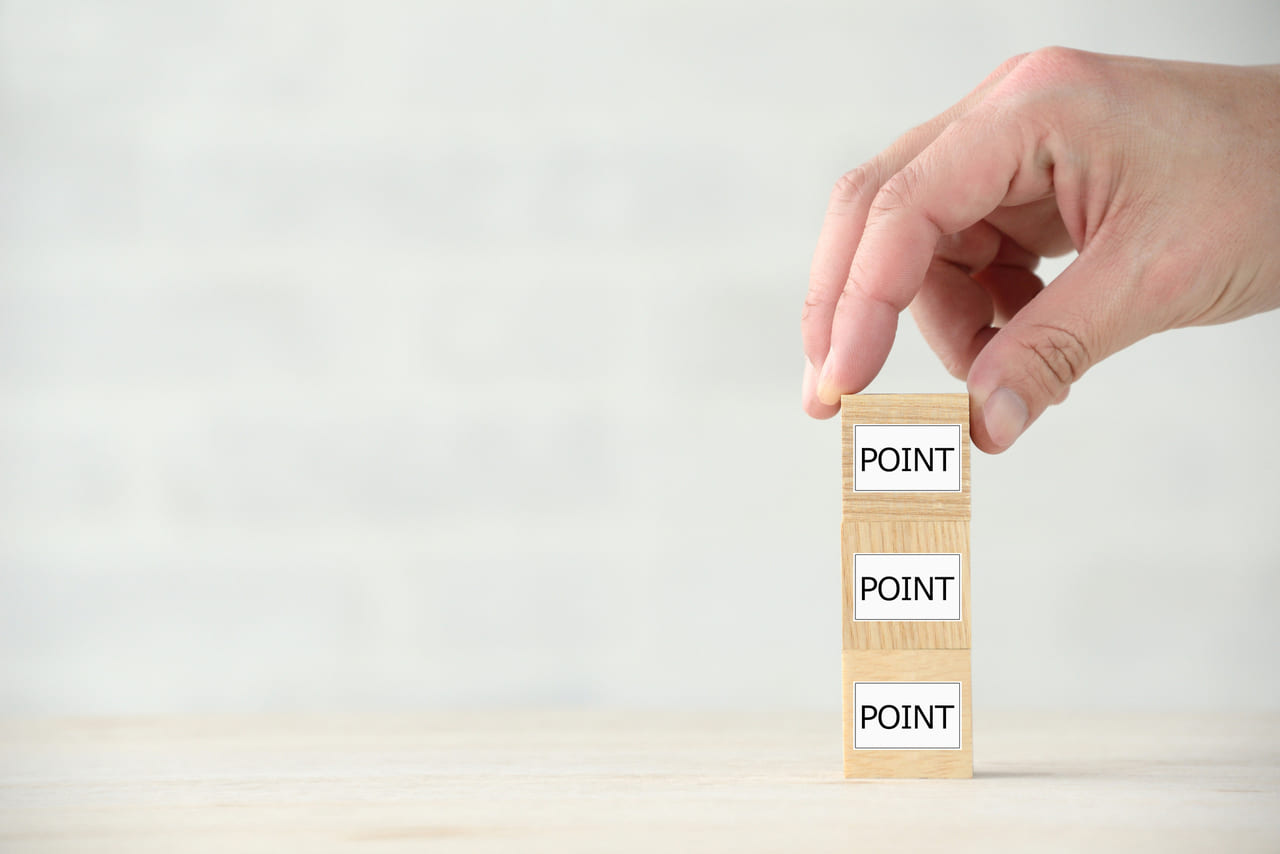
次に、個人事業主が住宅ローンを申し込んだときの審査ポイントを8つ紹介します。注意点も合わせて説明するので、自身の条件と照らし合わせてみることで、審査が通りにくい状況かどうかわかるでしょう。
- 所得に関するポイント
- 他に借入や滞納の問題がないか
- 税金の支払いに問題はないか
- 借入金額の限度額
- 頭金などの自己資金について
- 借入時の年齢や健康状態
- マイホームを事業所兼用にする場合の注意点
- 物件価値について
では、一つずつポイントを確認していきましょう。
所得についての審査ポイント
ここでは、個人事業主が住宅ローンを借入する際の所得に関する審査ポイントを解説します。個人事業主の所得審査で見るポイントは大きく分けて2つあります。ポイントを押さえることで、審査に通りやすくなるでしょう。
所得額が審査基準を満たしていること
住宅ローンの第一に重要な審査ポイントは所得額についてです。ここでいう所得とは、個人事業主の売上イコール所得のことではなく、売上から保険料などの経費を引いた金額が審査の対象になります。
個人事業主は、収入を得るために必要な費用を経費として計上しますが、必要以上に多く計上して所得額が少なくなってしまうと、審査が難しくなることに注意してください。仮に審査に通ったとしても、所得が少なくなるので借入金額も減ります。
所得が安定していること
会社員が借り入れをするときは基本的に前年度の所得額を見ますが、個人事業主は前年度だけでなく直近3年分の所得について審査をします。審査時には、直近3年分の確定申告書や決算書の用意が必要です。
事業開始から3年以上経っていることや、連続して黒字になっている必要もあります。さらに所得が安定していない場合は、所得額が一番低い年度を基準とする可能性もあるでしょう。
住宅ローン以外の借り入れに滞納がないこと
自動車ローンなどの他の借り入れや、クレジットカード・キャッシングの利用歴や返済状況は、個人信用情報機関で管理しています。金融機関から借り入れを行う際は、申込者の審査にこの機関の情報を利用しますが、滞納や債務整理がある場合は審査が難しくなるでしょう。
税金や健康保険料の滞納がないこと
住宅ローンの申込には各種税金や健康保険料の他に、国民年金保険料の滞納情報を知るために、金融機関へ納税証明書の提出を求められます。税金や各種保険料の滞納は、信用情報機関に問い合わせてもわかりません。よって、滞納状況を知るために納税証明書を必ず確認します。
滞納がある場合は審査に影響するので、申し込み前に滞納があれば必ず支払いを済ませましょう。また、過去に借り入れや滞納をした人は、審査を申し込む前に信用情報機関に問い合わせてみてください。もし滞納歴が残っている場合は、審査に通りにくい可能性があります。
借入金額が多すぎないこと
個人事業主は、どのくらいの金額まで住宅ローンの借り入れができるのでしょう?一般的に金融機関では、住宅ローンの借り入れ上限の返済比率は、年収の35%としている金融機関が多いです。
返済負担率は、以下の計算式で求めることができます。
自分の返済能力に対して、借入金額がこれを上回った金額になると審査は難しくなります。
住宅ローン借り入れ時の目安になる金額やおすすめの金利については、以下の記事で解説しています。より詳しく知りたい人はご覧ください。


自己資金があること
個人事業主は会社員よりも得られる収入が不安定なため、安定性が不安視されます。審査に通るためには、住宅購入代金の頭金を多めに準備しておくべきでしょう。頭金が多ければ毎月の返済額や借入額も減り、審査のときに金融機関の印象が良くなる可能性があります。
また他の借入金がある場合は、少しでも返済して借入金の金額を減らしておきましょう。
年齢や健康状態に問題がないこと
住宅ローンには借入時の年齢要件があり、上限75歳までとしている金融機関が多いです。また完済時の年齢も80歳未満としているところも多いため、他の要件を満たしていても借入時や完済時の年齢が要件から外れていれば、借りられない場合があることに注意しましょう。
借入時には、ほとんどの金融機関で団体信用生命保険の加入を条件としています。団体信用生命保険とは、住宅ローン契約者が亡くなったときや重度障害を負ったときに、その後の支払いが免除される保険です。生命保険加入時と同様に、加入時には健康の告知をする必要があります。万が一、健康上の問題ありとなって加入できないときは、住宅ローンの借り入れが難しくなるでしょう。
住宅ローンは何歳まで組めるのかについて、さらに詳しく知りたい方は下記の記事を読んでみてください。

事務所兼用なら住居部分が1/2以上であること
個人事業主が住宅併用事務所として、住宅ローンを借りるケースがあります。住宅の規模に対して、一区画程度なら問題はありませんが、事業用の区画が2分の1以上になっていれば住宅ローンは原則、適用されません。
なぜなら、住宅ローンというのはあくまでも住居用のローンであり「床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するもの」と定められている金融機関が多いためです。住居面積が2分の1以上であれば、住宅ローンが使える期間はあるので確認してみてください。
物件価値が低すぎないこと
住宅ローンを万が一返せなくなったときを想定し、融資する側は物件を担保として貸し倒れのリスクを防ぎます。このときの物件の担保とは土地と建物の両方を指し、その価値を金融機関は審査します。
現代建築基準に合わない建物のことを「既存不適格建築物」といいます。そのような物件に該当する建物や物件の築年数が古い場合は、担保としての価値が低くなってしまいます。その場合は、住宅ローンが組めないか借入額の減額、または金利が高くなることがあります。既存不適格建築物や借地権の物件は、審査が厳しくなるか融資を受けられなくなることに注意してください。
個人事業主なら2つの金融機関から選ぼう

個人事業主が住宅ローンを利用する金融機関選びにはポイントがあります。金利の安さやサービスで選ぶことも大切ですが、審査が通りやすい金融機関選びや商品選びも重要です。ポイントを理解し、住宅ローンを借り入れる金融機関選びの参考にしてください。
取引がある金融機関を選ぶ
すでに事業で付き合いがある地元の金融機関があれば、相談してみるのもよいでしょう。付き合いの長さによっては融資してくれる可能性があります。
個人事業主としての所得は少ないものの世帯としての所得が多い場合や、設備投資など事業に必要な出費をしたばかりの場合は、個人事業主向けの住宅ローンに特化した金融機関に相談するのもひとつです。また、節税対策のためにあえて赤字決算とした場合は、審査が通ることもあるでしょう。
ローン審査が甘い金融機関について、さらに詳しく解説した記事があるのでご覧ください。

フラット35を選ぶ
住宅ローンの借入先として「フラット35」を選ぶことも一つの手でしょう。フラット35というのは、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して融資を行う機関で、全期間固定金利の住宅ローンです。
金融機関は直近3年分の所得を見て審査しますが、フラット35では1年分を見るため借り入れがしやすいので検討してみましょう。
フラット35の特徴
フラット35の特徴を他の金融機関と比較してみました。
| 項目 | フラット35 | 他の金融機関 |
| 保証料 | 不要 | 必要 金利上乗せタイプ0.2% 一括前払いタイプ2%が多い |
| 金利タイプ | 全期間固定金利のみ | 自分で選択する |
| 審査基準 | 総返済負担率が基準 年収400万円未満は30%以下 年収400万円以上は35%以下 |
年収ではなく収入の安定度が基準 |
| 建物の基準 | 技術基準を満たすこと | なし |
| 団信の有無 | 任意 | 必須 |
| 繰り上げ返済手数料 | Web、窓口共に無料 | Webは無料の場合が多い |
フラット35と他の金融機関の住宅ローンの違いは上記の通りですが、特に違う点について下記で詳しく説明するので、住宅ローン選びの参考にしてください。
- 金利タイプ
フラット35は借入時の金利が、返済終了時までずっと一定になっているタイプです。他の金融機関は、全期間固定金利型・金利変動型・固定金利期間選択型の3種類が用意されていることが多く、申込時に契約者が選択します。
- 建物の基準
他の金融機関での住宅ローン借り入れには、建物の基準は特にありません。対して、フラット35では独自に建物の基準を設けています。新築戸建住宅は広さが70㎡以上、マンションは広さが30㎡以上であること、そして購入金額や竣工からの年数制限、中古物件は新耐震基準を満たしていることが条件です。
低金利ローンランキングを紹介した記事があるので、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

個人事業主の住宅ローン申請の申し込み方

個人事業主が住宅ローンを申請する流れや必要な書類について解説するので、よく読んでスムーズに申請できるようになるでしょう。
住宅の売買契約を結ぶ
住宅ローンの借り入れを申し込む前に、買いたい住宅の売買契約を結びます。購入する物件を担保として融資を行うため、契約する前に住宅ローンの申込みはできないことに注意してください。
売買契約を結ぶ前には自己資金がどのくらいあるのかや、毎月返済できる金額について調べておくことをおすすめします。
住宅ローンを組む際の返済目安について詳しく知りたい人は、以下の記事もおすすめです。

金融機関に住宅ローンを申し込む
売買契約を締結したら金融機関に住宅ローンの申請をしますが、住宅ローン審査後の審査の進み方は以下のとおりです。
- 事前審査(1週間程度)
- 正式に申し込み→本審査(10日~2週間程度)
- 審査結果の連絡がくる
- 住宅ローン本契約
- 引き渡し時に住宅ローン実行
申し込み前に以上の流れを知っておくことをおすすめします。また、申込みの流れの中で知っておきたいことがあります。
事前審査には1週間程度かかることが多いですが、個人事業主の場合は長くなることがあります。事前審査に通ったあとは、申込みをして本審査が行われます。本審査に進めても審査に通らないこともありますが、そのようなときは、売買契約時に契約が解除できる住宅ローン特約が付いているかを確認してみてください。
個人事業主のローン審査で必要な書類
個人事業主が住宅ローン審査を受けるときに、必要な主な書類は下記の通りです。必要な書類をあらかじめ準備しておくとよりスムーズに進むので、準備できるものはしておきましょう。
- 確定申告書3期分
事前審査・本審査両方に必要
付表も必要で申告を行った税務署の受付印が必要
e-TAXで行った場合は受領メールが受付印の代わりになる - 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなどの写真入り、健康保険証のコピーなど)
- 借入償還表(他に借り入れがある場合)
- 売買契約書や重要事項説明書
住宅ローンの基礎についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

個人事業主でも利用できる住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して購入した場合に確定申告を行うことで、ローン残高に応じた所得税の軽減や還付が行われることです。会社員が住宅ローンを利用して購入したときと同様に、個人事業主も住宅ローン控除は利用できます。会社員とは違う条件や注意点がありますが、所得の確定申告を行うことで控除できることを知っておきましょう。
住宅ローン控除を受けるための条件
住宅ローン控除を受けるためには条件があり、適用されるためには細かい条件を全て満たす必要があります。その条件は以下のとおりです。
- 新築もしくは取得日より半年以内に居住を開始し、住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで居住していること
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
- 居住する住宅の床面積が、50㎡以上であり、床面積の1/2以上が自身の居住部分であること
- 中古物件の場合は築20年以内(マンションは25年)、または耐震基準適合証明や住宅性能評価等を受けていること
- 身内から購入した物件でないこと
個人事業主が特に注意したいのが、住宅の床面積の2分の1以上が自己居住用であるということです。2分の1以上が自己居住用ではないときは、住宅ローン控除は受けられません。
個人事業主の住宅ローン控除に必要な書類
住宅ローン控除の申請1年目は、確定申告書に以下の書類を添付する必要があります。2年目以降は年末残高証明書のみ添付が必要です。2年目以降は、税務署より住宅借入金等特別控除の計算明細書が送付されます。
| 書類 | 入手先 |
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 | 住宅ローン借入先の金融機関 |
| 登記事項証明書 | 法務局 |
| 売買契約書 | 契約時に不動産会社から発行される |
| 住民票 | 東京都の場合は区役所、市町村役場 |
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務局、国税庁のサイトでダウンロード |
住宅ローン控除の対象は住宅部分のみ
個人事業主は住宅併用事務所として借りるケースがありますが、住宅ローン控除を利用する際に気をつけたいことは、住宅ローン控除は住居として使われている部分のみ適用されるということです。事務所や店舗としての部分は、住宅ローン控除の対象外です。
例えば、自宅が60%で事務所が40%という割合で使用していて、事務所の分を経費として計上している場合は、自宅としての割合である60%が住宅ローン控除を適用されることになります。事業使用割合を10%以下にしているなら、すべて住居としてみなされるので全額住宅ローン控除の対象です。
控除額と期間の目安
住宅ローン控除は控除できる期間と金額が決まっていて、控除金額は居住開始年月日によって異なり、控除期間は最大10年までです。
例として2021年1月から2021年12月31日までに、居住を開始した場合の控除金額の計算方法を説明します。
- 控除限度額は40万円まで
- 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
- ただし、長期優良住宅や低炭素住宅など認定住宅の場合は、控除限度額は50万円
- 住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円
住宅ローンについてさらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

まとめ

個人事業主が住宅ローンを組みづらい理由は、収入の不安定さが大きな要因です。個人事業主が住宅ローンを組むときの審査のポイントを知ることで、通りやすい状況にできるでしょう。
手続きの流れや必要な書類を事前にそろえることで、よりスムーズに手続きを行えます。個人事業主が住宅ローンの借り入れ機関を選ぶ際は、フラット35を利用したり事業で付き合いのある金融機関に相談したりすることで、借り入れがしやすくなります。
会社員と同様に住宅ローン控除は利用できますが、個人事業主に多い事業併用住宅の場合は、2分の1以上の面積が自己居住用であることで利用可能です。本記事を読むことで、スムーズに住宅ローンを利用でき、住宅ローン控除が受けられるようになるでしょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。

西崎さん.jpg)

