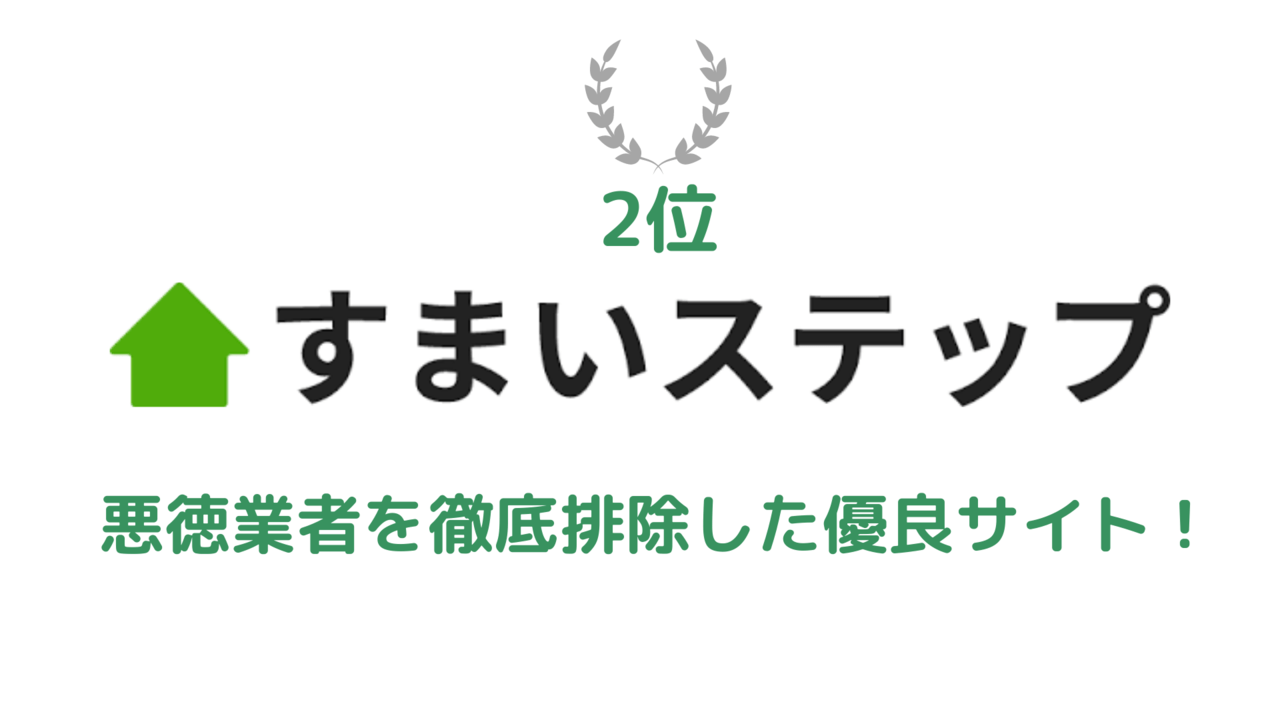マンション売却を検討している方の中には、「築10年目が売り時」と耳にした方も多いのではないでしょうか。
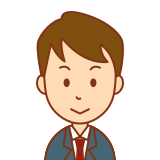
マンションの売却額は築年数とマンションを建てたエリアに左右されます。築年数の観点から言えば、不動産は築10年を境に売却相場が大きく変わる傾向にあります。
本記事では、「マンション売却額が築年数ごとにどのように変化するのか」「なぜ築10年が重要となるのか」について解説します。また、エリアごとの売却相場の動向、売却価格の調べ方、マンション売却の流れについても紹介していきます。
とくに「マンションの売却経験がなく、何をもとに考えたらよいのか分からない」という方にとって役立つ内容になっているため、ぜひ参考にしてください。
不動産一括査定サイト利用者が選んだおすすめサービスTOP3
この記事を読まずに、先におすすめの査定サービスを知りたい人におすすめなのが、以下の3サービスです。
※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)
築年数によってマンション売却額はどう変わる?

それでは、築年数によってマンション相場がどのように変動するかを見ていきましょう。不動産流通機構が運営するレインズ(REINS)のデータによると、築年数によって売却額は上記のように下落していきます。
具体的な数値を抽出すると以下のようになります。
| 築5年以内 | 築10年以内 | 築20年以内 | 築30年以内 | 築30年以上 | |
| 売買価格 | 6,018万円 | 5,214万円 | 4,212万円 | 2,108万円 | 1,872万円 |
| ㎡単価 | 90.8万円 | 76.9万円 | 57万円 | 33.8万円 | 32.9万円 |
”参考:東日本不動産流通機構レインズ「首都圏中古マンション・中古戸建て住宅 地域別・築年帯別成約状況【2020年7〜9月】」より価格データを抽出”
時間の経過とともに、売買価格が大きく変わっていくことが分かります。
次にこの表を参考に、マンションの売却相場を築年数別に詳しい動向をご紹介します。ぜひ、ご自身が売却予定のマンションの築年数と照らし合わせてご覧ください。
なお、築年数ごとのマンションの売りやすさに関してより詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。

築10年以内のマンションは5年以内に比べ約15%下落
築10年以内のマンションは築浅物件とされ、とくに築5年以内は新築時の価格から大きく変わらない価格で売却が可能と言われています。割合としては、新築価格の8割程度となるケースが多く見られます。
ただし、例えばそのエリアの土地開発が進み、商業施設の開業や利便性の改善などがあった場合、状況によっては新築時よりも高額で売れる可能性もあります。
また、築6~10年になると、築5年以内に比べて1㎡あたりの単価が約15%低下する傾向があります。築5年未満のマンションを所有していて、売却を検討中の方は覚えておくとよいでしょう。
築20年以内のマンションは築浅より約20~35%下落
築11〜20年となると、築浅の物件より約20~30%程度、価格が下落すると予想されます。この場合でも、駅近や施設の近くなど、周辺環境の利便性が良ければこの水準よりも高く売れる可能性があります。
また、マンションなど耐火建築された建物に関しては、築25年まで住宅ローンの控除が適用できる制度があります。買主からすれば、控除をできるだけ長く受けられた方が税金が安くなるため、築25年に近づくほど、マンションは需要は少なくなります。
”参考:国税庁「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」”
築30年以内のマンションは築浅より約55%~60%下落
築21〜30年のマンションは、築浅の物件の半分以下に価格が落ちるとされています。なぜなら、築年数21年以上になると修繕やリフォームが必要になってくる場合が多いためです。修繕にかかる費用の分、必然的にマンションの売却額も下げることになります。
さらに、築25年を超えてくると前述した住宅ローンの控除も受けられなくなり、内装や設備の経年劣化により価値がさらに低下します。築21〜30年のマンションはよほど好条件が揃わない限りは半額以上での取引は難しいと考えておく必要があるでしょう。
築31年以上のマンションは築浅より約60%下落
築31年を超えるマンションの売却相場は、法定耐用年数が迫っていることからも築浅に比べて60%以上価格が下落すると言われています。中でも古い物件の場合は、室内も目に見えて劣化や設備機能の低下が目立つことが多いため、リフォームがほとんど必須になってきます。
また、耐震対策も建物の寿命に関係してくるため、1981年以降に建築された新耐震基準がマンションに適用されているかによっても査定額は左右されます。そのため、築31年を超えたマンションの場合は新耐震基準であるか確認しつつ、リフォームをしてから売却することも視野に入れて検討するとよいでしょう。
中古マンションのリフォームについて、費用相場は以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

マンション売却が狙い目の築年数は?
ここまでのデータをまとめると、築10年~築20年までは価格の下落差が大きく、21年を超えてからは比較的緩やかになっていることが分かります。築10年までなら、元の価値を比較的削ぐことなく売れる可能性が高いですが、築20年が迫ってくると控除期限や建物の劣化の影響を大きく受けてしまうのです。
マンションを高く売却できるかは築年数10年がターニングポイントとなり、築20年を超えるとそれなりに低い価値になってしまうと覚えておきましょう。
マンション売却を築10年以内におこなうメリット

ここまで、マンションは価格の下落幅が比較的少ない築10年以内のうちに売却したほうが利益を上げやすいことを説明しました。
とはいえ、「高く売れるのは分かったけれど、それだけで売却を決めてしまってもよいの?」と感じる方もいるのではないでしょうか。
実は、マンションを10年以内に売却することには、価格面以外にも以下のようなメリットがあります。
- 長く住むことができるので買い手が見つかりやすい
- 売却時のリノベーションが必要ない
- 修繕積立金の負担を抑えられる
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
長く住むことができるので買い手が見つかりやすい
建物には法定耐用年数という建物自体の寿命を意味する年数が設定されています。耐用年数は建物の構造や用途によって異なりますが、例えば鉄骨造の住宅用建物であれば47年が寿命とされています。そのため、築年数10年以内は築浅物件の部類になるのです。
仲介をする不動産業者の立場からすると、築10年以内のマンションは長期的に住める物件と言えます。このような物件は、築浅物件を探している、もしくは安価な中古マンションを探している顧客に対して広く営業を行うことができるので、買い手が見つかりやすくなります。
”参考:国税庁「耐用年数(建物/建物附属設備)」”
耐用年数についての詳しい情報は、こちらの記事もおすすめです。

売却時のリノベーションが必要ない
通常、中古マンションを売却する際にはリフォームを行うことも多いですが、築10年以内のマンションであれば劣化も少なくそのままの状態で売却しやすいというメリットがあります。
マンションのデザイン、設備、セキュリティシステムなども、10年たてば最新のモデルとの違いが大きくなります。もちろん買い手側がリフォームをする場合もありますが、できるだけ修繕の必要がない比較的新しいマンションのほうが好まれる傾向があるのです。
マンション売却時にリフォームをする場合の費用については以下の記事も参考にしてみてください。

修繕積立金の負担を抑えられる
もし築5~10年以内にマンションを売却したとしたら、修繕積立金の負担額を小さくすることができるというメリットもあります。
修繕積立金とは、マンションで入居者(所有者)が管理会社に大規模なメンテナンスを行ってもらうために毎月積み立てるお金です。売主側がマンションを売りやすくするために最初は安く設定されており、徐々に高くなっていくのが一般的です。
値上げのタイミングは5年・10年単位などで設定されているため、なるべく早めのタイミングで売却したほうが費用の負担を抑えることができます。そういった意味でも築10年以内にマンション売却がおすすめといえます。
また、この修繕積立金は引き継がれるため値上がりは買い手に告知しなくてはなりませんが、値上げ前に売り出すことで安く見せることが可能となります。
マンションの修繕積立金の仕組みについては、下記の記事で具体的に解説していますのでご一読ください。

エリアによるマンション売却相場の違い

ここまで、早期にマンション売却をするメリットについて解説してきました。
マンション売却について本格的に考えているのであれば、マンションがあるエリアごとの売却相場についても知っておきましょう。
以下の表に、レインズの不動産取引のデータをもとに、マンションの取引数が多い東京、大阪、福岡、札幌などの都心部の売却相場をまとめました。ぜひ参考にしてください。
| エリア | マンション売却相場 |
| 東京 | 約4,481万円 |
| 大阪 | 約2,450万円 |
| 福岡 | 約1,811万円 |
| 札幌 | 約1,971万円 |
”参考:東日本不動産流通機構レインズ「マーケットデータ全国版【2019年】」より価格データを抽出”
東京のマンション価格は全国的にも高めの相場となっており、売却価格も比較的高い傾向があります。一方、同じ都心部でも大阪、福岡、札幌などは東京の半額程度のマンション売却額となっており、大きく違いが出ていることがわかるでしょう。マンション売却では、こういったエリアの相場も加味した価格設定も行う必要があります。
マンションの売却相場を調べる方法は?

ここまで築年数別や都心のエリア別のマンション売却相場をご紹介してきました。
ただし、これまでの情報はあくまで平均的なデータです。売却をするか判断するためには、所有するマンションと類似する物件がおよそいくらで売却されているのか、より詳細な相場を調べる必要があります。
所有するマンションの売却価格を調べるためには以下の3つの方法があります。
- レインズで調べる方法
- 土地総合情報システムで調べる方法
- 不動産売買のポータルサイトで調べる方法
ここからはそれぞれの調べ方を解説していきます。
レインズで調べる方法
レインズとは、国土交通省から指定を受けて不動産流通を管理している公益財団法人です。レインズでは過去の不動産取引から直近の取引記録までのデータを公開しており、マンションの売却相場もここから検索することができます。さらに築年数、地域別、平米単価などカテゴリー別にも相場を見ることができるため、細かく比較したい場合にも向いています。
また、レインズは東日本、西日本、中部、近畿ごとにサイトがあるので、見当する地域のサイトで公開しているマーケットデータもあわせてご覧ください。
土地総合情報システムで調べる方法
土地総合情報システムは、国土交通省の運営する不動産売買の価格情報をデータ化した検索サイトです。実際に取引された土地や建物の情報を見ることができます。具体的には不動産の取引価格、地価公示、都道府県地価調査の価格などの項目を回覧が可能です。マンションの売却相場は不動産の取引価格から検索して確認してみましょう。
不動産売買のポータルサイトで調べる方法
不動産のポータルサイトを使って、売却相場を調べることも可能です。SUUMOやat home、HOME’sなど、大手の不動産売買のポータルサイトでは、エリア・面積・間取りなどの条件をもとに、マンションの売却相場を分かりやすくまとめられています。所有するマンションと同じ条件のマンションがどれくらいの価格で売却されているか、参考にしてみるとよいでしょう。
マンション売却のおおまかな流れ

自身のマンションの相場を把握して売却を決意したなら、具体的に手続きを進める必要があります。ここからは実際のマンション売却の流れを解説していきます。主な売却手順を下記にまとめました。
- 売却準備を進める
- 複数社に査定依頼を出す
- 仲介業者を決めて媒介契約
- 内覧の準備や対応をする
- 買い手が決まったら売買契約を結ぶ
- 引き渡し
それぞれについて、順番に確認していきましょう。
1.売却準備を進める
売却準備では大きく分けて以下3つのポイントがあります。
- 資金計画を立てる
- 必要書類を用意する
- 管理費など未納分を支払う
特に1つ目の資金計画は最も重要なポイントとなります。例えば住宅ローン残高の有無、残っている場合はマンションの売却収益で完済しきれるのかは重要です。また、買い替えの場合は売り・買いどちらが先行なのか、売却収益を新しい物件の購入費用に充てられるかなど、経済面の計画をしっかり立てておく必要があります。
マンション売却の手順や流れに関してはこちらの記事もおすすめです。

必要書類一覧
マンションの売却では、主に以下の基本的な書類が必要となります。
- 登記済権利証か登記識別情報
- 身分証明書(運転免許証や健康保険証)
- 間取り図
- 管理規約や使用細則
- 重要事項に関する調査報告書
- 固定資産税納税や都市計画税納税通知書
- 固定資産評価証明書
- 実印
- 印鑑証明書
- 預金通帳
これに加えて場合によっては住民票や戸籍付表、ローンの残高証明書や新築時のパンフレットなども必要になる場合があります。実際に売却する時になったら、予め不動産会社などに確認するようにしましょう。
マンション売却での必要書類について、詳しくはこちらの記事も参考にしてみてください。

2.複数社に査定依頼を出す
次に複数の不動産会社へ査定依頼を行います。資金計画を練ったり売却価格を決めるためには、自身のマンションがどれくらいの価値を持つのか査定をし、把握しておかなくてはなりません。
この際、1つだけでなく、複数の不動産会社へ査定依頼をすることがポイントです。1社だけに依頼する場合、相場とは異なる査定金額を提示されても気づくことができません。複数社に依頼することで、適正な査定金額を把握することができます。また、不動産会社の得意分野、担当者の対応力や信用度も比較し、もっとも信頼できる会社に売却を依頼できます。
複数社に依頼するなら一括査定サイトの利用がおすすめです。サイトによって査定依頼できる会社が異なることもあるので、いくつかの査定サイトを併用してみるのもよいでしょう。
おすすめの一括査定サイトは「すまいステップ」

- 初めてで不安だから実績のあるエース級の担当者に出会いたい
- 厳選された優良不動産会社のみに査定を依頼したい
- 悪徳業者が徹底的に排除された査定サイトを使いたい
\ 厳選した優良会社に査定依頼 /
すまいステップで一括査定する
一括査定サイトの選び方について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

3.仲介業者を決めて媒介契約
信用できる不動産会社を見つけたら、いよいよ媒介契約に進みます。媒介契約とは、不動産会社が売り手・買い手と結ぶ契約のことです。
媒介契約には以下の3種類があります。
| 項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
| 複数社との契約可否 | 可 | 否 | 否 |
| 自己発見した買い手との取引可否 | 可 | 可 | 否 |
| レインズへの登録義務 | 任意 | 要(7日以内) | 要(5日以内) |
| 販売活動の状況報告義務 | 任意 | 要(2週間につき1回以上) | 要(1週間につき1回以上) |
一般的に、専任媒介契約は不動産会社に積極的な販売活動の義務が課せられるため、制約は厳しくなりますが、売れにくい物件・ターゲットが絞られてしまう条件を持っている物件に適しています。
一方、一般媒介契約は自由度が高い反面、不動産会社の販売意識が低くなり、他により良い条件での契約があれば後回しにされてしまうケースもありますので、立地や物件の状態が良く売れやすい・自分でも買い手を見つけられそうな心当たりがある、という方におすすめの方法です。
自身の所有物件の状態や環境を考慮し、適切な媒介契約を選びましょう。
4.内覧の準備や対応をする
媒介契約を交わしたら、販売活動の準備に入ります。不動産会社のホームページやチラシ、不動産会社のポータルサイトなどの準備を進めましょう。
また、内覧申し込みがあれば、自身で内覧の対応をする必要があります。その際、気をつけておきたいのは部屋の状態です。内覧に来るのはそこに実際に住むことを想定した顧客なため、清潔感がなかったり散らかっている部屋では購買意欲は沸きづらいでしょう。そのため、部屋は整理整頓し、隅々まで掃除して顧客が買いたいと思える部屋にしておくことが大切です。汚れが目立つ場合はハウスクリーニングをするのも良いでしょう。
当日は人数分のスリッパを用意しておくなど、細かな配慮も忘れずに内覧希望者を迎えるようにしてください。
5.買い手が決まったら売買契約を結ぶ
スムーズに買い手が決まれば、次は買い手と売買契約を締結します。実印・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)、本人確認書類を用意しておきましょう。
また、売買契約の一環として、買い手から手付金の支払いを受けます。手付金とは、売買契約を交わした後に買い手側の都合で解約の申し出があった場合のキャンセル料の意味合いがあり、通常は取引価格の10%程が相場となっています。
6.引き渡し
買い手が無事に住宅ローンの審査に通れば、引き渡しをして晴れて取引終了です。引き渡しの際は、売り手・買い手・不動産会社・司法書士、更に売り手・買い手それぞれの銀行担当者が集まって行われます。
また、一般的に売買契約から引き渡しまでは約1ヶ月程度となるため、その間に不用品の処分、清掃などの退去作業を終わらせ完全に綺麗な状態で引き渡せるようにしておきましょう。
築10年以内のマンションの売り出し方

前章では、マンション売却の流れについて解説しました。
ここでは、築10年以内のマンション売却を成功させるためのポイントをご紹介します。売却活動を始める前にポイントを予習して、効果的な売却計画を立てていきましょう。
競合物件が多いことを念頭に置いて売値を決める
先述したように、築10年以内のマンションは築浅物件として売れやすいため、競合物件が多い傾向があります。
その中でスムーズに売却を進めるには、競合物件の価格を加味しつつ売値を決めることがポイントです。築浅物件を探している人は多いため、相場を無視した極端に高い売値を付けたりしない限り、買い手が見つからないということはまずないでしょう。
また、もし環境や利便性、ブランドなどで他の物件よりも評価できる特性を持っていれば、相場より高値を狙う価値はあります。そのため適正価格をきちんと見定め、相場と価値に見合った売値を検討しましょう。
立地がよければ強気で売り出してもよい
先に少し述べたように、物件の特性によっては相場より高く売れる可能性があります。例えば、以下のような条件を持っているマンションであれば、相場以上の売値を検討する価値は十分にあるでしょう。
- 立地・・・最寄駅から徒歩5分圏内、公共施設の近く、都心部や都市開発が進んだ人気エリア、幹線道路が近い、利便性が高い場所など
- 物件・・・デザイナーズマンションやリノベーション物件などの独自性がある、ペットや楽器可などの希少物件、内装のダメージが少ないなど
- ブランド・・・大手不動産会社の物件、高級思考の分譲マンションなど
例えば、大手不動産会社のブランドはネームバリューもあります。高級マンションだからこその良質な建築技術、デザイン性、充実したサポートなどの安心感が要因となり、査定額アップにつながる可能性が高いでしょう。
マンション売却後の確定申告について
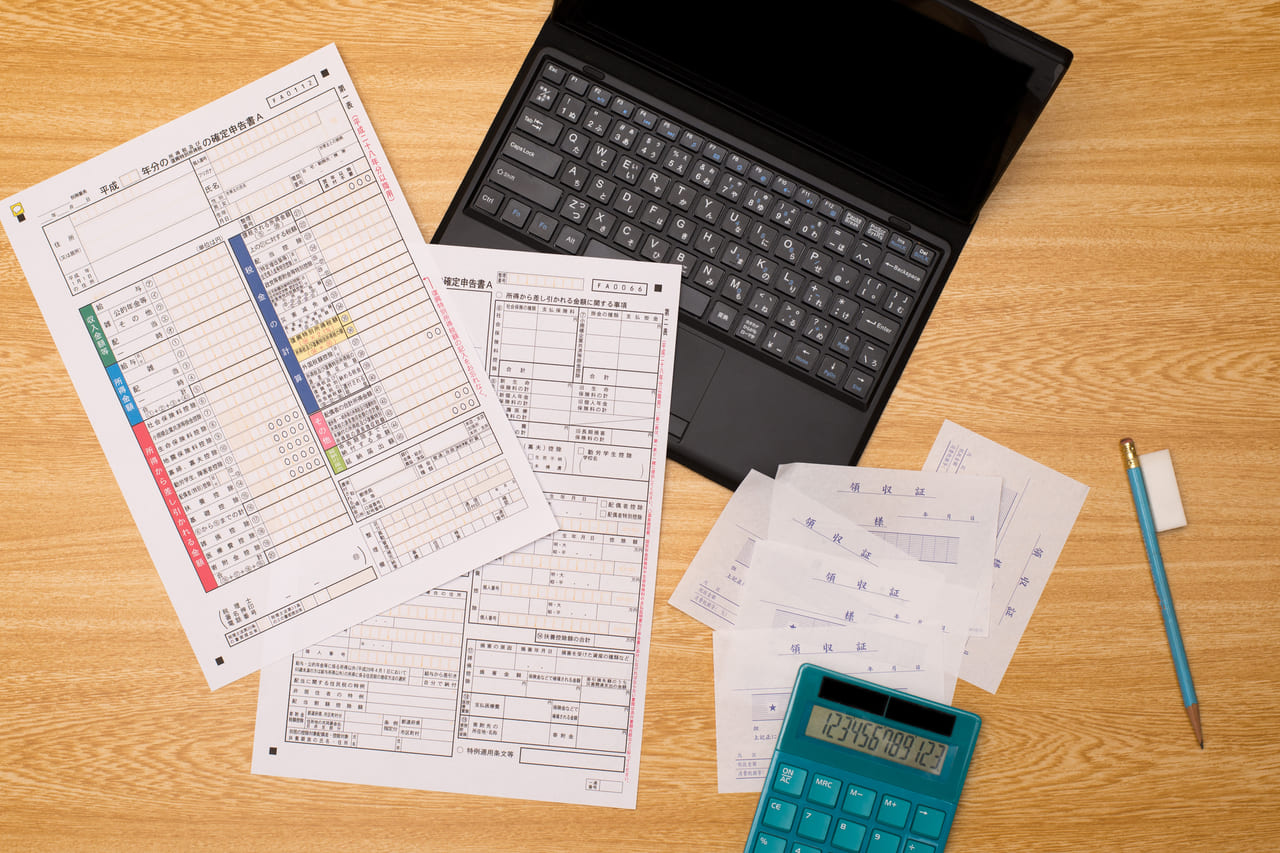
ここまでで、マンション売却の流れや、売り出し方について説明してきました。
しかし、マンションは売却したらそれで終わりではありません。売却によって得た収益は譲渡所得となるため確定申告を行う必要があります。ここでは、次に売却後の確定申告の流れや控除制度について解説します。
売却益が出たら必ず確定申告を行う必要性あり
不動産を手放して得た売却益の確定申告の手続きは、マンションの売却が完了して収益を得た翌年2月16日〜3月15日の間が期限となります。ただ、年度によっては申請期間がずれることもあるため、注意が必要です。申告を怠った場合はペナルティとして延滞税や無申告税などが課せられる場合がありますので、忘れずスケジュールに入れておきましょう。
また、もし売却で利益がない場合は確定申告の必要はありません。
マンション売却の際の確定申告について、詳しくはこちらの記事もご参考ください。

知って得する3つの控除特例
確定申告ではマンション売却により発生した譲渡所得に対し、以下のような特例を使って税金を抑えることが可能です。不動産売却では得られる利益が大きい分、支払う税額も大きくなります。控除制度をうまく活用して少しでも税金を抑えられるようにしましょう。
- 3,000万円特別控除特例…譲渡所得から3,000万円まで控除が可能となる制度
- 軽減税率特例…10年以上所有した不動産を売却した際に軽減税率が適用される制度
- 買い換え特例…売却後、住み替えのために新たな物件を購入した際に受けられる制度
特例を利用するための詳しい要件は以下の記事で解説しています。

また、もし住み替えで新しい物件を購入した際には、上記と合わせて住宅ローン控除も検討して下さい。住宅ローンの控除に関する詳しい情報は、以下の記事をご覧ください。

マンション売却でよくある疑問

最後にマンション売却でよくある疑問にお答えします。マンション売却に関わる用語についてや、売れやすい月になどについて解説します。疑問を解決してマンション売却に挑みましょう。
「買い先行」「売り先行」とは?
買い先行と売り先行とは、不動産を売却する際に所有者が家にいる状態で進めるか否かの方法を言います。売り先行は住んでいる状態で売却する方法で、買い先行は先に新しい物件を購入し、古い物件を空にしてから売却する方法です。どちらを選択するかによって買い手の付きやすさや、売主の負担が変わります。
例えば、買い先行は綺麗な状態で内覧ができるために印象が良く買い手が付きやすいという面がありますが、新しい物件との二重ローンとなるために返済負担が重くなるという側面もあります。そのため、負担面の問題からは比較的売り先行が選ばれる傾向があります。それぞれのメリットを検討して選ぶ必要があるでしょう。
築年数に関わらず何月が売れやすいの?
一般的にマンションや戸建物件の取引が頻繫になるのは、以下の月と言われています。
- 2~3月の新学期・新生活などの引っ越しシーズン
- 9~10月の過ごしやすく負担が少ないシーズン
2~3月は4月の新生活に向けて、通学や通勤のために引っ越すことが多いためマンションも売れやすい傾向にあります。また、2~3月よりは劣るものの、9~10月も、夏が過ぎて過ごしやすくなるために、引っ越しする際の負担が少なくなることから需要が高まる月です。もし可能なら、こういった月やシーズンの動向も予め考慮して、早め売却準備を進めておくことをおすすめします。
まとめ

マンションの売却では築年数が重要となり、特に築10年という時期が大きな区切りとなっています。10年を超えると建物の劣化などの影響でマンション自体の価値が下がってしまいます。さらに買い手もなるべく安価でありつつ、綺麗で不具合のない物件を理想としていることからも築10年以内のマンションは魅力的な条件となりやすいでしょう。
とはいえ、立地や物件の状態によっては築年数に関わらず、相場より高値でも買い手がつく可能性もあります。そのため、築10年に近づいているマンションについてはなるべく早く売却を検討しつつ、物件ごとの特徴も考慮して検討していきましょう。
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。