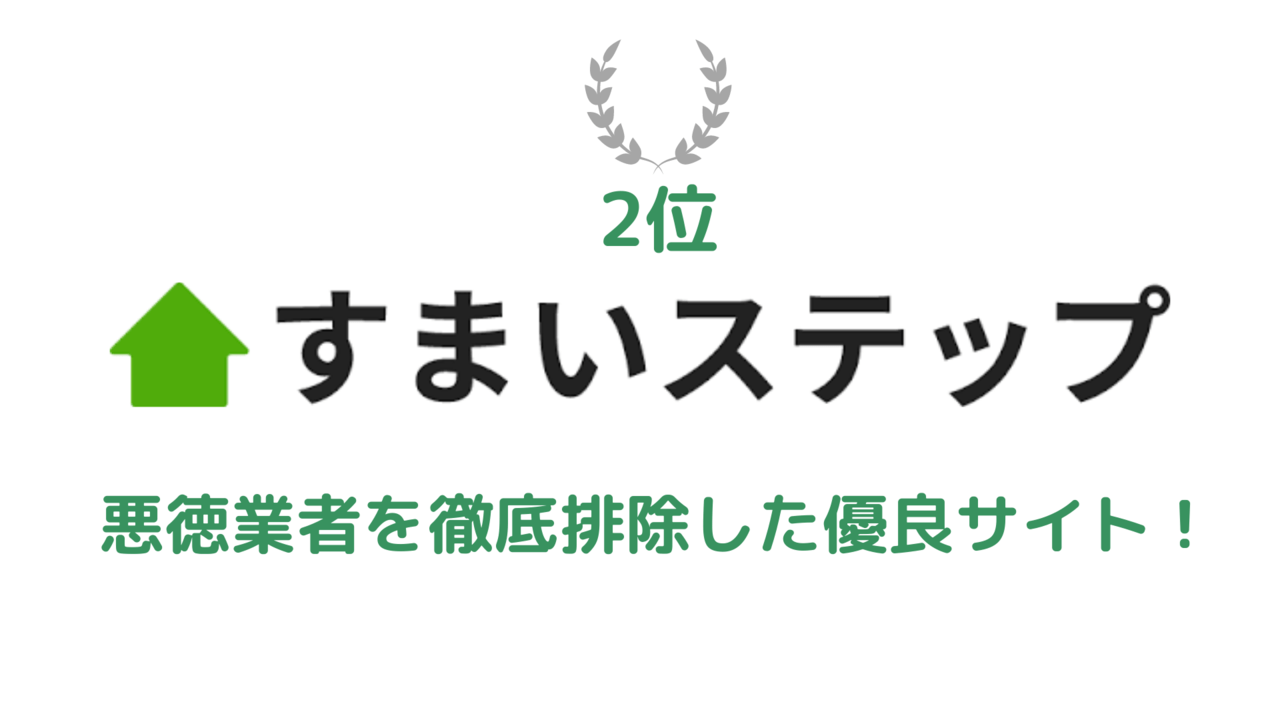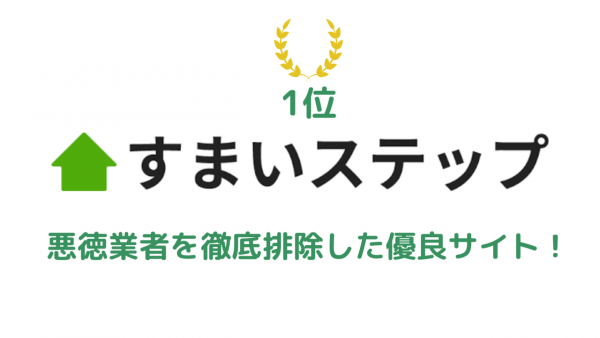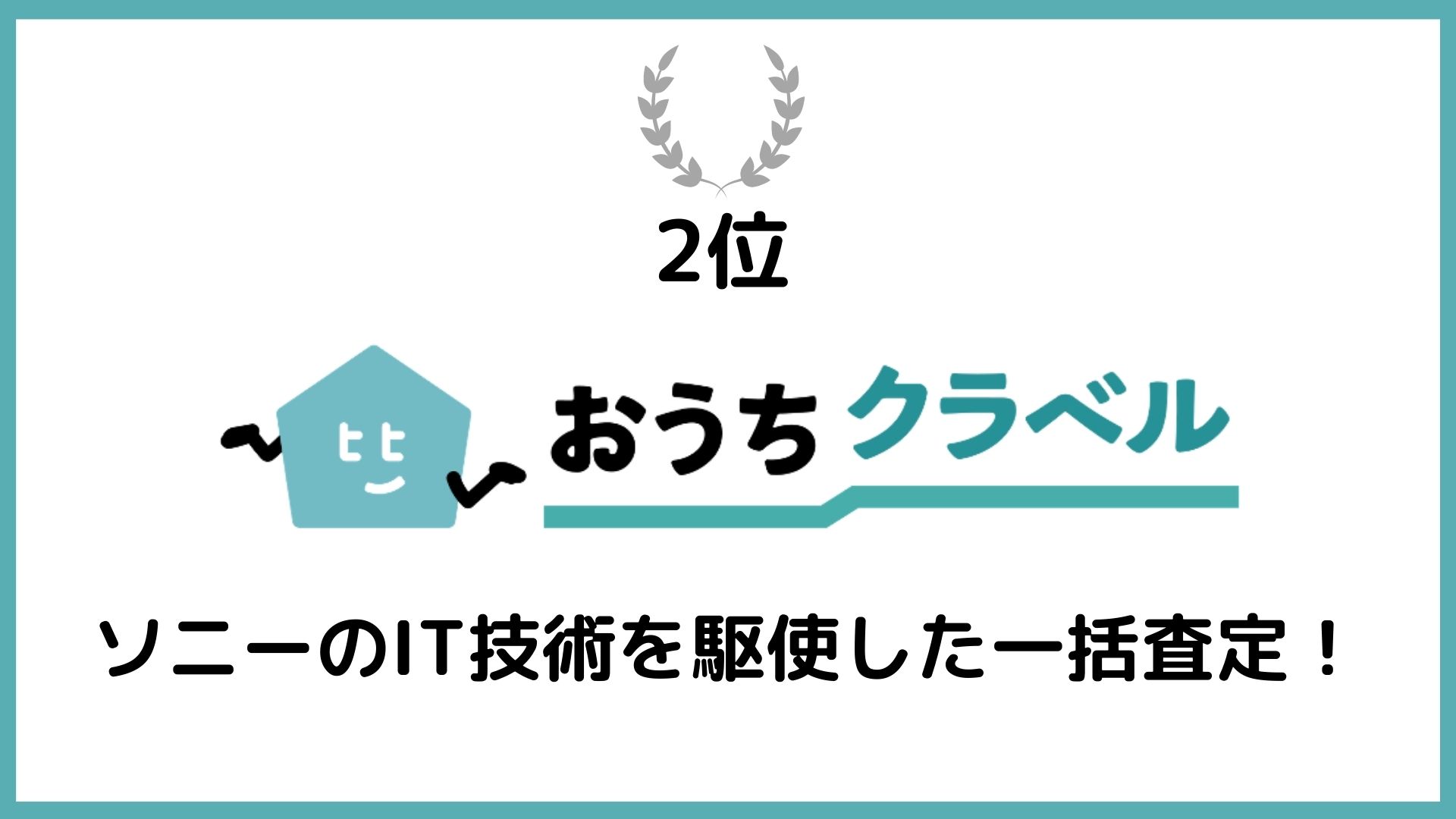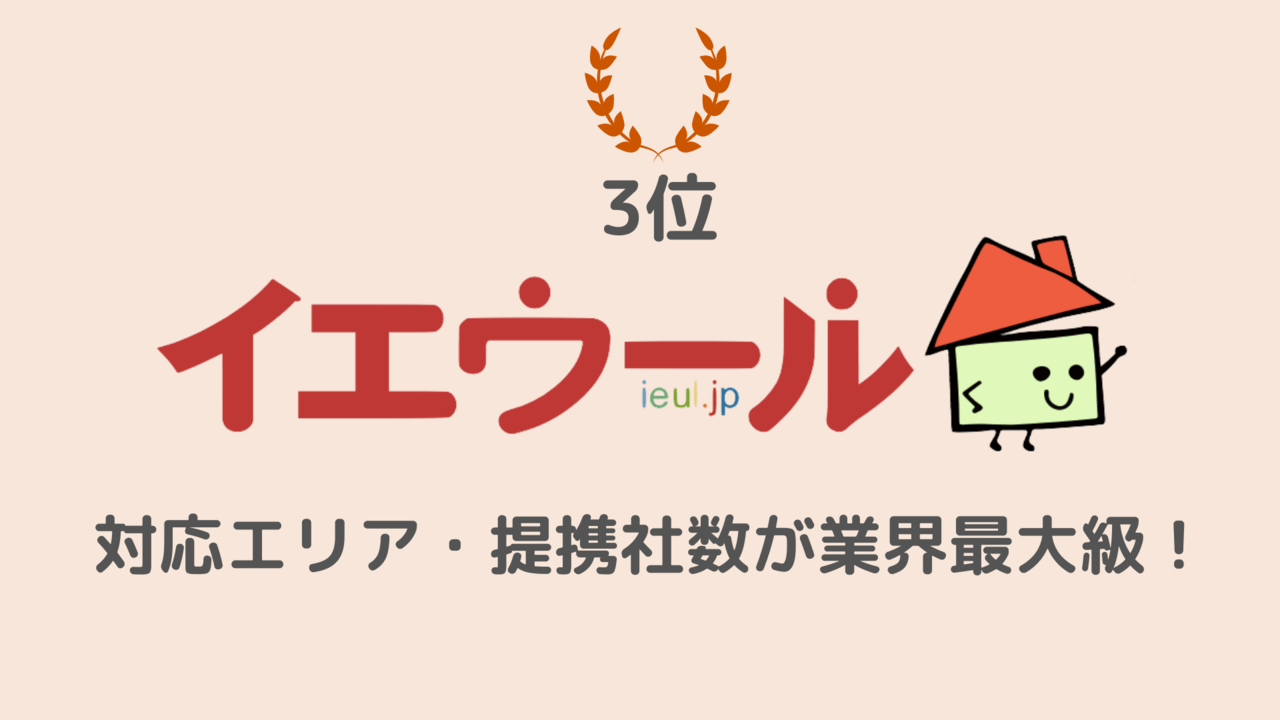建物には耐用年数という期限があることをご存知ですか。また、不動産売買や事業を始めたいと考えたとき、法定耐用年数について悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事は、鉄骨造の建物に着目し、耐用年数についての基本知識から、その計算方法や構造別の耐用年数、また耐用年数を過ぎた場合に起きるリスクなど網羅しています。今後の不動産の活用方法を検討するための必見情報として、ぜひお役立てください!
\土地活用プランを専門業者に無料請求/
HOME4U土地活用で一括依頼
そもそも耐用年数とは
 建物の耐用年数を調べる前に、まず耐用年数がどういうものを指すのかを知っておきましょう。ここでは、耐用年数の概要と、どのような時に必要になるのかを解説していきます。
建物の耐用年数を調べる前に、まず耐用年数がどういうものを指すのかを知っておきましょう。ここでは、耐用年数の概要と、どのような時に必要になるのかを解説していきます。
資産の消費期限を意味する
耐用年数には資産の消費期限の意味合いがあり、その期限によって資産の価値が決まります。不動産の場合、一般的に土地は劣化しないと考えられているため、経年劣化する建物の価値を求める際に用いられます。不動産以外のカテゴリでは、公道や貯水池などの構築物、車両や飛行機などにもこのような期限が設けられています。
建物の耐用年数には、建物の構造や立地条件などが関係しており、実際に使用できる年数と税制上で定められている年数の2種類が存在します。以下でそれぞれ詳しく解説します。
実際に使用できる耐用年数
一つ目は、建物の実際の寿命を考える方法です。ここでは、建物の立地条件や使用状況が重要になってきます。例えば、海の近くで毎日潮風にあおられるような立地であれば、錆びやすく劣化も早いため、耐用年数は短くなりますし、逆に寺院や歴史的建造物のように、木造でも手入れの行き届いている建物であれば数百年と形を変えず存在しているものもあります。
建物の構造や築年数に関わらず、その土地の環境とメンテナンスの具合によって大きく左右される、物理的に見る耐用年数となります。
税制上の定めである法定耐用年数
二つ目は、税制上で定められた法定耐用年数です。ここでは建物の構造と厚みを基準として用途(住宅・事業用など)によってそれぞれの耐用年数が決められています。
ここで気をつけたいのは、法定耐用年数は先に説明した建物の寿命とは異なるということ。例えば、木造建築の場合の法定耐用年数が20年だったとしても、常にメンテナンスし上手に使用していれば50年以上住める場合もありますし、逆に鉄骨造の建物の法定耐用年数は最長34年となっていますが、立地条件によってはそれよりも早く劣化して使えなくなってしまう場合もあります。
尚、法定耐用年数は新築で購入した時点での耐用年数となります。中古物件を購入した場合は別途、耐用年数の見積もりが必要となりますので留意しておきましょう。法定耐用年数を超えた時点でその資産の価値はゼロになります。
構造と厚みにより法定耐用年数がどのように決められているかについては、後の章にて詳しく解説します。
減価償却の計算に使用される
耐用年数は、戸建て住宅の他にアパートやマンション、店舗、事務所などに設定されていますが、主に減価償却を行う場面で法定耐用年数が関係してきます。
減価償却とは、物件を購入したときにかかった費用全額をその年度の経費とするのではなく、法定耐用年数に応じて年度ごとに分配して経費として計上していく考え方を言い、節税対策や事業の会計処理などに用いられます。つまり、できるだけ法定耐用年数が長い物件の方が、節税効果が高いということになります。
減価償却について詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。

住宅ローンの判断基準として使われる
不動産の購入を検討している場合にもう一つ知っておきたいのが、法定耐用年数が住宅ローンの融資可否に影響する可能性があるということです。金融機関によって審査基準は異なるため断言はできませんが、一般的に住宅ローンを組む際は、金融機関がその物件を担保として融資を行いますので、その不動産の担保価値がどれほどのものかが重要になります。
特に中古物件の場合は耐用年数も短くなっている可能性が高いため、その物件にどのくらい耐用年数が残っているかも確認しておくと良いでしょう。
鉄骨造の耐用年数

それではいよいよ、本記事が注目している鉄骨造の建物の耐用年数について見ていきましょう。まず、実際の建物の寿命と法定耐用年数の考え方を解説します。
鉄骨造の実際の寿命
売却などはせず、住居として長く住むのであれば、法定耐用年数よりも実際の家の寿命(いつまで住み続けられるか)を考えます。その際、鉄骨住宅の場合は、ハウスメーカーや建築業者の保証期間がポイントになります。各業者の有料保証期間の目安を比較してみましょう。
- ダイワハウス:30〜50年
- 積水ハウス:20〜60年(10年毎)
- パナホーム:25〜60年(5年毎)
メーカーにより期間の幅や点検回数は異なりますが、概ね60年が保証期間終了の目安となっています。そのため、法定耐用年数に関わらず60年がその家の寿命と言えます。
鉄骨造の法定耐用年数
上述した通り、不動産の売却や賃貸などの事業を行う場合は、減価償却を行う必要がありますので、法定耐用年数を知っておかなくてはいけません。
鉄骨造の建物の法定耐用年数は最長34年とされていますが、その骨格材の厚さを3mm以下・3mm超え〜4mm以下・4mm超えに分類し、それぞれ異なる耐用年数が設定されています。
また、厚さが4mm以下のものは軽量鉄骨、6mmを超えるものを重量鉄骨と呼びます。重量鉄骨はH型をしたしっかりとした資材になりますので、比較的大きな建物に使用している傾向にあります。メーカーや業者により資材の採用方法は異なりますので、所有不動産がどのような構造になっているかも調べておきましょう。
その他にも、鉄骨・鉄筋コンクリート造(SRC)や鉄筋コンクリート造(RC)などのタイプもあります。次の章では、それぞれの構造別に耐用年数を比較していきます。
用途別・厚さ別の耐用年数を比較

さて、ここからは法定耐用年数についてより詳しく考えていきます。前章では、建物の構造とその厚さによって耐用年数が変わる旨を紹介しました。しかし、そこから更に建物の使用目的(用途)によっても細かく耐用年数が区切られています。
以下で比較しながら見ていきましょう。
鉄骨の厚さ別
まず、鉄骨の種類・厚さ別で下記のような法定耐用年数が定められています。
| 種類・厚さ | 法定耐用年数 |
| 鉄骨・鉄筋コンクリート造(SRC) | 47年 |
| 鉄筋コンクリート造(RC) | 47年 |
| 鉄骨(厚さ4mm超え) | 34年 |
| 鉄骨(厚さ3mm超え~4mm以下) | 27年 |
| 鉄骨(厚さ3mm以下) | 19年 |
尚、これらは使用目的を住居とした場合の新築時点の耐用年数となります。
用途別の場合
次に、構造別の耐用年数を踏まえたうえで、物件の用途別に分けて見てみましょう。
| 構造/用途 | 住宅 | 店舗 | 事務所 | 飲食店 | ホテル・旅館など | 工場・倉庫など |
| 鉄骨・鉄筋コンクリート造(SRC)、鉄筋コンクリート造(RC) | 47年 | 39年 | 50年 | 41年 | 39年 | 38年 |
| 鉄骨(厚さ4mm超え) | 34年 | 34年 | 38年 | 31年 | 29年 | 31年 |
| 鉄骨(厚さ3mm超え~4mm以下) | 27年 | 27年 | 30年 | 25年 | 24年 | 24年 |
| 鉄骨(厚さ3mm以下) | 19年 | 19年 | 22年 | 19年 | 17年 | 17年 |
※面積のうち占める構造の割合によっても変わる場合があります。例えば、述べ面積のうち30%以上が木造部分だった場合などは、耐用年数は短くなることがあります。
一覧で見比べると、軽量鉄骨などのプレハブ方式で建てられたものや、宿泊業や工場などの人の出入りが多く劣化速度が早いと予測できるような建物において、比較的耐用年数は短く設定されていることが分かります。
物件を購入する際は物件用途に加えて、どのくらいの期間使用するのか・物件の購入金額を何年後までの経費として相殺できるかなども、この表を参考に改めて検討してみましょう。
鉄骨造のメリット・デメリット

次の章ではいよいよ耐用年数の計算方法に移っていきますが、その前に鉄骨造の特徴も知っておくと良いでしょう。この章では、軽量・重量ともに鉄骨造ならではのメリデメを解説します。不動産を購入・新築するには特に、構造が与える影響・リスクをしっかり検討したうえで判断しましょう。
軽量鉄骨造のメリット・デメリット
軽量鉄骨は主に一般的な注文住宅で採用される部材となります。以下で具体的にみていきましょう。
メリット
- 木造よりも圧倒的に耐震性に優れている。
- 工場で生産されるため資材に個体差がなく安定性がある。
- 量産できるため建築費や修繕費も抑えられるほか、固定資産税などの維持費も比較的安く済む。
デメリット
- 暑さがないので遮音性・耐火性が劣る
- 強度を高めるために筋合い補強をする関係で、間取り変更やリフォームが難しい
- 通気性がないため結露ができやすく、夏は暑く冬は寒い。
重量鉄骨造のメリット・デメリット
重量鉄骨造は、3階建て以上のマンションやショッピングモールなど、大型の建物に主に使用されています。こちらも特徴を見ていきましょう。
メリット
- 強度が非常に高く、耐震性・耐火性・耐久性ともに優れている
- 工場で生産されるため資材に個体差がなく安定性がある。
- 少ない柱や梁で建築するため、間取りの自由度が高い。
デメリット
- 量産できないため建築費がかかる。
- 通気性がないため結露ができやすく、夏は暑く冬は寒い。
- 基礎や地盤作りに時間とコストがかかる。
中古物件を購入した場合の耐用年数の計算方法

中古物件を購入した場合、既に法定耐用年数を経過しているため、改めて耐用年数(減価償却できる年数)を算出しなければなりません。この章では、法定耐用年数の一部を経過している場合と、完全に超過している場合の、それぞれの計算方法を紹介します。
中古物件の耐用年数は、見積法と簡便法の2種類の求め方がありますが、一般的に使用されるのは簡便法で、以下がその算式となります。
法定耐用年数の一部を経過している場合
法定耐用年数のうち一部年数を消化してしまっている建物に関しては、次の方法で耐用年数を求めます。
例えば、築14年の鉄骨造(法定耐用年数34年)の中古物件を店舗用として購入した場合、以下の計算になります。
このとき、計算結果が2年未満になった場合は2年に繰り上げされ、それ以上の場合は1年に満たない端数は切り捨てとなります。よって、上記の中古物件の耐用年数は22年となります。
減価償却を行う場合は建物を取得してから22年間、物件購入費を分割して経費計上できることになります。
法定耐用年数をすべて経過している場合
法定耐用年数を完全に消化してしまっている場合は以下の算式で耐用年数を求めます。
例えば、もともと法定耐用年数が34年の中古物件を購入した場合、耐用年数は6.8、つまり6年の計算になります。
たった6年しか経費として上げられないというデメリットはありますが、そもそも法定耐用年数を過ぎているにも関わらず減価償却ができることは大きな利点ですし、更に耐用年数を超えている物件は安く購入できる可能性もあります。中古物件の購入を考えるならば、あえて耐用年数を超えている建物を探してみるのも良い方法かもしれません。
尚、資産の減価償却費の求め方には定額法と定率法の2種類ありますが、どちらの計算法を用いるかは資産の区分によって異なります。不動産の場合は定額法を用いる場合が多く、建物部分のみ減価償却をします。(土地の価値は減少せず減価償却の対象外とされているため)
減価償却や償却率について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参考ください。

鉄骨造の耐用年数を延ばす方法

耐用年数についての基本知識や計算方法などが理解できたところで、今度は耐用年数を延ばす方法も考えていきましょう。ここでは、建物の実際の寿命に目を向け、より快適に、より長く暮らしていくための方法を紹介していきたいと思います。
メンテナンスや大規模修繕を行う
まず覚えておきたいのは、不動産の性質に合ったメンテナンスを行うことです。上述したように、同じ構造の家だとしても、立地条件やその地域特有の気候によって建物の劣化速度や具合は異なり、実際の寿命も変わっていきます。法定耐用年数に関わらず、こまめな手入れを行うことで実際の寿命を延ばし、長く住み続けることが可能になります。
家の修繕が必要となる箇所には、主に以下のようなものが考えられます。
- 外壁・屋根
雨風や日照、湿気などにさらされやすい外壁や屋根は、特に定期的なメンテナンスが必要です。壁の塗装が剥がれたり、ひび割れなどが雨漏りの原因になることもあります。最低でも10年に1度は修繕を行った方が良いとされています。
- 水回り
トイレ、洗面所、風呂場、台所などは、湿気によるカビや水漏れで思った以上に劣化は早いものです。劣化だけではなく、水漏れや臭いなどが原因で近隣とのトラブルも考えられます。こちらも最低10年を目安にメンテナンスを行いましょう。
- クロス、内装
壁紙の染み、汚れ、臭いなどが気になってくるのが7年〜10年あたり。専用洗剤などで定期的にケアしておくのも大切ですが、10〜15年ほど経った頃に他の修繕部分と合わせて業者に依頼するのも良いかもしれません。
- 空調危機や排水管などの設備部分
築15〜20年も経てば、空調や給排水管などの設備の劣化が目立ってきます。全てを入れ替えるのか、部分的に修繕するのか複数の業者に見積もりを依頼して比較してみましょう。
その他の部分も、海の近くや雨の多い地域、日があたりにくい場所にあるなど、それぞれの環境によって対応策を考える必要があります。
分譲マンションの場合は、マンションの管理組合が居住者から修繕積立金というものを毎月回収し、随時適切なメンテナンスを行っている場合が一般的です。エレベーターや消防設備などの定期点検から、劣化や壊れた設備の大規模な修繕工事、また管理人や清掃人の人件費などに充てられ、建物の維持を担っています。
マンションの修繕積立金について詳しくはこちらの記事もおすすめです。

外部からのリスクを防ぐ
耐用年数を延ばすために考えておきたいもう一つのポイントは、外部からの影響です。せっかく高い資金をかけて耐用年数の長い物件を手に入れたとしても、その物件が建っている場所に弱点があれば元も子もありません。
例えば、以下の要因が考えられます。
- 土地が軟弱で地盤沈下の恐れがある
- 地震が多い地域
- 川や海の近くで水害が多い地域 など
このような状況下にある物件は、地盤を強化するための杭をしっかりと入れたり、浸水に備えて土嚢や柵を設置するなどの対策も考える必要があるでしょう。
現在は、地域ごとのハザードマップで災害予測や地盤の強度も知ることができます。法定耐用年数に関わらず、外部から受けるリスクも加味し、安全に過ごせる環境作りを行うことが重要です。
参考文献:ハザードマップポータルサイト
鉄骨造が耐用年数を超えた場合に発生する問題

ここからは、法定耐用年数を超えてしまった場合にどのようなことが起こるのかを解説していきます。主に以下のようなデメリットが考えられ、不動産売買や賃貸事業を行う際に影響を与えます。
- 住宅ローンが借りにくくなる
- 売却が難しくなる
- 税金の負担が増える
影響について把握することで対策を練ることが出来ます。考えられる影響について一つずつ見ていきましょう。
住宅ローンが借りにくくなる
不動産を購入する際は、ほとんどの方が住宅ローンを利用しますが、ローンを利用できるかどうかは融資を行う金融機関が審査を行います。金融機関は通常、抵当権というものを設定して不動産を担保に取り、万が一返済が滞ったときに金融機関側でその不動産を売ってお金を回収しなくてはいけないため、法定耐用年数をローンの審査基準の一つとして不動産の担保価値を測ります。
そのため、法定耐用年数を超えている不動産は資産価値が見出せず、審査に通りにくい傾向にあります。また、同じ事情により、法定耐用年数を大幅に経過している不動産は、審査に通っても、返済期限が短いローンしか組めない場合があるなどの不利な状況が発生する可能性があります。
売却が難しくなる
不動産売却の際にも、上記と同じ事情でデメリットが生じることがあります。法定耐用年数を超えてしまった不動産を販売してうまく買主が見つかったとしても、その買主が住宅ローンを組めなければ売却が成立しません。
金融機関にとっては不動産の売主・買主が納得しているかどうかは関係なく、あくまでも不動産の資産としての価値を見て審査を行いますので、その面でも売却するまでにはかなり時間がかかってしまったり、希望の価格で売却できないなどの状況も想定されます。
税金の負担が増える
ここからは、賃貸などで事業を行う場合のリスクです。不動産価格を減価償却して経費計上できる旨は既に説明しました。
ただし、経費として計上できるのは法定耐用年数分までとなるため、それ以降は不動産所得が増えてしまうため、納める税金が急に増えるという難点があります。不動産所得とは、主に不動産の貸付を行って得る家賃や更新料などの収入のことを言い、総収入額から必要経費を差し引いた部分の金額を指します。
下記の図は、減価償却ができていたときと、減価償却できなくなったときの費用の割合を比較したものです。

これはどういうことかと言うと、減価償却費は、あくまでも不動産の購入費を耐用年数で分割した会計処理のことであって、実質上は出費しない額となります。
法定耐用年数を超えると、それまで経費として計上できていた減価償却費分も不動産所得に組み込まなければいけなくなるため、総収入額はほとんど変わらないにも関わらず、納税額だけが突然増えるということになります。法定耐用年数を超える前後で不動産を手放すオーナーが多いのもそのためです。
耐用年数が過ぎた鉄骨造物件の活用方法

法定耐用年数を超えてしまった建物のデメリットをご説明してきましたが、実は、上手に活用することでそのような問題を解決に導くこともできます。ここでは、法定耐用年数を超えた鉄骨造物件について、以下のような活用方法を提案していきます。
- 一括査定サービスで価値を調べて売却する
- 建物を新しく建て替える
- リフォームとセットで融資を受ける
以下で具体的に見ていきましょう。
一括査定サービスで価値を調べて売却する
賃貸にしろ売却にしろ、今後の収益が見込めない・売れにくい物件は不動産会社の仲介を利用して売却を検討してみましょう。不動産会社には独自のネットワークや営業力があり、自分で売却活動を進めるよりも早期に解決できる可能性があります。
注意したいのは、不動産会社によって得意分野があることです。これは大手なのか中小企業なのかは関係なく、売却したい物件の性質に合った売り方が上手いかどうかがポイントになります。
例えば、住宅を売却したいのであれば住宅を探している顧客を沢山持っている不動産会社を、投資用マンションの売却をしたいのであれば賃貸物件を探しているオーナーをメインに顧客に持つ不動産会社を、という視点が非常に重要です。
各不動産会社のホームページやパンフレットなどで売却実績などを見ることも判断の材料になりますが、複数社を比較できる不動産一括査定サイトを利用するのもおすすめです。一括査定サイトは、登録している不動産会社を客観的に見て、ある程度の水準をクリアした企業のみを厳選しているものが多く、安心して利用できるというメリットがあります。
また、不動産会社の仲介でもなかなか売却がかなわない場合は、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう買取という方法もあります。仲介よりも売値が落ちる可能性はありますが、すぐに現金化できるという点では検討の価値は十分にあるでしょう。
一括査定サービス利用者が選んだおすすめサービスTOP3
※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)
こちらは、サービス利用者のアンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声と編集部の知見が合わさったできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。
なお、不動産一括査定サービスは、それぞれ対応するエリアや提携する不動産会社が異なるため、1つだけでなく複数のサービスを利用することをおすすめします。
次の記事ではより多くのサービスを含めたランキングや「査定結果の満足度TOP3」や「親族・友達におすすめしたいTOP3」などカテゴリ別にもランキングを紹介しています。さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。

建物を新しく建て替える
賃貸事業に関しての活用方法は、建物を新しく建て替えることです。法定耐用年数がリセットされることはもちろん、古い物件は建てられた当初のニーズに合わせて造られた建物のため、現在のニーズにはそぐわない場合がありますので、現在の需要に合った新しい物件に変えることで、より効率的に収益が期待できるでしょう。
また、古い物件はその時代の建築方法で造られているため、新しい物件よりも使用している資材がもろかったり耐震基準が甘い可能性もあり、将来的に改築や修繕費用などのコストが多くかかることも予測されます。
利便性が良い、立地が良い、治安が良いなど、住環境としての条件が揃っているのであれば、今後も入居者を確保できる可能性が高いため、思い切って建て替えを検討してみてはいかがでしょうか。
リフォームと一緒に融資を受ける
不動産購入の場合に活用したいのが、物件をリフォームし、そのリフォーム費用も含めた金額の融資を申し込む方法です。法定耐用年数を超えた不動産は、住宅ローンの審査に通りにくくなることは否めませんが、リフォームをして性能がアップしたことや住居として何ら問題がないことなどをアピールすれば、金融機関側も考慮してくれる場合があるのです。
一般的な住宅ローンでは、リフォーム費用も一緒にすることができるプランもありますので、ぜひ複数の金融機関に相談し比較してみましょう。
ひと昔前に比べ現代の建築技術は飛躍的に向上し、リフォーム、リノベーションでも新築に劣らないほどのクオリティに改善させることができるようになっています。建て替えよりも早く、安価に実現できる可能性もあり、大変おすすめな方法の一つです。
ただし、ここで忘れてはいけないのが金融機関が注目するのは不動産の価値であるところ。単に見た目や内装を綺麗にするだけであったり、独特な間取りにこだわりすぎて機能性が噛み合わない改装をしてしまっては意味がありません。耐震性、断熱性、防音性やバリアフリーなど、誰が見ても「十分な機能を揃えている」と判断できることが重要です。
まとめ

建物の耐用年数には、実際の建物の寿命と税制上で定められている法定耐用年数の2種類の考え方が存在します。それぞれ使用される場面は異なり、構造やその物件の使用目的によっても耐用年数が変わります。
また、不動産売買や賃貸事業など行う際には法定耐用年数が大きく影響し、耐用年数を超えた物件はデメリットもありますが様々な活用方法があることも分かりました。
ぜひ本記事を参考に、ご自身の不動産の資産価値を見直し、今後どのように活用していけるのかを検討してみてください。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
不動産一括査定サイト利用者が選んだおすすめサービスTOP3

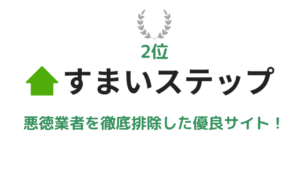

不動産一括査定サイト利用者が選んだカテゴリ別TOP3
≪査定結果の満足度TOP3≫
≪サイトの使いやすさTOP3≫
≪親族・友達におすすめしたいTOP3≫
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。