不動産の売却で購入時の価格より下回ってしまったり、買い換えの際に売却する家より購入する家の価格が高かったりなど、不動産売買において売却損に陥るケースは少なくありません。
売却損が出た場合は、確定申告によって住民税や所得税の控除が受けられ、納税の負担が軽減される制度があります。しかし、自営業やフリーランスで勤めている方以外には確定申告はあまり馴染みがないので、不安や抵抗を感じる方も多いのではないでしょうか。
そこでここでは、確定申告における申告方法や計算方法などの解説を交えて、節税方法について徹底的に解説します。この記事で確定申告に対する不安や抵抗を取り除き、節税することで負担を軽くしていきましょう。
- 不動産売却では売却損が出た場合、損益通算と繰越控除を利用すれば納税額の控除が受けられます。
- 不動産売却損の確定申告には、売却損を生じた不動産の取得費や譲渡費用を含めた計算が必要です。
- 確定申告での失敗を避けるコツは売却した時点で準備を始めることです。わからない部分は税務署への相談や税理士への依頼で対処していきましょう。
不動産の売却損と確定申告のルール
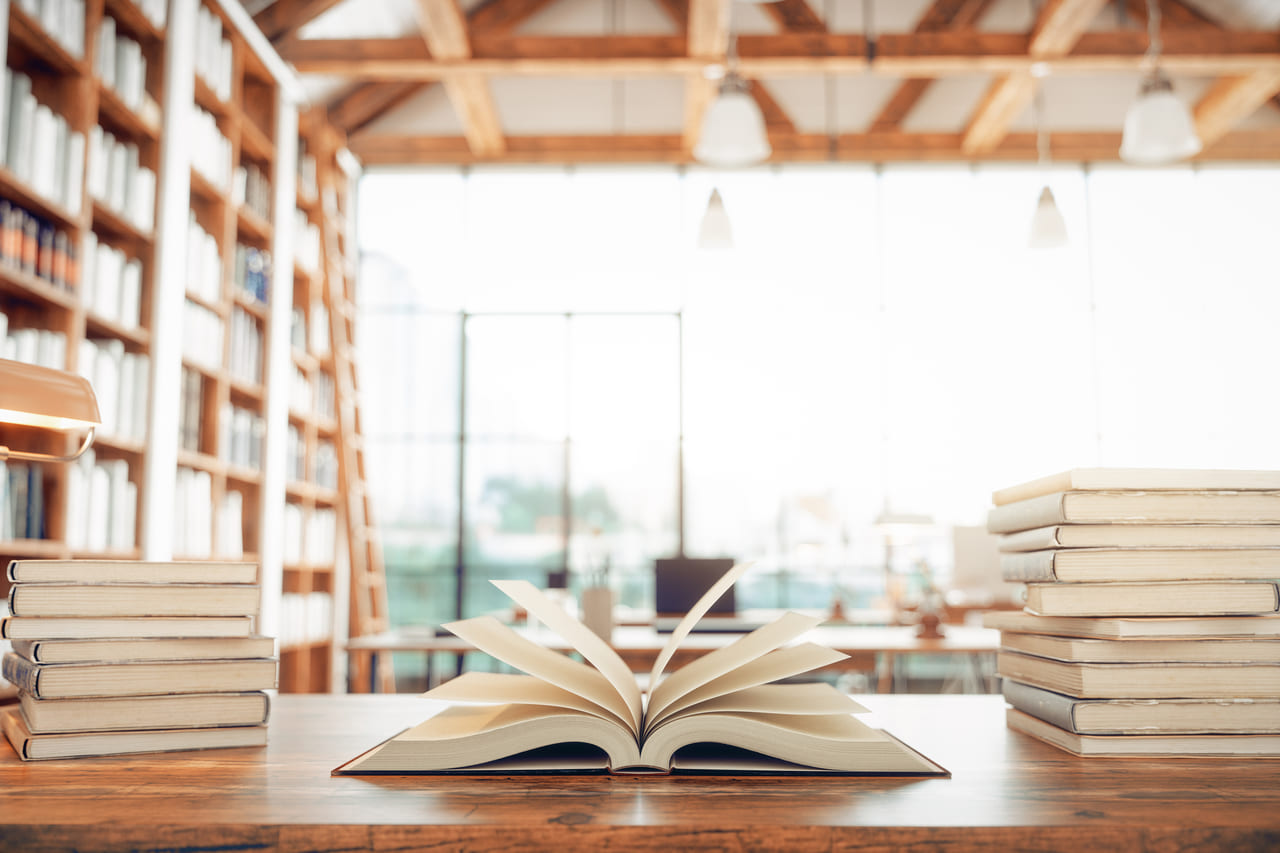
ここでは確定申告が必要か必要でないかや、計算方法など申告に関する基礎知識を解説していきます。以下の順で見ていきましょう。
- 不動産の売却損の計算方法
- 確定申告の要・不要
- 確定申告の提出機関
売却損の計算方法
譲渡所得とは土地や建物などの不動産や、株式やゴルフ会員権などの資産を譲渡(売却)することによって生じる所得のことで、計算式は下記の通りです。不動産の売却損は、この譲渡所得がマイナスの際に発生しているといえます。
| 収入額 | 不動産を売却し、買主から売主へ支払った金額 |
| 取得費 | 売却した不動産の購入代金。改良費や建築費、設備費もこの代金に含まれる。購入の合計金額から所有期間中の減価償却費の相当額を差し引いた金額を所得費という |
| 譲渡費用 | 売却するために要した費用(※仲介手数料、登記費用、測量費など) |
確定申告は不動産売却で利益があれば必須
計算式によって算出された数字が0円以下のマイナスであれば、課税対象にならず確定申告の必要はありませんが、利益が1円でもあれば所得が発生するため確定申告が必要です。利益があるのに申告がされていない場合は税の無申告扱いになり、下記のようなペナルティーが科せられますます。
- 50万円までの部分:納付すべき税額×15%
- 50万円超えた部分:納付すべき税額×20%
上記の課税が上乗せされてしまいますが、これを無申告加算課税といいます。税務署の指摘前に申し出れば、納税額×5%扱いになるため、気づいた時点で即座に申告したほうが無難です。
もし確定申告後に確定した納税額の納付が遅れてしまうと、本来の納税額に延滞税が課税されてしまいます。申告や納税が遅れてしまうことで、納税額は上がり負担が大きくなるため注意が必要です。確定申告も納税も早期行動で損を減らすことができるので、あらかじめ備えておきましょう。
確定申告の申請時期
確定申告は1年間いつでもできるわけではなく、期間が限られています。不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日に確定申告をしましょう。ただし税務署は土日は閉庁しているため、曜日の関係で数日前後するケースがあります。
また、税務署の外に確定申告用の投函箱が設置されているので、記入済みの申告書を提出する場合は土日祭日や平日時間外の提出も可能です。
不動産の売却損でも損益通算と繰越控除で節税

売却損が出た場合には確定申告は不要ですが、あえて確定申告をすることで納税額が控除されるケースもあります。その制度がどのような節税につながるのかを解説していきます。
損益通算とは
不動産の売却損で利用できる税制度の一つでもある損益通算とは、不動産売却によって出た赤字分を、他の所得に課税される所得税や住民税から控除する制度です。控除することによって、納める所得税や住民税の負担を軽減することができます。この通算損益の制度を利用するためには、次のような条件があります。
- 源泉徴収を受けている必要がある
- 特例の要件を満たす必要がある
- 確定申告をする必要がある
特例の要件や内容について詳しくは後述しますが、この制度には限度額が存在します。1年で損失のすべてを控除することができなかった場合の措置があるので、次の項目で確認しましょう。
繰越控除とは
不動産売却はもともと金額が高いことから、売却損が発生した場合はその額も高くなる傾向にあります。損益通算にて引ききれなかった売却損を、翌年以降から3年間の間その年の所得から順次控除することが可能です。対象になる所得は以下の通りですが、これら所得税の1年遅れで住民税の控除が受けられます。
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 雑所得
なお、これらの合計所得が3,000万円を超える年分は除外されます。
2つのパターンで損益通算と繰越控除

不動産の売却損が出たときは、損益通算と繰越控除には2つのパターンが存在し、それぞれに対して適用条件や必要な書類が異なります。ここでは、その2つのケースごとに必要な書類や条件を解説していきます。
不動産の売却損が買い換えで発生
マイホームの売却額より、新たに住み替える住居の購入額が高かったときは売却損が発生します。しかし、損益通算と繰越控除の制度は、すべての買い替えの売却損に適用されるわけではありません。この制度を利用するためには適用条件をすべて満たす必要があり、適用が除外される条件もあります。これらの内容を、必要な書類とあわせて詳しく解説します。
買い換えでの適用条件
買い換えで適用される条件は法で定められており、内容は以下の通りです。
- 1998年1月1日~2021年12月31日までに譲渡の年の1月1日現在において、土地建物の所有期間がいずれも5年を超えている
- 譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までの間、居住を買い替えていること
- 住居を取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供した、あるいは供する見込みである
- 資産の譲渡にかかわる損失が生じていること
- 住み替え後の資産を取得した年の12月31日、または繰越控除の特例の適用を受けようとする年の年末において、「買い換え資産」にかかわる住宅ローン(償還期間10年以上)がある
これらすべての条件を満たす必要がありますが、売却する不動産を5年以上所有し、新たな住居の住宅ローンが10年以上あるなど、一般的な買い替えであれば大抵の人が該当するでしょう。では次に、この特例が使えない条件を紹介します。
特例が使えない買い換えの条件
使用できる条件と同じく、特例が使用できない条件も次のように定められています。
- 損益通算をしようとする年の前年以前の3年以内に、他の居住用財産の譲渡損失について損益通算の特例の適用を受けている
- 売却した年の前年または前々年において行った資産の譲渡について、以下の特例の適用を2つ受けている
・マイホームを売却した場合の「長期譲渡所得の課税」の特例居住用財産の譲渡所得「3,000万円の特別控除」
・特定の居住用財産の買い替えの場合の「長期譲渡所得の課税」の特例
・特定の居住用財産を交換した場合の「長期譲渡所得の課税」の特例
- 譲渡した年またはその年の前年以前3年以内に「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例」の適用を受けている
- 売却損が生じた年の翌年以後3年以内の各年分のうち、所得金額が合計3,000万円を超える年については、繰越控除の対象外(損益通算の特例は利用可能)
この特例を利用できない条件として挙げられるのが「損益通算を利用しようとする年の前年から3年前の間に、他の不動産売却で譲渡損失を損益通算したことがない方」ですが、よくあるのが特例の適用をすでに2つ受けている場合です。
「3,000万円の特別控除」やいずれかの「長期譲渡所得の課税」を受けている場合は、損益通算と繰越控除の特例を受けることができなくなるため、確定申告の際は注意が必要です。
買い換えでの損益通算の必要書類
「買い替えでの損益通算」の確定申告時に必要な書類を紹介します。
【基本の書類】
- 確定申告書
- 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
- マイホームの売却損の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
【売却する不動産に必要な書類】
- 登記事項証明書や売買契約書の写しなど(居住していた証明に使用)
【買い替える不動産に必要な書類】
- 登記事項証明書や売買契約書の写しなど(購入した年月日、家屋の床面積がわかるもの)
- 年末における住宅ローン等の残高証明書
- 居住を開始する予定年月日とその他の事項を記載した書類(※確定申告書の提出の日までに、買換えた住宅に住んでいない場合)
買い替えの際に特例を利用したい場合は、損益を証明する明細書以外にも、実際にマイホームとして居住するという証明が必要です。売却する不動産と住み替えの先についての契約書や、証明書等を確定申告用に各自用意しておきましょう。
不動産の売却損が特定居住用財産の売却で発生
特定居住用財産に対する特例とは、住宅ローンが残っている状態で、5年を超えて保有しているマイホームを売りに出したが、売却損になってしまったときに使える特例のことです。
売却損を一定の限度額で、その年の給与所得などの他の所得から差し引くことができるうえに、その年に引ききれなかった金額については、その翌年以降3年間繰り越して控除できます。この特定居住用財産の特例にも、適用条件や除外のケースもあるので詳しく解説していきます。
特定居住用財産の売却での適用条件
特定居住用財産の売却での適用条件をすべて満たす必要がありますが、内容は以下の通りです。
- 2004年1月1日から2021年12月31日までに売却の年の1月1日現在において、土地建物の所有期間がいずれも5年を超えている
- 1の売却にかかわる契約を締結した日の前日において、売却する不動産にかかわる住宅ローン等(契約における償還期間が10年以上のものに限る)の残債があること
- 1の譲渡にかかわる売却損の金額があること
- 売却する不動産が以下のいずれかに該当するものであること
- 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超える住居
- ①の家屋でその個人の居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるもの
- ①または②の家屋及びその家屋の敷地となっている土地など
譲渡する個人の①の家屋が災害により滅失した場合においては、その個人が家屋を引き続き所有していたら譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなる、その家屋の敷地の用に供されていた土地等(ただし、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限る)
特定居住用財産の特例は、少なくとも売却する不動産を5年以上所有し、住宅ローンの償還期間が10年以上ある場合に利用することが可能です。1の条件を満たすことで、必然的に4(1)の条件も満たすことになります。
特例が使えない特定居住用財産の売却の条件
では、特例が使えない条件を見てみましょう。
- 損益通算をしようとする年の前年以前3年以内に、他の特定居住用財産の譲渡損失について損益通算の特例の適用を受けている場合
- 売却した年の前年もしくは前々年に行った資産の売却について、他の特例の適用を受けている場合
・マイホームを売却した場合の「長期譲渡所得の課税」の特例
・居住用財産の譲渡所得「3,000万円の特別控除」
・特定の居住用財産の買い替えの場合の「長期譲渡所得の課税」の特例
・特定の居住用財産を交換した場合の「長期譲渡所得の課税」の特例
- 売却した年またはその年の前年以前3年以内に、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けている場合
特定居住用財産の場合の特例が使えない条件は、買い替えの条件とあまり違いはみられません。売却した年またはその年の前年以前3年以内に特例を受けた方は、対象外なのでご注意ください。
特定居住用財産の売却での損益通算の必要書類
特定居住用財産の損益通算の確定申告時に必要な書類を紹介します。
【基本の書類】
- 確定申告書
- 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
- マイホームの売却損の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
【売却する不動産に必要な書類】
- 登記事項証明書や売買契約書の写しなど(所有期間が5年を超えることを証明するもの)
- 売却した不動産にかかる住宅ローン等の残高証明書(売買契約日の前日のもの)
買い替えと比較すると書類のボリュームが少ない傾向にあります。特定居住用財産の売却に関しては、基本の書類と不動産の所有期間、住宅ローンを証明する書類があれば特例の確定申告ができます。住宅ローンの残高証明書に関しては、売買契約前日のものを用意する必要があるので、添付間違えのないように注意が必要です。
また、確定申告を準備する際のポイントですが、確定申告をするためには多くの書類を申請に使います。よって、申請内容ごとに整理整頓して書類の種類を把握しやすくしておきましょう。管理不足の場合は、後々添付して提出する際に余計な時間を割くことになります。
不動産の売却損の確定申告で失敗しないコツ

売却損の税の控除や仕組みをみてきましたが、確定申告書に記入して提出しないことには、控除を受けて税の負担を軽減することはできません。
「記入の項目が多く、複雑で時間がかかる」「本当に数字があっているか不安」など悩みは尽きないでしょう。そんな確定申告ですが、失敗しない秘訣があるので確認しましょう。
税務署で相談をする
不動産の確定申告はプロでも難しさを感じるほどですが、税額の計算を自身で行うので間違いに気づきにくい傾向にあります。そんな不安な気持ちは税務署に相談することで払拭できます。相談はまず電話で行いましょう。管轄の税務署へ電話をかけると自動音声へ切り替わり、以下のいずれかを選択します。
- 国税庁電話相談センター
- 管轄税務署
確定申告のサポートを税理士に依頼
不動産の売却に関する特例は、多様で複雑なため費用の見落としがあったり、評価方法によっては税金に大きな差が生じたりするケースもあるでしょう。そこで、下記に当てはまる方には税理士の利用をおすすめします。
- 計算に自信がない
- 確定申告に時間をとることができない
- 税務署へ相談したけれどそれでも不安
まとめ
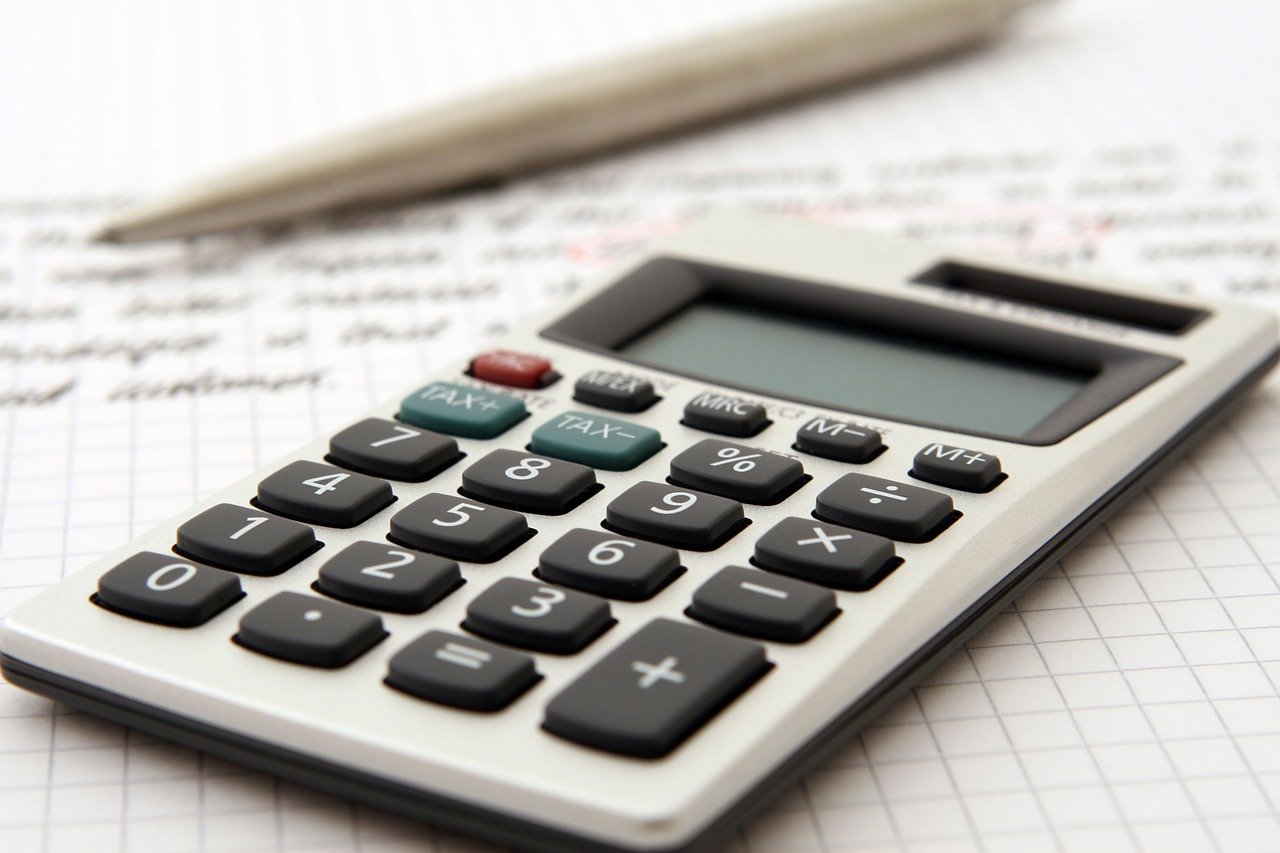
確定申告で失敗しないために、売却した時点で確定申告の準備を始めましょう。あらかじめ書類を入手したり、相談しておいたりすることで失敗を防ぐことが可能です。この記事で得た知識を生かし、賢く節税対策を行いませんか。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。



