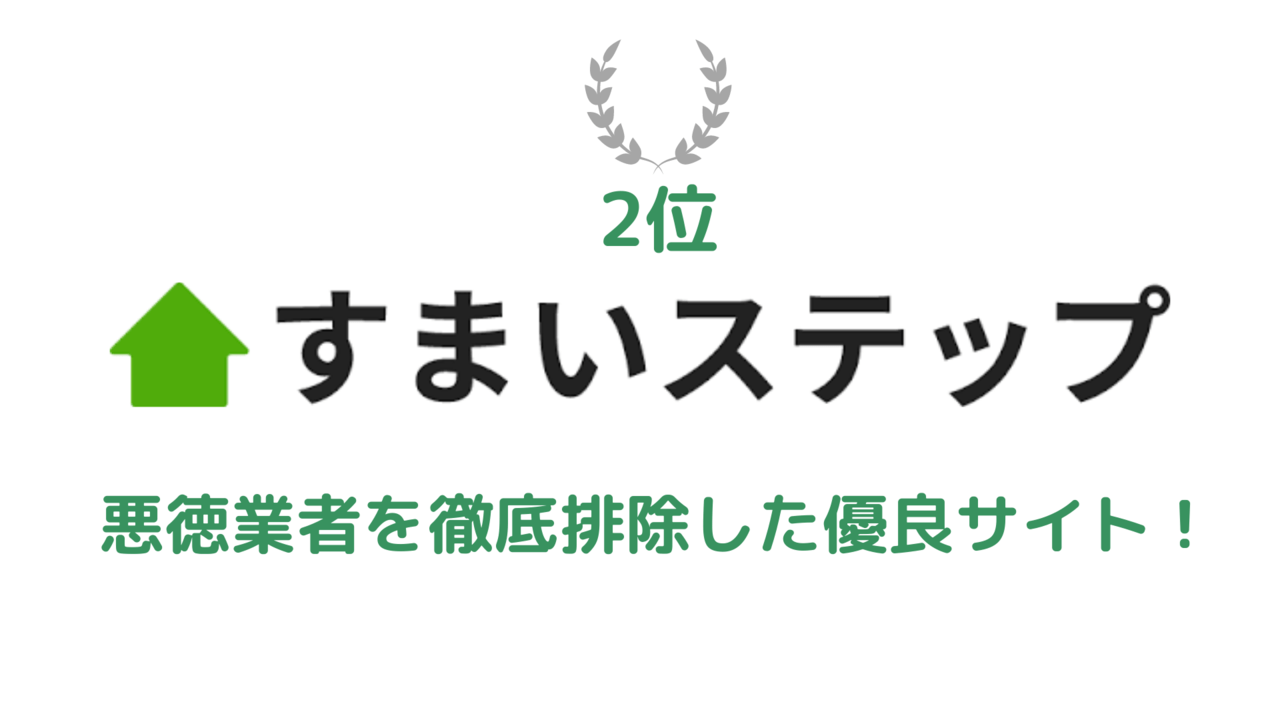相続した不動産の売却、またはマイホームの買い替え特例を利用したい時など、事前に理解しておきたいのが譲渡所得の特別控除です。さまざまな種類と共に控除額や条件こそ異なりますが、適用されれば節税対策として大きなメリットがあるこの制度、ぜひ利用したいですよね。
そこで当記事では、不動産における譲渡所得の特別控除制度について、さまざまな角度から解説していきます。特別控除の種類や控除額、手続きの詳細、利用するための注意点などを取り上げますので、ぜひ売却時の節税対策にお役立てください。
不動産一括査定サイト利用者が選んだおすすめサービスTOP3
この記事を読まずに、先におすすめの査定サービスを知りたい人におすすめなのが、以下の3サービスです。 マイナビ編集部で実施した独自アンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声と編集部の知見が合わさってできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)
譲渡所得の特別控除とは

譲渡所得の特別控除は所得を減額できる制度ですが、それぞれ特例ごとに限度額が定められています。この章では、基本となる譲渡所得の特別控除制度の概要をまとめました。
要件を満たすことで所得を減額できる制度のこと
譲渡所得の特別控除とは、土地や建物など不動産の売却で譲渡所得が発生した際、一定の要件を満たすことで所得を減額し税金の負担を軽くできる制度のことで、他人に譲り渡した際の必要経費を差し引いた額になります。
また不動産の譲渡所得では、1年間の所得すべてを合計して課税の対象とみなす「総合課税」ではなく、所得にあわせた税率を課する「分離課税」を採用しています。その理由は、以下の通りです。
- 不動産の譲渡所得は高額になることが多く、納税額を高くしないため
- 事業所得や給与所得のように、何度も所得を得ることがないため
総合課税は全体の所得が多いほど納税額が上がります。しかしながら分離課税であれば所得の種類ごとに個別に課税されるため、納税額を抑えることができます。
不動産に採用される分離課税について、詳しくはこちらの記事もぜひ参考にご覧ください。

課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡所得を算出する際は、以下の計算式を用います。
譲渡収入とは、不動産を売却した金額のことです。取得費や譲渡費用の詳細は次のようになっています。
| 課税譲渡所得金額の計算に必要な費用 | 税率 |
| 取得費 |
|
| 譲渡費用 |
|
譲渡所得の計算方法については、こちらの記事もおすすめです。

特例ごとに限度額がある
譲渡所得の特別控除の種類によって、800万円や3,000万円など控除を受けられる上限額が異なり、譲渡収入や取得費、譲渡費用の金額次第では、特別控除を利用しても譲渡所得が高くなってしまう可能性もあります。また、控除を受けられる限度額は合計で5,000万円までとされています。
譲渡所得の特別控除の種類および各控除額は、次の章で詳しく解説します。
不動産以外の特別控除額は最高50万円まで
土地や建物以外の資産の譲渡所得の場合、特別控除額は長期譲渡所得と短期譲渡所得の合計で最高50万円までと定められています。この特別控除は「総合課税」の場合のみ利用でき、「分離課税」が採用されている不動産売却の利益においては利用できません。
また不動産の譲渡所得税を算出する際、所有期間によって税率が異なる旨にも注意しておきましょう。
| 譲渡所得の種類 | 税率 |
| 不動産の所有期間が5年を超えている長期譲渡所得 |
|
| 不動産の所有期間が5年以下の短期譲渡所得 |
|
上記のように長期譲渡所得の税率は、短期譲渡所得よりも低くなっています。そのため、不動産を所有している期間が長いほど税金を抑えられるということが分かります。
短期譲渡と長期譲渡について、さらに詳しく比較解説しているこちらの記事もおすすめです。

譲渡所得の特別控除の種類一覧

譲渡所得の特別控除は以下のようにさまざまな種類があり、その条件や控除額もそれぞれ異なります。
- 5,000万円の特別控除
- 3,000万円の特別控除
- 2,000万円の特別控除
- 1,500万円の特別控除
- 1,000万円の特別控除
- 800万円の特別控除
- 2020年7月1日より開始した100万円の特別控除
各控除の詳細を紹介しますので、所有している土地や建物がどの控除に該当するのかチェックしておきましょう。
5,000万円の特別控除(公共事業などのために土地・建物を売却)
土地収用法または収用権が認められている公共事業などのために土地・建物を売却した場合、譲渡所得から最高5,000万円を控除できる特例があります。5,000万円の特別控除の適用条件は以下の通りです。
- 売った不動産が固定資産である
- 代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていない
- 最初に買取の申し出を受けた日から6ヶ月を経過するまでに売却を終えている
- 公共事業の施行者から直接買取などの申し出を受けた本人(相続人)による譲渡
特別控除のなかでも1番高額なため、大幅な節税になると考えて良いでしょう。なお、この特例に関する注意点は以下となります。
- 同一の公共事業に対して2年以上またがって売却できるケースであっても、控除の適用は1度のみ
- 5,000万円の特例を受ける場合「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」は受けられない
3,000万円の特別控除(マイホーム・居住用財産を売却)
所有年数に関係なくマイホームを売却した場合、最大で3,000万円が控除される特例もあります。主な適用条件は下記の通りですが、他の特別控除に比べて条件が複雑となっており、チェックの際には注意が必要です。
- 今現在、所有者がその家屋に入居している
- 住まなくなった日から3年が経過する年の12月31日以内に譲渡している
- 家屋の取り壊しをした場合、その土地を他の用途(駐車場など)として使っていない
- 不動産売却の過去2年以内にこの特例を受けていない
- 売主と買主が特別な関係(親族や親子、内縁関係など)ではないこと
そして、以下のような家屋は控除の適用除外となります。
- 新築中の仮住まい等、一時的に入居した家屋
- この特別控除を受けるために入居している家屋
- 別荘、または保養・娯楽施設のために所有している家屋
3,000万円の特別控除については、さらに詳しく掘り下げて解説をしている記事がおすすめです。

「特定の居住用財産の買い替え特例」であれば併用ができる
居住用財産の売却を考えたとき、上記の3,000万円特別控除とマイホーム買い替え特例のどちらが節税対策になるのか?メリットやデメリットはどうなっているのか?と悩む人が多いようです。
まず、買い替え特例は譲渡所得が出た場合の「特定の居住用財産の買い替え特例」と、損失が出た場合の「居住用財産の買い替えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の2種類があることを理解しておきましょう。
そして、買い替え特例にもやはり適用するための条件が定められています。この特例に関する詳しい説明はぜひ、下記リンクからご確認ください。

2,000万円の特別控除(特定土地区画整理事業などのために土地を売却)
特定土地区画整理事業のために土地を売却する場合、譲渡所得から2,000万円が控除されます。
「区画整理」という言葉に聞き馴染みがある人も多いのではないでしょうか。この特例は市街地の再開発や防災設備事業などを目的として、国や地方公共団体などが土地を買取りを申し出た際に対受けることができるものです。
この特別控除に関しては、以下の2点を事前に確認しておきましょう。
- 同一の公共事業に対して2年以上またがって売却できるケースであっても、控除の適用は1度のみ
- 居住用財産との買い替え特例や1,000万円特別控除など、他の控除と併用ができないケースがある
1,500万円の特別控除(特定住宅地造成事業等のために土地を売却)
特定住宅地造成事業のために土地を売却する場合、譲渡所得から1,500万円が控除されます。
これは地方公共団体などがその土地に住宅の建設を目的とするケースや、宅地の造成(特例措置に基づき、住宅などを建設ができる土地にする)を目的とした買取の申し出に対して受けることができる控除です。
主な適用条件は以下の通りです。
- 住宅建設事業のための売却でも適用可
- 特定住宅地造成事業のために売却すること
不動産ではよく「収用」という言葉が使われます。収用とは土地などの所有権を強制的に取得することを指しており、そのための手続きや、損失が起きた場合の保障について規定したものが土地収用法と呼ばれています。
1,000万円の特別控除(国内にある土地を譲渡)
建物ではなく国内にある土地を譲渡した場合、譲渡所得から1,000万円を控除できる制度もあります。もし1,000万円に満たなくとも、譲渡所得額がそのまま控除額となります。主な適用条件は以下です。
- 平成21年に取得した土地は平成27年以降に譲渡
- 平成22年に取得した土地は平成28年以降に譲渡
- 売主と買主が特別な関係(親族や親子、内縁関係など)ではない
- 相続や遺贈などによって取得した土地等ではない
- 譲渡した土地に対して、他の特例を受けていない
なおこの特別控除の対象は、長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在において所有期間が5年超の土地)に限られるため注意が必要です。土地と建物を一緒に購入している際は、土地部分の金額を算定し購入した時の土地金額を差し引き、土地の売却益を計算しておきましょう。
800万円の特別控除(農地保有の合理化のために土地を売却)
農業委員会のあっせんなどにより、農地保有の合理化のために農地を地域の担い手に売却した場合、譲渡所得から800万円を控除できます。
農地保有の合理化とは、担い手農家の経営規模の拡大や農地の集団化などにより、効率的な農業生産が行われるようにすることです。有効活用されていない農地を譲渡したい場合は、この特別控除を活用しましょう。
2020年7月1日より開始した100万円の特別控除(低未利用土地等を売却)
上記で紹介したものだけではなく、2020年7月1日から「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」という制度が始まりました。この特別控除は、500万円以下の不動産を売却した際、譲渡所得から100万円を控除できるものです。適用条件の詳細は、次の通りです。
- 譲渡年の1月1日において所有期間が5年をオーバー
- 譲渡物件が都市計画区域内にある
- 適用期間は2020年7月1日から2022年12月31までに行う譲渡
- 譲渡物件が低未利用土地等であり、譲渡後の土地等の利用について市区町村長の確認がなされたもの
都市計画区域は、都市計画法に基づき計画的に街作りを行うために指定されたエリアのことです。また、空き家や空き店舗などの建物付きの不動産も、譲渡物件に含まれています。
参考:国税庁「譲渡所得の特別控除の種類」「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
譲渡所得の特別控除を受けるための手続きについて

譲渡所得の特別控除を適用させるためには、確定申告が必要です。
この章では、確定申告の方法や必要書類、手続きの期限などをそれぞれ詳しく紹介します。
確定申告の手続きが必要
特別控除の特例を受けるためには、確定申告をしなければなりません。確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間に得た所得の合計を計算し税務署に申告・納税する手続きのことです。忘れてしまうと、特別控除が受けられないだけではなく、脱税になってしまう恐れもあります。
また、利益が出た場合のみ確定申告が必要とされていますが、損失が出ても確定申告することをおすすめします。なぜなら、赤字の所得を黒字の所得から差し引く損益通算によって、節税できる可能性があるからです。
不動産売却をした際の確定申告について、詳しく知りたい人はこちらの記事もおすすめです。

確定申告の方法
確定申告は、直接税務署に行って申告する方法の他にも、書類を郵送で送ったりネット上でも申告が可能です。初めて申告する場合は、分からないことも多いと思うので窓口で申請しましょう。そうすれば、税務署のスタッフに相談しながら、その場で申請書の作成や提出書類の確認がおこなえ、安心して手続きを進められます。
また「e-Tax(イータックス)」というオンラインサービスで確定申告することも可能です。e-Taxを利用する方法は、以下の2通りになっています。
| e-Taxを利用する方法 | 詳細 |
| マイナンバーカード方式 |
|
| IDパスワード方式 |
|
PCだけなくスマートフォンからも申請できますので、仕事などで忙しく税務署に行く時間がない場合は、積極的な活用をおすすめします。
手続きに必要な書類
確定申告に必要な書類は、自身で準備する不動産に関する書類だけではなく、税務署・役場・法務局で入手する書類もあります。
| 必要書類 | 詳細 |
| 自身で準備する不動産に関する書類 |
|
| 税務署・役場・法務局で入手する書類 |
|
また特別控除の種類によって必要書類が異なるため、下記リンク先のチェックシートを活用すると便利です。さらに詳しく調べたい場合は、国税庁のホームページを確認するようにしましょう。
参考:国税庁「土地や建物など譲渡所得について主な特例の適用を受ける場合の申告書添付書類チェックシート」
手続きの期限
確定申告の期限は、不動産を譲渡した年の翌年の2月16日~3月15日の間であることが一般的です。この間に手続きしないと特別控除が受けられなくなってしまうので、忘れずに対応しましょう。
もし自分で手続きができそうにない場合は、税理士に依頼することもおすすめです。費用はかかるものの、税金のスペシャリストが申告を代理してくれるため、脱税や期限忘れのリスクを避けることができます。
譲渡所得の特別控除を受ける際の注意点

譲渡所得の特別控除を受ける際、以下の注意点をおさえておきましょう。
- 特別控除額は5,000万円までが限度になる
- 相続した空き家の売却には期限が定められている
- 適用が除外される場合もある
- 適用要件の確認を忘れない
正しく節税できるように、こうした譲渡所得の特別控除を受ける際の注意点も参考にしてください。
特別控除額は5,000万円までが限度になる
ここまで様々な種類の特別控除を紹介してきましたが、その年に発生した譲渡益の全体を通じて、特別控除が受けられるのは合計5,000万円までと定められています。そのため、複数適用条件に該当したとしても、特別控除額は5,000万円までが限度と認識しておきましょう。限度額に達するまでの特別控除額は、その額が高い順から合計していきます。
相続した空き家の売却には期限が定められている
相続で取得した居住用財産は、平成28年4月1日~令和5年12月31日までの間に売却しないと、最高3,000万円までの特別控除を受けられません。また、対象となる不動産も以下のように定められています。
- 昭和56年5月31日以前の建築
- 相続開始の直前で被相続人以外に居住していた人がいない
- 区分所有建物登記がされていない建物
自分が住んでいた住居のみならず、相続した空き家の売却においても、特例を利用できるのか事前に確認しておきましょう。
適用が除外される場合もある
マイホームの売却に関する3,000万円の特別控除では、特例を受けるための売却や別荘として所有していた場合、適用不可になってしまいます。仮に店舗と居住を共有している住居であれば、居住スペースのみ適用されますが、居住スペースが全体の90%以上を占めている場合はすべて適用されるという基準もあります。
いずれにしても、特別控除の適用が除外されてしまうケースがあることも認識しておきましょう。
適用要件の確認を忘れない
譲渡所得の特別控除は、特例ごとに適用条件が異なります。そのため条件を事前によく確認し、テンポよく手続きを進めていくことが大切です。
また家を売却することになった場合、できるだけ早めに対応することも重要となります。場合によっては、期間が定められている特別控除の適用条件から外れてしまうリスクがあるからです。不動産売買では、不動産会社や税理士などの専門家からサポートを受けながら、速やかに行動することを心がけましょう。
まとめ

定められた要件を満たすことで所得を減額できる譲渡所得の特別控除は、不動産を売却する際に上手く利用することで節税ができます。控除には複数の種類があり、それぞれ適用できる条件や控除額が異なる他、相続した空き家の売却には期限が定められているので控除を受ける際には注意しましょう。
譲渡所得の特別控除を受けるためには、確定申告が必須となります。確定申告のやり方や必要書類、手続きの期限について、事前に確認しておくとスムーズに行うことができます。確定申告の方法に不安がある方は、税務署の職員に相談したり、税理士に依頼すれば安心して進められるでしょう。譲渡所得の特別控除について理解を深め、しっかりと節税対策をして不動産を売却してください。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。