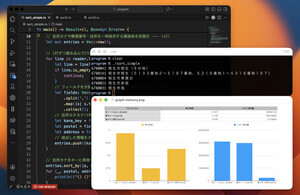先月(2023年9月)に、NATOがフィンランドで演習 “Exercise Baana” を実施した。その際に、英空軍のユーロファイター・タイフーンFGR.4と、ノルウェー空軍のF-35AライトニングIIが、フィンランド国内にあるハイウェイ・ストリップを使用して、初めて道路上での離着陸を実施した。F-35Aが道路上での離着陸を実施したのは、これが初めてのこと(F-35Bは、以前に別のところでやったことがある)。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。
道路を使用する分散運用の本質
もともとフィンランド空軍ではF/A-18C/Dホーネットを道路上で運用しており、そのために長い水平直線道路を国内のあちこちに確保している(Google Mapsの航空写真で探してみよう)。そして、道路から戦闘機を飛ばすといえば、なんといっても冷戦期のスウェーデンが有名。
ハイウェイ・ストリップといわれているが、スウェーデンでもフィンランドでも、「幹線道路」という方が実態に近いだろう。日本でいうところの高速道路とは限らない。
さて。本来の航空基地とは別に道路から離着陸できるようにすることに、どんな狙いがあるのか。パッと思いつくのは「基地の滑走路が敵軍の攻撃で壊されても戦闘機の運用を継続できる」だろう。それは確かにその通りなのだが、道路だって物理的に存在する不動産なのだから、敵軍の攻撃目標にされる可能性はある。どちらにしても、滑走路を壊したり修理したりのイタチゴッコは避けられない。
むしろ意味合いとして大きいのは、「戦闘機を発着できる場所の選択肢を増やし、機敏に場所を移動しながら運用することで捕捉を困難にする」ではないだろうか。滑走路は壊されても修理する手立てがあるが、戦闘機はいったん壊されたら補充が困難だから、そちらの保全の方が大事だ。
決まった空軍基地からしか戦闘機を飛ばしません、ということになれば、その基地を攻撃目標にすればいい。しかし、分散運用のためのベースがいくつも周辺にあり、かつ、それらを飛び回りながら運用するとなると、戦闘機戦力の捕捉は困難になる。
敵軍にしてみれば、送り狼みたいになって「どこに着陸するか」とつけ回して、降りたところで攻撃を仕掛けなければならない。これを継続的に行うのはけっこうな手間である。では、立場を逆にして見たらどうなるか。
迅速な再発進の必要性
戦闘機がどこかの道路に降りて、燃料・兵装の補充を行って再発進する。敵軍の送り狼が着陸場所を突き止めて、その後に攻撃を仕掛けてくる可能性を考えると、再発進はできるだけ迅速に行いたい。
そして、戦闘機の運用に必要な支援機材はすべて移動式にしておいて、再発進が済んだら直ちに店じまいして別の場所に移動する。ここまでやれれば、捕捉・破壊は困難になると期待できる。
米空軍がしばらく前からいいだして、最近では英空軍も始めているACE(Agile Combat Employment)のキモは、おそらくはこの辺にある。抜き打ちで別の分散基地に展開して航空作戦を展開するプロセスに、慣れておこうという話。
すると、その再発進のプロセスをどれだけ迅速に行えるかどうかが鍵になる。そしてこれは、単に人員・機材の問題だけでなく、機体の設計にも関わってくる問題となる。
例えば、冒頭で触れたF-35Aのケース。ノルウェーのF-35Aは氷結した滑走路で安全に着陸・停止できるようにドラッグシュート(制動用パラシュート)を備えているが、着陸後にドラッグシュートを畳んで収容する手間がかかる。タイフーンや、サーブJAS39グリペンはカナード(先尾翼)を立ててスピードブレーキにするから、ドラッグシュートは持っていない。
また、支援機材をたくさん必要とする機体では、再発進の際に機体の周囲に多数の機材が取り付くことになるし、その分だけ人手も多く必要とする。それなら支援要員や支援機材を最小化する方が望ましいが、これもまた、機体の設計に関わる問題になる。
例えば、機体を地上で移動するための牽引車や、エンジンを始動するための起動車を別に用意する必要があるのと、機体が自力で解決できるのと、どちらがいいか。
つまり、機体が地上に降りてから再度、飛び立つまでにかかる時間、すなわちターンアラウンドタイムを短縮しようと思ったら、最初からそのつもりで機体を設計しなければならないということ。
軍用機に限った話ではない
ここまでは「つかみ」の話題の関係から戦闘機の話をメインにしてきたが、ターンアラウンドタイムの短縮は、なにも戦闘機に限った話ではない。民航の分野でも重要である。
LCC業界の標語は「飛ばない飛行機は利益を生まない」であるらしい。手持ちの機体の数が同じなら、それを使ってできるだけ多くの運航を行い、お客を乗せて売上を稼ぐ方がいい。燃料や乗務員みたいに、運航する度にかかる経費は増えるが、機体にかかるコストはそこまで増えない。
しかしそれをやろうとすると、機体が地上にいる時間をできるだけ短くしなければならない。目的地に着いてお客を降ろしたら、速やかに次のお客を乗せて飛び立つ。これもまたターンアラウンドタイムの問題である。燃料補給、機体の点検整備、そして降機・機内整備・搭乗にかかる時間の短縮が鍵を握る。
ただし、戦闘機の業界では「ターンアラウンドタイムの短縮を図るための専用設計」が可能だが(具体例は次回に取り上げる)、旅客機はありものを使うしかない。だから、機体の構造・設計に関する工夫よりも、運用の工夫に依存する部分が大きくなりそうだ。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、姉妹連載「軍事とIT」の単行本第3弾『無人兵器』が刊行された。