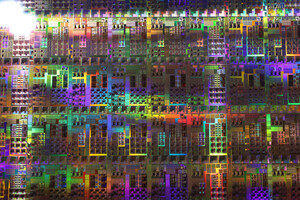2024年11月7日に開催されたArmの年次イベント「Arm Tech Symposia 2024」に経済産業省(経産省) 商務情報政策局長の野原諭氏が登壇。ゲスト基調講演として「我が国の半導体政策」をテーマに、日本の今後の半導体産業の方向性についての政府の考えを披露した。
現在の日本政府が進める半導体政策の3つの目的
野原氏は、現在、日本政府が推進している半導体政策には3つの政策目的があるとする。1つ目は将来の半導体不足から日本国民の生活や産業、そして経済活動を守ることで、安定供給の確保の意味合いを挙げる。奇しくもコロナ禍で生じた半導体不足により、一般生活でさまざまなものが手に入らないという状況が生じた。
こうした経験は日本のみならず世界各国で生じ、少なからず半導体の現代社会における重要性をグローバルで浮き彫りにする結果となった。日本のみならず、各国が半導体政策を重視し、自国内での安定供給を図ろうという動きを見せるようになった。日本も同様に半導体の確保に向かおうということとなるわけだが、過去の政府方針とは異なり、日本経済の安定供給に貢献する国内投資であれば、国内外の企業問わずに支援すると割り切った政策展開を進めることにした点が大きな意味を持つこととなる。
2つ目は経済成長戦略としての半導体戦略という観点。社会活動になくてはならないと認識された半導体は、社会のデジタル化を背景に、その市場規模を拡大。1兆ドル産業になると予測される規模へと成長しつつある。あらゆるものに使われる重要物資であり、その結果、成長が持続する稀有な産業と認識されるようになった。そうした産業を各国とも、自国の基幹産業として持ちたいという思惑を持ち、次々と有利な条件を打ち出し、グローバルな半導体企業の誘致合戦を繰り広げるようになっている。こうした世界情勢の中、日本にそうした企業を誘致しようと思えば、各国と比べても見落とししない支援策を打ち出す必要がある。そうした意味で、大規模な財政出動が必要であり、過去3年間で約4兆円という支援を実施。これだけの規模は、これまでの日本の経済政策の中でも類を見ないとする。
野原氏は「日本の産業は自動車が引っ張ってきた。それに続いて、半導体産業も基幹産業として育て、将来にわたって成長させていくことが重要」との認識を強調した。
そして3つ目はグリーントランスフォーメーション(GX)、いわゆるエネルギー政策との関係性という観点。生成AIの登場により、データセンターで消費する電力量は劇的に増加しており、データセンターを建てようと思っても、電力の供給が追い付くのか、という問題が懸念されるようになっている。「電力需給がAIの社会実装の上限になってくるという心配がある」(同)ということで、そうした懸念を少しでも減らすために、テクノロジーによって電力消費を抑制していくことが重要になる。そうした低消費電力テクノロジーの社会実装の代表的な例が半導体のイノベーションとなる。
プロセスの微細化は半導体の低消費電力技術の進展も促してきた。現在も材料、素子、アーキテクチャなどさまざまなレイヤで消費電力の削減に向けた挑戦が続けられ、新たな製品へと実装され、社会へと還元されており、Rapidusが目指す2nmプロセスの量産であったり、NTTが中心となって推進する光電融合技術なども今後、社会実装が進むことが期待される。
野原氏はこうした政策展開を図っていくうえで、過去の政策の振り返りを行い、日本の半導体デバイス産業が凋落した理由を分析、5つの反省点を踏まえて取り組んでいるとする。
日本政府が考える日の丸半導体凋落の5つの要因
1つ目の反省点は日米貿易摩擦のころに締結された日米半導体協定。野原氏は、日本が半導体で強くなった結果、グローバルでの国際共同研究の仲間として参加できなくなったりしたことに触れ、「国際連携、仲間づくりの失敗」があったとする。
2つ目の反省点は、垂直統合(IDM)から水平分業へのビジネスモデルの変化の波に乗れなかったこと。日本の半導体ビジネスの多くは電機メーカーの一部門という位置づけで、半導体の設計、製造から最終製品までがセットで提供されるIDMが主流であった。これはデジタル家電の波が押し寄せた2000年前後であっても基本姿勢は変わらず、電機メーカーの多くが身動きがとりやすいように半導体事業だけを分社化したのは、さらにその後であり、そのころにはTSMCをはじめとするファウンドリに製品製造を委託するファブレスという水平分業モデルが主流になりつつあった。野原氏は、自社ブランドでの製造を行わないファウンドリという存在が多くのファブレスを育てたとし、ファウンドリとして日本にもRapidusが立ち上がったが、「提供する顧客価値はなんであるのかを考えなければ、すでにTSMCという優秀なガリバーがいる中で顧客が振興企業を試してみようという話をしてくれない。同じようなことをやって、質が劣るものができたとして、それを顧客が必要するのか? ということになる。TSMCが量的に対応できないときのバックアップ以上の価値はなくなる。そういうビジネスモデルではなく、きっちりと成長を目指すためには、Rapidusにしかない顧客価値がなければビジネスとして試してみる価値がないと思っている」とし、オール枚葉を掲げ、他社よりも早い生産性を差別化要因とするRapidusが価値を生み出すことへの期待を述べた。
3つ目の反省点はデジタル産業化の遅れ。PC、スマートフォン(スマホ)、そしてデータセンターと、世界的にデジタル技術の活用に向かう中にあって、川下のそうした多くの産業がグローバル展開に足踏みをした結果、売れる半導体が生み出せなかったことを踏まえ、「スマホの後、データセンター、AI、自動車、ヘルスケアなど、次の川下の最先端半導体を活用する産業において、海外の顧客を捕まえることで、日本として強い産業へと育てていくかがカギになる」とする。
4つ目の反省点は日の丸自前主義へのこだわり。Rapidus設立以前にも日本の半導体メーカーを統合した日の丸ファウンドリ構想などもあったほか、国家プロジェクトとして半導体の技術開発なども多く進められてきた。古くは超LSI技術研究組合であったり、EUV露光装置の開発を目指したEUVAなどがあるが、その多くが日本企業で構成されていた。「日本の企業や国民が負担してくれた税金を投じるのであれば、日本企業に投じないといけないという思いがあった」と野原氏は当時の状況を振り返るほか、官民の役割分担として、国は研究開発は支援するが、その後の事業化からは手を引くということで、研究開発から事業への橋渡しがうまくいかなかった点があり、日本企業のみの集団となった結果、国際競争力に乏しく、結果としてうまくいかなかったとの見解を示し、「もっとも国際的に競争力のあるパートナーと日本企業が組んで、競争に乗り出していくことが重要」という方向にシフト。安定供給のためには海外から強いグローバルプレイヤーを呼び込む方向性を指向することにしたという。
そして5つ目が競争力があった時代に、産業政策を批判された結果、政府として萎縮したという点。産業政策を推進しようとすれば、米国から批判がくる可能性などを考慮している間に、台湾など別の国や地域で半導体産業が成長していくこととなった。また米国自身も安全保障の観点から政府が産業への投資を積極的に行っており、そうした世界的な動きを踏まえ、日本も同様の方向へと方針転換をすることにしたとする。
日本の半導体産業は復活するのか
既報のとおり、日本の半導体産業復活に向けては3つのステップが戦略として提示されている。その中でも重要とされているのが国内での先端半導体の製造基盤整備。TSMCが熊本県にJASMを立ち上げ、22/28nmおよび12/16nmプロセスラインを設置することを決めるまで、日本にはロジックプロセスについては、ルネサス エレクトロニクスの那珂工場など、ごく一部の半導体工場(ファウンドリ含む)で製造されていた40nmプロセスがもっとも微細なプロセスであった(かつては一部の工場では32nmプロセスまで進めるロードマップを描いていたがさまざまな事情からとん挫している。また、メモリに関してはエルピーダの後を継いだMicron、東芝から独立したキオクシアならびにパートナーのSanDiskと同社を買収したWestern Digitalが微細化や3D積層を継続して進めてきた)。
特にこのJASMに関しては、九州地方での投資の盛り上がりの呼び水となっており、半導体関連投資のみならず、半導体向け技術開発投資による精密機械や大型の製造工場新設の増加、食品や輸送用機械などの増加といった製造業関連全体の設備投資を増加させる効果があったとするほか、雇用についてもJASMそのもので2024年4月時点で約1500人の従業員雇用に加え、試算では2022年~2031年の10年間で熊本県内の電子デバイス産業全体(熊本県にはソニーセミコンダクタソリューションズの工場などのほか、製造装置メーカーの拠点などもある)で1万700人の雇用効果が見込まれるとする。
さらに、そうした企業で働く熊本県内の一人当たり雇用者報酬増加効果は年間で38万円の増加とされ、JASMの設置自治体である菊陽町は、TSMC(JASM)からの税収増を見込み、町内の小中学校8校の給食費ならびに保育施設における副食費の2025年度からの無償化を予定するなど、さまざまな波及効果が生まれているという。
一方、北海道での拠点建設を進めるRapidusだが、政府はこれまでの3年間で合計最大9200億円の支援を決定している。ちなみにこれらは補助金ではない点に注意が必要である。現在、北海道で建設が進められている工場の建屋や製造装置は国(新エネルギー・産業技術総合開発機構、NEDO)の資産という扱いであり、Rapidusのものではないためである。Rapidusは2027年10月の量産開始を目指して研究開発を進めているが、それまでにこうした国の資産をどのようにして引き渡して商用サービスに活用していくのかがポイントになってくるとする。
野原氏によれば、Rapidusによる2nmプロセス開発は順調に進行しているとのことで、2025年春にはテストラインが立ち上がり、同年内に現在、米ニューヨーク州アルバニーのIBMの拠点でIBMのエンジニアとRapidusのエンジニアが開発している量産技術の移管を進め、2025年中のテストチップ製造ならびにPDK(プロセス デザイン キット)の作成が予定されている。
さらに、そうした先端プロセスを活用した半導体回路の設計そのものや、そうした設計のためのツールを活用ができる人材の育成にも国として注力していく姿勢も見せる。回路設計人材の育成としては、LSTがホストとなり、Tenstrrentに人材育成プログラムを委託する形で、トータル1000人の回路設計エンジニアの育成を目指すとするほか、後工程についてもTSMCやSamsungの研究センターの開設に加え、Intelやダイフク、レゾナック、村田機械、ローツェなど日本の製造装置・材料企業で構成される「半導体後工程自動化・標準化技術研究組合(Semiconductor Assembly Test Automation and Standardization Research Association:SATAS)」への支援も決定するなど、半導体産業全体の育成を推進しているとする。
今後についても、岸田内閣時代に出された2024年の骨太の方針において、複数年度で大規模計画投資を検討するという方針が打ち出されており、その具体化作業に取り組んでいるとするほか、石破総理も総裁選のころより、半導体への投資を自身の公約の1つとし、岸田内閣の方針を継続することを示唆してきたことから、半導体への投資は引き続いて行われていくとの見通しを示す。また、現在、10月に行われた衆議院選挙にて与党であった自民党・公明党の議席が過半数割れを起こすという結果となったが、野原氏は野党である国民民主党も立憲民主党も半導体への重点投資ということを掲げていることから、与野党の垣根を越えて協力していける雰囲気があるとの見方を示しており、政策として半導体産業の成長を推し進める方針に変わりはないとしていた。