マンションの購入は人生の中でもトップクラスの出費となり、失敗しても簡単に買い直すことはできません。ローンの支払いは数十年続き、将来の生活もある程度決まってくるため、慎重に選びたいものです。
そこでこの記事ではマンション購入で抱えるリスクと、後悔しないための物件の選び方を紹介していきます。すべてのリスクをゼロにはできませんが、長期で問題に直面することなく快適に生活を送れるようになるでしょう。もしものときの対処法も紹介しているので、ぜひ参考にしてマンションの購入を決断してください。
※株式会社リンクアンドパートナーズによる調査。アンケートモニター提供元:GMOリサーチ株式会社
マンション購入の7つのリスクとは

マンションの購入は、これまで賃貸に住んでいる人にとっては人生の転機になり、自身が考える理想の住まいが手に入って快適な生活ができるだろうと思いを巡らせます。しかし実際に生活を始めてから抱えることになるリスクに気づくと、後悔はいつまでも続いてしまうでしょう。そこでマンションの購入前に知っておきたい次のリスクについて解説していきます。
- 購入した直後から築年数で資産価値の低下
- 収入の低下でローンの返済が破綻
- 住民トラブルから簡単に逃げられない
- 購入するマンション自体に欠陥
- 高層階は災害で生活に支障
- 住民の減少で不十分な管理
- 独身での購入は結婚や出産で暮らしづらい
購入した直後から築年数で資産価値の低下
しっかりしたつくりのブランドマンションであっても、築年数による経年劣化は避けられません。マンションの資産価値は購入したときが最大で、築年数とともに低下していくことが基本です。例えば築35年ともなると、新築時の3割程度の価値になってしまいます。
マンションよりも構造の耐久性が低い木造の戸建住宅では、築15年で新築の2割程度の価値になります。マンションのほうが少しはマシですが、将来手放すときに購入時よりも高く売却することは困難です。
また新築のマンションは住み出すと新築の価値はなくなり、それだけで2割程度は低下するといわれています。3,000万円で購入したマンションを、諸事情で1年後に売却することになったとして、3,000万円で売り出したとしてもなかなか購入希望者は現れません。
収入の低下でローンの返済が破綻
マンションは高額な商品なので、購入する人の多くはローンを利用します。借入期間は数十年になり、長いものでは50年間毎月支払いを行います。しかしそれだけの長い期間、安定した収入があり続けると断言することは難しく、万が一勤め先の経営不振や倒産で収入が減ったとしても、返済額はそのままです。
もしローンの滞納が続いてしまうと、最終的にマンションは競売にかけられて売れた額は返済に充てられます。不足分は借金として残り、住処も失う悲惨な状況になりかねません。新型コロナのような突発的な事情で経済が低迷することもあるため、完済までリスクは残り続けます。
ローンを滞納する危険性について、詳しく知りたい方にはこちらの記事もおすすめです。

住民トラブルから簡単に逃げられない
購入するマンションの立地や間取りは選べても、同じマンションに住むことになる住人は選べません。理不尽なクレームをしてくる人がいても、近所付き合いは続きます。特に新築のマンションを購入する場合は、どのような人が住むことになるのかを予測することは不可能です。賃貸であれば引っ越すことで住民トラブルから逃げられますが、購入してしまうと簡単にはいきません。
明確なクレーマーはいなくても、マンション内では格差も問題になります。低層階と高層階で価格に大きな違いがあることから、生活レベルの違いで格差が生まれます。マンション全体で、微妙な雰囲気がいつまでも続くことになるのです。
購入するマンション自体に欠陥
実際に遭遇するリスクは低いのですが、購入したマンション自体に欠陥がある可能性もゼロではありません。過去には構造の計算書を偽造して十分な耐震性がなかったり、ずさんな工事でマンションが傾いたりしたケースがありました。建て替えが必要になると、元の生活に戻れるまで長い年月がかかります。
マンションの欠陥は、新築の物件選びでモデルルームを見るだけでは気づけず、完成前のディベロッパーによる現場見学でも見えない部分は判断できません。そのため、欠陥が大々的に報道されると資産価値は大幅に下がり、売却しようとしても敬遠されてしまいます。
高層階は災害で生活に支障
購入するマンションの部屋は、景観や防犯性を考えると高層階が魅力的です。しかし高層階になるほど、災害が起きたときの生活への支障は大きくなります。例えば電気系統が故障するとエレベーターは使えず、外出するときは毎回長階段の上り下りが必要です。また生活用水の排水が十分にできず、トイレに困ることもあります。
購入するマンションが、最新の建築基準を満たして安全性を謳っていても、地震や台風などでどこまで被害が出るのかを正確に予測できません。災害が起きたときは、高層階に住んでいる人ほど日常生活が戻るまで苦労してしまいます。
住民の減少で不十分な管理
マンションの維持管理は、住民から徴収される管理費や修繕積立金で成り立っています。大規模な修繕は定期的に必要で、老朽化が進むと建て替えも必要になるでしょう。
しかし何十年も住んでいると住民の高齢化が進み、購入したときは満室でも将来は空室が目立つかもしれません。そうなると維持管理の費用が十分に集まらずにマンションが荒れやすくなります。管理組合が機能しなくなってしまうと、大規模修繕や建て替えの計画がまとまらず、住民はさらに減っていきます。
マンション管理の現状や管理組合の仕組みについて解説したこちらの記事もおすすめです。
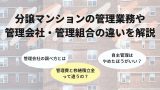
独身での購入は結婚や出産で暮らしづらい
生涯独身のつもりで住みやすい間取りのマンションを購入しても、すてきな出会いがあれば結婚して一緒に住むこともあり得ます。もしワンルームなどの独身向けのマンションであれば、2人で生活することは手狭に感じてしまうでしょう。
出産でさらに家族が増えると寝るスペースの確保さえ難しくなり、住み替えが必要になってしまいます。しかしローンが残っていると簡単に住み替えはできないため、不自由な生活が続くことになりかねません。
リスクを回避できるマンションの選び方

リスクがあると分かってしまうと、マンションの購入を躊躇してしまいます。しかしマンションの購入を諦めるのは待ってください。次で紹介する物件の選び方によってリスクは回避しやすくなります。
- 購入するマンションは人気のエリアから選ぶ
- ローンの返済に余裕のあるマンションにする
- マンションのディベロッパーの実績を見る
- マンションの立地をハザードマップで確認する
- マンションの階数は妥協点を探しておく
それぞれ、どのように選ぶのかを詳しく見ていきましょう。
購入するマンションは人気のエリアから選ぶ
築年数による資産価値の低下は避けられませんが、需要があるマンションの場合は古くなっても高値が付きやすいです。需要があるマンションで重要になるポイントは、人気のエリアにあるかどうかです。次のようなエリアであれば、購入の選択肢に入れてよいでしょう。
- マンションからの景観がよい
- 高級住宅街などのよいイメージがある
- 使い勝手のよい交通機関が近くにある
- スーパーや病院、役所など生活に関わる施設が近い
- 再開発が行われる予定がある
人気のエリアであれば、たとえ空室ができてもすぐに新しい入居者が現れ、マンションの管理も維持されます。
資産価値のあるマンションの選び方や、資産価値の計算方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。


ローンの返済に余裕のあるマンションにする
理想のマンションに住むためであっても、高額すぎると滞納するリスクは高まります。できるだけローンの返済に余裕がある範囲で、中古も視野に入れて購入予算を決めましょう。
目安となるのが、次の式で求められる返済負担率です。
ローンの審査でも使われますが、額面年収ごとに返済負担率の基準があります。フラット35と呼ばれるローンでは、額面年収が400万円以上あっても返済負担率は35%以下にする必要があります。
しかしローンの審査に通る返済負担率でも、手取りの年収で考えると生活はギリギリになってしまうでしょう。余裕のある生活を送るためにも、返済比率が20%程度に抑えられる価格のマンションを選んでください。手取り換算で返済額が月収の3分の1程であれば、多少の収入減少にも耐えやすいです。
返済負担率について、借入金額ごとの返済額の計算例を詳しく知りたい方は、こちらの記事が参考になります。

マンションのディベロッパーの実績を見る
購入するマンションの欠陥は、中古であれば目視である程度は問題箇所を確認できます。しかし新築は判断が難しいため、ディベロッパーの実績から信頼できるマンションなのかを見極めましょう。
大手が販売するブランドマンションでも、実際の設計や施工は下請けが行い不正が行われている可能性はあります。設計から販売、管理まで全て1社で行っているディベロッパーのマンションであれば、欠陥のリスクを下げられ長く安心して暮らせます。
マンションの立地をハザードマップで確認する
災害のリスクを避けたい人は、購入を考えているマンションがある地域のハザードマップを確認しましょう。ハザードマップとは、洪水や土砂災害、地震などの被害が起きやすい地域が示された地図で、危険な地域が一目で分かります。
ハザードマップは、マンションがある地域の自治体が作成したパンフレットや、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」から確認が可能です。安全を重視するのであれば、ハザードマップの警戒区域内にあるマンションは避けたほうがよいでしょう。
マンションの階数は妥協点を探しておく
ハザードマップで安全な地域のマンションでも、災害は想定外に広がることもあります。しかし深刻な被害が出る災害は滅多に起きないため、リスクを警戒しすぎても損です。マンションの高層階と低層階では次のメリット・デメリットがあります。
| 階数 | メリット | デメリット |
| 高層階 |
|
|
| 低層階 |
|
|
購入するマンションの階数は、メリットとデメリットを比較して自身が妥協できる範囲で決めましょう。正解はないため、中古マンションであれば内覧で問題がないかじっくりと検討してください。
将来の家族の人数にあった間取りや広さにする
生活しやすい間取りや部屋の広さは、人数ごとに次のようになっています。
| 家族の人数 | 間取り | 広さ |
| 1人 | 1DK、1LDK | 40~50平米 |
| 2人 | 1DK、1LDK | 55~75平米 |
| 3人 | 2LDK | 75~100平米 |
| 4人 | 3LDK | 95~125平米 |
1Rでなければ、1人向けでも2人までは問題なく住むことはできますが、3人以上になると1人向けでは苦労します。将来の住み替えを避けたい人は、家族の人数に合った余裕のある間取りや広さのマンションを購入しましょう。十分な収入があり結婚の予定はなくても、20代でのマンションの購入は避けたほうがリスクは少なくなります。
購入したマンションでリスクが深刻化する前の対処法

リスクを回避できる厳選したマンションでも、住みだしてから発生するトラブルはあります。そこで問題が深刻化する前にやるべき3つの対処法について解説してきます。
- 住民トラブルは第三者を挟んで対処
- 資産価値が残っている内に住み替え
- ローンは滞納前に銀行で相談
住民トラブルは第三者を挟んで対処
自身に全く落ち度がない状況でも、クレームを入れられたり被害を被ったりすることがあります。しかし直接相手にすると、問題はこじれて解決不可能になるかもしれません。感情的な言い合いになり、暴行に発展することもあるため危険です。
穏便に解決したいのであれば、第三者を挟んで対応するのがおすすめです。まずはマンションの管理組合やオーナーを通して、問題のある住人に改善を求めます。要点を整理してから相談すると、最適な対応を検討してくれます。もし脅迫や嫌がらせなどで直接被害がある場合は、弁護士や警察に相談しましょう。また無料の相談窓口もあるため利用するのも一つです。
資産価値が残っている内に住み替え
老朽化や住民の減少などで資産価値が落ち続けているマンションであれば、できるだけ早く住み替えを検討しましょう。古くなりすぎて管理も行き届いていないマンションは売却できず、相続で子供に迷惑をかけてしまいます。
具体的には、住み替えのタイミングは40代~60代の内がおすすめで、家族構成が変わる可能性が低く、老後を視野に入れた間取りを検討できるでしょう。さらにローンの完済時の年齢制限(80歳が多い)も余裕があります。
売却する際は一括査定が可能なサイトを利用すると、マンションに強い不動産会社に出会いやすく、相場も簡単に把握できます。おすすめの一括査定サイトや選び方を詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

また住み替えの手順については、次の記事で解説をしています。

ローンは滞納前に銀行で相談
長い人生の中で節約していたとしても、経営不振や倒産による減収、両親の介護による急な出費などで、ローンの滞納は起こりやすいです。滞納してしまうことが分かっていてそのまま放置していては、金融機関の対応は厳しく購入したマンションを失うこともあります。
そのため滞納の恐れがあるときは、まずローンを組んだ金融機関に相談してください。一時的な減収であれば返済計画の見直しで月々の負担を減らし、滞納を回避できる可能性があります。
またローンの借り換えで、組んだときより金利の安い金融機関を利用することでも、滞納を回避できるかもしれません。ただし借り換えでは、既存ローンの一括返済の手数料や新規ローンを組む手数料がかり、一時的に出費が増えることがあります。
マンションを購入するための基礎知識

リスクに納得してマンションの購入を決意しても、いきなり気になる物件の購入申し込みをすることは危険です。後悔しないためには、基礎知識として次のことも押さえておきましょう。
- 購入は信頼できる不動産会社に依頼
- マンションの購入までに必要な諸経費
- 購入したマンションのローン以外の維持費
- 購入したマンションでも自由なリフォームはできない
購入は信頼できる不動産会社に依頼
物件探しは不動産のポータルサイトでもできますが、最終的な書類のやり取りは不動産会社のサポートを受けて行います。公開されているマンションの購入は、どの不動産会社からでも手続きは可能ですが、適当に選んでしまうことは問題です。
こちらの要望を汲み取ってくれなかったり、なかなか連絡が付かなかったりすると理想のマンションが見つからず、ライバルに先を越されるかもしれません。また知識不足を狙い、条件の悪いマンションを提案してくることもあり、そうなると無駄に時間がかかります。
不動産会社の善し悪しは担当と実際に話してみて、自身が信頼できるかどうかを判断しましょう。問い合わせだけであれば無料でできるため、利用しやすい不動産会社で相談してみてください。
マンション探しを効率よく進めるなら、「タウンライフ不動産売買」がおすすめ
※株式会社リンクアンドパートナーズによる調査。アンケートモニター提供元:GMOリサーチ株式会社 希望に合う住宅を効率よく探すなら物件情報の一括取り寄せサイトが便利です。住みたい街の情報を入れるだけで、複数の不動産会社から希望の条件にマッチした物件情報が届きます。
とくに、編集部がおすすめしたいサービスがタウンライフ不動産売買です。タウンライフ不動産売買がおすすめな理由を以下にまとめています。
希望に合う住宅を効率よく探すなら物件情報の一括取り寄せサイトが便利です。住みたい街の情報を入れるだけで、複数の不動産会社から希望の条件にマッチした物件情報が届きます。
とくに、編集部がおすすめしたいサービスがタウンライフ不動産売買です。タウンライフ不動産売買がおすすめな理由を以下にまとめています。
マンションの購入までに必要な諸経費
マンションの購入にかかる費用は、広告などに記載されている建物の価格だけではありません。引き渡しまでの手続きの過程で次の費用が必要になります。
| 諸費用の内訳 | 費用の目安 | 支払う理由 |
| 仲介手数料 | 3,000万円のマンションで105万6,000円 | 購入手続きを仲介してもらう報酬 |
| 印紙税 | 5,000万円以下で1万~2万円 | 売買契約書の作成で必要になる税金 |
| 登記費用 | 5万~13万円 | マンションの登記設定で支払う |
| ローンを組むため費用 | 借入額の6~10% | 事務手数料や保証料 |
| 不動産取得税 | マンションの固定資産税評価額の3% | 購入したときに都道府県に支払う税金 |
| 固定資産税などの精算金 | マンションの評価額や売主の負担割合で変動 | 中古マンションの購入で、売主負担分の一部を支払う |
| 引っ越し費用 | 2人家族で7万~10万円 | 購入したマンションへの引っ越し費用 |
新居に合わせて家具やインテリアも一新しようとすると、諸費用はいくらでもかかってしまいます。目安は新築で物件価格の3~5%、中古で6~10%です。
またこれらの費用も、金融機関によってはローンに組み込むことができます。しかし金利は上がってしまうため、その都度支払っていくことがおすすめです。
購入したマンションのローン以外の維持費
購入したマンションはローンの支払い以外に、次のものが維持費としてかかり続けます。
| 維持費の内訳 | 費用の目安 | 支払う理由 |
| 管理費 | 月1万5,000~2万円 | 管理の人件費や共有部分の光熱費など |
| 修繕積立金 | 月1万~1万5,000円 | 大規模修繕に備えた積立金 |
| 駐車場代 | 月5,000~3万円 | 自身の車を停めておくため |
| 保険料 | 年5,000~1万円 | 加入した火災や地震保険 |
| 固定資産税・都市計画税 | 新築で年10万~15万円 | 所有している資産にかかる税金 |
新築のマンションでは、年間の維持費として50万円以上確保しておきたいです。特に管理費・修繕積立金・駐車場代は毎月支払いを求められるため、ローンの返済負担率を下げておかないと生活費が確保できません。
なお固定資産税は、一括か年4回の分割払いを選択できますが、高額のため毎月貯蓄しておくことをおすすめします。滞納してしまうと財産を差し押えられ、解消するために追加で延滞税の支払いも必要です。
購入したマンションでも自由なリフォームはできない
購入したのであれば自由にリフォームしたいと考えていても、マンションでは管理規約によってさまざまな制限がかけられています。例えば窓や玄関ドアは外観のイメージを統一するため、好きな色や材質にリフォームできません。
また内装であっても、強度を維持するために壁や柱の撤去は自由にできず、水の流れを確保するために水回りの移動も制限されます。遮音性を確保するために、床材の性能を定めているマンションもあります。
特に中古マンションの購入を検討している人は、管理規約を確認してどのようなリフォームであれば可能なのかを、専門家に相談しておきましょう。
まとめ

マンションの購入には高額なお金が動き、一度手に入れてしまったら簡単には手放せません。ローンを組むと返済は数十年続き、完済するまでに想定外のことが起きることがあります。リスクとしては資産価値の低下やローンの滞納、住民減少による管理不足などが考えられます。
購入するマンションの選び方によって多くのリスクは回避できますが、住民トラブルや突然の収入低下による滞納の危険については、その都度対処が必要です。紹介してきた内容を頭の片隅に残しておき、将来発生したときはスムーズに対処しましょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。


