住宅ローン関連の記事で「連帯債務」という言葉をよく目にはするものの、連帯債務の概要を詳しく認識している人は少ないのではないでしょうか。
連帯債務とは、夫婦2人の収入を合算してお金を借りることが可能な住宅ローンの形態です。別々に住宅ローンの控除を利用できるため、共働きの夫婦が住宅ローンを選択する際に利用するケースが多く見られます。
今回は、連帯債務に関する基礎知識をまとめました。まずは連帯債務の概要を大まかに学んでから、連帯債務がもつメリットとデメリットについて1つずつ見ていきましょう。合わせて後半部分では連帯債務と連帯保証およびペアローンとを比較していくので、今後住宅ローンを組むときの参考にしてください。
- 連帯債務では1人が主債務者、もう一人が連帯債務者となって同様のローンを借り入れます。主債務者と連帯債務者で同等の返済義務を負っているのがポイントです。
- 連帯債務のメリットは2人分の控除が受けられる、希望借入額の引き上げなどがあります。一方で2人とも安定した収入が必要、離婚しても返済義務あり、団信加入は1人しかできないなどがデメリットです。
- 連帯債務以外にもペアローンや連帯保証を利用してローンを借り入れることもできます。それぞれの特徴を把握したうえで自分に合ったものを慎重に選びましょう。
\住宅ローンを探している人におすすめのサービス2選/
【新規】住宅ローンのプロに相談するなら「HOME'S 住まいの窓口」
不動産の大手ポータルサイトを運営する株式会社LIFULLの「HOME'S 住まいの窓口」では、住宅ローンを含め注文住宅に関するあらゆる相談が無料でできます。専門アドバイザーが中立的な立場でサポートしてくれるため、不動産会社やハウスメーカーなどから営業を受ける心配はありません。
【借り換え】住宅ローンを見直すなら「モゲチェック」
ローンの借り換えなら、低金利のローンへの借り換えサービスが便利です。モゲチェックでは、人気の住宅ローンを比較し、自身が借りられる最も低金利のローン(※)を案内します。毎月の返済額を平均約2万円軽減することも可能です。 ※付帯する団体信用生命保険を加味して運営会社 株式会社MFSが最も低いと判断する金利
連帯債務に関する基礎知識

まずは、連帯債務とはどのようなものなのかを把握しましょう。
連帯債務は、夫婦はもちろん親子関係にある人同士でも利用できるローンの形態です。1人が主債務者となり、もう1人は連帯債務者となって住宅ローンを借入れます。
親子や夫婦の1人が主債務者になる
連帯債務型の住宅ローンでは、夫婦や親子などのどちらか1人が主債務者となってローンの借入れをし、もう1人は連帯債務者として同様のローンを借り入れます。
要するに、主債務者と連帯債務者は同等の返済義務を負うことになり、1人当たりの返済義務が半減されるのです。
例えば、主債務者の夫の収入のみでは借入れを希望する金額に満たない場合、妻が連帯債務者となり収入を合算して希望金額を引きあげる、といった利用の仕方があげられます。
住宅登記の名義は共有名義になる
夫のみの名義で住宅ローンを契約した場合、住宅登記の名義人は当然夫1人です。
一方、連帯債務型の住宅ローン契約時には、住宅登記の名義は出資割合に基づいた持ち分で定めた共有名義になります。
そのため連帯債務を選択するのであれば、まず夫婦で加担する割合を話しあい、お互いが納得できる加担配分を設定したうえでローンを組む必要があります。
フラット35も利用できる
一定の条件を満たせば、フラット35と呼ばれる住宅ローンも連帯債務(収入合算)で利用できます。フラット35とは、民間の金融機関と住宅金融支援機構とがともに提供しているローンのことです。
民間金融機関は、リスクが高い長期固定金利型の商品よりも変動金利型のものを売却したい傾向にあります。そこで、金利が固定されているリスクを住宅金融支援機構が代わりに担うのが、フラット35です。
つまり、民間金融機関が提供する住宅ローンなら契約した金融機関とのやり取りのみとなるのが、フラット35では住宅金融機関が中心となってお金を扱っているのです。
ただし、次にあげる要件をすべて満たしていなければ、フラット35を契約することはできません。
- 申込み者本人の親・子・配偶者など(※直系親族もしくは配偶者・婚約者や内縁関係でも可能)
- 申込み時の年齢が70歳未満
- 申込み者本人と同居している
フラット35には、全借入れ期間が固定金利なので返済額が変動せず安心できたり、「フラット35S」という商品を利用すればさらに金利を引き下げられたりなどのメリットがあります。
一方、返済するときに金利が下がったとしても返済額は下がらない、変動金利よりも金利が高めに設けられているなどといったデメリットも合わせもっているため、利用を検討する際には慎重な判断が必要です。
連帯債務のメリット

連帯債務がもつメリットを次のリストにまとめたので、まずは一覧してみてください。
- 2人の収入を合算できる
- 別々に住宅ローン控除が利用できる
- 借入れ可能額が多くなる場合もある
- すまい給付金が2人とも受給できる
連帯債務型の住宅ローンでは夫婦や親子など2人ともの収入を合算して借入れ可能額を計算するので、1人のみの収入でローン申請をするよりも借入れ額を増やすことができるのです。
2人の収入を合算できる
1人だけの収入では住宅ローンの条件を満たしておらず借入れが難しい場合でも、連帯債務型なら夫婦や親子などの収入を合算することが可能です。
2人分の収入を合算して条件を満たすことにより、住宅ローンの借入れが可能になります。
別々に住宅ローン控除が利用できる
連帯債務者は債務に対し、主債務者と同等の返済義務を負います。そして2人ともが条件を満たしている場合には、それぞれが住宅ローン控除(住宅ローン減税)を利用することが可能です。
連帯債務型の住宅ローンでは、主債務者と連帯債務者がともに返済義務を担うと同時に、同等の優遇措置も受けられるのです。
住宅ローン控除とは
年末調整や確定申告を行えば、入居した年より10年間(※)にわたり、住宅ローンの各年の年末残高のうち1%が所得税から控除されます。連帯債務の場合はそれぞれが契約者となるので、負担割合に応じた住宅ローン控除が受けられます。
仮に、年末時点での住宅ローン残高が3,000万円だったとしましょう。そして、主債務者が60%・連帯債務者が40%という負担割合で契約している場合、主債務者は18万円・連帯債務者は12万円もの所得税が差し引かれることになります。
返済額の持ち分にもよりますが、年間で最大40万円(認定長期優良住宅などは50万円)の控除を受けることも可能なので、こちらの特例はぜひとも活用するようにしましょう。
(※)消費税10%が適用された住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日の間に入居した場合の期間は13年間になります。
借入れ可能額が多くなる場合もある
前述の「連帯債務のメリット/2人の収入を合算できる」でも記載した通り、連帯債務では収入合算ができるので、単独名義で住宅ローンを組む場合よりも住宅ローンの借り入れ上限額を増やすことが可能です。
住宅ローンの借入れ上限額はそのローンの名義人の収入により異なり、収入が多ければその分借入れられる金額が上昇します。つまり、配偶者や親・子などの収入も合算すれば、借入れの上限額を引き上げられるのです。
すまい給付金が2人とも受給できる
すまい給付金とは住宅購入の消費税の負担を軽減させる目的で、収入に応じて10万円から最大30万円の給付金が貰える制度です。
50m2以上の床面積や収入条件など一定の条件を満たしている住宅を、住宅ローンを組んで購入した人に対し、収入金額に応じた給付金が払い渡されます。
こちらの制度では、夫婦や親子などのどちらか1人ではなく2人とも給付金を受け取ることが可能です。そのため、2人の収入によっては合計60万円も支給される可能性があるのです。
ただしこの給付金は、住宅を引渡されてから1年以内に「すまい給付金受付事務局」に出向いて申請しなければもらえません。自分が該当する場合は、早めに手続きを済ませましょう。
連帯債務がもつデメリット
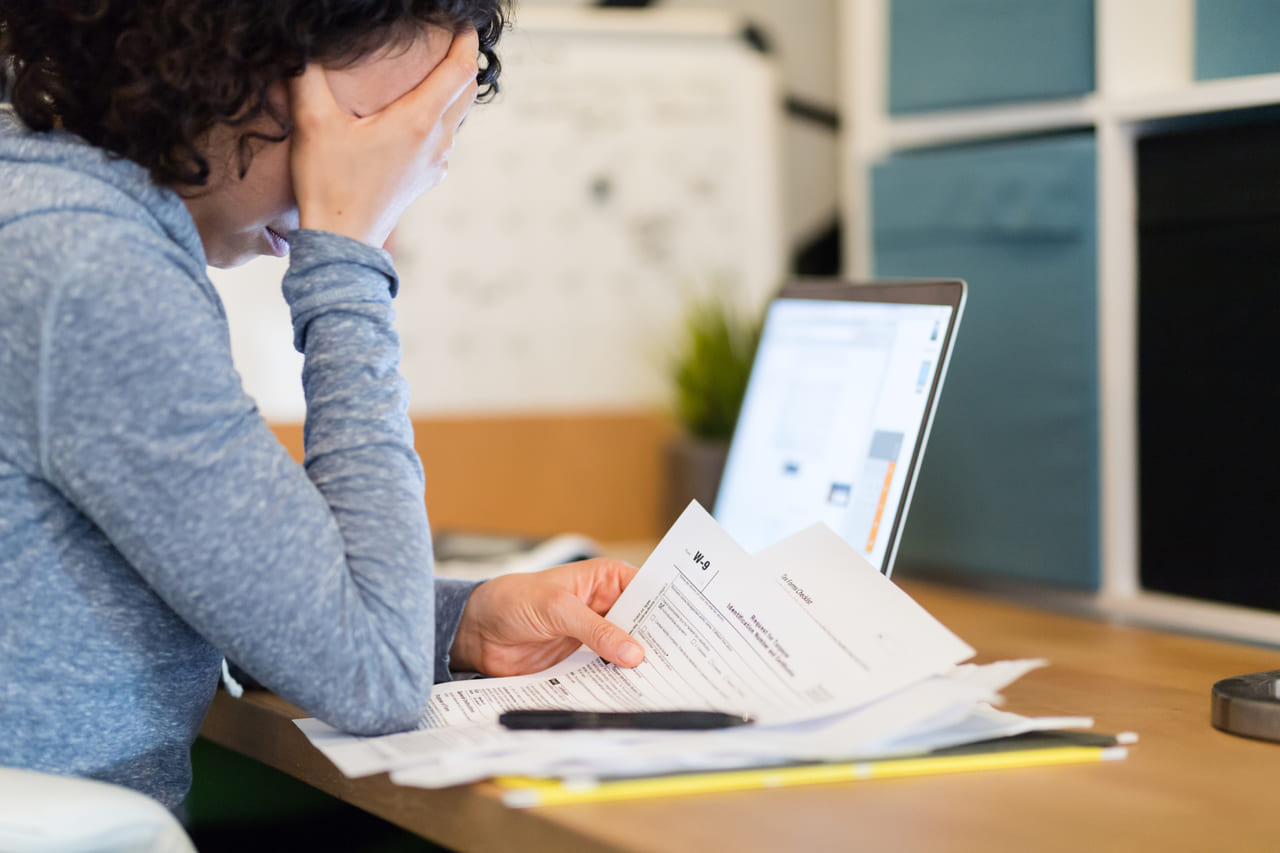
連帯債務は、メリットだけではなくデメリットも合わせもっています。この章では大きく次の6点のデメリットを紹介していくので、しっかりチェックするようにしましょう。
- 連帯債務者になるために安定した収入が必要になる
- 離婚しても返済義務がなくならない
- 育休中や産休中でも返済は免除されない
- 団体信用生命保険(※)に加入できるのは原則1人だけ
- 贈与税の対象になる場合がある
- 将来借り換えが難しくなる可能性がある
中でも注視したいのが「団体信用生命保険に加入できるのは原則1人だけ」という点です。
夫婦や親子関係にある2人ともが保険に加入できないため、保険に加入できていないほうの人の身に万が一のことがあった場合には、1人だけでローンの残債を抱えていかなくてはなりません。
連帯債務者になるために安定した収入が必要になる
連帯債務者は主債務者と同等の返済義務があるので、連帯債務者になるためには主債務者と同じように安定した収入を得ていることが必要です。
さらに、今後も継続して収入を得られるかどうかも大切なポイントとなります。
離婚しても返済義務がなくならない
主債務者である配偶者と離婚したとしても、ローンの返済義務がなくなるわけではありません。
また、連帯債務者がもっていた住宅の所有権がなくなった場合でも、住宅ローンの契約はそのまま残っているため連帯債務者の返済義務は消失しません。
そのため、連帯債務型の住宅ローンを契約した後は連帯債務者としての地位を変更することが難しいとあらかじめ認識しておくことをおすすめします。
育休中や産休中でも返済は免除されない
連帯債務型の住宅ローンでは、夫婦や親子関係にある2人両方に返済義務が発生します。そして毎月の返済額は連帯債務者の収入を含めて計算し、設定されています。
しかし、連帯債務者である妻が妊娠して産休や育休に入った場合、妻の収入は当然大きく減少します。そのような状況でも、妻が義務付けられている返済額を減らすことはできません。
そのため、近々子どもを作る予定があるのであれば、妻の妊娠前の収入はこれからも続かないことを想定したうえで返済計画を立てるようにしてください。
団体信用生命保険に加入できるのは原則1人だけ
万が一のことがあった場合の生命保険だが、加入できるのは原則的に2人のうち1人だけなので、加入していない1人に何かあった場合は住宅ローンを1人で返済しなければなりません。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの契約者が死亡したり高度障害状態になったりしたときに、残債を代わりに支払ってもらえる生命保険のことです。住宅ローン専用の保険で、略して「団信」とも呼ばれます。
こちらの保険に2人ともが加入できない点が心配な場合は、後述の「連帯債務とペアローン・連帯保証の違い」で解説する「ペアローン」型での契約を検討してみてください。
ペアローン型の住宅ローンなら、2人揃って団信に加入することが可能です。
ただし、どうしても連帯債務型ローンを選択したいなら、団信に加入できないほうの人が住宅ローンの残債を賄えるだけの保証がある生命保険に加入することをおすすめします。
贈与税の対象になる場合がある
主債務者が返済するべき住宅ローンを連帯債務者が代理で返済したときには、経済的利益の移転があったとみなされて贈与税の対象となることがあります。
もしも贈与税が発生した場合、贈与税には年間あたり110万円まで基礎控除が適用されるので、できるだけ早いうちに税理士や自分の住んでいる管轄の税務署に相談するようにしましょう。
将来借り換えが難しくなる可能性がある
自分が借りたときよりも金利が低くなっていたり、繰上返済の条件がよくなっていたりなど、条件がよい商品があれば新しい住宅ローンに借り換えたくなることもあるでしょう。
しかし連帯債務型のローンでは、どちらかが退職して収入がない場合や、健康上の理由から団体信用生命保険に加入できない場合は、借り換えができなくなってしまうケースが見られます。
そのため、連帯債務で住宅ローンを契約した後、借り換えを検討する可能性があるのであれば、連帯債務型のローンを借り入れるのは断念したほうがよいかもしれません。
連帯債務とペアローン・連帯保証の比較

住宅ローンには、連帯債務型をはじめ「ペアローン」型や「連帯保証」型があります。
次に、夫婦や親子で借入れる場合の住宅ローンの組み方をタイプ別に表にまとめました。1人で組む場合とも比較しながら、目を通してみてください。
| 1人で組む場合 | 連帯債務(収入合算) | 連帯保証(収入合算) | ペアローン | |
|---|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 1人分の収入で計算 | 2人分の収入で計算する | ||
| 住宅ローン控除 | 1人しか受けられない | 2人とも受けられる | 1人しか受けられない | 2人とも受けられる |
| 団体信用生命保険 | 1人しか加入できない | 1人加入が原則。2人で夫婦連生団信(※)に加入できるケースもある | 1人しか加入できない | 2人それぞれが加入できる |
| 返済口座 | 1人の口座から引落とし | 1人(主債務者)の口座から一括で引落とし | 1人の口座から引落とし | 2人それぞれの口座から引落とし |
| その他の注意点 | 共働きでない夫婦はこの組み方しか選択不可 | 連帯債務を選べるのは「フラット35」と一部の金融機関のみ | 返済が滞った場合は、連帯保証人が肩代わりしなければならない | 借りるときの諸費用が2人それぞれにかかる |
(※)夫婦連生団信:主債務者と連帯債務者である夫婦が2人で加入できる制度のことです。夫婦のどちらかが死亡したり所定の高度障害状態になったりした場合、住宅の持ち分や返済金額などに関わらず残債が全額弁済されるため、ローンの返済義務が残りません。
これらローンのタイプを選択する際には、それぞれがもつメリットとデメリットを比較検討したうえで決定するようにしましょう。それではペアローンと連帯保証について、より詳しく解説していきます。
ペアローンとは
夫婦や親子それぞれが住宅ローンを借りることです。ただし、2人とも同じ金融機関で借りることが前提となります。
こちらのローン型では夫婦や親子それぞれの収入を基にして審査されるため、1人で借りる場合よりも借入可能額を増やすことが可能です。
連帯債務とペアローンの違い
ペアローンは、夫婦や親子それぞれが別のローンを同じ金融機関で借入れているというイメージをもつと分かりやすいです。
前章で、ペアローンでは「夫婦や親子それぞれの収入を基にして審査される」と記述しました。こちらは連帯債務のように収入を合算するのではなく、別の収入として分類したうえで審査がスタートします。
そのため、返済時には夫婦それぞれの口座から引き落としがされて、借りるときの諸費用も2人それぞれに発生するのです。
一方ペアローンには、団体信用生命保険に2人とも加入することが可能で、さらに住宅ローンの控除を2人ともが受けられるというメリットがあります。
住宅ローンの控除については、連帯債務でも同様に2人ともが適用されるのですが、団体信用生命保険に2人で加入できる点は連帯債務がもっていない特徴です。連帯債務においては、団信には原則として1人しか加入できません。
ただし、ペアローン契約で団信に加入した2人のうちのどちらかが死亡したり高度の障害を負った場合は、それぞれが借入れていたローンのみが保険で完済され、もう一方のローンはそのまま残債が残ります。
団信への加入は、ローンの契約者のみに万が一のことがあったときに重要になるポイントです。よって、ペアローンと連帯債務型のどちらを選択するかはじっくりと検討する必要があります。
連帯保証とは
夫婦のどちらか1人が債務者として借入れた住宅ローンを、残りの1人が保証するローン形態のことです。そのため連帯保証人は、債務者が返済できなくなった場合に返済を肩代わりしなければなりません。
連帯保証人になることは重大な責任を背負うことを意味するので、たとえ信頼関係にある債務者に「連帯保証人になってほしい」と頼まれたとしても、引き受けるかどうかを慎重に検討する必要があります。
連帯債務と連帯保証の違い
借入れ可能金額を決定する際、2人の収入を合算して計算をするのは連帯債務と同様です。
しかし、連帯債務は主債務者と連帯債務者どちらに対しても返済を請求できるのに対し、連帯保証は債務者の返済が不可能になったときに初めて連帯保証人の返済義務が発生します。
また連帯保証人は債務者にならないので、住宅ローンの控除をうけることも団体信用生命保険に加入することもできません。
現在、民間の金融機関が扱っている住宅ローンは連帯保証型がほとんどで、連帯債務による収入合算ができる金融機関は限られています。
なお、先述の「連帯債務に関する基礎知識」で紹介したフラット35は、連帯債務型のみを選択できる稀な住宅ローンです。連帯債務を利用してローンを組もうかと悩んでいる人は、一度公式サイトを検索してみてください。
連帯債務に関するQ&A

最後に、連帯債務にまつわるよくある質問をQ&A形式で紹介していきます。
今回は大きく3点の疑問に答えていくのですが、特に「連帯債務で住宅ローンを組むのに適している人は?」という質問に関しては、住宅ローンを契約する際の重要なポイントとなります。
ローンを組んでしまってから後悔するのを防ぐため、内容にしっかりと目を通して連帯債務についての理解を一層深めましょう。
連帯債務で住宅ローンを組むのに適している人は?
次に、連帯債務型で住宅ローンを組むのが向いている人の特徴をまとめました。
- 1人だと収入が足りなくて住宅ローンを借りることができない人
- 諸費用の負担を増やしたくない人
- 住宅ローン控除を夫婦でそれぞれ受けたい人
- いずれ配偶者が仕事を辞める可能性が高い状況にある人、など
連帯債務型はペアローンとは違い住宅ローンの契約が1本となるので、諸費用の負担を1人分で済ませられるうえ連帯債務者が住宅ローンの控除を受けることも可能です。
また、夫婦のどちらかが今後仕事を辞める可能性があるのであれば、ローンを2本に分けていると返済が困難になるかもしれません。その場合、連帯債務型を選択しておけば、返済の負担は単独ローンを同じなので安心です。
ただし連帯債務型のローンを取り扱っている金融機関は少ないため、自身が借入れを希望する金融機関に取り扱いがあるかどうかを事前に確認しておきましょう。
連帯債務者も審査に影響がある?
連帯債務型の住宅ローンを組む場合には、連帯債務者も審査の対象に含まれます。具体的には、申請者(主債務者)と同じように連帯債務者が同意書に署名・捺印をした後、金融機関は個人信用情報の照会を行います。
連帯債務者は、主債務者が住宅ローンを返済できなくなったときに返済の回収対象となるため、金融機関にとっては非常に重要な人物です。
つまり、前述の「連帯債務のデメリット/連帯債務者になるため、安定した収入が必要になる」でも記載しましたが、連帯債務者には毎月の返済をしっかりとこなせる返済能力が求められるのです。
万が一、配偶者がブラック状態(信用情報に傷がある状態)で住宅ローンの連帯債務者になる場合、審査に与える影響は高くなります。なお、ブラック入りになる原因は、「踏み倒し」や「自己破産」、「強制解約履歴」から「多重申込み」に至るまで様々です。
多重申込み(1ヶ月に3社以上ほど)によるブラック期間はおよそ半年なのですが、自己破産をした場合にはブラック期間が10年以上続くこともあります。ブラック入りしているかもしれない連帯債務者をどうしても使いたいのなら、ブラック明けになるまで待つしかありません。
連帯債務者の年収はすべて収入合算できる?
連帯債務者の収入は年収の全額まで合算することが可能です。ただし、連帯債務者の収入合算額が年収の50%を超過する場合は、返済期間が短くなることがあります。
収入合算した場合の借入れ期間の上限は、次の公式に当てはめて計算してください。(※「フラット35/親子リレー返済」を利用する際に限る)
- 主債務者
- 収入合算額の年収の50%を超える場合の連帯債務者
例えば、主債務者(30歳)の年収が400万円で連帯債務者(55歳)の年収が600万円だと仮定して話を進めましょう。収入を合算する側である連帯債務者の年収を全額合算するのであれば、連帯債務者の年齢(56歳(1歳未満切上げ))が基準となるので、借入れ期間は24年が最長になります。
一方、合算額を300万円(600万円の50%)以下にする場合は、主債務者の年齢(31歳(1歳未満切上げ))が基準となるので、借入れ期間は35年が最長になります。
まとめ

夫婦のうち1人が主債務者となる「連帯債務」は、1人のみの収入では住宅ローンの条件を満たせないときでも2人の収入を合わせられるうえ、別々に住宅ローンの控除を利用できる魅力的なローン形態となります。
ただし、連帯債務にはメリットだけではなく、デメリットもいくつかあるのが現状です。連帯債務では、夫婦がそれぞれ連帯債務者になるため2人ともの安定した収入が必要で、万が一離婚した場合でも返済義務がなくなりません。
団体信用生命保険には夫婦のどちらかしか加入できなかったり、将来の借り換えが難しくなったりなどのデメリットもあげられます。そのため連帯債務型の住宅ローンは、デメリットをふまえたうえで必要な場合にだけ利用するようにしましょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
\住宅ローンを探している人におすすめのサービス2選/
【新規】住宅ローンのプロに相談するなら「HOME'S 住まいの窓口」
不動産の大手ポータルサイトを運営する株式会社LIFULLの「HOME'S 住まいの窓口」では、住宅ローンを含め注文住宅に関するあらゆる相談が無料でできます。専門アドバイザーが中立的な立場でサポートしてくれるため、不動産会社やハウスメーカーなどから営業を受ける心配はありません。
【借り換え】住宅ローンを見直すなら「モゲチェック」
ローンの借り換えなら、低金利のローンへの借り換えサービスが便利です。モゲチェックでは、人気の住宅ローンを比較し、自身が借りられる最も低金利のローン(※)を案内します。毎月の返済額を平均約2万円軽減することも可能です。 ※付帯する団体信用生命保険を加味して運営会社 株式会社MFSが最も低いと判断する金利
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。


