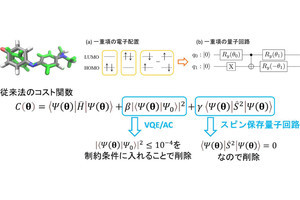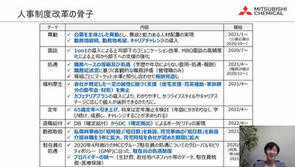国内では新型コロナウイルスの感染拡大前からDX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性が叫ばれていたが、遅々として進んでいなかったのが現状だ。しかし、コロナ禍を機に中小企業から大企業まで多くの日本企業がDXに舵を切り始めている。
本連載ではコロナ禍前よりDXに取り組み、着実に事例を積み上げてきた三菱ケミカルグループにおけるDXの取り組みについて紹介する。過去の「トップダウンで方向性を、ボトムアップで実現力を - 三菱ケミカルグループのDX」の回はこちらを参照。
同社では製造現場におけるDXを進めるにあたり、「トップダウン施策」と「ボトムアップ施策」の両輪で取り組む必要性を説いている。そのため「基盤整備」と「技術開発、検討」をトップダウン施策、「技術、ツールトライアル」「市民開発」をボトムアップ施策として位置づけている。
第1回、第2回はトップダウン施策を、前回はボトムアップ施策として社内における「交流」に着目したデータサイエンスコンテストについて紹介した。
最終回となる今回は、ローコードプラットフォーム「Microsoft Power Platform」を中心とした“市民開発”について、三菱ケミカル サプライチェーン所管 広島事業所 企画管理部 DX・ものづくり強化グループの手塚理沙氏、同 鶴見工場 企画管理部の彦坂源氏、同 デジタル所管 ビジネスソリューションデリバリー本部 サプライチェーンソリューションデリバリー部 北関東&東北ISグループ(筑波)の熊谷栄美氏に話を聞いた。
グループ全体で4万9000人が利用する「Microsoft Power Platform」
従来、全社的な業務アプリケーション基盤として同社はHCL Notes/Dominoでアプリケーションを作成していたが、2025年度末の利用停止を決定し、その代替基盤として2019年にPower Platform導入の検討を開始した。
基本的に共通で利用するアプリはデジタル所管部門で作成するものの、それと並行して社内における市民開発にも活用していくことを見据えていた。その後、Power Platform自体が機能拡充をしていたという背景を含め、2021年に社内で取り進めていく判断を下した。
手塚氏は採用に至った経緯について「ユーザー視点として、マイクロソフト製品は世の中に浸透していることが大きいです。すでにPower Platformに興味を持っている人たちは、いち早く使いたいと感じていました」と振り返る。
そして、2022年7月に同社における市民開発の環境として全従業員での利用を開始した。導入の社内調整については、デジタル所管のインフラ系部門と機能分担会社が共同で実施しており、経営層に対しては2022年初の経営執行会議で報告し、その後に従業員側に取り進めについて説明した。
実際、Microsoft自身もアプリ開発の民主化を進めるうえでもキーソリューションとしてPower Platformを位置付けている。三菱ケミカルでは主に、ローコーディングによるビジネスアプリ開発の「Power Apps」、RPA(Robotic Process Automation)機能を含む自動ワークフロー作成ツール「Power Automate」、データ分析・可視化が可能なBI(ビジネスインテリジェンス)ツール「Power BI」を利用している。
ユーザー規模はグループ全体で最大4万9000人となり、うち市民開発という観点でのアプリ作成者は1200人程度、運用自体はデジタル所管のインフラ系部門で利用規定やガイドラインを作成し、利用開始とともに公開。
利用規定に違反するような使い方をしている人はリマインドなどを行い、適正化を行っている。アーリーアダプターの人たちは事前に勉強をしていたため、公開と同時にアプリ作成に取り組んだという。
利用開始から1年で開発したアプリは6500
手塚氏は「マイクロソフト製品はグローバルスタンダードであり、当社の海外グループ会社も含めてワンチームで、共通利用できるのは大きなポイントです」との見解だ。現在、公開・未公開のアプリを含めてPower Apps、Power Automateで開発したアプリ数は6500ほどあり、同氏は「ボトムアップ的なものが多い印象です」と話す。
Power Apps、Power Automateの事例
例えば、予約アプリは会議室や備品、プラント場内移動用の自転車などを予約できる。従来はPCでの申請だったが、QRコードを備品などに貼り付けて読み込めば、その場ですぐ予約できるため手間を省けており、予約の確認も可能なことから利便性が向上したという。
予約アプリを開発した熊谷氏は「Power Platformは、デファクトスタンダードのコラボレーションツールとして推進されてきたため、その延長線上にあると感じています。また、スマホで撮影した写真をそのままOneDriveに保存できるアプリも作成しています。アプリを起動と同時にカメラも起動し、そのまま直接OneDriveに保存されるためメンバーと共有できるというものです。画像のサイズ、データ容量が小さいファイル形式で保存でき、二次利用もしやすいです。アプリをTeamsで共有したところ、多くの方から使いやすいという反応をもらいました」と説明する。
また、彦坂氏は「マイクロソフトではテンプレートのアプリを用意しています。その中でも会議調整のアプリは非常に便利だと感じています。対象メンバーと共通で空いてるスケジュールを自動で提示してくれます。テンプレートのままでも十分に利用できるアプリでしたが、解説もあり、アプリをカスタマイズすることでPower Appsの理解を深める教材として活用することもできました。これもTeamsのチャネルで共有しています」と、有効的に活用できている点を強調した。
そのほか、工場勤務のオペレーターは4直3交替で働いているため、誰かが休日の際は異なる当番の人が早出・残業でカバーしなければならなく、従来は人が紙で書き込んでスケジュールを調整していたが、Power AppsとPower Automateを活用してアプリを作成したことで調整がしやすくなっているという。
さらに、九州事業所の熊本地区では昼食などを事前に予約しなければならなかったが、食堂予約アプリを開発し、食堂の運営会社とデータを連携させている。さらには、これまでは備品の発注は購買担当者に口頭やカードで伝えていたが、備品置き場にNFCタグを貼り付けて、発注が必要になったら、スマホを近づけるだけで備品発注依頼メールが送信される在庫管理アプリも作成し、複数の部署で展開・活用されている。
Power BIの事例
一方、Powe BIの適用も進めている。これまでは、月1回の報告会議のためにデータを複数カ所からダウンロードし、集計したうえで表にまとめてExcelに転記して月報などを作成していたという。
手塚氏は「社内に散在するデータをまとめて集計することが可能となり、レポート作成が簡単になりました。また、自動更新機能により、最新のデータから現状の実態を把握できるようになっており、考察する時間や会議の質を向上させることに役立っています。さまざまな部署の人が閲覧できるため、朝のミーティングで確認しつつ工場勤務のオペレーターの人たちも設備の調整が有効か否かということが視覚的に分かるため効果的ではないかと思います」と語っている。
加えて、品質管理や生産管理の面でも活用している。品質管理では品種ごとの規格に準拠しているか否かなどのデータが管理図として可視化され、日々更新されている。
生産管理では歩留まりに加え、シート状の製品におけるムラなどの規格外れについて、画像解析などを用いて欠損分類や定量化を行い、その結果を運転条件と合わせて可視化することで工程管理の面でも寄与しているという。こうしたデータの取得、可視化は複数拠点で取り組んでいる。
「Teams」を活用して草の根的に市民開発を活性化
ただ、アーリーアダプター以外の使い慣れていない人たちに対する支援も必要だ。そのため、同社では熊谷氏と彦坂氏が言及したように情報交換の場として「Teams」を活用している。
手塚氏は「事例をTeams上のPower Apps & Power Automateチャネルと、Power BIチャネルで紹介してメンバーと共有し、他の部署でも使えるようにする動きが出てきています。市民開発者が開発したアプリを全社公開するための『アプリカタログ』も2023年3月に公開し、作成したアプリを登録・閲覧・利用できます。ゼロから作るのは難しいと感じている方でも、誰かが作成したアプリの横展開がしやすくなってきています。痒い所に手が届くようなアプリを作成できるため、業務効率や開発の生産性向上に寄与しています」と効果を口にする。
アプリ作成において何か行き詰った際にTeamsのチャネル内を検索したり、相談を投稿したりすれば、解決策を見つけられるという意味では市民開発ユーザーでも、勉強できるネタや参照できる情報が多くあるという。
さらに、同じレベル感でアプリ作成を誰しもができるとは限らないため、教育という観点で拠点ごとに取り組みを進めている。
具体的には、DX推進メンバーの配置や情報システム担当者が支援する形で勉強会やハンズオンセミナーなどを任意の参加者を集めて開催している。また、個別相談にも対応し、アプリ作成ができるようになるまでフォローしているという。
「アプリ作成者の裾野を広げていくことを主眼にTeams上にコミュニティを作り、事例紹介や相談を行っています。全社コミュニティに加え、拠点ごとにコミュニティを形成し、勉強会の動画公開やUdemyで勉強する人もいます。将来的にはアプリのコンテスト開催などもできればと考えています」と、コミュニティを形成する意義を説明した。
市民開発の文化醸成に「Power Platform」
このように、三菱ケミカルグループはPower Platformの利用を市民開発という観点から促進している。
手塚氏は「認知度の高まりとともに熱量も高まっていると感じています。業務改善のツールとしては着手しやすく、ボトムアップで広がり、話題性もあります。しかし、今後は全社的な視点でアプリなどを乱立させないようにカタログを活用した横展開に加え、蓄積すべきデータの蓄積方法などのルールを設けていくことなどに取り組めればと考えています」と話す。
その半面、同氏は「アーリーアダプターやアーリーマジョリティの方は興味を持ってくれますが、何ができるのかを理解して、現状の業務変革まで取り組めるようなアプローチは引き続き必要だと思います。メリットを認識し、興味を持った方だけでなく、上司の指示のもとでリスキリングも含めて取り組む必要があります。これは、本人の興味だけだと繁忙期でやらなくなる恐れもあるなかで、定着させる必要があるからです」と、今後の課題感も認識しているようだ。
また、彦坂氏は「普段の業務を変革できるツールのため、1人でも多く市民開発にチャレンジする雰囲気になればと思います」と述べており、熊谷氏は「市民開発自体が独り歩きしていることが怖い側面もありますが、ロジカルシンキングや要件定義などを理解しつつ、市民開発が進んでいけばと感じています」と両氏は期待を口にしている。
そして、手塚氏は「これまで製造現場は改善に当たり前のように取り組んでいたため、その1つの手段としてPower Platformを多くの人に活用してもらいたいです。痒いところに手が届くようなアプリを作成できると同時に、自動化も可能であることを認識してもらい、業務自体も変革できるキーファクターです。当社グループは、さまざまな会社が統合して成り立っています。同じ会社でもプロセスも生産するものも異なり、従来は縦割り感が強かったのは否めません。しかし、資細かい業務は共通している部分も多いことから、Power Platformの活用で横展開を活性化し、さらなる市民開発の文化醸成ができればと考えています」と力を込めていた。