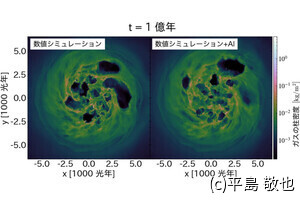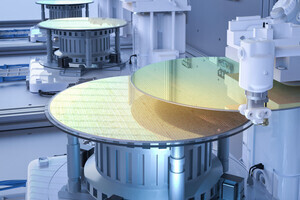航空機をセンサー・プラットフォームとして利用することの利点は、「高い位置に陣取って広い範囲を見渡せること」。だから、用途の多くは下方を見下ろす形になる。では、飛んでいる飛行機からさらに上方を見るような用途があるんだろうか、と思ったら、あった。→連載「航空機の技術とメカニズムの裏側」のこれまでの回はこちらを参照。
RC-135Sコブラボール
その一例が、RC-135Sコブラボール。名前でお分かりの通り、C-135シリーズの一族で、頭に付いている任務変更記号が「R」だから、偵察用と分かる。ただし、RC-135Sは地上や洋上を見るための偵察機ではない。
主なターゲットは、宇宙空間から地上・海上に向けて突っ込んでくる弾道ミサイル。といっても実戦用ではなくて、開発・維持管理・訓練などのために行われる試射が狙い。
だから、例えば北朝鮮が弾道ミサイルを発射しそうだということになると、RC-135Sが日本の近隣に現れるのはお約束みたいなもの。ロシアが実施している弾道ミサイルの試射も、着弾地点はたいていカムチャッカ半島近辺だから、きっとその周辺の公海上をRC-135Sがうろついているはずだ。
)
好都合な低翼配置
RC-135Sの機首右側面・上寄りに複数の窓が設けてあり、その内部にカメラを据え付けてある。これを使って、突入してくる弾道ミサイル(またはその先端に積まれている再突入体)を捕捉追尾して、数量・サイズ・速度・角度といったデータを記録する。それと平行して、弾道ミサイルに対する指令電波も傍受する。
発射した弾道ミサイルはいったん大気圏外に飛び出して、また大気圏内に再突入してくるので、高いところを飛んでいるRC-135Sから見ても、頭上から降ってくることになる。すると、機内に設置したカメラなどのセンサーにとっては、上方の視界が開けていないと具合が悪い。
その点、C-135シリーズは低翼配置だから好都合。多くの軍用輸送機に見られるように高翼配置になっていたら、胴体内から外を見ようとすると主翼が視界の妨げになりかねない。下方を見下ろすなら話は逆で、ATRみたいに「弊社の機体は高翼ですから、下方の景色がよく見えます」とアピールする事例も出てくるが。
右側だけ艶消し黒に塗られている
RC-135Sのもうひとつの特徴は、右側だけ主翼やエンジンナセルが艶消し黒に塗られていることだが、これは光の反射が撮影の邪魔にならないようにするための工夫。もしかすると、艶消し塗装のせいで空気抵抗が微妙に増えているかも知れない。
なお、RC-135Sが備えるカメラ窓の数や外形は変化しており、数が減っただけでなく、大きな丸窓だったものが小さな角形窓に変わっている。中身のカメラが変化した様子がうかがえる。
RC-135Sと同じように、側面にカメラ窓を設けて機内にカメラを並べた機体というと、核爆発実験観測機のNKC-135Aもある。可視光線に限らず、あらゆる種類の光線や放射線を観測するための機器を備え付けていたという。
そしてこのNKC-135A、米航空宇宙局(NASA : National Aeronautics and Space Administration)向けに、日蝕や彗星や宇宙船の観測といったアルバイトもしていたそうだ。これもやはり「上方を見る用途」といえる。
EC-135N ARIA
C-135一族には、宇宙空間を見るための機体もあった。それがEC-135N。ただし天体観測をするわけではなくて、アポロ計画において宇宙船の追跡と通信中継を担当するのが目的。だから名称はARIA(Apollo Range Instrumentation Aircraft)という。
宇宙船は宇宙空間を飛んでいるわけだから、当然、飛行中の機体よりも上にいる。そこでEC-135Nでは機首に直径3mぐらいある巨大なレドームを取り付けて、その内部に追跡用のレーダー・アンテナを収容した。
普通、この手の大型機で機首に設置するのは気象レーダーだから、以前にも書いたように前方に指向できれば用が足りる。ところが、EC-135Nのレーダーが相手にするのは頭上の宇宙船。そこで、アンテナを上に90度ばかり回転させて真上を向けられるようにした。
そのアンテナも直径が2.13mもあるデカブツだから、レドーム付根の隔壁から、ある程度の距離を置いて取り付けないと上向きにできない。そのため、レドームは長さの方も3m以上あり、これも異例のサイズ。
アポロ計画が終了した後で、このEC-135Nのうち4機がエンジンをTF33に換装してEC-135Eにコンバートされた。ただしこちらは航空機や巡航ミサイルの追跡が目的なので、レーダーが向く方向は下方になったと思われる。
C-135の派生が多い理由
機体の基本配置からすると、上方を見るのに都合がよいのは事実だが、これに限らずC-135一族は偵察などに用いる派生型が多い。
KC-135ストラトタンカー給油機が大量に使われているから、他系列の機体あるいは新規の機体を起こすよりも、同系列の機体を派生させる方が訓練や整備補給の面で都合がいい、という理由が大きかろう。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、姉妹連載「軍事とIT」の単行本第3弾『無人兵器』が刊行された。