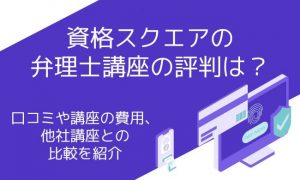中小企業診断士は、経営コンサルタントの唯一の国家資格であり、毎年多くのビジネスパーソンが受験をする人気資格です。
科目数が多く、長期的な試験勉強を必要とするため、十分な勉強時間の確保と徹底した試験対策が欠かせません。
「中小企業診断士を目指すためには、実際どのくらい勉強時間が必要なのか気になる」
「中小企業診断士試験の勉強法が知りたい」
実際にどの程度勉強時間が必要なのか、気になる方も多いのではないでしょうか?
この記事では、中小企業診断士試験の勉強時間について解説します。
この記事はこんな方におすすめ!
|
中小企業診断士試験の受験を見据え、ぜひ記事の内容を参考にしてください。
中小企業診断士の試験対策は通信講座での学習がおすすめです。
中小企業診断士の通信講座については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
→【中小企業診断士】おすすめの通信講座ランキング5選の記事はこちら
中小企業診断士の勉強時間

資格の学校TACとLEC東京リーガルマインドで紹介されている勉強時間目安は以下の通りです。
| 学校名 | 勉強時間目安 |
|---|---|
| 資格の学校TAC | 1000時間 |
| LEC東京リーガルマインド | 800~1000時間 |
(引用元:各社公式HP)
中小企業診断士の合格には、資格の学校TACの発表によると1000時間、LEC東京リーガルマインドの調査によると800時間〜1000時間程度が必要とされています。
つまり、1000時間程度の勉強が必要ということです。
中小企業診断士試験は、一次試験で7科目、二次試験で4事例が出題され、試験範囲が広く各科目で試験傾向が異なることが、長時間の試験勉強を必要とする理由といわれています。
具体的には各科目・事例で50~200時間、トータルで1,000時間の勉強時間が必要です。
勉強時間の目安に関しては、専門知識や実務の有無、学習環境によって異なります。
中小企業診断士に関連する専門知識や実務経験がある場合は、勉強時間を短縮できる可能性があります。
一方で知識・実務経験共になく、中小企業診断士試験を初めて受験する方は、1,000〜1,200時間もしくは、それ以上に勉強時間が必要になるケースもあるでしょう。
長時間に及ぶ試験勉強を効率よく進めるためには、科目別に綿密な学習計画を立てるのが必要です。
まずは、中小企業診断士試験の科目別勉強時間を紹介します。
科目別勉強時間の目安
中小企業診断士試験は、一次試験・二次試験に分かれています。
一次試験は7科目、二次試験は4事例あり、科目によって勉強時間や学習ボリューム・学習内容が大きく異なるため、注意が必要です。
長時間に及ぶ中小企業診断士試験対策を効率よく進めるためには、一次試験・二次試験の科目別の勉強時間をしっかり把握しておきましょう。
一次試験
中小企業診断士一次試験の科目別勉強時間(目安)は以下の通りです。
| 科目名 | 勉強時間(目安) |
|---|---|
| 財務・会計 | 100-200時間 |
| 企業経理理論 | 100-200時間 |
| 運営管理 | 100-150時間 |
| 経済学・経済政策 | 100-150時間 |
| 経営情報システム | 100-150時間 |
| 経営法務 | 100-150時間 |
| 中小企業経営・政策 | 50-100時間 |
(引用元:アガルート公式HP)
一次試験の「財務・会計」「企業経理理論」「運営管理」は、二次試験と関連性が高い科目です。
出題範囲が広く、難易度も高いことから勉強時間は多い傾向にあります。
中小企業経営・政策は、参考資料をベースとした試験勉強となるため、短時間の勉強時間で十分に試験範囲を網羅可能です。
効率よく試験勉強を進めるには、二次試験との関連性を意識しながら、バランスよく学習計画を練ることが必要でしょう。
二次試験
中小企業診断士二次試験の科目別勉強時間(目安)は以下の通りです。
| 科目名 | 勉強時間(目安) |
|---|---|
| 事例1(組織を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例) | 80-120時間 |
| 事例2(マーケティング・流通を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例) | 80-120時間 |
| 事例3(生産・技術を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例) | 80-120時間 |
| 事例4(財務・会計を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例) | 80-120時間 |
(引用元:アガルート公式HP)
二次試験は、4つの事例で構成され、1事例に対して4~5問を記述式で解答します。
一次試験と関連性がありますが、一次試験と出題形式が異なるため、二次試験に特化した試験対策が必要です。
暗記要素が多い一次試験に対して、二次試験は論理的思考力を身に付けることが合格のポイントとなるでしょう。
スタイル別の勉強時間
中小企業診断士の勉強スタイルは、大きく分けて独学・通信講座・通学(資格学校)の3種類に分かれます。
勉強方法と勉強時間の目安は以下の通りです。
| 勉強方法 | 勉強時間(目安) |
|---|---|
| 独学 | 1,000~2,000時間 |
| 通信講座 | 800~1,000時間 |
| 通学 | 800~1,000時間 |
(引用元:資格の学校TAC公式HP・LECリーガルマインド公式HP)
通学・通信講座を利用する場合、教材選びは必要なく、合格ポイントに的を絞った学習で勉強時間の短縮ができます。
一方で独学の場合、テキスト選びや学習計画、試験傾向の予測まで全て自分で行う必要があり、勉強時間が多くなる傾向です。
ここでは通信講座・通学・独学の各学習スタイルについて、勉強時間・学習法の特徴とポイントを比較します。
独学の勉強時間
独学の場合は、平均勉強時間の1,000時間では合格に必要な知識が十分に身に付かない可能性もあります。
昨年8月から初めて、
合計勉強時間は1460時間。内、一次試験で1145.5時間。二次試験で314.5時間。中小企業診断士初回の受験にあたって、私は特に活用できる知識や経験がなく、独学のため、
周りと比較して進捗を判断する基準も無かったので、勉強時間を積み重ねる事だけがモチベーションでした。
(引用元:X)
んー。中小企業診断士の参考書試しに買ってみたけど、専門用語のオンパレードで想像以上にさっぱりだわ…
リプしてくれた人が勉強時間2000時間だつってたけど、独学だったらリアルにそれくらいかかるかもしれん。笑
(引用元:X)
ネット上では、独学で1,000時間以上の勉強時間が必要だったという口コミが数多く見られました。
専門知識や実務経験がない場合には、プラス500〜1,000時間必要となるケースもあるでしょう。
独学で資格取得を目指している方の意見を見てみると1,000時間が平均とされていますが、更に勉強時間が必要となったケースも多く、学習スケジュールに余裕を持つことが大切です。
また、中小企業診断士試験は科目数が多く、各科目によって出題傾向に特徴があるため、たとえば資格の学校TAC公式HPでは、独学における二次試験対策の難しさを指摘しています。
二次試験合格のために必要な解答方法テクニックを身に付けることが困難で、自分の実力を客観的に判断できないことが理由として挙げられるでしょう。
独学の場合は、各科目で異なる試験対策をいかに効率よく進められるかが勉強時間短縮のポイントといえます。
通信講座の勉強時間
通信講座を利用した場合、合格ポイントを押さえた効率性重視の学習カリキュラムで勉強時間を短縮できる可能性があります。
スマホを利用したオンライン学習が可能な通信講座を選択すれば、移動時間や休憩時間など短時間の隙間時間も有効活用できるでしょう。
短時間・短期間で集中的に勉強したい方や仕事と試験対策を上手に両立したい方に最適な学習方法です。
スマホを利用して最短ルートで合格を目指す方は、オンライン完結型のスマホ学習で効率よく学べるスタディングをおすすめします。
通学の勉強時間
通学の場合は、勉強に集中できる環境が整っているため、モチベーションを維持しやすく、受験コースによっては、1年で無理なく合格を目指せます。
資格の学校TACとLEC東京リーガルマインドで紹介されている勉強時間目安は以下の通りです。
| 学校名 | 目安勉強時間 |
|---|---|
| 資格の学校TAC | 1000時間 |
| LEC東京リーガルマインド | 800〜1000時間 |
(引用元:各社公式HP)
各社が紹介している中小企業診断士における具体的な学習時間の例としては、資格の学校TAC公式HPでは1,000時間、LEC東京リーガルマインドでは800〜1,000時間です。
つまり、最低でも800時間程度の勉強時間が必要ということがわかります。
通学・通信講座を利用した場合にも、平均的な勉強時間が必要となり、計画的に試験対策を進める必要があるでしょう。
専門知識や実務経験がある場合には、自分のレベルに合ったコース選択をすることで、勉強時間の短縮になります。
講座の受講前に、対象者やコース内容を必ず確認しましょう。
合格に必要な期間と年数
合格に必要な年数を、LEC東京リーガルマインドによる合格者の学習期間データを参考に紹介します。
| 学習期間 | 合格者の割合 |
|---|---|
| 1年以内 | 27% |
| 2年以内 | 21% |
| 3年以内 | 21% |
| 4年以内 | 13% |
| 4年以上 | 15% |
(参照:LEC東京リーガルマインド公式HP)
1年以内の学習期間で合格できた方が、全体の4分の1を占めています。
一方で、全体の55%の受験生が、複数年にわたる試験勉強の末に合格できたことが分かります。
十分な学習時間が確保できる場合は1年、仕事と両立し無理なく合格を目指す場合は、2~4年ほどの学習期間が目安となるでしょう。
1年で合格を目指す場合は、試験勉強に集中できる学習環境やスケジュールを整えることが必要です。
平均勉強時間1,000時間を目安に計算すると、1年で合格するためには、毎日2~3時間程度の学習時間が必要となります。
| 1年で1000時間を確保する際の勉強時間の例 |
| 3時間×365日=1,095時間 |
1年で合格を目指すことも十分に可能ですが、無理に詰め込みすぎて各科目の勉強が中途半端になる可能性もあります。
1日や1週間単位で、勉強可能時間を調整し、無理のないスケジュールで学習を進めましょう。
勉強開始時期
中小企業診断士一次試験は、例年8月上旬に実施されています。
資格学校や通信講座では、最新の試験傾向を分析した上で9・10月に講座を開講する場合が多く、勉強開始時期として最もおすすめです。
9・10月に勉強を始められなかった場合には、1~4月に勉強を始めるといいでしょう。
通信講座では、短期集中コースとして1~4月に開講するコースもあり、試験の申し込み日程を見据えながら勉強を始められるからです。
資格学校のTACでは、短期集中コースとして1・2次速修本科生コース・1次速修本科生コースを1・2月開講しています。
短期間で集中的に学びたい方や、実務経験・専門知識があり勉強時間を短縮できる方におすすめです。
勉強開始時期に関しては、一般的に9~10月がおすすめといわれていますが、学習期間・学習環境を踏まえて、自分にベストな時期を選択しましょう。
中小企業診断士おすすめの勉強方法

中小企業診断士試験に効率よく合格するためのおすすめ勉強方法を紹介します。
中小企業診断士は、一次試験が7科目、二次試験が4事例で構成されているため、それぞれの科目・事例に特化した試験対策が必要です。
また、過去問を中心としたアウトプット学習が効果的とされているため、上手く活用することで合格に必要な知識が身に付きます。
その他にも、学習効率が上がると話題のサブノート勉強法や、副教材として活用したいおすすめの勉強サイトも紹介しているので、試験対策の参考にしてください。
一次試験におすすめの勉強法
一次試験の勉強方法は、「テキストと問題集をバランスよく活用すること」と、「合格点を見据えて、重点的に学習すること」をおすすめします。
科目数が多く、暗記要素も含まれる中小企業診断士試験は、テキスト学習によって得た知識をすぐに問題演習でアウトプットし、理解を深めることが重要だからです。
スタディングでは、テキスト・問題集を有効的に活用した学習方法を推奨しています。
| テキストを使った知識の習得と、問題集を使った問題演習をバランスよく行う勉強法が効果的です。ここで重要なのが「それぞれを1つのセットとして行うこと」です。
具体的には、「1つの論点について同じタイミングでテキストと問題集を使って勉強する」ということを意味します。 |
(引用元:資格取得エクスプレスbyスタディング)
インプット・アウトプット学習どちらかにバランスが崩れていると、思うように知識が定着しないこともあります。
暗記要素が大きく、試験範囲が広い科目では、テキスト、問題集をバランスよく活用する反復学習は、しっかりと意識しておきたい学習のポイントといえるでしょう。
また、中小企業診断士一次試験を目指す上で、忘れてはいけない重要なポイントが「試験の合格ラインが60%以上」ということです。
8・9割の正解率を目指す必要はなく、過去問を利用し、試験頻出論点に着目した重点的な試験対策が効果的といえます。
過去問活用術に関しては、後ほど詳しく解説しますが、学習ボリュームが多い一次試験は、勉強方法の工夫が必要不可欠です。
二次試験におすすめの勉強法
二次試験は、記述式の試験で明確な答えがない試験です。
そのため、過去問を利用して事例問題に取り組み、模範解答や合格者回答を参考に、試験傾向を掴むことや論理的思考力を養うことが大切になります。
過去問は、試験傾向を掴むためにも5年分ほど、2~3回繰り返し解くことで十分な試験対策になるでしょう。
一次試験の合格発表から、二次試験までは十分な時間がないため、一次試験と関連性が高い科目は、試験勉強を同時進行にするなど、学習スケジュールにも工夫が必要です。
二次試験対策は、論理的思考力を養い、試験傾向を掴むことや学習スケジュールの調整を意識しましょう。
サブノート勉強法と過去問活用術
中小企業診断士試験の勉強法で効果的といわれている「サブノート勉強法」と「過去問活用術」について、詳しく解説します。
サブノート勉強法は、勉強スタイルや学習の進捗状況によっては、必要がない場合もあるため、自分にとって必要か見極めることも大切です。
過去問活用術は、一次試験・二次試験共に欠かせない重要な学習法であり、有効活用するためにもポイントを把握しておきましょう。
【サブノート勉強法】
中小企業診断士の勉強方法として、サブノートを利用する方法がネット上で話題となっています。
そもそも、サブノートとは、テキストや講義の内容、問題集で間違えたポイントをまとめた勉強ノートのことです。
サブノートを作る勉強方法により、各科目の重要ポイントを掴めることに加え、苦手箇所を反復して理解を深められます。
作成に時間がかかるデメリットがありますが、自分が最も理解しやすい言葉で学習ポイントを見返せるため、理解しやすく、苦手克服に役立つでしょう。
サブノート学習法の注意点としては、学習スタイルや進捗状況によって、向き・不向きが分かれることです。
以下のような方には、サブノートでの学習法がおすすめできます。
|
3点のいずれかに当てはまる方は、サブノートを上手く活用し、要点チェックや苦手克服に役立てましょう。
【過去問活用術】
過去問は、実力確認や試験傾向を掴むために欠かせない学習教材です。
ここでは、具体的なおすすめ過去問活用術を2つ紹介します。
①過去問は5年分以上のものを繰り返し解く
中小企業診断士の1次試験は、難易度にバラつきがあるため、5年分以上解くのがおすすめです。
5年分あれば、難易度のバラつきを加味した上で、平均的な自分の実力を把握できます。
最新の試験傾向を掴むためには、昨年度の試験が重要ですが、最低でも5年分、余裕がある方は更にプラスして2〜3年分解くと、十分に試験傾向が理解できるでしょう。
②間隔を空けて、2回以上解く
まずはテキストや講義を受けてインプット学習をした後に過去問を解くのがおすすめです。
インプットした知識がしっかり身に付いているのか、理解度を確認できます。
そして、試験が近付いてきた4月以降に再び解くことで、最終的な実力チェックになります。
試験形式に慣れておくことも大切です。
活用方法を工夫することで、学習効果を更に高めることもできるため、2つのポイントを押さえて有効利用しましょう。
中小企業診断士おすすめの勉強サイト
中小企業診断士の最新の試験傾向をチェックするときや、過去問の詳しい解説が必要なときに重宝するのが勉強サイトです。
ここでは、中小企業診断士の試験勉強に役立つおすすめ勉強サイトを2つ紹介します。
【一発合格道場】

中小企業診断士試験に合格した複数の経験者が、自らの勉強方法や試験の必勝法を伝授する情報サイトです。
最新の試験対策まで網羅されていて、セミナーなどイベントも定期的に開催されています。
独学者や勉強方法に行き詰まった時に活用したい勉強サイトです。
【資格取るなら.tokyo】

中小企業診断士過去問を一問ずつ丁寧に解説する情報サイトです。
市販の過去問題集の解説では分かりにくい部分も、細かく解説してくれるため、曖昧な部分もきちんと理解できます。
中小企業診断士試験では、過去問を有効活用することが合格のポイントとなるため、過去問演習と合わせて利用するといいでしょう。
中小企業診断士は独学で合格できる?

中小企業診断士は独学で合格が目指せます。
しかし、科目数が多い中小企業診断士試験に合格するには、綿密な学習スケジュールを立て、計画的に勉強を進める必要があるでしょう。
中小企業診断士に必要な勉強時間は、1,000時間といわれていますが、独学の場合はプラス500時間〜1,000時間の勉強時間を必要とするケースがあります。
独学の場合、教材選びから試験傾向の把握まで自分で行う必要があり、重点的に学習すべき合格のポイントを掴みにくいことが理由として挙げられます。
また、勉強方法が間違っていたり、苦手科目の学習に時間をとられてしまったりと、予定通りに勉強が進まない場合もあるでしょう。
資格の学校TAC公式HPでは、独学における二次試験対策の難しさを指摘しています。
| 特に難しい理由は2次試験対策です。
独学で勉強した場合、点数を獲得できる解放テクニックを学びにくいため、「模範解答と意図していることは同じなのに、なぜ点数が低いのか」「自分の解答の方が模範解答より適切なはずだ」など、客観的な自分のレベルが把握できないケースが考えられ効率的から効果的な学習計画を立てることが難しいしょう。 |
(引用元:資格の学校TAC公式HP)
二次試験は、一次試験とは出題傾向が大きく異なります。
二次試験合格のために必要な解答方法テクニックを身に付けることが困難で、自分の実力を客観的に判断できないことも理由として挙げられるでしょう。
ここでは、独学をより効率よく進めるために必要な情報として「独学のメリット・デメリット」と「独学が向いている人・向いていない人」を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
独学のメリット・デメリット
独学のメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット
デメリット
|
独学のメリットは、費用を抑えられ、自分のペースで勉強できることです。
通信講座では、最もリーズナブルなスタディングの中小企業診断士講座1次2次合格コースミニマムで約5万円の費用が必要です。
独学の場合は、テキスト、問題集、過去問など必要な学習教材を揃えても費用は半分以下に抑えられるでしょう。
また、通信講座や通学は開講時期が決まっているものもありますが、独学では好きなタイミングで勉強を始められます。
仕事が忙しくまとまった勉強時間が確保できない場合も、長期的な計画を立て無理なく学習が進められるでしょう。
一方で、独学はモチベーションの維持が難しく、挫折者も多いのが現実です。
勉強方法に行き詰った時や試験勉強が思うように進まない時のサポートがないため、モチベーション維持には十分な対策が必要でしょう。
独学が向いている人・向いていない人
独学には性格や学習環境によって、向き・不向きがあります。
独学に向いていない人は、無理に継続しても試験勉強の効率性が下がり、十分な実力が身に付かない可能性もあるでしょう。
最低限の勉強時間で効率よく学習するためには、自分が独学向けタイプなのか事前にチェックすることをおすすめします。
独学が向いている人・向いていない人の特徴は以下の通りです。
向いている人
向いていない人
|
独学経験がある方は、モチベーションの維持から学習スケジュール管理など独学に必要な基本的スキルを習得している場合が多く、効率よく学習を進められます。
一方で、日常生活でも自己管理が苦手な方は、勉強管理を意識して綿密に学習計画を練ることに重点をおきましょう。
中小企業診断士におすすめの通信講座3選

約1,000時間の勉強時間を必要とする中小企業診断士試験に合格するためには、効率よく学習できる通信講座の利用がおすすめです。
ここでは、各通信講座の料金と講義時間、合格率・合格者の実績を比較して中小企業診断士試験のおすすめ通信講座を3つ紹介します。
| 中小企業診断士 おすすめ通信講座ランキング |
|
| 通信講座 | 料金(税込) |
| スタディング | 中小企業診断士 1次2次合格コース[2026年度試験対応]
→スタディング 評判はこちら →スタディング 中小企業診断士講座 評判はこちら |
| アガルート | 【2025年合格目標】
→アガルート 評判はこちら →アガルート 中小企業診断士講座 評判はこちら |
| クレアール |
→クレアール 評判はこちら |
スマホを利用したオンライン学習を希望する方はスタディング・アガルートが、費用を抑えた効率性重視の学習スタイルを希望する方は、クレアールがおすすめです。
なお、こちらの記事でも中小企業診断士の通信講座に関して詳しく紹介しています。
→【中小企業診断士】おすすめの通信講座ランキング5選の記事はこちら
ここでは、通信講座3社の特徴を比較し、詳しく解説しますので、通信講座選びの参考にしてください。
スタディングの中小企業診断士講座
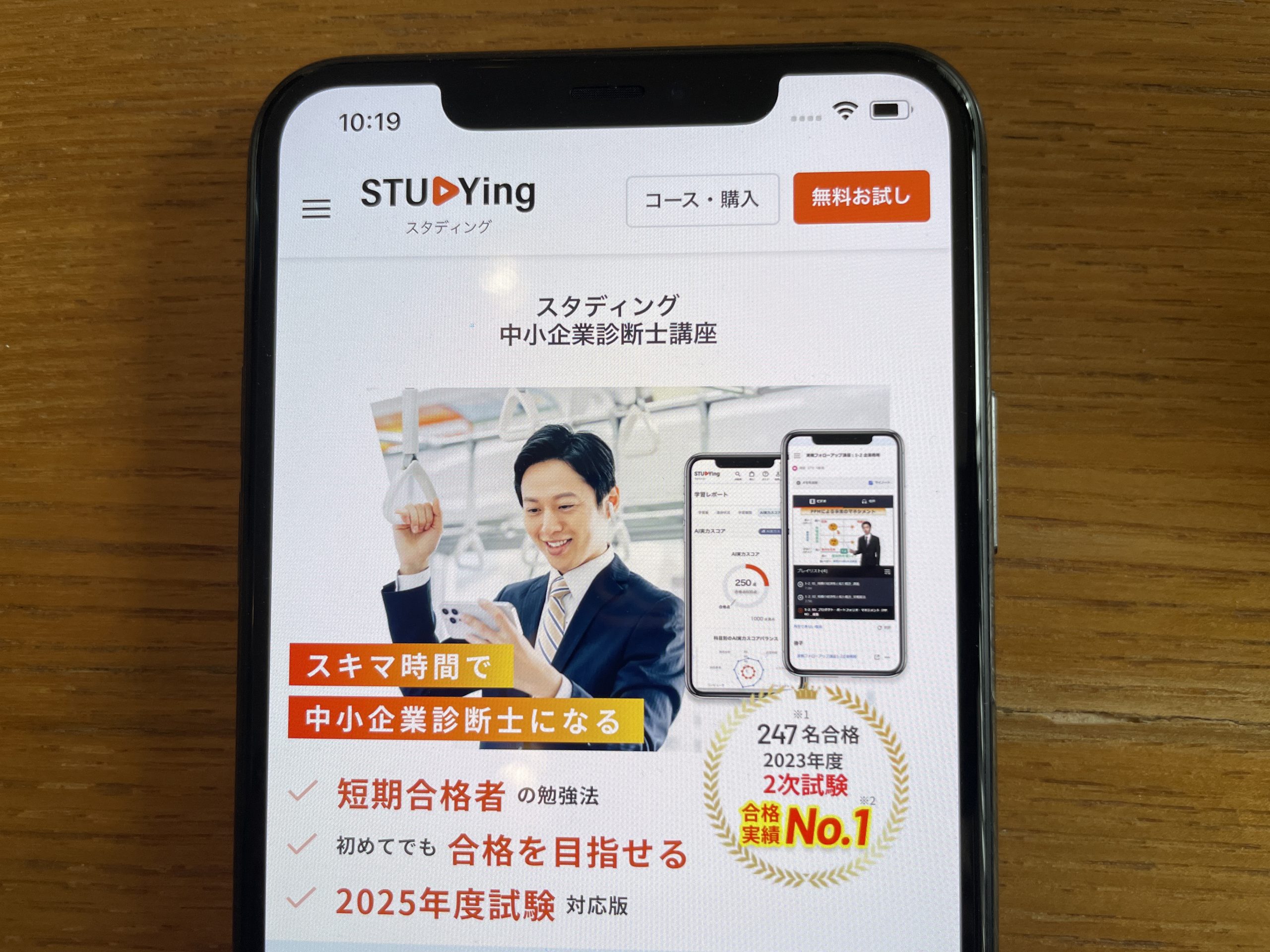
(引用元:スタディング公式HP)
| 通信講座名/料金 |
|
|---|---|
| カリキュラム |
|
| 教材/テキスト |
|
| eラーニング |
|
| 合格率/実績 |
|
| サポート体制 |
|
圧倒的な低価格とスマホを利用した効率性重視のオンライン学習が魅力の通信講座です。
一問一答形式のスマート問題集や、過去10年分の過去問を厳選した過去問セレクト講座など、隙間時間を活用できるアウトプット教材が豊富です。
問題演習の進捗状況はマイページで確認でき、学習内容のバランスを調整しやすいのも魅力といえます。
問題演習によって苦手な箇所を把握し、集中的にアプローチすることで、合格に必要な実力を効率よく身に付けられるでしょう。
また、スタディングは、コース内容がシンプルで自分に合ったカリキュラムを見つけやすいこともメリットといえます。
中小企業診断士1次・2次合格コースは、予算や学習スタイルに合わせて、ミニマム・スタンダード・コンプリートの3種類から選択できます。
ミニマムコースは、動画講義によるインプット学習中心のカリキュラムです。
最小限の学習教材・5万円以下のリーズナブルな受講料が特徴で、費用を抑えて学習したい方、インプット学習中心のカリキュラムをお探しの方におすすめです。
問題演習から模擬試験まで、総合的に学びたい方には、学習教材が充実したスタンダード・コンプリートコースがいいでしょう。
スマホを活用した学習スタイルを希望する方や短期間・短時間で集中的に効率よく合格を目指す方に適した通信講座ですね。
スタディングの中小企業診断士講座について、詳しくはこちらをご覧ください。
アガルートの中小企業診断士試験講座

(引用元:アガルート公式HP)
| 通信講座名/料金 |
|
|---|---|
| カリキュラム |
|
| 教材/テキスト |
|
| eラーニング |
|
| 合格率/実績 |
|
| サポート体制 |
|
オンライン完結型の学習教材で、短期間に効率よく合格が目指せる通信講座です。
動画講義は1チャプターが10〜40分と短時間に区切られているため、隙間時間を有効活用できます。
また、音声ダウンロードや8種類の倍速機能など、効率性を高めるための機能が充実しているのもアガルートの特徴です。
コンパクトな講義を自分の学習スタイルに合わせて視聴することで、短時間・短期間でも十分な学習効果が得られるでしょう。
更に、アガルートはテキスト作成から講義まで、専門講師が一貫して担当するため、テキスト・講義が分かりやすく、要点が掴みやすいことも魅力です。
コンパクトな動画講義と初心者でも分かりやすいテキスト、丁寧な学習サポートもついて、コストパフォーマンス抜群のおすすめ通信講座といえます。
アガルートの中小企業診断士講座について、詳しくはこちらをご覧ください。
クレアールの中小企業診断士講座
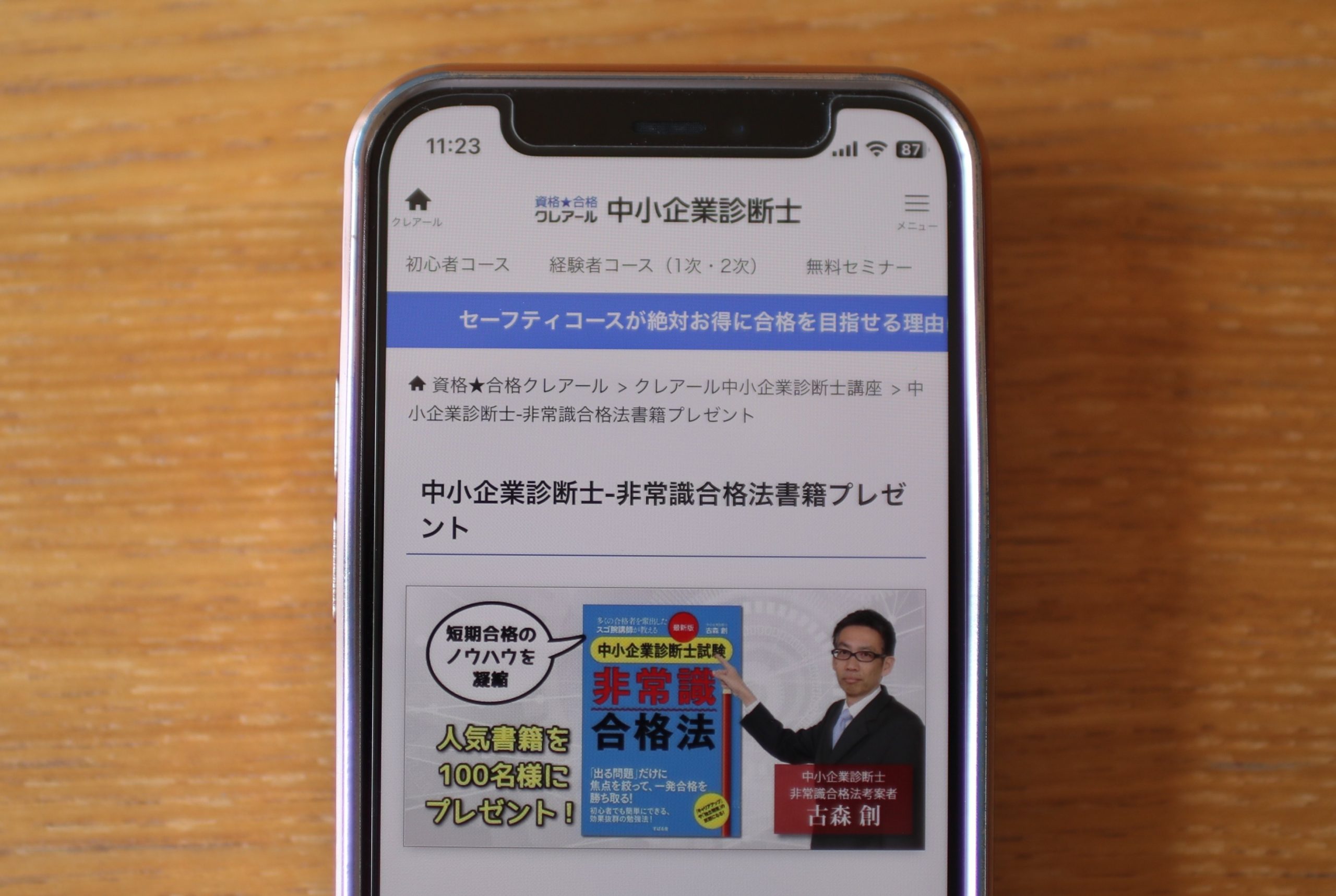
(引用元:クレアール公式HP)
| 通信講座名/料金 |
|
|---|---|
| カリキュラム |
|
| 教材/テキスト |
|
| eラーニング |
|
| 合格率/実績 |
|
| サポート体制 |
|
非常識合格法と呼ばれる独自の学習カリキュラムが魅力の通信講座です。
非常識合格法とは、合格に必要な得点範囲を厳選して、集中的に学習する効率型学習方法です。
過去21年分の過去問データから厳選された合格論点に的を絞っているため、一般的な学習方法と比較して、圧倒的に学習範囲が狭まり、最短ルートで合格が目指せます。
動画講義やテキストは、全てスマホで視聴できるため、移動時間など隙間時間も有効活用でき、更なる効率化が可能です。
メール、FAX、電話にて、気軽に講義内容の質問が可能で、通信講座でもモチベーションを維持しやすく、安心して受講できます。
効率性重視の方や、短期間で集中して受講したい方におすすめです。
クレアールの中小企業診断士講座について、詳しくはこちらをご覧ください。
中小企業診断士資格の活かし方【仕事内容・メリット】
中小企業診断士は、日本版MBAといわれ、毎年1万人以上が受験する不動の人気資格です。
人気の理由は、中小企業診断士資格取得後の仕事内容や中小企業診断士資格の特徴にあります。
中小企業診断士の仕事内容・メリットは以下の通りです。
【仕事内容】
【メリット】
|
中小企業診断士の仕事内容は、経営コンサルティングとセミナーや執筆活動があります。
メリットとしては、経営コンサルタントとしての信頼性がアップすることや、就職・転職・キャリアアップにつながることが挙げられます。
また、高収入も期待でき、独立・開業も可能でしょう。
ここでは、各仕事内容やメリット・デメリットを詳しく解説します。
【仕事内容】
中小企業診断士は、経営コンサルティングが主な仕事内容です。
企業内でコンサルティング業務に従事する「企業内診断士」と、独立して各中小企業と契約し、経営コンサルティングを行う「独立診断士」の2種類に分かれます。
企業内診断士・独立診断士は、勤務形態は異なりますが、企業の経営状況の診断・分析を基に、専門知識を活かして経営のアドバイスをする業務内容に違いはありません。
他にも、補助金申請の代行・補助業務や公的業務、経営コンサルティングの専門知識を活かしたセミナー講師や執筆活動で情報を発信することも可能でしょう。
中小企業診断士は、その他国家資格のような独占業務はありませんが、コンサルティング業務以外にも役立てるため、活躍の場が幅広い資格といえます。
【メリット・デメリット】
中小企業診断士になるメリットは、経営コンサルタントとしての信頼性が上がり、就職・転職・キャリアアップにつながることが挙げられます。
経営コンサルタントは、資格がなくてもできますが、資格保持者は経営コンサルタントとしての専門知識を身に付けている証明となり、信頼感につながります。
そのため、コンサルティング会社や一般企業への就職・転職はもちろん、資格取得によってキャリアアップも期待できるでしょう。
また、中小企業診断士の平均年収は約740万円で、日本人の平均年収を大きく上回るデータがあり、高収入を得ることも可能です。
資格保持者の約34%は、独立・開業をしているデータもあり、独立・開業を目指す方にも有利な資格といえるでしょう。
一方でデメリットとしては、独占業務がないためその他国家資格と比較すると専業で稼ぐことが難しい場合もあります。
独占業務がないからこそ、幅広い分野で活躍できる資格ですが、資格取得の目的や取得後にどのように活かしていくかを明確にしておくといいですね。
中小企業診断士に関連する国家資格難易度ランキング
公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士は、中小企業診断士と関連性がある国家資格です。
ここでは、人気国家資格6種の難易度を合格率や受験者数・勉強時間で比較しました。
国家試験【公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士】難易度ランキング
公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士は、いずれも合格率20%以下の難関試験です。
| 資格 | 合格率 | 受験者数(令和6年度) | 勉強時間 |
|---|---|---|---|
| 公認会計士 | 7.4%(令和6年度) | 21,573 人 | 3,000~5,000時間 |
| 司法書士 | 5.27%(令和6年度) | 13,960人 | 3,000時間 |
| 税理士 | 16.6%(令和6年度) | 34,757人 | 3,000時間 |
| 社会保険労務士 | 6.9%(令和6年度) | 43,174人 | 1,000時間 |
| 行政書士 | 12.9%(令和6年度) | 47,785人 | 1,000時間 |
| 中小企業診断士 | 5.14%(令和6年度) | 一次試験18,209人 二次試験8,119人 |
1,000時間 |
(参考情報:アガルート公式HP)
公認会計士は、学習ボリュームが最も多く、合格率が10%を下回る超難関資格です。
続いて、司法書士・税理士も、平均勉強時間3,000時間で合格率が約5~20%を推移する難関試験といえるでしょう。
社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士は、公認会計士・司法書士・税理士と比較すると勉強時間は少ない傾向にあります。
しかし、合格率は約10%、もしくはそれ以下で、合格のためには徹底した試験勉強が必要です。
USCPA(米国公認会計士)と比較
USAPA(米国公認会計士)は、国際的に知名度の高い会計士資格です。
中小企業診断士としてキャリアアップを目指す方におすすめのUSAPA(米国公認会計士)ですが、どのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、USAPA(米国公認会計士)と中小企業診断士の勉強時間や難易度・合格率を比較します。
【勉強時間】
USAPA(米国公認会計士)と中小企業診断士の勉強時間を比較しました。
| 資格名 | 勉強時間 |
|---|---|
| USAPA(米国公認会計士) | 1,200~1,500時間 |
| 中小企業診断士 | 1,000時間 |
(引用元:Abitus公式HP)
USAPA(米国公認会計士)の勉強時間は、一般的に1,200~1,500時間といわれています。
試験科目は、財務会計・ビジネス環境及び諸概念・監査及び証明業務・諸法規(税務・会社法)の4科目で、中小企業診断士と比較すると科目数は少なめですが、各科目の試験範囲が広く、難易度も高いことが理由として挙げられます。
各科目の勉強時間目安は、以下の通りです。
| 科目名 | 勉強時間 |
|---|---|
| 財務会計 | 400~500時間 |
| ビジネス環境及び諸概念 | 240~300時間 |
| 監査及び証明業務 | 280~375時間 |
| 諸法規(税務・会社法) | 280~375時間 |
(引用元:Abitus公式HP)
各科目で300時間以上の勉強時間が必要となるケースが多く、学習計画に余裕を持つといいでしょう。
【難易度・合格率】
USCPA(米国公認会計士)の2024年度平均合格率は約53.2%です。
中小企業診断士試験と比較して、合格率は高く、難易度も低いといえるでしょう。
グローバルに活躍したい方、ビジネスパーソンとしてキャリアアップを目指す方におすすめの資格です。
中小企業診断士の試験概要
令和7年度中小企業診断士試験の試験概要をまとめました。
申込日程や実施スケジュールなど、逃さないよう参考にしてください。
| 試験日程 | 【一次試験】令和7年8月2日(土)・3日(日)
【二次試験】筆記試験:令和7年10月26日(日) 口述試験:令和8年1月25日(日) |
|---|---|
| 受験地 | 【一次試験】札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇
【二次試験】札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡 |
| 受験申込期間 | 令和7年4月2日(木)~5月28日(水) |
| 受験料 | 【一次試験】14,500円
【二次試験】17,800円 |
| 合格発表 | 【一次試験】令和7年9月2日(火)
【二次試験】筆記試験:令和8年1月14日(水) 口述試験:令和8年2月4日 (水) |
【科目合格制度・科目免除制度】
中小企業診断士試験は「科目合格制度」と「科目免除制度」を採用しています。
制度の仕組みを理解し、有効活用することで勉強時間の短縮や、試験勉強の効率化も可能です。
ここでは、「科目合格制度」と「科目免除制度」の特徴や違いを解説します。
【科目合格制度】
科目合格制度とは、一次試験不合格者を対象に、基準点を超した科目に関しては科目合格を与える制度のことです。
科目合格の基準は「満点の60%を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率」と公表されています。
つまりは、各科目で60点以上取ることが合格の条件となります。
一度の受験で7科目全てに合格する必要はなく、翌年の試験以降は合格した科目を免除できるのが特徴です。
3年間の有効期限はありますが、科目合格制度を活用し、長期にわたって合格を目指すことも可能でしょう。
【科目免除制度】
科目免除制度は、一定条件を満たした受験生が試験科目の免除を受けられる制度です。
|
上記2つのパターン、どちらかを満たした場合に科目が免除されます。
後者の資格保有や条件を満たすことによる免除は、保有資格や条件によって、免除される科目が異なります。
中小企業診断士試験の免除科目と対象者は、以下の通りです。
| 免除科目 | 対象者 |
|---|---|
| 経済学・経済政策 |
|
| 財務・会計 |
|
| 経営法務 |
|
| 経営情報システム |
|
(参考情報:アガルート公式HP)
科目免除制度は対象者が限られていますが、最短ルートで合格を目指すために有効活用したい制度といえます。
中小企業診断士の難易度・合格率
中小企業診断士試験は、国家試験の中でも難関試験といわれています。
科目数が多く、試験範囲が莫大なことに加え、合格率(一次試験合格率×二次試験合格率)が10%を下回る、難易度の高い試験であるためです。
ここでは、中小企業診断士の難易度をより細かく解説するために、一次試験・二次試験の合格率を紹介します。
中小企業診断士試験全体の難易度を把握するための参考にしてください。
【一次試験・二次試験合格率】
中小企業診断士試験の過去8年分の一次試験・二次試験合格率は以下の通りです。
| 年度 | 一次試験合格率 | 二次試験合格率 | 合格率(一次試験合格率×二次試験合格率) |
|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 21.7% | 19.4% | 4.2% |
| 平成30年度 | 23.5% | 18.8% | 4.4% |
| 令和元年度 | 30.2% | 18.3% | 5.5% |
| 令和2年度 | 42.5% | 18.4% | 7.8% |
| 令和3年度 | 36.4% | 18.3% | 6.6% |
| 令和4年度 | 28.9% | 18.7% | 5.4% |
| 令和5年度 | 29.6% | 18.9% | 5.6% |
| 令和6年度 | 27.5% | 18.7% | 5.1% |
(引用元:中小企業診断協会HP)
令和元年度の試験以降、一次試験の合格率は30%を上回り、難易度は低下しつつあります。
一方で、二次試験は、合格率に大きな差がなく、約18~20%を推移しています。
一次試験・二次試験それぞれの合格率は、さほど低くありませんが、試験全体を通しての合格率は、10%を下回るため、非常に難易度が高い試験といえるでしょう。
中小企業診断士試験に有利な知識や実務経験は?
中小企業診断士試験は、実務と関連する科目もあり、経営の知識を幅広く問われるため、実務経験や専門知識の有無が試験勉強に大きく関わります。
勉強時間の短縮や、試験勉強の効率化にもつながる、中小企業診断士に有利な知識や実務経験をまとめました。
【金融・経理・IT・システムエンジニア】
金融機関や経理に関係する仕事に就いている方は「財務・会計」の科目で有利になります。
また、IT関連の仕事に従事していたり、システムエンジニアの経験がある方は「経理情報システム」の科目で知識や経験を活かせるでしょう。
専門知識や経験がある科目の試験勉強は、理解しやすく、勉強時間の短縮にもつながります。
経営コンサルタントとして活躍している方はもちろん、関連性がある専門職に従事している方は、知識・経験を試験勉強にも十分に活用していきましょう。
【経済学部・経営学部・法学部出身】
経営や経済について幅広く学習する中小企業診断士の試験では、経済学部・経営学部の出身者が有利です。
経済学に精通している方は「経済学・経済政策」に有利で、経済学博士号を持つ方は科目免除の対象にもなります。
また、法学部出身者は「経営法務」の科目で知識を活かせるため、勉強スケジュールを練る際には、関連性が高い科目を意識しておくといいですね。
中小企業診断士試験合格のポイント
中小企業診断士試験合格のポイントは以下の4つです。
|
約1,000時間の勉強時間を要する中小企業診断士の試験は、実際に勉強を始める前の綿密な学習計画が重要です。
1日の学習可能時間から長期的な学習期間を見据えることや、自分の生活スタイルに合った学習スタイルを確立することは、学習を継続するために欠かせません。
また、勉強する科目の順序や一次試験・二次試験の関連性を考慮することは、勉強の効率性アップや勉強時間の短縮に直結します。
最短ルートで合格を目指すためには、勉強を始める前に合格のポイント4つを押さえておきましょう。
学習計画を立てる【1日の学習時間】
まずは、試験までの学習計画を立てることが重要です。
試験勉強の全容が見えていないまま、勢いで始めてしまうと試験勉強が非効率になる可能性があるためです。
1日に学習できる時間を考え、1ヶ月・1年単位に落とし込み、1年で合格を目指すのか2~3年に分散して合格を目指すのか選択しましょう。
1年で合格を目指す場合は、毎日2~3時間程度の学習時間が必要です。
| 3時間×365日=1,095時間 |
仕事の状況や、体調、生活環境の変化などで、思うように学習が進まない可能性もあります。
集中して学習に取り組める環境や時間が確保できるのかを考え、無理のない学習計画を立てましょう。
学習スタイルを確立する
中小企業診断士試験の学習スタイルは大きく分けて3つあります。
学業に専念できる方や、自宅ではモチベーション維持が難しい方は通学が、仕事が忙しく限られた時間で効率よく学びたい方は、通信講座がおすすめです。
勉強に集中できる環境が整っており、学習計画からモチベーション維持まで、自己管理ができる方は、独学も可能です。
通信講座を選択した場合も、スマホを利用してすきま時間で学習するのか、テキストを活用して集中して学ぶのかによっても選択肢は異なります。
自分が継続可能な学習スタイルを確立することは、勉強時間短縮に大きく関係してくるため、慎重に選択しましょう。
スマホを利用してすきま時間に効率よく学習したい方は、通信講座のスタディングがおすすめです。
勉強する科目の順番を考慮する
中小企業診断士の一次試験は、7科目で構成されています。
科目別で勉強時間や難易度が異なるため、勉強する科目の順序を考えておくと学習計画が立てやすく、スムーズに学習が進められます。
LEC東京リーガルマインドで公表されている科目の学習スケジュールは以下の通りです。
| 第1科目 | 企業経営理論 |
| 第2科目 | 運営管理 |
| 第3科目 | 財務会計 |
| 第4科目 | 経済学・経済政策 |
| 第5科目 | 経営法務 |
| 第6科目 | 経営情報システム |
| 第7科目 | 中小企業経営・中小企業政策 |
(引用:LEC東京リーガルマインド公式HP)
中小企業診断士の基礎となる企業経営理論は、始めに学習することで、その他科目の勉強にも必要な知識が身に付きます。
暗記要素が強い科目は後半に、中小企業診断士の基礎となり、理解しておくべき科目は前半に学習します。
紹介した順序は、一般的に効率よく試験勉強が進められるおすすめの順序ですが、専門知識や実務経験がある方は、得意な科目を先に学習すると試験勉強がスムーズに進められます。
科目別の勉強時間と、知識・実務経験のバランスを考慮して勉強する科目の順序を決めておきましょう。
一次試験と二次試験の関連性
一次試験と二次試験は、科目によっては試験内容に関連性があります。
一次試験と二次試験の関連性は以下の通りです。
| 二次試験との関連性 | 一次試験科目 |
| 高 | 企業経営理論、財務・会計、運営管理 |
| 中 | 経営情報システム |
| 低 | 中小企業経営・中小企業政策 |
| 関連性なし | 経営学・経済政策、経営法務 |
(引用:スタディング公式HP)
一次試験の「財務・会計」「企業経理理論」「運営管理」は、二次試験と関連性が高いことから勉強時間は多い傾向にあります。
二次試験に関連性がある科目は、基礎を固めておくことで二次試験対策が効率よく進められるため、優先的に時間を十分にとって学習しましょう。
中小企業診断士に関するよくある質問
中小企業診断士に関するよくある質問をまとめました。
中小企業診断士に関するよくある質問
|
受験を検討している方は、事前に確認しておくと安心です。
中小企業診断士合格に必要な実際の勉強時間や年数は?最短でどのくらい?
中小企業診断士の勉強時間は1,000時間といわれていますが、実際には1,500~2,000時間かかった方もいます。
科目数が多く、学習範囲も広い中小企業診断士試験は、学習環境や実務経験・専門知識の有無で必要な勉強時間・学習期間が異なるためです。
LEC東京リーガルマインドによる合格者の学習時間データによると、2年以内で合格できた方が全体の約50%、4年以上かかった方が全体の15%です
また、最短の勉強時間としては、200時間で合格できた方もいます。
中小企業診断士一次試験
経済学72点
財務会計64点
企業経営理論85点
運営管理73点
経営法務68点
情報システム40点
中小企業58点
合計460点公式で再採点したら色々と間違っててシステム40点あるかも!?
無学・独学・8ヶ月・計200時間で受かったメソッドそのうち共有します。
(引用元:X)
500時間以内の勉強時間で試験に合格した方もいますが、一般的には1,000時間、もしくはそれ以上の勉強時間が必要になるため、学習スケジュールには十分に余裕を持ちましょう。
社会人でも合格できる?
中小企業診断士試験は、社会人でも十分に合格が目指せます。
しかし、働きながら合格を目指すためには、勉強時間の確保と長期的な学習計画が必要です。
隙間時間を活用するなど、学習方法を工夫することも効率よく学習するポイントといえます。
社会人の場合、限られた時間内で合格に必要な知識を身に付けるために、学習方法を工夫しましょう。
中小企業診断士の試験勉強は楽しいって本当?
中小企業診断士の試験は、難易度が高く、勉強時間も長いため、試験勉強が大変だと感じる方も多いですが「試験勉強が楽しい」と感じる方もいます。
おはようございます!
今日も朝から中小企業診断士の二次試験対策です。
経営しながら資格勉強するって大変ですが、何より楽しいです
試験日という締切効果もありますし(笑)仕事は終日打合せ入ってますが、気合で乗り切ります
今日も一日頑張りましょう!!
(引用元:X)
初めまして。今年1次試験に受かることを目標に中小企業診断士試験の勉強をしています。
本業が、中小企業さんの経営に近いところに関わるので、
勉強していることがダイレクトに役に立っている感触があり、楽しいですどうぞ宜しくお願いいたします。
(引用元:X)
SNS上では、「実務に役立つ内容が学べるため勉強内容が楽しい」「試験勉強が面白い」という意見もありました。
中小企業診断士試験は、試験範囲が幅広く、多くのことを学べるため、仕事上でも即戦力となるでしょう。
中小企業診断士試験は将来的になくなる?
結論からいうと、中小企業診断士の資格制度がなくなる予定はありません。
インターネット上では、中小企業診断士の資格がなくなるという噂があり、不安に感じている方もいますが、なくなる予定はないため安心して受験できます。
中小企業診断士試験がなくなる、意味がないといった否定的な意見や噂が飛び交う理由は、中小企業診断士には、独占業務がないことや専業で稼ぐことが難しいことが挙げられます。
しかし、中小企業診断士の平均年収は約740万円で、日本人の平均年収を大きく上回るデータがあり、資格取得後の高収入や、キャリアアップにつながる資格ということが明確に分かります。
中小企業診断士はなくなる・意味がないといった噂もありますが、実際になくなるわけではないため安心して受験しましょう。
中小企業診断士の勉強時間:まとめ
今回は、中小企業診断士の勉強時間や勉強法、おすすめの通信講座について紹介しました。
中小企業診断士試験に必要な勉強時間は、1,000時間といわれており、長期的な勉強計画が必要です。
科目数が多く、試験範囲も広いため、一次試験・二次試験の関連性を意識して学習するなど勉強方法にも工夫が必要でしょう。
また、自分に合った学習スタイルを選択することは、勉強時間の短縮や試験勉強の効率化につながります。
通信講座を有効活用し、合格ポイントに的を絞った学習で実力を身に付けていきましょう。
最短ルートで合格を目指したい方は、スマホ学習で効率よく学べるスタディングがおすすめです。