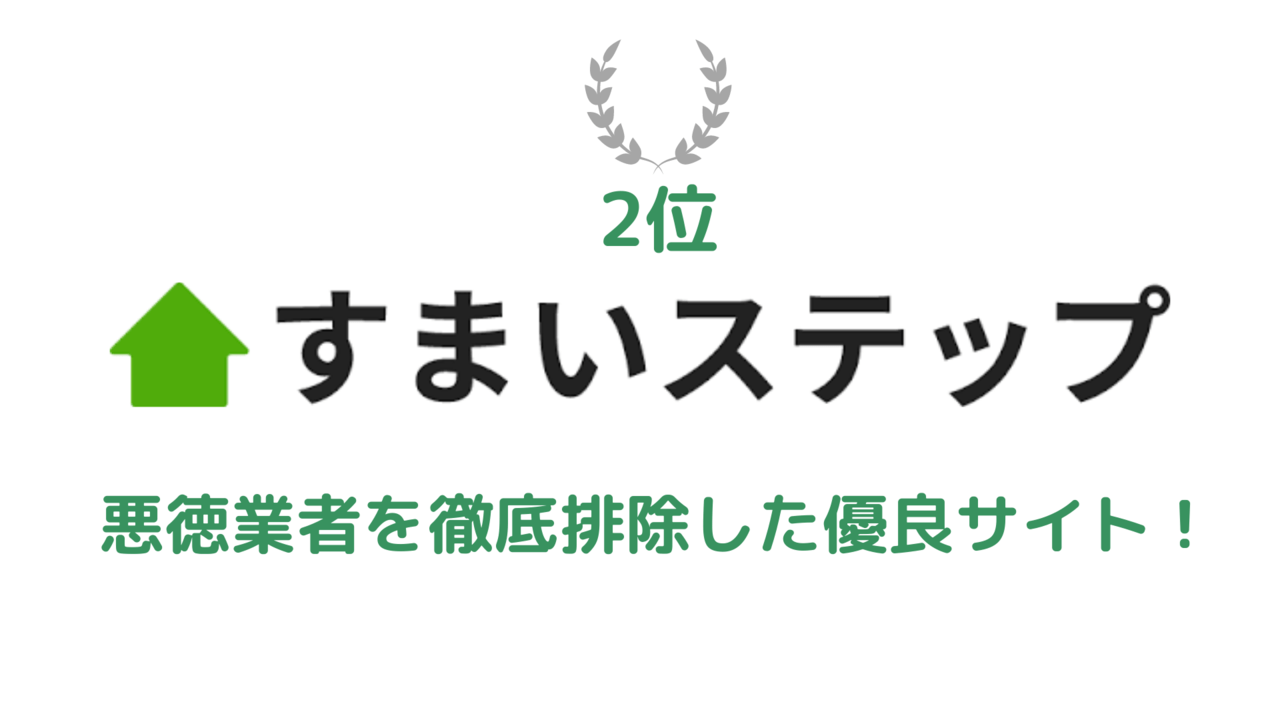古家付きの土地の売却を検討する際、更地渡しという方法があるのをご存知でしょうか。また、知っていたとしても、どのようなメリットがあるのか、手順や手続きなど詳しく知らない方が多いのではないでしょうか。
更地渡しは、老朽化して住むのが難しい物件を売却する手段の一つです。しかし、解体工事を行うタイミングや、どこまでの責任を売主が持つべきか理解しておかなければ、更地渡しを行うメリットは得られません。
本記事では、更地渡しの概要からメリット・デメリット、解体工事を始めるタイミングなど大事なポイントを分かりやすく解説していきます。
不動産一括査定サイト利用者が選んだおすすめサービスTOP3
この記事を読まずに、先におすすめの査定サービスを知りたい人におすすめなのが、以下の3サービスです。
※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)
不動産の更地渡しに関する基礎知識

実は、更地渡しの定義は明確に定まっていない部分があるため、更地渡しは不動産業界では難しい取引手段とされています。この章では、まず更地渡しの概要についてご説明します。
更地渡しとは
更地渡しとは、劣化した部分はそのままの状態で引き渡す現状渡し(現状有姿)とは逆で、もともとあった建物を売主の責任のもと取り壊し、更地にした土地を売却することを言います。古家付きの土地に採用される方法で、更地にすることで住居以外の用途でも活用できるようになり、売れやすい・買いやすい不動産にする目的があります。
ただ、更地渡しの際には知っておかなくてはいけない注意点やトラブルリスクも多いことや、不動産業者の高度な対応力を要するなど、難しい手続きであるとされています。
更地渡しが適切なケース
上記の理由から、更地渡しが選択されることはそう多くありませんが、以下のような場合には、更地渡しを検討する価値があります。
- 事故物件
- 住宅として機能しないほど古い物件
- 築年数は浅いがシロアリ被害を受けている
- 解体業者を時間をかけて選びたい
- 立地条件が良く購入希望者が見つかりやすい
一般的に、事故物件や古すぎる物件は入居者が現れる可能性は低く、まだ住めそうな物件だったとしてもシロアリ被害で脆弱になってしまっている物件は取り壊した方が良いでしょう。
また、建物解体を請け負う業者は多数ありますが、中には低価格で請け負っておいて危険ゴミや不用物を隠したり、そのまま放置するような悪徳業者もありますので、業者選びは慎重に行いたいものです。しかし、ようやく業者を決めて解体してもすぐに買主が見つかるわけではありませんし、更地にしてしまうことで固定資産税が上がってしまうため、解体を前提とした物件を、業者選びと並行して先に売り出しておくケースがあります。
更にそのような解体前の状態であれば、解体費用の一部を買主に負担してもらえないか交渉することも可能です。立地条件が良く人気の土地であれば、複数の購入希望者が集まる可能性がありますので、より強く希望してくれる購入者に優遇措置を設けて費用交渉を持ちかけるのも良い方法です。
更地にすれば高く売れる可能性について、こちらの記事でも詳しく解説していますので、是非参考にしてみてください。

- 全国の事故物件に特化した買取業者!
- 事故物件でもしっかり適正価格で最短即日現金化が可能!
- 買取以外の提案や遺品整理など状況に応じてワンストップサービス!
更地渡しの流れ
更地渡しの基本的な手順は以下の通りです。
- 解体業者へ見積もり依頼
- 解体業者と契約
- 行政機関へ解体工事の届出書を提出
- ライフライン停止
- 工事開始
- 引き渡し
- 法務局へ滅失登記申請
なお、ライフラインには電気・ガス・セキュリティ・電話・テレビなどがありますが、水道は散水で使用しますので停止しないようにしましょう。また、登記している建物を解体したことを申請するための滅失登記申請に関しては、解体から1ヶ月以内が原則となります。
工期にもよりますが、全工程の期間の目安としては、おおよそ1ヶ月〜2ヶ月と考えておくと良いでしょう。
更地渡しに必要な費用

次に、解体工事に際して発生する費用の諸々を確認していきましょう。主にかかる費用は以下の通りです。
- 建物の解体費用
- 解体作業の追加費用
- 建物滅失登記の費用
一つずつ詳しく見ていきましょう。
建物の解体費用
建物の解体費用は通常、以下のように求められます。
※延床面積…建物の各フロアの床面積の合計のこと。1坪=約3.306㎡。
坪単価は建物の構造やその地域によって変動します。ここでは、建物の種類ごとの金額の目安を紹介します。
| 構造 | 坪単価 |
| 木造 | 2万5,000円〜4万円 |
| 軽量鉄骨造 | 2万5,000円〜4万5,000円 |
| 鉄骨造 | 2万5,000円〜5万円 |
| 鉄筋コンクリート | 3万円〜8万円 |
例えば、延床面積30坪の木造住宅を解体する場合、坪単価4万円で計算すると解体費用は120万円となります。
これだけ考えただけでも大変な金額が発生することが分かりますが、それ以外にも発生する費用があります。次に説明する別途費用や滅失登記費用もしっかり把握して予算組みしておきましょう。
解体作業の追加費用
以下のような費用は坪単価に含まれていないものや割増料金が発生し、建物の解体費用とは別に追加請求される可能性があります。
- 外構、土壁、地下室などの撤去費用
- 養生、足場の設置費用
- 重機の回送費用
- 整地費用
- 警備、交通整理などの管理費用
- アスベスト(石綿)の除去費用
- 大きめの花壇、樹木の撤去費用
また、解体工事で一番懸念されるのは、地中に埋まった残置物です。後述しますが、地下埋設物の有無で後々トラブルに発展するケースは少なくありません。そのため、過去にどのような建物があったかの事前調査を依頼するための費用や、埋設物が見つかった場合はその撤去のためのコストも必要になってくるでしょう。
建物滅失登記の費用
建物を解体した場合は、解体が完了してから1ヶ月以内に滅失登記の申請をしなくてはなりません。申請をしないまま放置しておくと、その土地に新しい物件の建築許可が下りないという問題が発生します。また、既に無い建物の固定資産税がかかり続けるだけでなく、申請を怠ったことに対する10万円以下の罰金が科せられる場合もあるのです。
滅失登記申請は原則、建物の名義人または相続人が行いますが、土地家屋調査士へ依頼する方法もあります。法務局へ申請するため、自分で手続きを行う場合はその道中の交通費や、郵送の場合は切手代、また申請書を発行する際は手数料600円(1通)が発生する程度です。土地家屋調査士へ依頼する場合、そのエリアにもよりますが4〜5万円が相場となっています。
登記申請自体はそれほど難しい作業ではありませんので、少しでもコストを節約したいのであれば、自分で手続きを進めてみるのも良いでしょう。
建物の解体費用について詳しくはこちらの記事でも解説しています。

不動産を更地渡しで取引するメリット
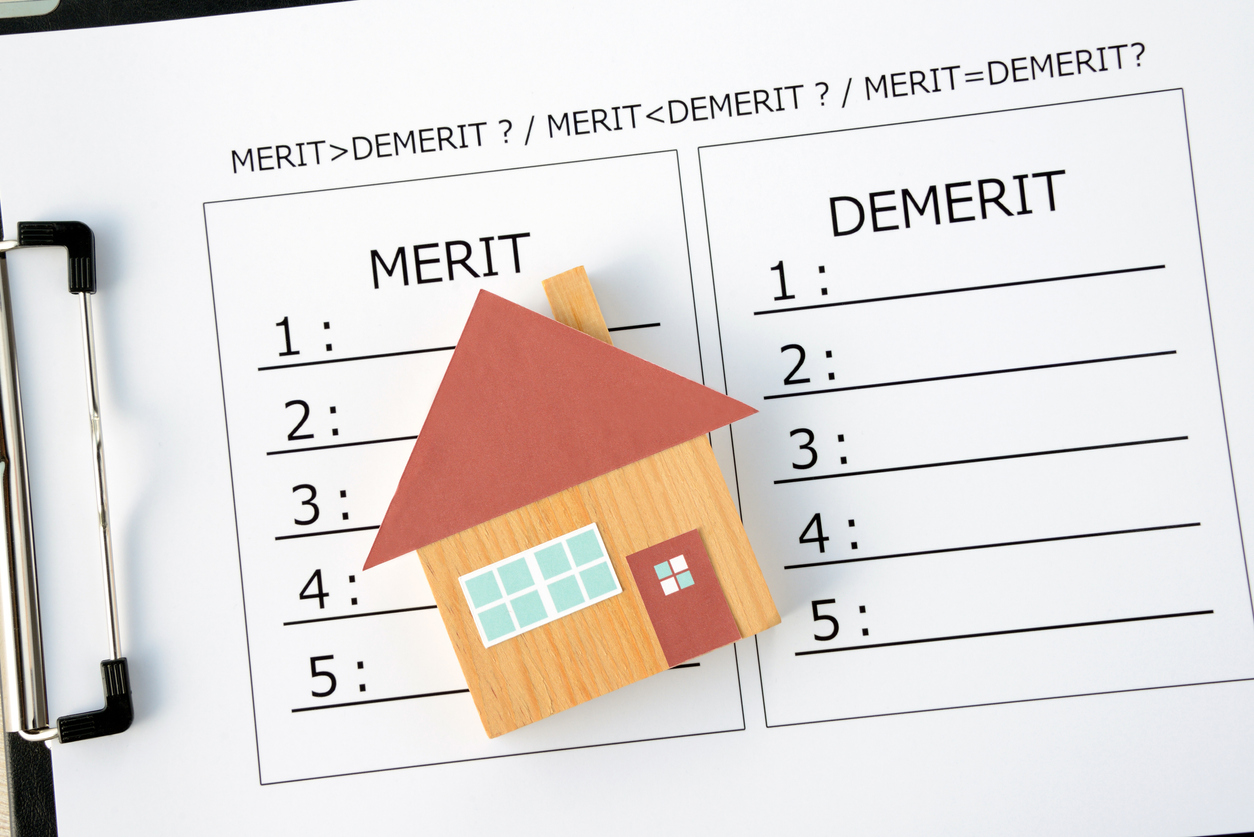
更地渡しで得られるメリットは、主に次の3つが挙げられます。
- 不動産が売れやすくなる
- 解体費用が経費にできる
- 地下埋設物を調べやすい
以下で詳しくご説明します。
不動産が売れやすくなる
冒頭で述べた通り、古い家を解体することにより土地活用の選択肢が大幅に広がることから、更地渡しをすると不動産が売れやすくなるというメリットがあります。
例えば、駐車場経営や賃貸マンションなどで不動産投資を考える購入希望者にとっては事業を始めやすいまっさらな土地の方が好まれますし、購入してから買主側で古家を解体するとなれば、前述したように埋設物が見つかった場合に余計な費用が発生してしまうため、古家付きの土地は敬遠されてしまうケースが多いのです。
上記のような理由より、更地にして売却した方が不動産が売れやすくなり、更に土地の査定額も上がる可能性もアップします。
解体費用が経費にできる
もう一つの大きなメリットとしては、工事費用が経費として申告できるということです。不動産を売却すると譲渡所得になりますので、所得税や住民税が発生しますが、解体費用と建物の取得費(もともと建っていた物件の購入費用)を経費として計上し、減税を狙うことができるのです。
課税対象となる譲渡所得額は以下のように求めます。
ただ、国税庁が定めるマイホームを売却した際の特例(3,000万円の特別控除額制度)があるため、この特例を受けた場合、売却する土地が3,000万円を下回る場合は経費申告する意味をなしません。
また、譲渡費用には解体費用のほか売却のために発生した仲介手数料や印紙税などが含まれますが、解体工事が完了した直後に土地を売却できなければ解体費用を譲渡費用として計上することが難しくなりますので注意が必要です。
“参考:国土交通省「No.1440譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」”
譲渡所得や不動産売却後の確定申告については下記の記事もご覧ください。

地下埋設物を調べやすい
地下埋設物については上記で少し述べましたが、後日新しい物件を建てる際に撤去が必要となったり、物によっては環境汚染に繋がる可能性もあり、残っていると大きなトラブルの元となります。
更地渡しを行うということは、このような地中埋設物の有無を事前に調査するきっかけにもなりますので、自身のトラブル回避のためでもあり、買主に対しても「地歴調査済み」と告知することで安心して購入してもらえる土地であることのアピールにもなります。
更地にする前にチェックしておきたいポイントや更地渡しのQ&Aなど解説したこちらの記事もおすすめです。

不動産を更地渡しで取引するデメリット

それでは逆に、更地渡しで取引する不利益も理解しておきましょう。以下のような点が挙げられます。
- 建物の資産価値がゼロになる
- 追加工事が必要になる可能性がある
- トラブルが起こりやすい
物件の性質によっては更地渡しがデメリットになってしまうケースがあります。具体的な内容を見てみましょう。
建物の資産価値がゼロになる
建物を取り壊すということは、持っていた資産を失うということになりますので、建物自体の資産価値をしっかりと把握しておかなければいけません。
また、更地にすれば高く売れるからと言って解体費用全額を売値に乗せることはできないでしょう。上述した「更地渡しがおすすめのケース」や、観光地・繁華街などの人気エリアにある土地でない限り、更地渡しは大きなリスクを伴う可能性がありますので、安易に解体を決断しないようにしましょう。
更に、住居があることで受けられていた固定資産税の優遇措置が更地にすることで無くなりますので、納税額も大幅に上がることも想定しておかなくてはいけません。
更地にする前後で税金がどのように変わるかについては、下記の記事をご覧ください。

建物の資産価値を調べるなら、不動産一括査定サービスが便利です。自宅にいながら、複数の不動産会社に無料で査定を依頼することができます。思ったより高く売れそうであれば、そのまま物件の売り出しに進むことも可能です。
おすすめの一括査定サイトは「すまいステップ」

- 初めてで不安だから実績のあるエース級の担当者に出会いたい
- 厳選された優良不動産会社のみに査定を依頼したい
- 悪徳業者が徹底的に排除された査定サイトを使いたい
\ 厳選した優良会社に査定依頼 /
すまいステップで一括査定する
追加工事が必要になる可能性がある
これまで何度か登場した地中埋設物の存在についてですが、これは実際工事を進めてみないとどのような物が埋まっているか分からないため、都度追加工事が発生し、見積もり時点から大幅に予算がオーバーしてしまう可能性もあります。
また、過去に何度か解体工事をした経緯がある土地では、以前の建物の基礎部分が埋まっている場合もあります。古くから活用されていた土地の場合はこのような残骸がある可能性が高いため、入念な地歴調査が必要となります。
トラブルが起こりやすい
更地渡しでトラブルが起こりやすい大きな原因は、責任の位置付けの曖昧さにあります。これはどういうことかと言うと、更地にするためには事前調査と地中残置物の処理が必要となりますが、それを売主・買主のどちらが請け負わなければいけないなどの責任定義が明確に定められておらず、不動産会社によっても認識が異なります。
そのため、「引き渡し後に物件を建てようとしたら残置物が見つかった」「予想以上の量の廃棄物が残っていたため負担額が跳ね上がった」などで、売主・買主のどちらかに不満が募り、後々トラブルに発展するというケースも少なくありません。
更地渡しで取引する際には、事前調査や残置物の処理は売主・買主のどちらが負担するのかや、予想外の場合にはどのように分担して対応するのかを、当事者同士で綿密に打ち合わせておくことが重要です。
更地渡しを成功させるためのポイント

更地渡しのメリット・デメリットについて理解したところで、実際に取引を進める際は何に留意すれば良いかを考えていきましょう。ここでは、更地渡しを成功させるポイントについて解説していきます。
事前調査を行う
まず第一に、その土地の地歴調査を十分に行うことです。以下のような方法で、地中に埋まった残置物の有無を事前に調べておきましょう。
- 法務局や市区町村へ調査(謄本、滅失登記などから建物の解体作業や焼失があったかどうか調べる)
- 近隣住民への聞き取り
- 国土地理院や図書館などで確認(過去の情報、地図、写真を確認する) など
また、解体業者に関しても適切な工事をする業者かどうかの選定も大切です。費用の安さだけにとらわれて廃棄物を埋め戻したり放置したりする悪徳業者に依頼してしまわないよう、複数社に見積もり依頼をして比較することもおすすめです。
売却間際に更地にする
土地や建物など、不動産を所有すると固定資産税・都市計画税が発生しますが、建物がある土地には以下のような特例が設けられます。
| 税金項目/用地タイプ | 200㎡以下の部分(小規模住宅用地) | 200㎡超えの部分(一般住宅用地) |
| 固定資産税 | 課税標準額が6分の1になる | 課税標準額が3分の1になる |
| 都市計画税 | 課税標準額が3分の1になる | 課税標準額が3分の2になる |
しかし、建物が無くなればこれらの特例も受けられなくなりますので、納税額が4倍以上になってしまう可能性があります。そのため、解体工事はできるだけ先延ばしし、引き渡し間際に済ませる方が望ましいです。
一戸建ての固定資産税・維持費について、こちらも合わせてお読みください。

周辺住民への配慮を徹底する
解体工事の期間は、近隣への影響も気を配らなくてはなりません。工事最中の騒音や予期せぬ事故などで近隣住民からのクレームが起こってしまえば、今後その土地を利用する買主にも迷惑をかけてしまいます。問題が大きくなれば裁判沙汰や、最悪の場合は怪我人が出るなどの恐れもあります。
余計なトラブルリスクを少しでも無くすためにも、解体工事の前には近隣住民への告知と挨拶周りを徹底するよう心がけましょう。
不動産の更地渡しに関するQ&A

最後に、更地渡しに関する様々な疑問を解決しておきましょう。この章では、更地渡し取引についてよくある質問をまとめました。
解体費用はどこまで売主が負担する?
更地渡しとは土地を更地にして綺麗な状態で引き渡すことを指しますので、整地・転圧(※)・地盤改良工事までは売主が費用を負担するのが一般的です。
新築に向けて地形を変化させる土地造成工事は、売却成立後の工程になるため買主が負担するのが通常です。
※転圧…重機などで地面に圧をかけ、土や砂の中にある空気を押し出して強化すること。
買主がローンを組む場合は?
買主がローンを組む場合、解体工事を開始するタイミングが非常に重要です。買主が新築を考える場合は、住宅ローンを組むことが一般的ですが、ローン審査に通らなかった場合は土地購入を諦めざるをえません。しかし、売買契約締結後の解約となれば多額の手付金を支払わなくてはならないため、そのようなペナルティ無しで契約解除ができるローン特約という制度が設けられています。
ローン特約は買主にとっては好都合な制度ではありますが、逆を言えば売主にとっては契約が成立していたのにもかかわらず一銭も手に入らないという状況になります。更に、買主が決まった時点で既に解体工事を開始していた場合、新しい買主を探し直す際に「解体前提」として販売活動ができず、更地渡しの恩恵を受けることができなくなります。
そのため、解体工事は必ず買主がローン審査に通った後に着手することがポイントとなります。住宅ローンの審査は仮審査・本審査の2段階ありますので、本審査まで通過したことを確認できるまでは待機しておきましょう。
不動産売買における手付金の概要についてはこちらの記事をご参照ください。

解体工事についての責任者は?
更地渡しにおいて、解体工事の責任と費用負担は売主側にあるのが基本です。例えば、解体工事の作業中に近隣から苦情がきた際の対応や、隣家の塀に傷を付けたなどによる損害賠償など、売主が責任を問われる可能性は大いにあります。
そのためにも、工事を依頼する際は信頼できる業者の選定が重要になります。各業者の工事実績や口コミ、担当者の対応力などもチェックしながら、複数の業者を比較して判断しましょう。
また、売買契約書には「どの範囲まで売主責任で、どこからが買主責任にあたるか」を明確に記述しておくことが重要です。
まとめ

更地渡しは、解体費用や解体工事においての売主の責任が大きくかかってきますので、事前の地歴調査や業者選びを慎重に行うことがポイントとなります。また、解体工事を行うタイミングを間違えば売却できないどころか多額の出費のみが発生するリスクもあります。
しかし、状況によっては不動産が売れやすくなったり解体費用を買主に分担交渉ができるなど、大きなメリットを得ることが可能となります。
本記事でご紹介した更地渡しがおすすめのケースにご自身の土地の状態が当てはまるか判断し、最適な取引方法を検討していきましょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。