離婚をするとなれば、気になるのは財産分与でしょう。慰謝料の有無とは別にして、基本的には共有財産を半分ずつ分けるのが財産分与です。所有しているマンション以外に大きな財産がなければ、売却して現金を分けるしかないと思うかもしれません。
しかし、売却すれば住居を失うわけですから、その後の生活に支障が出ることも考えられます。売却益が潤沢にあれば生活水準を落とすことなく賃貸住居へ引越したり、新たに自分用の住居を購入できたりしますが、そう上手くいくのかどうか不安になる人もいるでしょう。売却せずに一方が住み続ける選択をする場合は、ローン返済の責任所在やマンションの所有権も気になります。
そこでこの記事では、マンションを売却するか住み続けるかをしっかり判断できるよう、双方のメリットとデメリットを比較します。後半ではトラブル事例と対策も解説するので、慌てず冷静に対応できるよう参考にしてみてください。
- 離婚時にマンションを売却するか住み続けるかを決める際、住宅ローンの残債、マンションの査定額、オーバーローンかアンダーローンかの確認をしましょう。
- マンション売却のメリットには、夫婦関係を清算しやすい、財産分与額が確定しやすい、ローンの完済または残債を減らせるなどがあります。住み続ける場合、住み続ける側の生活が安定しやすい、すぐに別居できる点などがメリットです。
- 離婚に関するトラブルを回避するためには、夫婦で取り決めたことを「離婚協議書」または「公正証書」に記載しておくことが重要です。よくわからないことは弁護士や不動産会社などの専門家に相談し、冷静に協議を進めて内容を決めましょう。
売却か住み続けるかを決める3つのポイント

離婚時にマンションを売却するか住み続けるかを判断するときは、まず次の3つのポイントを整理することが大切です。
- 住宅ローンの残債を確認する
- マンションの査定金額を調べる
- オーバーローンかアンダーローンかを把握する
では、それぞれのポイントを詳しく解説していきます。
住宅ローンの残債を確認する
住宅ローンの残債がある場合は、その金額を確認しましょう。確認方法は次の4つです。
- 毎年10月下旬頃に金融機関から送付される残高証明書を確認
- ローンを組んだときに送られる返済予定表を確認
- Webサイト上のマイページで確認
- 金融機関の窓口で残高証明書を発行してもらう
現在の残債を確認する方法として最も正確なのは、4番目の残高証明書です。返済遅滞が生じている場合でも、その内容が記載されるため正確な金額がわかります。
1番目と2番目はリアルタイムな金額が記載されているわけではないので、予定通りに返済できていない場合は計算が必要です。
Webサイト上のマイページは、金融機関によって提供されているか否かが異なります。また、マイページがあっても残高を確認できない場合があるので、まずはログインしてみましょう。
マンションの相場を調べる
マンションがいくらくらいで売れるのか、相場を把握することも大切です。相場の調べ方には次のような手段があります。
- 国土交通省が提供する土地総合情報システムで過去の取引を閲覧・参考にする
- レインズマーケットインフォメーションで過去の取引を閲覧・参考にする
- 不動産ポータルサイトで売り出し中の物件の中から条件の似たマンションを探す
- 売却前提なら不動産会社に査定を依頼する
土地総合情報システムとレインズマーケットインフォメーションは、過去実際にあった取引を調べられるサイトです。立地や諸条件を入力すると売りたい物件に近しい物件の取引を一覧で確認できます。ただし、似た物件なのかどうかを明確に判断することは難しいため、あくまでも参考程度です。
不動産ポータルサイトには、現在売り出し中の物件が掲載されています。実際に売却できる金額ではなく「売り出し価格」なので、買主と売主の商談次第では売り出し価格よりも値下げされる可能性がありますが、似た条件の物件があれば参考になるでしょう。
実際の売却額に最も近い金額がわかるのは、3番目の不動産会社への査定依頼です。不動産会社が間取りや立地などの情報から机上査定を行った後、実際にマンションに訪問して査定(訪問査定)してくれます。机上査定の段階でも、市場価格(時価)に近い金額が提示されるため、有用な手段です。ただし、不動産会社が査定してくれるのは売却を前提とした物件のみであるため、住み続ける前提なら選択できない方法です。
オーバーローンかアンダーローンかを把握する
住宅ローンの残債とマンションの相場がわかったら、オーバーローンかアンダーローンかを判断します。
- オーバーローン:住宅ローンの残債>売却益+その他の財産
- アンダーローン:住宅ローンの残債<売却益+その他の財産
売却する際は諸経費と税金がかかります。売却額の5~7%ほどの支出を相場の価格(売却見込み額)から差し引いて、売却益の見込みを計算しましょう。
住宅ローンの残債と売却益+その他の財産の金額差が小さい場合は、計算上はアンダーローンだったとしても、実際に売却する金額次第でオーバーローンになることもあります。オーバーローンであればマンションを売却できても残債の返済が続くため、夫婦のどちらかが住み続ける選択をする人が少なくありません。
売却or住み続けるメリット・デメリットを比較
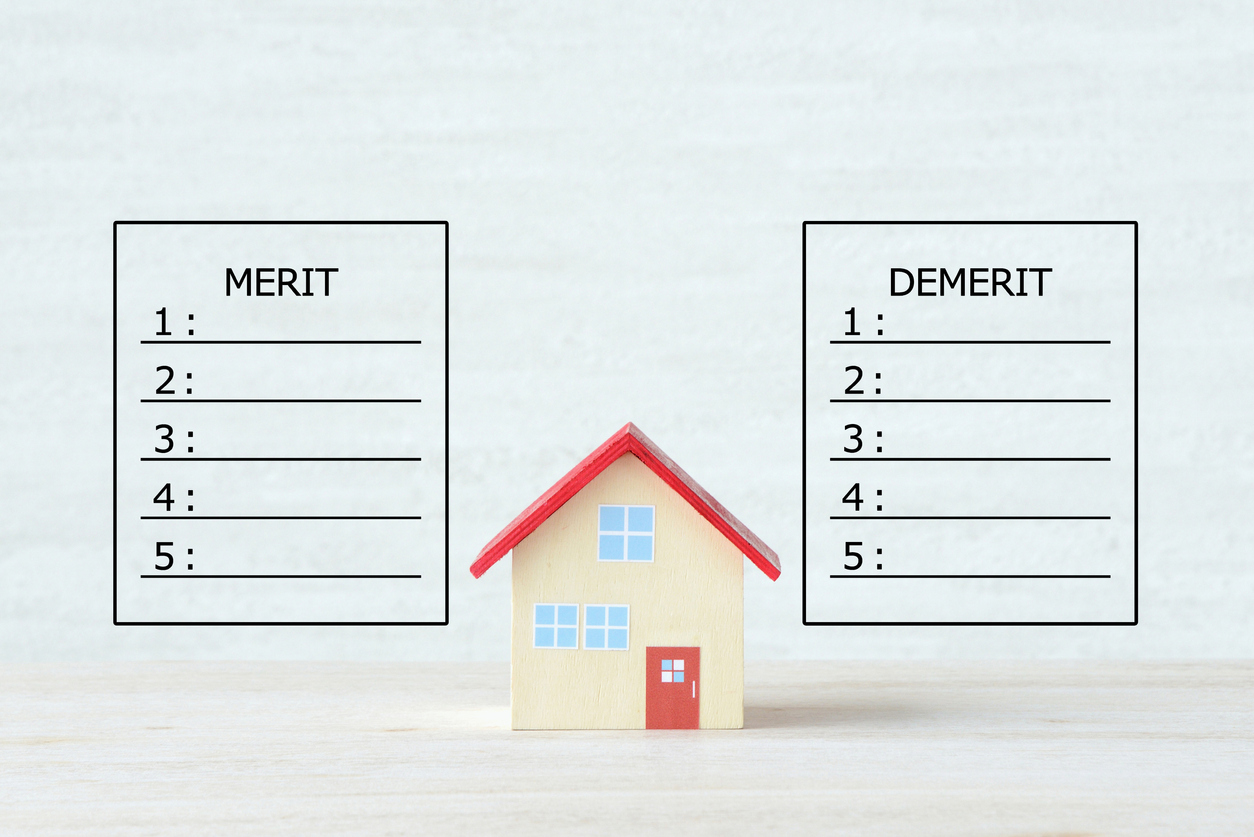
ここまでで、売却できる見込みがマンションを売却する場合と住み続ける場合とで、メリット・デメリットを比較します。
| 項目 | 売却する場合 | 住み続ける場合 |
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
売却する場合
| メリット | デメリット |
|
|
マンション売却後、財産分与が済めば夫婦が頻繁に連絡を取る必要がなくなります。まとまった金額を得られるため、ローンを完済したり残債を大きく減らしたりできるほか、ローンを完済しても利益があれば現金を公平に分けられるのもメリットです。
デメリットは、これまでの住居を失うため生活が大きく変化することです。子供がいる場合はとくに、生活の変化に慣れるまで大変かもしれません。引越しや住み替えにもお金がかかります。
また、不動産会社の訪問査定や買主候補の内見対応、売買契約に向けた商談などのシーンでは、夫婦の協力が欠かせません。円満離婚でない限り、コミュニケーションをとる機会が多いことがデメリットになる恐れがあります。
夫・妻どちらかが住み続ける場合
| メリット | デメリット |
|
|
住み続ける側は生活環境が変わりません。子供と一緒に住み続けるなら転園・転校の手続きをする必要がないのもメリットです。また、出ていく側の引越し費用を工面できればすぐに別居できます。
ただし、マンション以外の財産がほとんどない場合は、財産分与で不公平感が生じやすいことに注意が必要です。とくに、出ていく側がローンの返済を続ける状態だと、ローン返済が滞るかもしれません。また、住み続ける側がマンションの名義人でない場合、離婚後も相手に連絡しなければならないシーンが多くあります。この点については、後半のトラブル事例の項目で詳しく解説します。
状況別|離婚時にマンションを売却する4つの方法

住み続ける選択よりも売却する方が、段取りをイメージしづらいのではないでしょうか。そこで、ここでは状況別の売却方法を確認し、売却するか住み続けるかを判断する上での参考にしましょう。
| 状況 | 方法 |
| アンダーローンかつ適正価格で売りたい場合 | 不動産会社の仲介による売却 |
| アンダーローンで早く売りたい場合 | 不動産会社による買取 |
| 売却後に住み続けたい場合 | リースバック |
| オーバーローンの場合 | 任意売却 |
不動産会社の仲介による売却
不動産会社に買主を探してもらって売却するという一般的な方法です。相場に近い価格で売却しやすく、4つの選択肢の中では最も高額で売れる可能性が高いといえます。住宅ローンの残債を完済しても利益が残れば、財産分与で金額を受け取ることも可能です。
ただし、不動産会社の査定から実際に売却できるまで、3~4カ月はかかることに注意しましょう。この期間は不動産会社の訪問や買主候補の内見対応など、夫婦で協力しなければならないシーンが多いため、どのような離婚理由にせよ、お互いに冷静な対応が求められます。
スムーズかつ適正価格での売却を目指すなら、一括査定サイトを活用して相性のよい不動産会社を探しましょう。査定結果を比較すれば、希望に合った不動産会社を見つけやすくなります。
おすすめの一括査定サイトは「すまいステップ」

- 初めてで不安だから実績のあるエース級の担当者に出会いたい
- 厳選された優良不動産会社のみに査定を依頼したい
- 悪徳業者が徹底的に排除された査定サイトを使いたい
\ 厳選した優良会社に査定依頼 /
すまいステップで一括査定する

不動産会社による買取
住宅ローンの残債が少ない、または完済していて、金額よりも早く売ることを重視するなら不動産会社による買取を選択するのもおすすめです。
不動産会社がリフォームやリノベーションなどを行って再販したり、賃貸経営の物件にしたりするために、直接買い取ってくれます。買取を行っている事業者に相談後、1カ月以内に売却できる可能性があります。また、仲介手数料がかからないのもメリットです。
ただし、不動産会社も利益を上げなければならないため、買取金額は不動産会社の仲介による売却よりも低い金額になりがちです。
買取についてさらに詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。

リースバック
リースバックは不動産会社に買い取ってもらった後で、その不動産会社に賃料を支払い、同じ家に住み続ける方法です。契約内容によっては、一定期間内に資金を用意できれば買戻せる特約が付いていることもあります。
ローン返済額よりも賃料の方が高くなる傾向にありますが、不動産会社の買取によってまとまった資金を得られるため、離婚時に一方が引越すための費用やその後の生活費は確保できるでしょう。また、マンションの所有権が自分にはなくても住み続けられるため、生活環境が変わらないというメリットもあります。
リースバックについて詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。

任意売却
任意売却は、売主の一存で選択できるわけではないため、これまで紹介してきた方法とは性質が異なります。
任意売却を選択するためには、次の条件を満たさなければなりません。
- オーバーローン
- 住宅ローンの返済遅滞がある
- 金融機関が競売申し立てをしている
- 金融機関が任意売却を了承している
オーバーローンの状況では、マンションをローンの担保とするために設定された「抵当権」を抹消できないため、一般的な売却方法では売れません。任意売却は、金融機関の了承を得て抵当権を抹消してもらい、残債の返済は続ける約束をした上で売却するという方法です。
ただし、オーバーローンであっても返済遅滞がなく、金融機関が競売申し立てに至っていないときは、任意売却は認められません。
金融機関の了承を得たら任意売却を取り扱う不動産会社に仲介を依頼し、買主を見つけてもらいます。1つ目の方法で記載した不動産会社の仲介による売却と似ており、競売よりは市場価格に近い金額で売れる傾向にあります。しかし、金融機関が裁判所に競売を申し立ててから実際に競売にかけられるまでの、約6か月間で任意売却しなければならないため、時間の猶予はあまりありません。
任意売却についてさらに詳しく知りたい人は、次の記事もチェックしてみてください。

離婚時のマンションに関するトラブル事例

マンションを売却するか住み続けるか、マンションの売却方法も含めてイメージできたところで、次はトラブル事例を紹介します。代表的な事例を知っておくことで、事前に対策できる可能性が高まります。次の3つのジャンル別で見ていきましょう。
- 住宅ローン関連のトラブル
- 売却期間に関するトラブル
- 売却価格に関するトラブル
住宅ローン関連のトラブル
住宅ローン関連のトラブルには次のようなものがあります。
- 妻が住み続け、夫がローン返済を続ける約束だったが返済が滞っている
- ローンの名義変更をしたかったが審査に通らなかった
- ローン返済のために勝手に売却手続きが進められてしまった
- 任意売却後の残債の支払いで不公平感が生じている
どちらかが住み続ける選択をした場合、オーバーローン・アンダーローンを問わず住宅ローンの残債があれば返済が続きます。返済の責任を負う名義人が住み続ける側であれば、返済が続いたとしても納得しやすいはずです。
しかし、出ていく側が返済の責任を負う場合は、相手のために支出を続けることになります。住宅ローンを完済するために、マンションを売却されてしまうリスクがあるわけです。そこで住み続ける側にローンの名義人を変更しようとしても、金融機関に相談の上、審査を通過しなければ認められません。
また、任意売却後にも残債の返済が続く場合、夫婦で折半して返済していければベストですが、名義人でない方が金融機関に直接振り込むわけではないため、途中で連絡が取れなくなるリスクがあります。
売却期間に関するトラブル
売却期間に関するトラブルは、主に次の3つです。
- 財産分与できる期間で売却できなかった
- 一方が協力せず売却活動が進まない
- 別居後、二人のスケジュールが合わず対応できない
財産分与ができる期間は、離婚から2年間です。マンションを長期間売却できなければ、財産分与できる期間を超過する恐れがあります。
長期化する理由は、買主候補が現れないことだけではありません。夫婦が忙しく双方の協力がなければ書類を揃えたり内見に対応したりできない状況にも関わらず、一方が協力しない場合や、既に別居していてスケジュールが合わないといった場合も考えられます。
このような状況にならないよう、売却を決意したら夫婦で計画を立て、双方の協力を約束することが重要です。
売却価格に関するトラブル
売却か価格に関するトラブルは、夫婦のコミュニケーション不足で生じがちです。
- 売却価格の合意が得られず売却できない(共有名義の場合)
- 低い価格で勝手に売却されてしまった
マンションが夫婦の共有名義の場合は、双方が合意しなければ売却できません。買主候補が値下げ交渉をしてきた状況で、一方は「値下げしても構わないからこの買主候補に売ろう」と思っても、一方が「売り出し価格で買ってくれる人が現れるまで待ちたい」と思えば売却できないということです。
逆に、夫婦の共有名義ではない単独所有のマンションの場合、売却に関しては決断する権利がありません。財産分与の金額を計算したときに納得できない売却価格であっても、売却されてしまうリスクがあります。居住権を主張して住み続けながら抵抗する術はありますが、裁判に発展するでしょう。
トラブルを回避するための方法
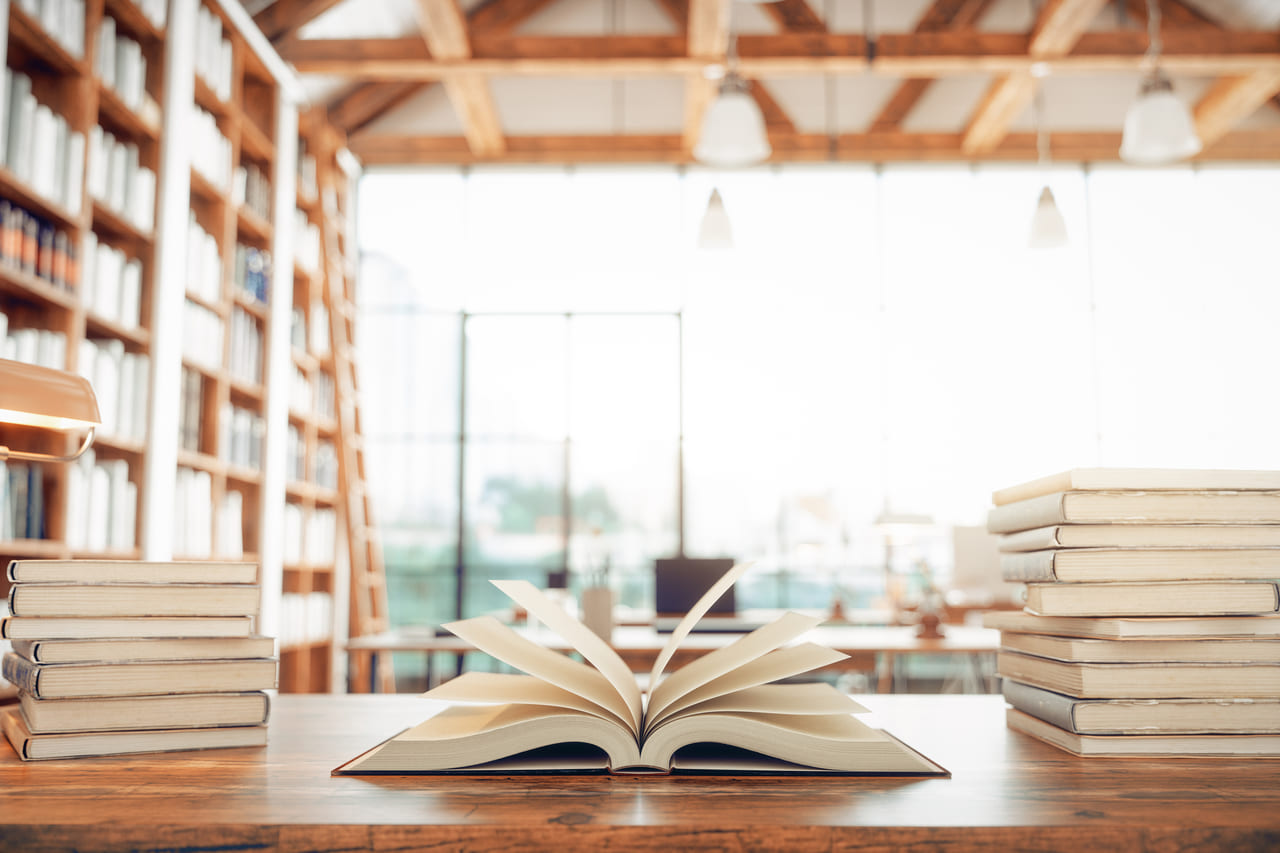
マンションに関することのみならず、離婚時に夫婦で取り決めたことは、「離婚協議書」または「公正証書」に記載しておくことをおすすめします。離婚協議書と公正証書の違いは次の表の通りです。
| 項目 | 作成者・機関 | 特徴 |
| 離婚協議書 | 当事者や弁護士 |
|
| 公正証書 | 公証役場 |
|
離婚協議書は相手が約束を破ったときに調停や裁判を起こす際の資料として使えます。弁護士が作成したものであれば法的効力を持つため、約束を破った相手を追求しやすくなるでしょう。
一方、公正証書なら相手が約束を破ったときに強制執行できる旨を記載しておけば、調停や裁判を経ることなく法的手続きによって義務を履行させられます。具体的には、住宅ローンの返済を続けるという約束を破った相手の給与や財産を差し押さえられるといったことです。
ただし、どちらを作成するにしても夫婦間の合意が必要になるため、情報を整理しながら冷静に協議することが重要です。よくわからないことがあれば、弁護士や不動産会社など、関連する事項の専門家に相談して内容を明確にしておきましょう。
離婚時の財産分与とは?

最後に、離婚時の財産分与について解説します。
財産分与とは
財産分与とは離婚した際に財産を公平に分配する制度のことです。法務省では次のように定められてます。
離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
財産分与は,(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配,(2)離婚後の生活保障,(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており,特に(1)が基本であると考えられています。
「夫婦が共同の生活を送る中で形成した財産」は一般的に「共有財産」と呼ばれ、結婚してから夫婦の協力によって形成された財産のことです。夫が働いて妻が専業主婦という場合でも、妻の協力がなければ夫は働けなかったと判断されるため、結婚期間の給与収入は共有財産に該当します。
ただし、結婚期間中に一方が相続や贈与で個人的に得た所得については、共有財産ではなく個人所有の「特有財産」になります。
マンションについては、結婚前に一方が購入していたとしても、結婚後に住宅ローンの返済が続いていれば、結婚前に支払った頭金や返済額の割合を差し引いた分が共有財産です。しかし、結婚前に購入者が住宅ローンを完済していた場合は、購入者の特有財産になります。
比率は基本的に2分の1が原則
財産分与の分配の割合は、基本的には平等に2分の1とすることが原則です。片方のみが就労していた場合でもこのルールが適用されます。ただし、例外があります。
2分の1が適用されないケース
場合によっては上記の2分の1の原則が適用されないこともあります。それは、財産への貢献度や離婚原因、その後の生活を支えていく経済的余力があるかなどが加味されて判断が下されます。
主なケースとして4つの例を挙げてみましょう。
- 一方の浪費が原因で財産が減ったことがある
- 一方が財産形成に大きく貢献していた
- 特有財産の占める割合が多い
- 一方の経済状況が考慮される
上記のようなケースでは、離婚理由などでさらなる考慮が行われ詳しい分与率が決定されます。自分にあてはまるケースがあれば、弁護士などの専門家と相談しながら財産分与を進めていきましょう。
財産分与の流れ
財産分与は以下のよう流れで行うとスムーズです。
- 財産リストを作る
- 分配方法を協議する
- 離婚協議書にまとめて合意
口頭で協議を行うこともできますが、トラブルを避けるために公的な離婚協議書などに記載して残しておくと安心です。協議がまとまらなかった場合には、離婚後2年以内に調停を申し立てて解決を図りましょう。
まとめ

離婚時にマンションを売却するか、一方が住み続けるかは大きな選択です。夫婦関係や子供のこと、その後の生活まで考慮すると一概にどちらが良いとは言えません。
また、離婚するかどうかを決めかねている人も、住宅ローンの残債やマンションの相場、そのほかの情報の整理は今からでも始められます。より多くの情報を集めて、最善と思える選択をしましょう。
なお、アンダーローンの状況でマンションを売却したいなら、ぜひ一括査定サイトを活用してみてください。複数の不動産会社に無料で査定依頼でき、結果を比較検討できます。
査定が初めての人におすすめの一括査定サイトは「すまいステップ」

すまいステップはこんな人におすすめ
- 初めてで不安だから実績のあるエース級の担当者に出会いたい
- 厳選された優良不動産会社のみに査定を依頼したい
- 悪徳業者が徹底的に排除された査定サイトを使いたい
すまいステップの特徴
すまいステップは、2020年4月にサービスが開始された比較的新しい一括査定サイトです。
その特徴は、提携不動産会社の数ではなく、質で勝負をしている点。一括不動産査定サイトを長年運営している株式会社Speeeが厳選した優良不動産会社に限っての査定依頼となるため、どの不動産会社が良いのかよく分からないという人に特におすすめです!
また、すまいステップを利用して査定依頼をすると、各不動産仲介会社で売買実績が豊富なエース級担当者に出会えるため、不動産の売却が初心者であっても安心です。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。


