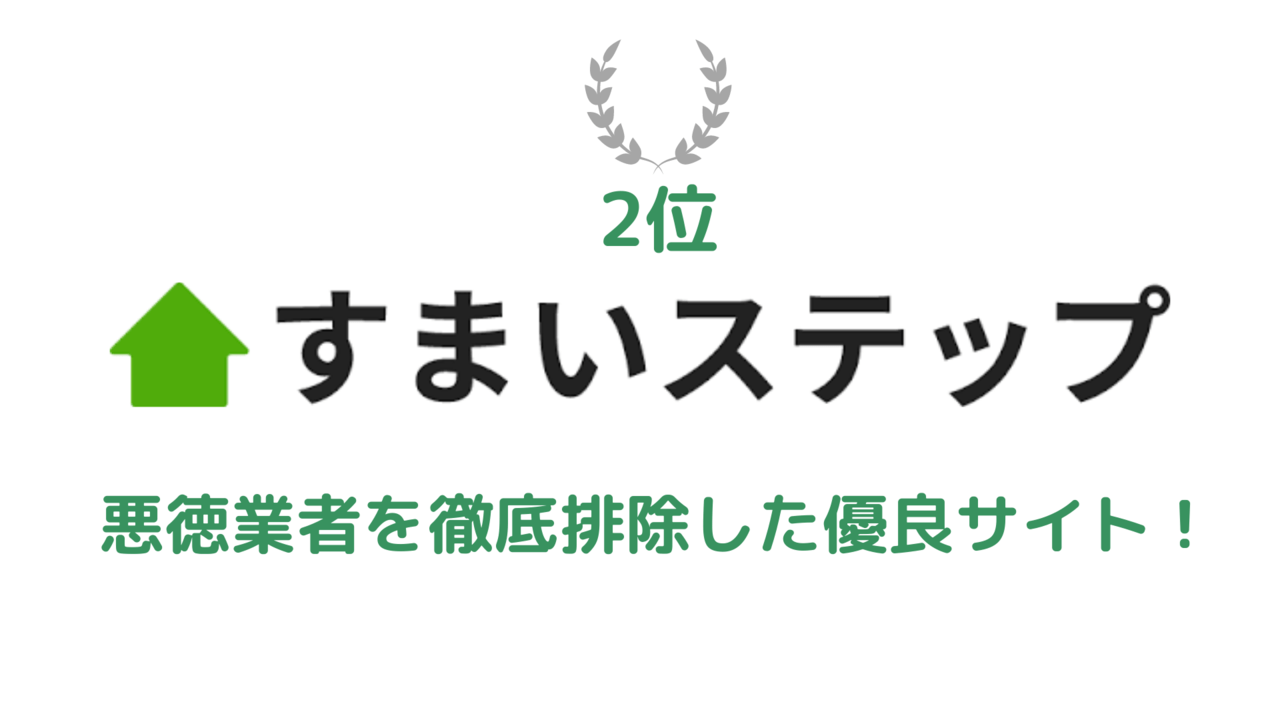田んぼや畑などの農地を売ったら税金がどれくらい掛かるのか、知りたいと思っていませんか?農地を売却する際は譲渡所得税をはじめ、印紙税や登録免許税といった税金を納めなければなりません。農地の価格によって納める金額が変わってくるので、この機会に具体的な納税額や税額の計算方法を知っておきましょう。
加えて、少しでも税金を減らすための方法と、確定申告についても解説します。農地を売却して利益を得た場合は、必ず確定申告をしなければなりません。自分で用意する書類も多いので、必要書類と申告の方法も知っておく必要があります。農地売買に関する節税対策も詳しく解説するので、これから農地の売却を検討している人も参考にしてください。
不動産一括査定サイト利用者が選んだおすすめサービスTOP3
この記事を読まずに、先におすすめの査定サービスを知りたい人におすすめなのが、以下の3サービスです。 マイナビ編集部で実施した独自アンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声と編集部の知見が合わさってできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)
農地売却でかかる4つの税金

まずは、農地を売却する際に掛かる税金を知っておきましょう。田んぼや畑などの農地を売る際には、次の4種類の税金を納付する必要があります。
- 譲渡所得税と住民税
- 復興特別所得税
- 印紙税
- 登録免許税
農地をはじめとした不動産を売った際に得た所得を「譲渡所得」といい、給与所得とは別に分離課税となるため、確定申告の方法も少し変わってくるので注意が必要です。他にも印紙税や登録免許税といった税金が掛かるので、税額の計算方法を知っておきましょう。それぞれ順番に説明していきます。
譲渡所得税と住民税
譲渡所得税は、農地を含む土地や住宅などの不動産を売却した際に掛かる税金です。不動産を売却して利益が発生すると譲渡所得になり、給与所得とは別に所得税と住民税が課せられます。
譲渡所得税額の計算方法
農地の売却によって得た金額(譲渡収入金額)が、その農地の取得と譲渡のために掛かった費用の合計よりも、大きければ譲渡所得となり譲渡所得税を納めなければなりません。
農地の取得費がわからない場合は、売却価格の5%を取得費とみなして譲渡所得の計算を行います。さらに、農地の所有期間が5年超の場合と5年以下の場合とでは、次のように課せられる譲渡所得税および住民税の税率が変わるので注意しましょう。
- 所有期間が5年超の場合(長期譲渡所得):譲渡所得税率は15%で住民税率は5%
- 所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得):譲渡所得税率は30%で住民税率は9%
たとえば、10年所有していた農地を売却して300万円の譲渡所得を得た場合は、納めるべき譲渡所得税と住民税の額は次のようになります。
(※譲渡所得税:45万円、住民税:15万円)
ただし、譲渡所得税は一定の条件を満たせば特別控除を受けられるので、納付する税金を安くできる可能性があります。詳しくは、農地売却方法別の節税方法の項で解説します。また、譲渡所得の長期と短期で税率がどう変わるのかについては、次の記事でも解説しているのでこちらも参考にしてください。

所得税に上乗せする復興特別税
復興特別税とは、2013年1月1日に施行された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」にもとづき、所得税や法人税などに上乗せされることになった税金です。
譲渡所得税や住民税にも該当するもので、2037年の12月31日まで譲渡所得税に2.1%を上乗せした金額を納付する必要があります。例えば、農地を売却して300万円の譲渡所得を得た場合は、復興特別税の額は「300万円×0.021=63,000円」です。
印紙税
印紙税は土地を売買する際の契約書や手形など、特定の文書を作成して金銭のやり取りをする際に発生する税金です。農地を売却する場合は、売買契約書に契約金額に合った税額分の印紙を貼付する必要があります。
不動産売買契約の場合は、売主と買主の2通分に印紙税が掛かるので注意しましょう。契約金額に応じて納付すべき印紙税額は次の通りです。
| 契約金額 | 印紙税額(本則税率) | 軽減税率 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超える場合 | 60万円 | 48万円 |
なお2014年4月1日から2022年3月31日までは、租税特別措置法によって印紙税の軽減措置が講じられており、1億円以下の売買までは、本則税率の半額を納付すればよいことになっています。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記手続きをする場合に納付する税金のことです。農地を売却すると所有権が買主に移りますが、それを証明するために所有権移転登記をする必要があります。その際に次の額の登録免許税を納付しなければなりません。
- 2021年3月31日までに所有権が移転する場合:売却価格の1000分の15
- 2021年4月1日以降に所有権が移転する場合:売却価格の1000分の20
たとえば、2021年の2月に農地を100万円で売却した場合は、納付すべき登録免許税は15,000円です。しかし、2021年の4月以降に売却すると、20,000円の登録免許税が必要になるので注意しましょう。
税金に加えて、農地を売却する具体的な方法についてもあわせて知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

農地売却方法別の節税方法

次に、農地の売却方法別に税金を安くする方法を解説します。他の不動産売買とは異なり、農地を売却する場合は農業委員会や農業関連団体を通じて譲渡したり、転用目的で譲渡したりすると税金の特別控除が認められます。売却金額によっては、税金を納める必要がなくなることもあるので、農地売却を検討している人は控除が受けられないか確認してみてください。
農業関連の委員会や団体を通して売却
農地利用目的の譲渡特例として、次の場合には800万円の特別控除が受けられます。
- 農用地区域内の農地を農用地利用集積計画又は、農業委員会の斡旋等により譲渡した場合
- 農用地区域内の農地を農地中間管理機構又は、農地利用集積円滑化団体に譲渡した場合
農用地利用集積計画とは、市区町村が農業委員会をはじめとした農業関連団体の協力のもとで、農地の掘り起こしや整備を行い、農地規模拡大を希望する農業者に活用してもらう計画のことです。このような行政の計画に協力する目的での農地譲渡の場合や、国民の農地利用の拡大に寄与する農地売却の場合に、税金を控除してもらえるわけです。
農地中間管理機構への譲渡
農業振興地域に密集している農用地や、農業利用に用いるべき土地として指定された区域などを「農用地区域」といいます。農用地区域内の農地を、農業経営基盤強化促進法にもとづく買入協議によって譲渡した場合には、1,500万円の税金控除が適用されます。
買入協議(制度)とは、農地所有者が農地を売却する場合に農業委員会の判断によって、所有者と農地中間管理機構との協議によって売却する方法です。
まず、農地所有者が農業委員会に対して農地の売り渡しの斡旋を申し出て、農業委員会からの要請を受けた市町村長が買入協議を行うことを決定します。それにより、農地所有者と農地中間管理機構が話し合い、農地の売却譲渡が決定する流れです。
農地中間管理機構がいったん買い入れた農地は、最終的に認定農業者に売り渡されることになります。農地を売却する側は1,500万円の税金の特別控除が受けられ、農業公社を通じて農地を購入する認定農業者は、不動産取得税などの軽減措置を受けられます。
農地転用目的で売却
農地が土地収用法などの法律に基もとづいて買い取られる場合は、5,000万円までの税金の特別控除が適用されます。つまり、公共事業などを行うために国の指定業者が当該農地を買い取る場合は、税金の特例措置を受けられるというわけです。確定申告の際には、公共事業の施工者から交付された買取等の証明書などの添付が必要です。
農地を売却したいなら一括査定サイト「イエウール」がおすすめ
農地の売却を検討している人に編集部がおすすめしたい一括査定サービスが「イエウール」です。イエウールがおすすめな理由について、以下にまとめています。
■イエウールがおすすめな理由
- 月間ユーザー数No.1で安心(2020年7月時点)
- 提携している不動産会社の数も業界No.1(2020年7月時点)
- 全国エリアをカバーしているので地方の不動産も売却しやすい
- 田んぼや畑など農地の売却にも対応している
- 悪徳業者が排除される仕組みがあるので安心して利用できる
※2020年7月「不動産の一括査定サイトに関するランキング調査」より(株)東京商工リサーチ調べ
農地売却をしたら確定申告

続いて、農地売却の際に必要な確定申告について解説します。農地の譲渡所得は、分離課税といって所得税とは別に申告する必要があるため、売却した翌年の3月15日までに確定申告をしておきましょう。確定申告で必要な情報を詳しく解説していきます。
確定申告で必要になる書類
農地の売却によって譲渡所得を得た場合は、確定申告が必要です。申告の際には次の書類が必要になるので、準備しておきましょう。
| 確定申告時に必要な書類 | 書類が入手できる場所 |
| 確定申告書第一表と第二表(B様式) | 管轄の税務署 |
| 確定申告書第三表(分離課税用) | 管轄の税務署 |
| 譲渡所得内訳書【土地・建物用】 | 管轄の税務署 |
| 譲渡時の売買契約書の写し | 売買契約時のものを自分で準備 |
| 譲渡に掛かった費用の領収書の写し | 自分で準備 |
| 農地を取得した際の売買契約書の写し | 売買契約時のものを自分で準備 |
| 当該農地の登記簿謄本(登記事項証明書) | 管轄の法務局 |
| 通常の確定申告に必要な書類(マイナンバーカードや預金口座番号がわかる書類、源泉徴収票など) | 自分で準備 |
上記の書類で、確定申告書の第一表~第三表までと、譲渡所得内訳書は税務署で直接もらうこともできますが、国税庁の公式サイトからもダウンロードできるので、こちらを利用してもよいでしょう。登記簿謄本に関しても、登記内容をコンピューターで処理している法務局では、登記事項証明書をオンラインで申請できます。こちらも詳しくは法務局のホームページを確認してください。
税の控除を受ける時に必要な書類
次に、譲渡所得税の控除を受ける際に必要な書類についてですが、各種控除を受けるためには以下の書類が必要です。それぞれ確認してください。
| 控除のタイプ | 必要書類 |
| 農地利用目的の譲渡の特例800万円控除 | ・譲渡所得の内訳書【土地・建物用】(確定申告書付表兼計算明細書) ・農地保有の合理化などのために、当該農地を譲渡した場合に該当することを証する書類 |
| 農地中間管理機構への譲渡1,500万円控除 | ・譲渡所得の内訳書【土地・建物用】(確定申告書付表兼計算明細書) ・農地中間管理機構が買入協議にもとづいて、当該農地を買い入れたことを証する書類 ・当該農用地が農用地区域内にあり、買い入れに関して市町村長が法律に則って適正に通知を行ったことを証する書類 ・当該農地を買い入れた者が農地中間管理機構に該当している旨を証明する書類 |
| 転用目的の譲渡の特例5,000万円控除 | ・譲渡所得の内訳書【土地・建物用】(確定申告書付表兼計算明細書) ・公共事業の施工者などから受けた収用等証明書 ・公共事業施工者から交付された公共事業資産の買取等の申出証明書 ・公共事業施工者から交付された公共事業資産の買取等の証明書 |
いずれの特例を受けるためにも譲渡所得の内訳書が必要です。確定申告書に添付する書類については、煩雑で手間がかかる印象を受けるかもしれません。しかし基本的には、農地の買い手となる農地中間管理機構や、公共事業の施工者などが発行する農地取引を証明した書類を添付することになります。
申告と納税は売却の翌年に行う
農地を売却した場合には、譲渡所得の申告は売却した翌年の2月16日から3月15日までに、現住所を管轄する税務署で行います。一括で納付できない場合は、確定申告の際に届け出をすることで分割での納付も可能です。ただし、その場合は1.7%の利子がつくので注意してください。
不動産を売却した際に、確定申告が必要な理由については以下の記事で解説しています。確定申告をする際の注意点についても説明しているので、申告の経験のない方はチェックしてみましょう。

農地売却にかかる税金に関してよくある質問

最後に、農地売却に関する税金の取り扱いについて、よくある質問に回答しておきます。
個人売買での税金はどうなるの?
農地売買は個人間で行う場合と、農地中間管理機構などの農業関連機関を介して行うことがほとんどで、必ず農業委員会の許可や斡旋が必要です。農地として売買すると譲渡所得税と住民税が掛かりますが、農業委員会の斡旋で売却しない場合は、特例控除を受けられない可能性があります。
また、農地を転用して売る場合は売却価格に関係なく、当該土地の不動産評価額の1.4%を税金として納めなければなりません。したがって、農地を宅地化した場合は土地の評価額が一気に高くなり、農地として売却する場合よりも、納税額が大幅に高くなる可能性があるので注意しましょう。
なお農地から転用して売る場合に、売れやすくするポイントを以下の記事で解説しています。こちらも参考にしてください。

農地を相続したら税金の特例はある?
農地を相続で取得した場合は、一定の要件を満たすことによって相続税や贈与税の納税猶予が受けられます。基本的に相続した農地を使って、農業を続けている期間は納税猶予が認められます。ただし、農業を辞めた場合や当該農地を譲渡した場合などは、それまで猶予されていた相続税や贈与税を納めなければなりません。
特に農地を譲渡・貸し付けした場合や、転用・放棄した場合、当該農地が全体の2割の面積を超える場合には、猶予された相続税・贈与税の全額を支払う必要があります。2割以下の場合は、相続税・贈与税の一部を納付することになります。
基本的に農地は面積が広く、相続税や贈与税も大きな額になるケースが多いため、農地を相続した場合は猶予制度を上手く活用しつつ、計画的に運用することが重要です。3年ごとに納税猶予の特例を維持するための継続届出書の提出も必要になるので、忘れないようにしましょう。
まとめ

農地を売却すると譲渡所得税や住民税、特別復興所得税、印紙税・登録免許税が掛かります。譲渡所得税は、売却の翌年に確定申告をする必要があるので、必要な書類は前もって準備しておきましょう。
土地の売却価格によっては、高額な譲渡所得税を納付しなければなりませんが、農業委員会の斡旋や農地中間管理機構との買入協議などで農地を譲渡した場合は、税金の特例措置を受けられます。条件に合う場合は、納税額を大きく減らすことができるので、必ず受けるようにしましょう。
それぞれの税金でしっかりと節税対策を行うことで、農地売却で得た利益を多く残すことができます。この記事で得た情報をもとに、節税対策を始めてみませんか。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。