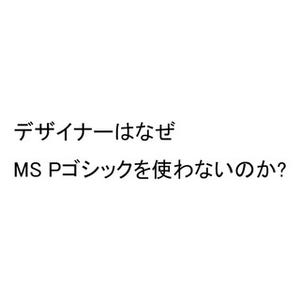活字製造現場めぐり
書体設計士の仕事はたいへんだとつくづくおもう。
基本となる文字とはいえ「永」だけを2カ月近くかけて完璧に習得したとしても、「永」を1万個つくるのかというと、そうではない。同じ書体でも「一」「永」「山」では全然ちがう。1万字必要といわれれば、1万種類の原字を描かなくてはならないのが書体設計(デザイン)だ。
文字修業をしていた最初の数カ月間、橋本さんはもうひとつの修業も同時におこなっていた。原字は、それを書き上げれば製品として完成するわけではない。そこから彫刻用の型(パターン)をつくって鋳型(母型)をつくり、それを用いてつくられた金属活字が最終製品だ。さらにいえば、その金属活字で紙に印刷された文字が、読者の目にふれる最終形となる。いくつもの工程を経て、最終形にたどりつくわけだ。
「いくら原字が美しくても、金属活字の状態でよい形でも、印刷された紙面の状態で美しくなければダメなんです。逆にいえば、印刷された紙面の状態がいちばん美しくなるためにはどういう配慮をしなくてはならないかを念頭において、原字を描かなくてはならない。そのことを、最初の数カ月間で教わりました」
橋本さんは、午前中は原字課の仕事をし、午後には社内のいろいろな部署をまわった。まず、原字の墨入れが終わると、それを製版の外注に出す。製版会社では、原字をネガフィルムにして亜鉛板に焼きつけ、腐食して、文字部分が凹んだ彫刻用の型(パターン)をつくる。外注先からできあがってきたパターンをもって、今度は彫刻部門に行く。母型(活字の鋳型)を彫るベントン彫刻機にパターンをセットし、フォロワーという針で凹んだ文字部分をなぞると、パンタグラフでその動きが縮小されて機械上部のカッターに伝わり、母型材が凹型に彫刻される。
母型ができると、それをもって活字鋳造の部門に行く。鋳造機に母型をセットすると、そこに鉛合金(鉛・錫・アンチモンの合金)が流しこまれ、次々と活字ができあがってくる。「永」の母型をセットしたなら、機械が動いているあいだ、「永」の字があっというまに数十本、鋳込まれていくという流れだ。
「自分で原字を描き母型を彫ってみてびっくりしたのが、こんなにヘタな原字が、12ポイントの小さな母型になるとすごくかっこよく見えるということ。ぼくの字もなかなかいいじゃないの、と(笑)。でも、彫刻機のカッターの刃が細いところには入りこまないので、文字のハネ先があまりに細く鋭角だと、うまく彫れない。自分で彫ってみたことで、ベントン彫刻機で彫るために原字上でなにが必要なのかということを教わったんですね」
教わったといっても、当時は「なんでも自分で覚えなさい」という時代。
「そこに行かないと教えてくれないし、こちらから聞かないことには教えてもらえない。だから、実際に自分でやってみることが必要でした」
鋳造機には火を使うため、鋳造現場はすごく暑いということも、行ってみて知った。
「猛暑どころの騒ぎじゃない。でもそこで鋳造機に自分で彫った母型をセットしたら、ピカピカに光った金属製の活字ができあがってくる。自分の描いた原字がこんなに美しい姿になるのかと感激でした」
ただ、鋳造の過程で文字が太るということも知った。さらに当時は活版印刷だ。凸版印刷の一種で、ハンコのように画線部が凸型になっていて、そこにインキをつけて紙をおき、ローラーで圧をかけて転写するというしくみである。圧力をかけて文字を紙に押しつけるので、余分についたインキがはみだして、印刷時にもわずかに文字が太る(インキのはみだした部分をマージナルゾーンと呼ぶ)。
「こういう過程を全部経験したことで、原字というのは製造工程での変化を見越して設計しなくてはならないということが、よくわかったんです」
50年前に覚えたことでもできるためには?
「モトヤでは、直属の上司は山田博人さんでしたが、活字デザインの基本や全体的なことの指導は部長の太佐源三さんがしてくれました。太佐さんの言葉では、『フリーハンドを覚えなさい』という教えがいまもつよく残っています。フリーハンドということは、定規もなにももたないで、自分の手で線を引くということです。下書きがあるとはいっても、自信をもって線を引かないとぐだぐだになってしまう。だから、自信をもってフリーハンドで線を描けるようになりなさいと教わったんです」
直線は直線定規、曲線は雲形定規で近いカーブを探して当て、烏口で引くという方法をとるひとが多かった。しかしたとえば明朝体の「ノ」は、ひとつのカーブだけでは描くことができない。描きはじめは直線に近く、それがすこしずつカーブになっていき、さらに進むと大きなカーブになる。雲形定規をあて、烏口でこれを引こうとすると、雲形定規を当てる場所をなんども変え、合うカーブをそのつど見つけて、継ぎ足しながら引いていかなくてはならない。そうすると、のびやかさや勢いは生まれず、ぎこちないカーブとなる。
「でもフリーハンドなら、始点から終点を目指して一気に引いていける。描く手の小指のつけ根あたりを支点にしてすーっと手を動かすと、自然なカーブが引ける。引けるということは、つくった線ではない、自然な線が描けるということ。つまり、線自体が生きているということなんです」
しかし、覚えなさいといわれても、どうやって練習したのだろうか。
「そのころのぼくは、ゼロからの出発でしょう。学校の知識も活字の知識もない。ゼロだから邪念がなくて、『こうしなさい』と言われれば素直にそれをやる。できなければ家に帰って練習する。フリーハンドで曲線や直線を引く練習をしょっちゅうしていましたよ」
とにかく手が覚えるまで、何度も何度もフリーハンドで線を引いたそうだ。
「ものごとは手で覚えれば、その後もずっと忘れない。でも後になって思ったんですが、『手で覚える』というけれど、頭で覚えないとダメだということ。この出発点からこのゴールまで線を引くということは、脳の司令で手が動くわけでしょう。手が動いているといえばそうなんだけれど、これは頭が覚えているということなのだと思うんです。物事はやはり頭で覚えないとダメで、でも、頭で覚えているということは、50年前に覚えたことでもできるということ。太佐さんの『フリーハンドを覚えなさい』という教えは、『頭をはたらかせなさい』ということだったんじゃないかと思うんです」
そして、書体デザインの腕を磨くために橋本さんがしたこと。それは、書道を習うということだった。
書道を習いに
「原字はひとつを完璧なかたちにして1万個描くのではない、1万字必要なら1万種類描かなくてはならない。その文字その文字に固有のかたちがあり、ひとつとして同じものはない。書体デザインの道に入ったぼくにとって、それがいちばんの悩みでした。そんなとき、上司で書家でもあった山田博人さんが村上三島(むらかみ・さんとう)さんというひとに書道を習っていると聞き、ぼくも習ってみることにしたんです。三島さんは漢字の先生でした」
「つくるということと、描く=ドローイングすること、そのふたつが合わさったのが活字デザインだから、機械的になんでもつくればよいというものではない。その言葉があって、モトヤに入って2年ほどしてから、村上三島さんの書道教室に通いました。戎橋にある丹青堂という書道用具店が教場でした」
そこで橋本さんは、楷書の基本といわれる唐代の書家・欧陽詢(おうようじゅん)の「九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんのめい)」を、正座にも耐えながら、学んだ。
「モトヤでの仕事を終えると、てくてくと歩いて、途中で551蓬莱の豚まんを1個買って、それを立ち食いしたあとに教室にいくと、ちょうどいい時間でした(笑)」
楷書の漢字を学ぶと、今度は仮名のことが気になりはじめた。書体設計では、仮名はある程度の経験を積んだひとが手がけることが多い。モトヤでは、太佐氏が明朝体やゴシック体の仮名を描いていた。
「描いたことがなかったから、ぼくは仮名のことなんて全然知らなかった。でも、仮名は大事だよとよくいわれました。極端なことをいえば、漢字は読めさえすればいい。しかし文章の表情は仮名で決まるから、仮名は読めるだけではダメなのだと」
太佐氏は、橋本さんにこんなことも語った。
「活字デザインは四角い枠のなかにすることが多いけれど、仮名は丸が基本だから、丸のなかに描きなさい、と。そういって、ご自分がデザインした朝日新聞の仮名を手本に見せてくれました。だから、ぼくはよく朝日新聞を切り抜いて勉強しましたよ。その影響か、いまだに見出し用書体の漢字を書くと『朝日新聞の漢字のようだね』といわれます」
橋本さんは、仮名の書道教室にも通いはじめた。こちらは宮本竹逕(みやもと・ちくけい)氏という先生だった。大阪で書道教室に通ったのは3年ほどだったが、その後も橋本さんは書道を続け、のちには自身で書道教室をひらくまでになっていった。
(つづく)
■本連載は隔週掲載です。
話し手 プロフィール
橋本和夫(はしもと・かずお)
書体設計士。イワタ顧問。1935年2月、大阪生まれ。1954年6月、活字製造販売会社・モトヤに入社。太佐源三氏のもと、ベントン彫刻機用の原字制作にたずさわる。1959年5月、写真植字機の大手メーカー・写研に入社。創業者・石井茂吉氏監修のもと、石井宋朝体の原字を制作。1963年に石井氏が亡くなった後は同社文字部のチーフとして、1990年代まで写研で制作発売されたほとんどすべての書体の監修にあたる。1995年8月、写研を退職。フリーランス期間を経て、1998年頃よりフォントメーカー・イワタにおいてデジタルフォントの書体監修・デザインにたずさわるようになり、同社顧問に。現在に至る。
著者 プロフィール
雪 朱里(ゆき・あかり)
ライター、編集者。1971年生まれ。写植からDTPへの移行期に印刷会社に在籍後、ビジネス系専門誌の編集長を経て、2000年よりフリーランス。文字、デザイン、印刷、手仕事などの分野で取材執筆活動をおこなう。著書に『描き文字のデザイン』『もじ部 書体デザイナーに聞くデザインの背景・フォント選びと使い方のコツ』(グラフィック社)、『文字をつくる 9人の書体デザイナー』(誠文堂新光社)、『活字地金彫刻師 清水金之助』(清水金之助の本をつくる会)、編集担当書籍に『ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(小塚昌彦著、グラフィック社)ほか多数。『デザインのひきだし』誌(グラフィック社)レギュラー編集者もつとめる。
■本連載は隔週掲載です。