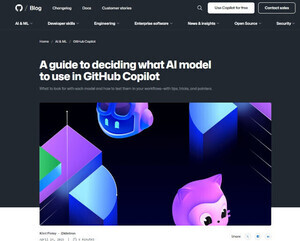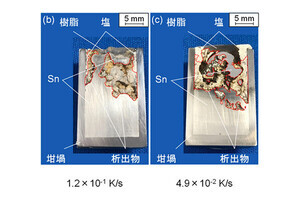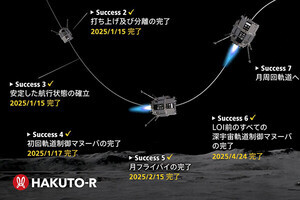ダイバーシティはディスアドバンテージではなく、「アドバンテージ」
続いて、IBMフェローの浅川智恵子氏が登壇した。浅川氏は14歳のときに失明しており、視覚障がい者として障がい者のアクセシビリティ(情報へのアクセス手段)に関する先駆的な研究で数多くの業績を挙げてきた。講演タイトルは「スマートマシンが支援する未来」である。
浅川氏は「目が見えないことは研究においてアドバンテージ(優位)である」と断言し、「目が見えないことはディスアドバンテージ(不利)である」という見方を完全に否定していた。研究テーマである「障がい者のアクセシビリティ」では、自分が障がい者であることから、健常者には分かり難い事柄(障がい者はどのように感じるか)を簡単に理解できる。このことは、研究を進める速度の向上にとても大きく寄与する。
その一例が、Webページの読み上げソフトウェア「Home Page Reader」である。1997年に浅川氏が開発したこのソフトウェア製品は、現在では日本語やイタリア語、フランス語、ドイツ語、米語、英語などの11カ国語のバージョンが存在する。
そして現在では、人間の肩にとまった小鳥がささやくように、視覚障がい者の身近に存在して障がい者を支援する仕組み「コグニティブ・アシスタント」の開発に挑んでいる。その一環として、米国のカーネギーメロン大学と共同で、人間の表情を認識する技術の開発に取り組んでおり、講演ではその一端を披露した。カメラ付きメガネを装着した浅川氏が会議室に着席し、相対して着席した参加者の顔面をカメラで撮影して表情を認識するというデモである。
また日本の社会が急速に高齢化していることから、高齢者のスキルを活かすことでダイバーシティを実現する「シニア・クラウド(高齢者クラウド)」という仕組みを東京大学と共同で研究している。高齢者個々人の異なるスキルをクラウドを通じてまとめることで仮想的に強力なワーカーを創造し、現場の要請に応えることが狙いだ。
「前例のない世界」を生きるための知恵
最後に登壇した土井美和子氏は、大学の工学系修士課程を修了後に東芝に入社し、定年まで東芝の研究開発職をつとめた。東芝が初めて採用した女性の修士卒であり、入社以降の土井氏は「東芝で初めて」が繰り返されるキャリアを歩んできた。講演タイトルは「キャリア構築を阻む3つの障害(バリヤー)を破る」である。
土井氏は講演タイトルにもある「3つのバリヤー」を、(1)前例がない(という障壁)、(2)時間がない、リソースがない(という障壁)、(3)成長できない(という障壁)、だと説明した。この3つの障壁は、土井氏の東芝での経験に基づくもの。同時に3つの障壁に衝突した訳ではない。3つの障壁に、番号の順番でぶつかってきた。
東芝に入社した当初は、「前例がない」という障壁に次々とぶつかった。まず、東芝100年の歴史で初めての女性院卒採用であること(現場がどのように扱ってよいかの経験がない)、次に、初めてヒューマン・インタフェースを研究テーマに選んだこと(当時はヒューマン・インタフェースは研究課題とは考えられていなかった)、などである。東芝では女性であることの苦労はあまりなく、ヒューマン・インタフェースを研究テーマとして認めてもらうことが、はるかに多大な苦労を要したという。
ただし、研究者や技術者にとって「前例がない」ことは「初めて」を意味するので、やりがいは大きい。そこで見方を改め、「前例を作る」ことで障壁を乗り越えた。
そして「時間がない、リソースがない」という障壁は、入社3年目で結婚し、二児を相次いで(出産の間隔は1年5カ月)もうけたことによって一気に立ち上がった。子育てと仕事による、あまりにも多忙な生活。二人目の子供が3歳になるまでの約3年間は「ほとんど記憶がない」と述懐するほどの忙しさである。
そこで「限られた時間をどのように投入するか」を考えた。例えば「平日は仕事」、「休日は子供の相手」と、日常を完全に切り換えた。両者を完全に切り換えることが重要で、中途半端はよろしくない、という。
それから、仕事でキャリアと実績を積んでリーダーになった頃に、3番目の障壁にぶつかった。新しいことに挑戦しづらくなったのだ。上手くいくかどうか分からないテーマを選んで失敗すると、上司や部下などに迷惑がかかる。自分のブランドに傷がつく。失敗を恐れてしまい。リスクを取れない。したがって新しいことに挑戦しづらい。
ここを乗り越えたのは、仕事の場所を変えることが始まりだったという。いろいろな仕事をすることで、時間がなくなる。ゴール(目標)を明確化するとともに、役割分担を明確化しなければならない。球技で受け取ったボールをほかのプレイヤーにパスして渡すように、受け取った仕事は、ほかの適切と思われる社員にすばやく渡す。こうすることで、リスクを取りやすくなり、新しいことができるようになった。
女性だけでの議論は煮詰まる可能性、男性の参加が重要
ポジショントークの後は、司会の佐々木氏がパネリストに質問する形で、パネル討論が始まった。ここで印象に残ったのは次の2点である。
1点目は、江田氏のコメントで、Intelの女性社員をサポートするグループ「WIN(Women at Intel Network)」について述べたものだ。女性だけのグループだと考え方に偏りがあり、議論が煮詰まってしまうことがあったという実体験である。男性社員がサポートグループに参加することで、この問題が解決されたということだ。
2点目は、ロールモデルの必要性に関する意見である。キャリアパスのロールモデルは、必要であるとも言えるし、不要であるとも言えるというのがパネリストの意見だった。興味深かったのは「ワーキングマザー(働く母親)のロールモデルは必要である」ことで、意見の一致を見たことだ。子育てと仕事の両立がいかに困難であるかを暗に示すとともに、父親による育児や家事の分担、会社組織における配慮といった課題がまだ大きく存在していることをうかがわせた。