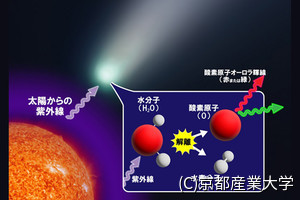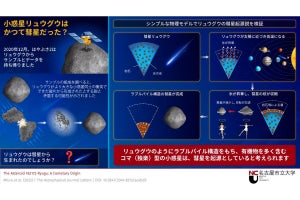国立天文台(NAOJ)は、ハワイ島マウナケア山頂にあるすばる望遠鏡、カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡(CFHT)、ジェミニ北望遠鏡などを用いて、太陽に極めて接近する周期彗星「323P/SOHO」の姿を鮮明に捉えることに成功し、塵を放出する様子を明らかにしたと発表した。
同成果は、米・ハワイ大学のハイ・マンタォ研究員(現・マカオ科学技術大学 博士)を中心に米国、ドイツ、台湾、カナダの研究者が参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。
太陽系では、地球をはじめとする8つの惑星や、冥王星などの準惑星に加え、大型の小惑星などは円軌道や楕円軌道のほぼ安定した軌道を公転しており、太陽に落下するような心配はない。しかし、小型の小惑星や彗星などの小天体は、そうした安定した軌道から外れているものも多く、極端な楕円軌道を描いていたり、場合によっては放物線を描いて一度だけ太陽に接近したら二度と帰ってこなかったり、さらには彗星として最終的に太陽に突入してしまったりするようなものもある。
このような彗星は、太陽への突入を免れたとしても、明るく輝く太陽の極めて近傍を通過するために観測が難しく、宇宙空間にある太陽観測望遠鏡「SOHO」などで偶然に発見される場合が大半を占めるという。一方、観測の難しさを考慮しても、そのような彗星の数は理論的な予想よりはるかに少なく、太陽への致命的な突入をする前に、何らかの作用が彗星を破壊していることを示唆していると考えられてきた。