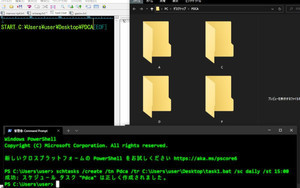ワクチン接種が進むなど新たな傾向も見え始めた2021年下半期。データは日々更新されるが、まだまだ先行きが不透明なコロナ禍の働き方。オフィス勤務はこれからどうなるのだろうか?米Microsoftの研究者Jaime Teevan氏が、ハイブリッド時代に向けた生産性を考察する「Let's Redefine "Productivity" for the Hybrid Era」という記事をHarvard Business Reviewに寄稿している。
2020年3月4日に完全リモートとなったMicrosoftの本社(ワシントン州シアトル)。Teevan氏によると、これを受け、Microsoftそして傘下のLinkedIn、GitHubのリサーチャーが集まりMicrosoftの歴史上最大のリサーチイニシアティブ「New Future of Work」が始動する。研究者たちはそれぞれの事情と環境の中で、50以上のリサーチプロジェクトをリモートで行っている。脳波調査によるリモート会議の疲労や仕事と生活の融合傾向などの新たな課題もレポート、世界100カ国以上に18万人以上にのぼる従業員を擁する同社は、先端機器や自前のデジタルツールを駆使して、コロナ禍の理想的な働き方を追求している。
ハイブリッドワークに関する調査(日本マイクロソフト資料より)
今月に入って、同社はCOVID-19の不確実性を考慮して10月4日のレドモンド本社の全面再開を延期し、データに基づいた柔軟なアプローチで対応することも発表している。そろそろオフィスに戻ることも可能になってきた一方で、従業員は、一度味わった在宅の自由度や柔軟性を失いたくないが、オフィスの良さもあったという状態にあるが、Microsoft CEOのSatya Nadella氏はこれを「ハイブリッドワーク パラドックス」と呼んでいる。それぞれの良いところ悪いところが交差している複雑な状態で今後10年の課題になるとしている。このようなパラドックスを考慮した、ハイブリッドなスタイルでの新しい生産性の定義を考えておく必要がある、というのがTeevan氏の主張だ。
Teevan氏は、断片化や分散化した時間を生産性に結びつけるコンセプト"Microproductivity"でも成果を挙げている研究者。タスクをアルゴリズムでマイクロタスクに分割するアプローチだが、細分化されたタスクはマイクロモーメント(ちょっとした時間)でも処理できる。例えば、仕事の合間に見てしまうFacebook。フィードにAIアプリを使いWordでの編集作業(文字を削って短くしたり、推敲したり)を挿入する。被験者は、ちょっとした時間において苦もなく生産性を上げられたという。たしかに、このような仕組みがいろんなところに溢れていると心地よく仕事を処理できそうだ。Microproductivityの考え方は、Microsoftの製品開発の現場にも取り入れられている。同氏は、ユニークな視点と実践で複数の受賞歴を持つ4人の母親でもあるが、育児とハードワークの境界線で苦闘した日々を回顧している。
そんなTeevan氏は、ハイブリッド時代に生産性を定義する上で、「従業員の活動が多いことを成功と結びつけがちだが、これは長期的で持続的なイノベーションを加速する要因を見逃すことになる」と警告する。コロナ禍での多くの指標で行動アクティビティが増加するが、従業員のほぼ半数が長時間労働の傾向を示し、わずか9%のみしか労働時間を短縮できていない。ワークライフバランスの難しさも影響し、過労や疲労の懸念も高まっているのだ。生産性を考えるときには、"ウェルビーング" "社会的なつながり" "コラボレーション" "イノベーション"に関する要素も入れるべきだと提案している。
ウェルビーイングの視点では、オフィスにいるときはブレストなどコラボレーションや関係構築につながるアクティビティを中心にし、リモートでは家族や健康なども優先順位に入れた時間の使い方を奨励すべきという。「単に時間があるからといって一日中仕事にならないよう境界線をひくことを奨励すべき」とアドバイス。またポイントにあげるのが、個人差。リモートの方がはかどる人、オフィスで仕事をする方がはかどる人と個人差があるため、社員に最も生産性が高くなる時間と場所・低くなる時間と場所について話し合う必要があるとしている。
コラボレーションはどうだろう。Microsoftの場合、オフィスで仕事がしたい理由は、コラボレーションと社会的な結びつきが得られるからだという人が多いという。もしオフィスに行って、チームメンバーがリモートだったらどうだろう?そこでMicrosoftでは、各チーム単位でハイブリッドで働くにあたっての自分たちのルールを作成するように求めているという。メンバーは自身に最適な方法を伝え、チームとしてミーティングを入れない日を設けるのか?定期的に集まるようにするか否か?といったことを決める。ハイブリッドでミーティングをする際には、誰もが意見を言えるようにすることも重要だとアドバイスしている。何かあれば挙手ボタンを押したり、チャットに書き込む雰囲気を作る。また、進行役とは別にモデレーターを設け、チャットに書き込まれた内容に対してフォローしたり、主題を確認することも提案している。
イノベーションーーつまり新しいアイディアを出すためには、メンバーが集まり意見を交換してソリューションについてブレストするというやり方をとることが多かった。これをハイブリッドではどう考えるべきか?個人ベースの作業の生産性という点ではリモートが適しており、他人に依存するダイナミックな作業は対面に向いている。そこで、大きなプロジェクトの場合、初期はリアル中心で作業し、それぞれの役割が明確になったらリモートに切り替えるというやり方が考えられる。また、新しいメンバーが入った、チームが立ち上がったばかりなどの時も、最初は対面がいいだろう。イノベーションでは関係性の構築と維持も重要な要素だ。リアルでも簡単なことではないが、リモートでもチームの結びつきを保てるように努めることを助言している。
ビジネスを動かす可能性のあるアイデアや企画は、生産性を追求する単独でのタスク処理とは異なる部分がある。良いアイデアや企画は、強制されるメカニズムでは実現しにくい。ハーモニーに裏打ちされた総合知ともいうべきものから生まれ、組織で処理する構造になっているためコロナ禍では、これらの仕組みの構築がより難しくなる。DXの究極には、様々なレベルでのイノベーションがあるはずだ。会社のビジネスを進化させる新しい仕組みや社会に貢献できる画期的な仕組み。その種を維持するには、理想的なハイブリッドワークを準備して置かなければならないーー常にパーソナルコンピューターを進化させ続けてきたHCI(Human–computer interface)分野の研究にも造詣が深い同氏のサジェッションは傾聴に値するものだと思った次第だ。