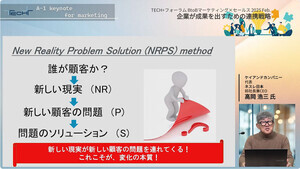1週間ほど前に子供の学校のオープンハウスに参加した。米国の学校の多くではオープンハウス(物件閲覧)と称して、新学年が始まる前に保護者と子供が自由に学校を見て回れるイベントが行われる。カフェテリアや体育館、ロッカーなど施設を確認し、そして教科担任の先生の教室を回って先生に挨拶する。
今年、先生との雑談でしばしば出てきたのが対話型AI「ChatGPT」である。生徒は全員Chromebookを支給されており、学校でも自宅でもChatGPTやGoogleの「Bard」のような対話型AIを使える。「AIに書かせた論文を丸写しして提出した」とか、「宿題のコードを書かせた」といったチーティングに使われているという記事を読んで心配する保護者が少なくない。
昨年末にChatGPTが米国で大変な注目を集め、学生の悪用が広がり始めた12月に、米国で2番目の規模のロサンゼルス統一学校区が学校のWi-Fiと学区所有の生徒用デバイスでChatGPTをブロックした。そして、米最大の学区であるニューヨーク市もすぐにそれに続いた。これらは大きな話題になったので、報道で知っている方も多いと思う。
しかし、当初、対話型AIを拒絶していた教育関係者の意識が急速に変化し始めており、今年初旬に比べて今はブロックしている学校が大幅に減少している。ChatGPTを使いたい子供は学校がブロックしても自宅で学区支給以外のデバイスを使ってアクセスするし、また悪い面ばかりではなく、良い面も見えてきたからだ。
5月に利用禁止を撤回したニューヨーク市は、教師や学区のスタッフが実際に使用してみた上で、学習のサポートを得たり、使い方によって思考能力を向上させるのに役立てられたりする可能性を確認できたとして、「条件反射的な拒否反応でブロックしたのは誤りだった」と認めた。このニューヨーク市の判断で、対話型AIを単に脅威とする見方は後退した。
Walton Family Foundationの依頼を受けて、Impact Researchがニューヨーク、ボストン、シカゴ、ワシントンDCなど東海岸の主要都市でK-12(幼稚園〜高校)の教師1000人に行った調査(2月2日〜7日に実施)によると、51%の教師がChatGPTを利用しており、その内の88%が「良い影響があった」と回答した。授業計画(30%)、ブレーンストーミング(30%)、授業やクラスに関連するリサーチ(27%)に利用していると答えており、高校では38%が授業計画に用いているなど学年が上がるほど利用率が高くなる。登場直後は教育を崩壊させかねない危険なツールと見なされたChatGPTだが、2月時点で教師の間に利用が浸透し、そして教師の方が生徒よりもChatGPTに依存し始めている。ChatGPTを利用したことがない教師の間でも、「マイナスの影響」(10%)より「影響はない」(44%)と回答する人が多かった。
ウチの子供が通う学校も対話型AIをブロックしていない。かといって、今のところ学習に取り入れる計画もなく、インターネットの使い方を指導する授業の中で、偏見、プライバシー、情報モラル、フェイクの問題とともに対話型AIのリスクに触れる予定があるのみだ。
一方で、対話型AIを効率化や時間の節約に利用するための教師向けの研修が秋に予定されており、夏休み中に行われた準備セッションには休暇返上で多くの先生が参加したそうだ。今は対話型AIについて教師が学び、その上でAIが教育にもたらす新パラダイムについて考える期間といえる。
そうした教師側のニーズに応えるように、8月中旬にCode.org、ETS、国際教育技術協会、Khan Academyが提携して、「AI 101 for Teachers」という教育者向けの無料オンライン講座を用意した。また、OpenAIも8月末に「Teaching with AI」という教育者向けガイドを公開している。
米国では中学生になったら数学の授業で電卓を使わせる。それが日本の生徒に比べて計算力が身についていない生徒が多い一因になっているのだが、電卓があるのだから「活用するべき」というのが米国的な考え方なのだ。約20年前、Web検索が便利になり始めると、それと同時にインターネットが良い場所にも危険な場所にもなりうるとの議論が生まれ、教育への影響も懸念された。しかし、今やインターネットはそれなしでは私たちの仕事や生活が成り立たないほど欠かせないものになっている。
今の生徒たちは将来、対話型AIが普及している社会に足を踏み入れる可能性がある。それに備えて「使い方を学ばせるべき」という見方が強まってきている。彼らは、対話型AIのリテラシーを高めることで、生徒たちが安全かつ効果的にこれらのツールを利用できるようになると指摘している。それにはまず教師が対話型AIについて知り、良い面も悪い面も理解することから始まる。
ただ、教師の作業の効率化ならともかく、生徒の学習への導入のハードルは高い。教育に対する対話型AIの影響力は電卓やWeb検索の登場を超えるほど大きく、学習に使うならAIを活用することを前提として、学習プロセスを根底から考え直さなければならない。しかし、対話型AIの可能性は認めても、今の教育の方法を変えることに抵抗を覚える先生は少なくない。
また、電卓問題に見られるように、子供たちが基礎学習を怠るようになる可能性のリスクも大きい。作文能力が高い生徒や思考能力が高い生徒なら対話型AIから新たな視点を得るなどさらにスキルを向上させられるだろうが、まだ基礎的なスキルを固めていない生徒だと結果を楽して得るだけで終わる恐れがある。
アプローチを誤ると、学習成果を達成するという目的において、対話型AIによって不公平が悪化する可能性がある。教育へのAIの浸透は避けられないという見方が強まるも、その中で慎重派と推進派、楽観派の間でかんかんがくがくの議論が続いている。