「修理する権利」法案に関して、Author Servicesという会社が米国著作権局に送った書簡が話題になっている。
書簡はデジタル・ミレニアム著作権法(DMCA)の第1201条の修正を求めている。これはデジタル著作物への不正アクセスを防止するための技術的な手段を回避することを違法としているが、「修理する権利」に関連してゲーム機、ノートPC、家電製品など一部の電子機器への適用が除外されている。
それについて、Author Servicesは「特定の資格を有するか、その機器の使用について特別な訓練を受けた者でなければ購入・使用できない機器」、「購入前に交渉・締結されたライセンス契約によって管理されるソフトウェア」は除外されるべきと主張している。そうした製品は購入前にライセンス契約が交渉され、合意した上で購入されており、安全で適切なデバイスの使用に関わる重要な制限が合意に含まれる場合があることを指摘している。
確かに、医療行為に関わるような機器なら、ユーザーの安全のために専門家に修理が任せられるべきである。そのような機器を想像しながら読むと納得できる要求である。では、Author Servicesは具体的にどのような機器のために、このような修正を求めているのだろうか?
Author Servicesは、サイエントロジー(Scientology)の創設者L・ロン・ハバード氏の著作物のライセンスを管理するChurch of Spiritual Technologyが所有する会社なのだ。それを最初に報じた404 Mediaが、サイエントロジーの「精神的苦悩の領域を見つけるのを助ける宗教上の用具」である「Eメーター」を「修理する権利」の影響から守るのが目的である可能性を指摘。
「修理する権利」でEメーターのソフトウェアが調査されることで、科学的な有効性が否定され、Eメーターと宗教活動が偽薬のように見なされるのを避けたいのではないかと推測している。EメーターにはEULA(エンドユーザー使用許諾契約書)があり、Eメーターのソフトウェアをアップデートするには国際サイエントロジスト協会の会員番号が必要だという。
-
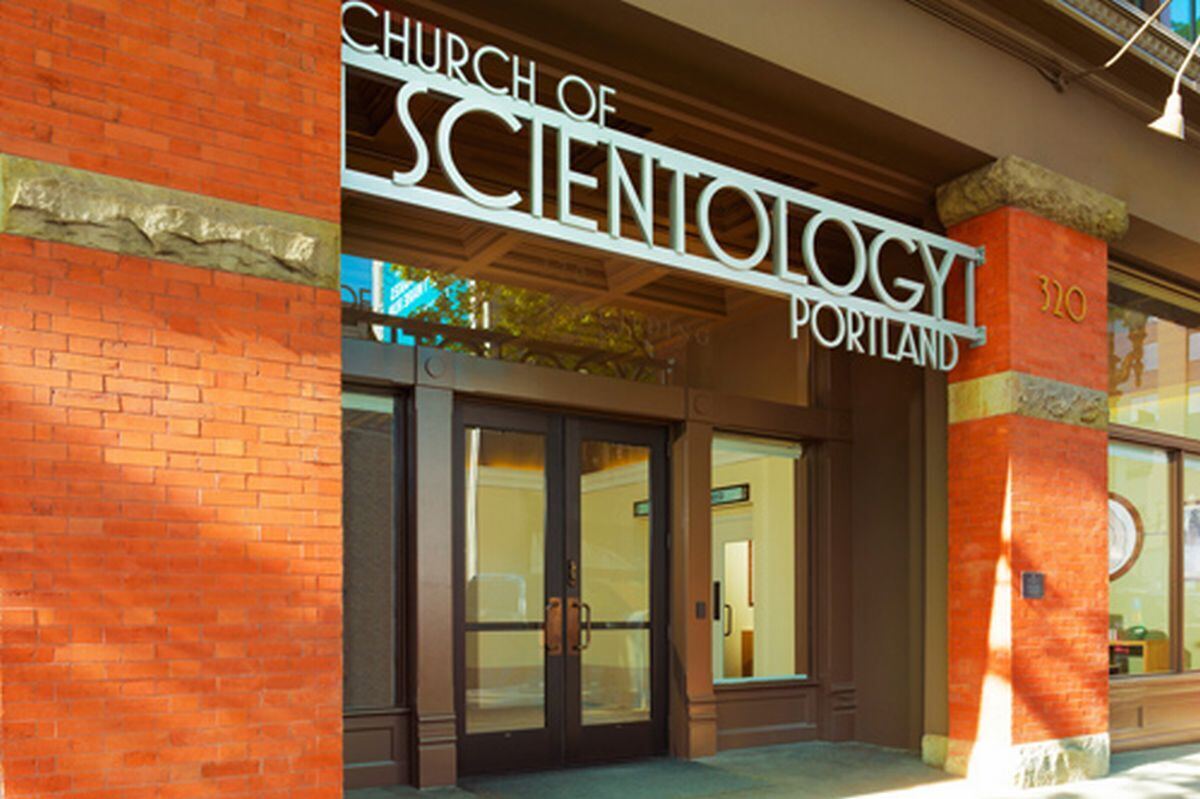
サイエントロジーが関わってきたことで「修理する権利」の議論に新たな展開。Author Servicesの提案を拡大解釈して、操作ガイドを読んだだけのユーザーを「訓練を受けたユーザー」と見なし、DMCAに基づいて修理のようなデバイスへのアクセスが制限する可能性を指摘する声も
Author Servicesの提案が認められた場合、「特定の資格や訓練を受けた人」の解釈やEULAによって本来「修理する権利」で保護されるべき電子機器がDMCAの制限の対象になる可能性がある。Eメーターの疑いはともかく、Author Servicesの提案は一理あるだけに、「修理する権利」保護の支持者は、「修理する権利」によって不都合な事実が明らかになるのを危ぶむ他のメーカーが修理権法の弱体化を狙ってAuthor Servicesの提案の支持に回る可能性を懸念している。
Appleの心変わりの真意は?
米カリフォルニア州の下院で12日に、修理する権利法案と呼ばれる「SB-244」が50対0の賛成多数で可決された。上院でもすでに38対0で可決されており、上院での最終投票を経て州知事の承認を得て成立する見通しだ。
「修理する権利」を保護する法案が成立するのはカリフォルニア州が初めてではなく、すでにコロラド州、ミネソタ州、ニューヨーク州で承認されている。しかし、カリフォルニア州には多くの大手テック企業が拠点を置き、米国で最も人口の多い州の一つでもある。同州で始まったテック関連の立法動向は全米に拡散する傾向がある。業界全体の動きを決定するような影響力を持つため、その成立が注目を集めている。
その数週間前に、「修理する権利」法案に根強く反対していたAppleが「SB-244」を支持することを公にした。これには多くの人が驚き、さらに「修理を独占する戦いでの敗北宣言」との見方も出ている。
しかし、私はそもそも「修理を独占する戦い」という見方に違和感を覚える。Appleが修理を完全な管理下に置くことを望んでいたのは事実だが、それは同社製品の優れた体験をコントロールすることを主目的としていた。消費者が簡単に修理を依頼できる環境と電子廃棄物の削減を目指しているのは、「修理する権利」保護の支持者と同様である。ただ、Appleはそれを法律ではなく、自社の取り組みでコントロールすることで実現しようとしていた。
Appleはリサイクル素材や再生可能な素材を積極的に使い、トレードイン・プログラムを充実させ、循環型経済に向けて邁進している。だが、全てのメーカーがそのような取り組みを進められるわけではない。Appleにとって「修理する権利」法案は不必要でも、業界全体で電子廃棄物を減らすためには修理権法は合理的といえる。
カリフォルニア州のSB-244は消費者がデバイスを長く使い続けられるよう、メーカーに部品や工具、ドキュメント、ソフトウェアの長期供給を義務付ける。現案では、50〜99.99ドルの製品は製造終了日から3年間、100ドル以上の製品は7年間の供給期間を求めており、違反には厳しい罰金を科す。また、修理業者が顧客に対してメーカー認定業者でないことの開示や、非純正部品を使用する場合の開示を求めている。Appleは「修理する権利」法案に関して、プライバシー保護やセキュリティが損なわれる可能性を懸念しているが、メーカーの企業秘密の保護も盛り込まれている。
今後、4州に続いて「修理する権利」法案が成立する州が増えていくだろう。しかし、全ての州の法案が同じ保護を消費者に提供しようとしているわけではない。成立することで、消費者の「修理する権利」が逆に骨抜きにされる可能性だってあるのだ。それでは、修理権法が存在する意味がない。電子機器を対象とする修理権法を設けるのであれば、それは消費者を保護する良い法律であるべきだ。
SB-244を立案したスーザン・タラマンテス・エッグマン上院議員にAppleが送った書簡で、同社はカリフォルニア州の「修理する権利」法案を良い法案と認めている。Appleが「修理する権利」法案に根強く反対していたことから、同社のSB-244支持を「敗北宣言」と見るのも分かるが、これは素直に「支持」と受け止めるべきだろう。
なぜなら、AppleがSB-244を支持したからといって、同社がカリフォルニア以外の州または他国のすべての「修理する権利」法案を支持するとは限らないからだ。数ある「修理する権利」法案の中で、カリフォルニア州のSB-244は消費者のための修理権法として評価されており、それをAppleも認めたことが重要なのだ。























