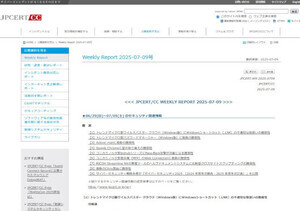子供を育てていて楽しいことの1つが、子供を通じて自分も子供時代をもう一度体験できること。自分が遊んでいたものを子供に伝えること以上に、今の子供の遊びを一緒に体験できるのが楽しい。第2の子供時代を過ごせているようで人生得した気分である。
しかも、最近は大人のための商品が子供向けの店にたくさん並んでいる。例えば、子供につきあってLEGOストアに行ったら、Beatlesのホワイトアルバムに付けられていたポートレートのLEGOが飾ってあり、つい自分のために購入してしまった。
玩具でありながら大人向け、そんな商品が増えているのは、「Kidult」(またはadultescents)と呼ばれる子供の娯楽を楽しむ大人が増えているからだ。NPD Groupのデータによると、世界の玩具市場におけるKidultの年間売上高は約90億ドル。全体の4分の1だが、"大人買い"するKidultは業界のドル成長率の60%を占めており、玩具市場の成長を牽引する勢力になっている。
Kidultは新しい言葉ではなく、1950年代から存在していたそうだが、その頃は大人になっても青少年向け番組を見ている人など限られた層を指していた。かつて大人になるというのは、特に米国において父親は、成熟して立派な社会人であることだった。
しかし、今は大人をそのようなイメージにはめ込むことが多様性に反する見方になる。今日のKidultは、玩具のコレクターなど子供向けの娯楽や文化を楽しむ層を広く指す。20年前や30年前に比べて大人が自由にファンダムを表現するようになり、独特の知性や感性をアピールしている。かつての日陰なイメージはなく、そうした大人の定義の広がりがKidultの拡大につながっている。
また、今の30〜40代はそれより上の世代に比べて子供時代に触れたコンテンツに深い思い入れを持っている。70年代から80年代にかけて、玩具業界は新しい玩具を生み出す業界から、エンターテインメント・フランチャイズに基づいた商品を展開する業界へと変化し始めた。それ以前にも映画やテレビ番組のキャラクターを用いた玩具はあったが、ファンに強いアイデンティティと所有感を与えるクロス・マーケティングが加速。1977年に「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」が公開され、子供達が様々な種類のライセンス商品を目にするようになり、キャラクターに特別な感情を持つようになった。その頃の子供達が今、30〜50代になっても愛着を持ち続けている。
つまり、今のKidult市場の拡大は一時的なブームではない。Kidult需要はこれからもあり続け、全年代に広がるまで拡大が続くだろう。そうした層のニーズを狙って玩具や子供向けのコンテンツに関わる企業は、子供向けではなく、Kidultをターゲットにノスタルジーを刺激する商品やコンテンツを提供し始めている。
例えば、来年公開予定の映画「バービー」だ。これは人形バービーの世界を実写映画化した作品で、バービーの映画だけど、今日のMarvelやDCの映画がそうであるように、明らかにKidultを意識している。Disneyのサブスクリプション型ストリーミングサービス「Disney+」が急速に契約者を増やせたのも、子ども向けに偏らず、「マンダロリアン」のようなKidultの興味をひくコンテンツを揃えたのが要因と見られている。Disney+は契約者の半数を子供のいない大人が占めている。
Basic Funは、オリジナルが1967年に発売されたレトロ玩具「Lite-Brite」の「ストレンジャー・シングス 未知の世界」バージョンを発売した。また、子供向けキックボード大手のRazorが20年前のクラシックスタイルのキックボードを電動化した「Razor Icon Electric Scooter」(最大時速18マイル)を大人向けに投入するなど、今のトレンドや技術にノスタルジーをとけ込ませた商品が多数登場している。
Samsungが広く展開し始めた「Galaxy Z Flip4 5G」「Galaxy Buds2 Pro」用のポケモン・テーマのアクセサリもKidult向けといえる。Nothingが狙っているかどうかは分からないが、スケルトンのゲームボーイが特別なデザインだった世代の私には、Nothingのスマートフォン「Phone (1)」にもノスタルジーを覚えてしまう。
言うまでもなく、世界のKidult市場の拡大は日本にとって大きなチャンスである。日本は世界中の人が愛着を持っている作品やキャラクターを長年にわたって提供してきており、国内のKidult市場は成熟している。これを世界のKidult市場に展開しない理由はない。「クールジャパンはうまくいっていないじゃないか」と言うかもしれないが、あれは外国人観光客を狙った土産物屋のようなアプローチでしかなく、土産物屋に商品を並べて伝わる文化は限られる。ゲームやアニメなどを通じて、海外の人が海外において日本のキャラクターに触れて育ってきた。そのノスタルジーを世界中で呼び起こせることが、今の日本の大きな資産になっている。特別なことをする必要はない。日本のKidult市場へのアプローチと同じように、大人になったファンダムのニーズに応えれば良いのだ。