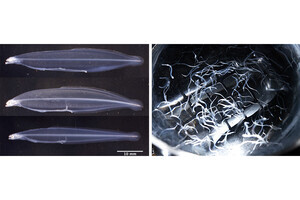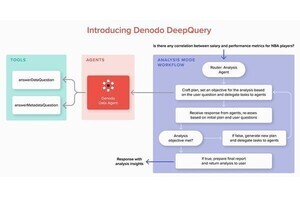前回は、コリンズ・エアロスペースが掲げる “connected battlespace” というビジョンについて取り上げた。今回はもう少し具体的な話に近付けてみる。それが、ロッキード・マーティンのDIAMONDShield。→連載「軍事とIT」のこれまでの回はこちらを参照。
-

DIAMONDShieldが持ち込まれた演習 “Variant Shield 2022” は、米四軍が参加して実施した大規模な統合演習。すると当然、異なる戦闘領域の統合が必要になる 写真:US Navy
マルチドメインの戦闘指揮
DIAMONDShieldには、“Multi-Domain Battlespace Management” というフレーズが付いている。日本語に訳すと「複数の戦闘空間をカバーする戦闘指揮」ぐらいの意味になろうか。
重要なのは、「陸だけ」「海だけ」「空だけ」ではなく、複数の戦闘空間にまたがる一元的な状況認識を実現すること。次に、その情報に基づいてどのような行動を起こすかという意思決定を、迅速に実現する。また、実際に作戦行動を発起した後で思い通りに物事が進まなかった場合には、迅速に打ち手を変えられるようにする。
その土台となるのは、以前に取り上げたJADC2と同じで、「複数の戦闘空間をカバーする、一元的なネットワーク化と状況認識」となる。ただしDIAMONDShieldは、既存の陸・海・空の指揮システムを御破算にして取って代わろうというものではない、というのがロッキード・マーティンの説明であった。
つまり、すでに陸・海・空の指揮システムが個別に稼働しているのであれば、それらから情報を得る形でDIAMONDShieldに取り込み、一元的な状況認識を実現するとの考え方。既存の資産が無駄にならず、かつ、従来はできていなかった一元的な状況認識が可能になるわけだ。
そこから先の話も、JADC2の文脈に沿っている。DIAMONDShieldの触れ込みはこうだ。
“Millions of data points, compiled and analyzed by artificial intelligence to deliver automated, all-domain battle management solutions for faster decision making.”
日本語にすると、こんな感じだろうか。「数百万ものデータ・ポイントから集めたデータを、人工知能(AI : Artificial Intelligence)を駆使して分析することで、自動化された、すべての戦闘空間をカバーする指揮統制ソリューションを実現、迅速な意思決定を実現する」
作戦は、思った通りに運ばない
ところが、誰がいったか「戦場で唯一確実なのは、物事は計画通りに運ばないということ」である。だいたい、敵軍がこちらの思惑通りに動いてくれると思って虫のよい作戦を立てて、それをそのまま実行すると、ロクなことにならない。
すると、作戦の進行状況を常にモニタリングして、その状況に応じて打ち手を変えていかなければならない。だからDIAMONDShieldには、「情報の収集」「作戦計画の立案」に加えて「作戦の実施とモニタリング」という仕掛けがある。
最初に立案した作戦を発起した後で、進行状況をリアルタイムでモニターして、もしも思惑通りに進まなかったら直ちに打ち手を変えて対応する、という話になろうか。
そして、「従来のやり方では、任務に関する指令(Tasking Order)を発出するまでに72時間以上かかっていたものが、DIAMONDShieldでは数時間、あるいは数分にまで短縮される」とうたう。状況の変化に応じて打ち手を変えるには、それぐらいのスピードアップが求められる。
つまり、DIAMONDShieldは「STRATEGIZE(計画立案) - TARGET(目標の明確化) - PLAN(計画の立案) - TASK(任務の割り当て) - EXECUTE(任務の実施) - MONITOR(任務進行状況の把握) - ASSESS(それらの評価)」というサイクルを回す過程で、一連のプロセス全体を支援するシステム、といえよう。最終的に意思決定するのはもちろん人間だが、より良い意思決定、より迅速な意思決定を実現するために、DIAMONDShieldが支援する形だ。
ところで。2019年に作られたDIAMONDShieldのブローシャを見ると、当初は「統合防空・ミサイル防衛の指揮統制」を企図して開発が始まったようである。しかし現在では、統合防空・ミサイル防衛に限定せず、すべての戦闘空間にまたがる指揮統制を実現するシステムとなっている。あれ、どこかで似たような話を聞いたことが…
すでにグアムで実験を行ったこともある
2022年にグアムで実施した演習 “Variant Shield 2022” において、DIAMONDShieldが提供する「AIによる計画立案・勧告の機能」を用いて、統合化・マルチドメイン化した打撃作戦の実験が行われた。このときには、仮想化環境の上で走らせるイージス武器システム(VAWS : Virtual Aegis Weapon System)と組み合わせた。
まず、DIAMONDShieldがデータを取り込み、処理して、指揮官に対して意思決定のための材料、すなわち「陸・海・空のどんな資産を使って脅威に対処すべきかという勧告」を提示する。過去の戦闘経験に関する学習を積ませたAIがあれば、それは実現できそうである。
そして「これこれこのように対応する」という方針が決まったら、それを実行する手段として、この演習ではVAWSを用いた。何に対して何を使って交戦するかは、配下にある資産の陣容や位置関係に依存するから、必ずVAWSを使うと決まっているわけではない。あくまで一例である。
ちなみにVAWSは、イージス武器システムの頭脳にあたる部分を取り出して、仮想化環境の上で走らせるもの。これがあれば、イージス艦がいなくても、イージス艦が持つ脅威評価や武器割当といった機能を利用できる。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。