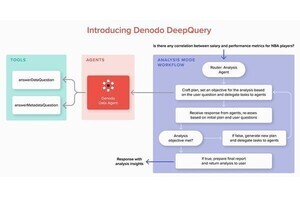米空軍は2022年4月26日に、E-3セントリーAWACS(Airborne Warning And Control System)の後継として、ボーイング製E-7の採用を決定したと発表した。「後継機は前任よりも高性能」という常識に照らして考えると、奇異に感じられる選択であるかもしれない。
ボーイングのE-7とは
E-7は、ボーイング737のエアフレームに、ノースロップ・グラマン製のMESA(Multi-role Electronically Scanned Array)レーダーを搭載した機体。すでにオーストラリア、トルコ、韓国で導入実績があり、イギリスも採用を決めて発注済み。
-

オーストラリア空軍のE-7。同国では開発プログラムの名称から、「ウェッジテイル Wedgetail」とも呼ばれるが、後に同機の採用を決めたイギリス空軍も、制式名称を「ウェッジテイルAEW.1」にしてしまった 撮影:井上孝司
日本でも、E-7はE-2Dアドバンスト・ホークアイと並んで導入候補に名前が挙がったことがあるが、その際に「米軍で制式採用していないから」という批判的な見解があったと記憶する。ところが、その後になって米空軍がE-7の採用を決めてしまったから、なにやらハシゴを外されたと感じる向きもあるかもしれない。
それはともかく。「AWACS機やAEW&C(Airborne Early Warning & Control)機の能力は、レーダーの探知・追尾能力に加えて、指揮管制能力で決まる」というのが基本的な考え方。その観点からすると、E-3からE-7への移行は、見かけ上はスペックダウンに見える。
しかし、「不正規戦・対反乱戦から、正規軍同士がぶつかり合う戦争形態への回帰」を進めている米軍が、航空戦のコーナーストーンであるAWACS機の更新に際して、スペック・ダウンを甘受するものであろうか? そんなことはあるまい。
筆者は拙著『戦うコンピュータ』の最初のバージョンで、AWACS機やAEW&C機について「将来は、レーダーだけ無人機に載せて、指揮管制の機能は地上で持つことになるんじゃないか?」という趣旨のことを書いた。さすがにこれは(飛行機の話だけに)飛ばしすぎだったようで、E-7は有人機である。しかし、このとき書いたことの何割かは、どうやら現実になりそうである。
キーワードはABMS
そこで出てくるキーワードが、ABMS(Advanced Battle Management System)。
ABMSの基本的な考え方は、「配下にある資産を一元的にネットワークでつないで、センサー・ノードから上がってきたデータを融合するとともに、最適な資産に対して交戦の指令を飛ばす」というもの。それを、AWACS機やAEW&C機みたいな、空中にある特定のプラットフォームに集約するのではなく、”頭脳” にあたる機能は地上側に置く。
すでにABMSの実証試験は始まっており、2019年12月に実施した実証試験では、本土防衛のシナリオを設定した。巡航ミサイルに見立てたQF-16標的機を飛ばして、メキシコ湾に配置したイージス駆逐艦「トーマス・ハドナー」(DDG-116)や、F-22A、F-35Aといった戦闘機、陸軍の防空部隊などが迎え撃つという内容。
また、2022年3月には、ジョージア州のワーナー・ロビンスにABMS施設を建設する契約が発注されている。
理屈の上では、信頼性と秘匿性が高く、十分な伝送能力を備えたネットワークがあれば、センサー・ノードからのデータ収集はできる。そのデータの収集による一元的な共通作戦図(COP : Common Operational Picture)の生成は、コンピュータの処理能力と、そこで動作するソフトウェアの問題。
そうなると、「優れたセンサー能力と優れた情報処理能力をひとまとめにした、AWACS機みたいなプラットフォーム」は、必須とはいえなくなってくる。ABMSの下では、ネットワークで結ばれたセンサー・ノードやデータ処理・指揮管制機能の集合体として何ができるか、が問題になるからだ。
そこで、センサー・ノードやデータ処理・指揮管制機能をひとつところに集約せずに分散化することで、抗堪性が高いシステムになる。一部がやられてしまっても、残った部分で(レベルの低下は起きるかも知れないが)機能を維持することができる。
狙われやすい資産はもう使えない
実のところ、AWACS機やAEW&C機は航空戦におけるコーナーストーンだけに、敵軍からは真っ先に狙われる。もう40年ぐらい前に出たトム・クランシーの小説『Red Storm Rising』(邦題『レッド・ストーム作戦発動』)では、NATO軍は開戦劈頭にソ連軍のAWACS機をステルス戦闘機で撃墜した。その後に出た『The Bear and the Dragon』(邦題『大戦勃発』)では逆に、米空軍のE-3が中国空軍に狙われた。
そして現実に、ロシアでは「AWACSキラー」との別名を奉られた、Novator KS-172という長射程の空対空ミサイルが開発された。全長6m以上あるデカブツで、射程距離は400kmぐらいあるとされる。AWACS機はレーダーを作動させなければ仕事にならないから、そのレーダーにホーミングすれば誘導可能との理屈。
高性能の大型レーダーと多数のコンピュータ、管制要員、通信機を積み込めば、機体が大型かつ高価になるのは避けられない。しかもそれは、狙われやすくなり、狙われたときには生残性が低くなることを意味する。そこで発想を転換して、センサー機能も指揮管制機能も分散化する。その土台となるのがABMSであり、実現に向けた第一歩がE-3からE-7への機種更新という話ではないか。
著者プロフィール
井上孝司
鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。
マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。