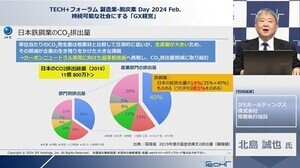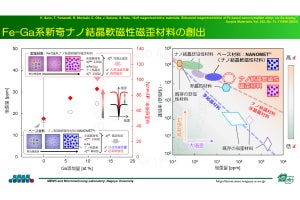京都大学(京大)と科学技術振興機構(JST)は6月17日、涙液糖駆動(涙液に含まれる糖分からのエネルギーで動作すること)が可能な0.9pWの消費電力、0.1Vの電源電圧で動作する環境適応型電源・デジタル変換半導体集積回路の開発に成功し、22nm CMOSプロセスで実証したことを共同で発表した。
同成果は、京大 情報学研究科の新津葵一教授、同・劉昆洋助教、同・張瑞琳特定助教、同・北池弘明大学院生、同・田川宏紀大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、ハワイ・ホノルルで6月16日から開催中のIEEE主催の超大規模集積回路に関する国際シンポジウム「2024 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits」の技術論文の要約集「Digest of Technical Papers」に掲載された。
トリリオンセンサとも言われるIoTの普及・促進には電源の確保が重要であり、内部バッテリーの搭載や、外部電源とのケーブル接続が不要な、振動や廃熱などを利用したセンサそのものによる環境発電の研究が進んでいる。しかし、そうした環境発電は、一般的に出力が環境状況に依存してしまうため、電源が不安定になってしまうという課題を抱えている。
そうした中で設立されたのが、電源が不安定な場合においてもIoTの各種センサが安定して動作するようなシステムの開発プロジェクト。同プロジェクトでは、コンセプトとして、生命体のようなIoTを実現することを目標として研究開発が行われているという。カエルのように食料の増減に応じて自身の動きを最適化し、自然環境に溶け込むIoTを実現し、社会へと貢献することが最終目標とする。
今回の研究では、環境に適応性を持たせるため、電源確保対象とセンシングデータ取得対象が同一のシステム(発電とセンシングを一体化して行うシステム)において、入力信号となる入力電源電圧の高低に応じて、動作する要素回路ブロックを自律的に最適化する半導体集積回路技術が開発された。
具体的には、異なるしきい値の電源電圧を有する複数の信号駆動回路(バッファ)を搭載し、クロック信号が与えられた際に動いたバッファ回路の数を数えることで、デジタル化をする手法が提案された。低入力電源電圧の際には少ない数のバッファが動作する仕組みのため、消費電力を低減させることが可能となったという。
今回開発されたシステムが、入力電源電圧をエサの量、クロック信号をメトロノームから発せられる指揮信号、異なるしきい値の電源電圧を有する複数のバッファを大・中・小のカエルに例えると、次のようになるとする。入手可能なエサの量が変化する環境下において、必要なエサの量の異なるカエルに合唱をさせると、エサの量に応じて声を出すカエルの頭数が変化する。この頭数を数えることで、必要なエサの量を量ることが可能となる。十分なエサが得られないカエルは声を発することができないため、合唱隊としての全体の消費エネルギーを下げることが可能になるとする。
-

今回の研究開発のイメージ(提案された回路の動作をカエルの合唱に例えて表現)。歌声を発するのに必要なエサの量が異なるカエルたちを複数設け(動作しきい値電源電圧の異なるバッファを複数設け)、環境中に存在するエサの量(環境中で得られる電源電圧)に応じて、指揮を受けた時に歌声を発するカエルの数(クロックを与えられた時に動作する回路の数)が変化することを活用してデジタル変換が行われる。この技術を、涙液糖濃度に応じて出力が変化する涙液糖発電素子と組み合わせることで、涙液糖と相関のある血糖推定に活用できるという(出所:共同プレスリリースPDF)
低リーク電流を可能とした22nm CMOSプロセスで設計・試作した半導体集積回路に今回のコンセプトを実装し、異なるしきい値の電源電圧を有する複数のバッファを、トランジスタのサイズや縦積み段数を調整することで実現し、その有効性確認を実施したところ、消費電力0.9pW(同精度に換算した場合、従来技術の1/27程度)、電源電圧0.1V(従来技術に比べて44%低減)が達成されたという。これにより、涙液糖駆動の単独動作が可能な、血糖濃度と涙液糖濃度の相関を活用して、涙液糖濃度から血糖濃度を推定し、持続的にモニターするコンタクトレンズ「持続血糖モニタリングスマートコンタクトレンズ」の開発が進展したとする。
なお、今回の研究開発のコンセプトは、「電源電圧に応じて自律的に動作を最適化する」という汎用的な半導体集積回路設計に関わるものだと研究チームでは説明しており、今後の半導体集積回路の低消費電力化技術の発展へと波及することが期待されるとしている。
また、今後については、低電力化設計基盤技術として、さまざまな集積回路において適用することを目指すと共に、応用開拓を進めていくことを考えているとしており、その応用開拓として、持続血糖モニタリングスマートコンタクトレンズのほか、デジタル錠剤、スマートステントといった体内環境で動作するIoTシステムの開発に取り組んでいくとしている。