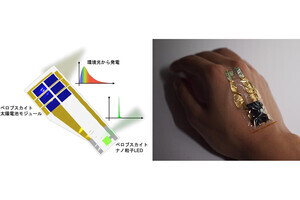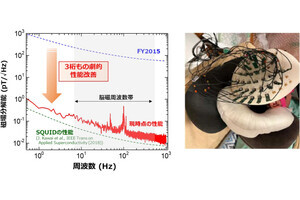理化学研究所(理研)は2月2日、超薄型有機太陽電池の耐水性を改善し、水中でも駆動可能な素子の開発に成功したことを発表した。
同成果は、理研 創発物性科学研究センター 創発ソフトシステム研究チームの福田憲二郎専任研究員、同・染谷隆夫チームリーダーらの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。
環境からエネルギーを得る「エナジーハーベスト(環境発電)」技術の中でも、ミリワット(mW)級の高い電力を供給でき、かつ柔軟性にも優れた有機太陽電池は、ウェアラブルセンサ用電源の有力候補として期待されている。ただしその実用化には、雨天時の外出、結露、手洗い、洗濯などに対する耐水性が必須だ。しかし、超薄型有機太陽電池の柔軟性を保持したまま完全に防水できる封止膜技術はまだなく、有機太陽電池の構造を根本的に改善する必要があったという。
従来の有機太陽電池には、陽極と発電層の間に、発電層から陽極へ効率的に正孔を輸送するための正孔輸送層が設けられているが、こここそが水に弱い部分だった。そこで研究チームは今回、陽極を構成する銀を酸化させると通常の銀よりも仕事関数が増加することに着目し、陽極/発電層界面において銀を酸化させ、陽極と発電層との界面に酸化銀を備える構成とすることで、発電層から陽極に正孔を効率的に輸送できる“正孔輸送層フリー”の有機太陽電池を作製したとする。
-
(左)従来の有機太陽電池の断面模式図。従来構造では、陽極となる銀と発電層の間に正孔輸送層を成膜していた。(右)今回作製された有機太陽電池の断面模式図。陽極となる銀を成膜した後、大気中加熱処理により銀電極と発電層との界面にその場成長させた酸化銀を含む構成。水に弱い正孔輸送層を使用しないため、高いエネルギー変換効率を持ちながら耐水性の向上が実現した(出所:理研Webサイト)
しかしその開発にあたり、発電層に陽極となる銀を直接積層して、発電層と陽極との間に正孔輸送層を含まない有機太陽電池は、発電層の正孔がうまく陽極に抽出されないため、発電効率が著しく低いことが課題となる。今回の研究では、この有機太陽電池を大気中で24時間加熱処理することで、陽極と発電層との界面において銀を酸化させたとのこと。その結果、陽極と発電層との間の酸化銀が正孔輸送層の役割を果たして効率的に正孔を抽出するため、有機太陽電池のエネルギー変換効率が格段に向上したことが確認されたという。
作製された超薄型有機太陽電池に疑似太陽光(出力100mW/cm2)を照射すると、短絡電流密度は15.8mA/cm2から26.5mA/cm2に、開放電圧は0.05Vから0.77Vに、フィルファクターは27%から71%にそれぞれ改善され、エネルギー変換効率は0.2%から14.3%へと改善されたとする。なお今回の陽極/発電層界面において銀を酸化させる技術は、研究チームが超薄型太陽電池の耐熱性を向上させるために長年培ってきた技術があってこそだとしている。
-
正孔輸送層のない有機太陽電池の大気中加熱処理による電流密度変化。図は有機太陽電池の電流電圧特性。電圧0V時の電流密度を短絡電流密度と、電流値が0になる電圧値の開放電圧のそれぞれ絶対値が、大きいほど有機太陽電池の性能は良い。大気中で有機太陽電池を24時間加熱処理すると、加熱処理前後でエネルギー変換効率は0.2%から14.3%に向上(出所:理研Webサイト)
次に、陽極を構成する銀、発電層および陽極と発電層の界面中に含まれている酸素元素の強度が評価された。すると、加熱処理が行われた有機太陽電池は、陽極と発電層の界面付近で酸素シグナル強度が著しく上昇していることが判明。新たに生成された酸化銀は通常の銀に比べて仕事関数が大きく、発電層からの正孔の輸送に効果的に寄与することが明らかにされた。
続いて、酸化モリブデンと銀を備えた従来の有機太陽電池と、今回の酸化銀と銀を備えた有機太陽電池に対し、大気中で陽極と発電層との引っ張り剥離試験を実施。その結果、酸化モリブデンの有機太陽電池では酸化モリブデン/発電層界面の接着力が最も小さく0.7MPaだったのに対し、酸化銀の有機太陽電池では酸化銀/発電層界面の接着力が1.5MPaと倍以上に強化されていることがわかった。
なお、通常の正孔輸送層材料である酸化モリブデンの有機太陽電池は接着力が弱いため、水中に浸漬させることで酸化モリブデンと発電層とが容易に剥離してしまう一方で、酸化銀の有機太陽電池は水中に浸漬させても酸化銀と発電層との剥離がまったく観察されなかったといい、酸化銀を用いた有機太陽電池は、耐水性が圧倒的に改善されていることが確認されたとしている。
-
酸化モリブデン/発電層界面と酸化銀/発電層界面の接着力評価結果。(左)従来の酸化モリブデン/銀(MoOx/Ag)と、今回の酸化銀/銀(AgOx/Ag)を使用した初期サンプルのフォースストロークカーブ。MoOx/AgよりもAgOx/Agの方が剥離するのに大きな力が必要になっていることが分かる。(右)発電層上のMoOx/Ag電極とAgOx/Ag電極の発電層との接着力の比較。接着力のプロットのエラーバーは標準偏差を示されている(サンプル数:3)(出所:理研Webサイト)
今回作製された厚さ3μmの超薄型有機太陽電池は、水に4時間浸漬した後もエネルギー変換効率の保持率は89%、水中で30%の圧縮歪みと復元を繰り返す機械的な変形を300回加えた後も、エネルギー変換効率の保持率は96%だったという。さらに、この超薄型有機太陽電池は水中での60分以上の連続駆動を達成。これらの水中での試験結果から、今回の超薄型有機太陽電池の安定性が、従来の有機太陽電池と比較して飛躍的に向上していることが示されたとした。
-
超薄型有機太陽電池の水中浸漬後の特性変化。(左)超薄型有機太陽電池の水中浸漬の様子。(右)水中浸漬時間とエネルギー変換効率の保持率の関係。従来のMoOx/Agを用いた素子では60分後にエネルギー変換効率の保持率が20%以下と大幅に減少している。一方、AgOx/Agを用いた素子では240分後でもエネルギー変換効率の保持率は89%と高い(出所:理研Webサイト)
-
(左)超薄型有機太陽電池の水中で圧縮歪みと、復元を繰り返す機械的な変形を繰り返し加える試験の様子。(右)水中での圧縮歪み回数に対するエネルギー変換効率の保持率の変化。従来のMoOx/Agを用いた素子では、100回の歪みサイクル後に素子が完全に破壊されている。一方、AgOx/Agを用いた素子では、300回の歪みサイクル後でも96%以上の高いエネルギー変換効率が保持されている(出所:理研Webサイト)
研究チームは今後、高いエネルギー変換効率と耐水性を両立する発電層材料の開発が進み、今回の技術と組み合わせることにより、さらに耐水性が改善された高効率の超薄型有機太陽電池が実現可能となるとする。
また今回作製された耐水性と柔軟性を備えた超薄型有機太陽電池は、衣服に貼り付けることができる環境エネルギー電源として、ウェアラブルデバイスやe-テキスタイルに向けた長期安定電源応用の未来に大きく貢献することが期待できるとしている。