中古住宅にも、新築住宅の購入同様に不動産取得税という税金がかかります。でも新生活に向けてなるべく出費は控えたいのが本音ではないでしょうか。
不動産取得税というものは、いったいどういう時に課税されるのか、どのタイミングで支払い、税の控除は受けられるのでしょうか。事前に手続きのタイミングや方法を知っておくことで、税金への出費を抑えることが可能になります。
この記事では、具体的に不動産取得税とは何か、中古住宅を購入した際の不動産取得税の支払い方法や心得ておくべき減税対策について徹底解説するとともに、不動産所得税でよくある疑問点について触れていきます。
税金にたいして不安なく家の購入ができるよう、この記事で情報収集して節税対策を行っていきましょう。
不動産取得税とは

住宅を購入すると、数々の税金が掛かることはご存じでしょうか。その中でも代表的な税金が「不動産取得税」です。
では不動産取得税とはどのような税金が掛かるのか、どのタイミングで支払う必要があるかについて、ここでは解説していきます。
不動産購入時に支払う税金
この不動産取得税は、都道府県が以下の条件に対して課税する税金のことを指します。
- 売買で不動産を取得
- 贈与で不動産を取得
- 新築住宅を建てた、購入した
- 増築した
- 不動産の交換を行った
この不動産取得税は、基本的に上記の条件に対して4%の税が課せられます。しかし期間を2024年3月31日までに限定して土地及び住宅は3%、住宅以外の家屋は4%になっています。
税率に関しては条例により各市区町村で定めることが出来るため、住居を取得する場所によって税率が異なることがあります。その際は自治体のHPなどで確認できるため、あらかじめ見ておきましょう。
また、その税率は固定資産税評価額に対して課税されますが、この固定資産税評価額とは、固定資産税などの税金に対して基準となる評価額のことです。用途として固定資産税の基準だけでなく、不動産取得税、都市計画税、登録免許税を算出する際にも使用します。この固定資産税評価額は、相場を知りたいときの参考にもなるので、購入の際に活用してください。
購入価格と固定資産税評価額の違い
固定資産税評価額は購入価格そのものではありません。購入価格に税率が課税されるわけではなく、公示価格7割の水準になるように調整されているなど、公正な基準で設定されています。
また、永遠にその評価価格で固定されるわけではなく、各市区町村(東京都23区の場合は都)が3年に1度見直す形で算定しています。
中古住宅の不動産取得税の支払い方法
この不動産取得税に関しては、中古住宅を取得後からおおよそ3ヶ月から6ヶ月で納税通知書が届く仕組みになっています。この通知書は明確に送付時期が定められているわけではありません。自治体によって送付の遅い早いが異なり、中には1年経過するケースもあります。
自治体によって送付のタイミングが異なるのは、都道府県が税額を計算し納税者へ通知する方式を取っているためです。税額計算のために事前調査が必要な事で、その分時間を要することになります。
この納税通知書が手元に届き次第、支払期限を確認して早急に納税の手続きを行いましょう。短い期限を定めているケースが多く、おおよそ1ヶ月以内の支払いを求められますので注意しましょう。
この記事では中古住宅の不動産取得税について説明しますが、下記で新築住宅の不動産取得税について詳しく説明していますのでご覧になって下さい。

中古住宅の不動産取得税を軽減する方法

住宅購入はそう何度もあるライフイベントではなく、ただでさえ慣れていないことのうえに大金が動きます。かかるコストはできるだけ節約して、新生活に向けてその分の費用を回したいと思うのが当然でしょう。今回紹介する中古住宅における不動産取得税も、土地と建物の部分で控除が受けられ、節税効果が期待できます。
ここでは、中古住宅の建物と土地に分けて控除内容と適用条件、その手続きについてを徹底解説します。
建物部分の取得税控除の計算方法
中古住宅に対する不動産取得税の軽減措置は、新築住宅と同様の仕組みです。条件を満たすことで建物部分を固定資産税法価額から控除額を引いた分に対して税率を課す仕組みになっています。
不動産取得税に対して控除する際の計算式は以下の通りです。
固定資産税評価額に対して控除額が引かれますが、この控除額は建築した時期ごとで控除の金額が異なります。建築時期別で控除額と計算後の実質軽減額を表にしましたので、参考に下記を一覧ください。
| 新築年月日 | 控除額 | 軽減税額の相当額
(※税率3%の場合) |
| 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 | 30,000円 |
| 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 | 45,000円 |
| 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 | 69,000円 |
| 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 | 105,000円 |
| 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 | 126,000円 |
| 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 | 135,000円 |
| 平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 | 300,000円 |
| 平成9年4月1日以降 | 1,200万円 | 360,000円 |
上記の表から読み取れるように、最大36万円の節税が可能になります。
参考文献:住建ハウジング「不動産取得税の軽減措置」
建物部分の不動産取得税を減額させる条件
ではこの建物部分の不動産取得税で、どのような条件を満たせば税の控除が受けられるのでしょうか。控除を受ける際の条件は以下の通りです。
- 住宅を取得した方が、その建物に居住している事
- 取得した建築物の床面積が50平米以上、240平米以下であること(※敷地内の物置小屋や車庫及びマンションの共用部分を含む床面積)
- 昭和57年1月1日以後に新築された建物
- 上記の建築期間に該当していない場合は、住宅取得日前2年以内に有資格者が耐震診断によって、新耐震基準の適合を証明した建物であること
上記の条件から、中古住宅に買主がマイホームとして住んでおり、ごく一般的な家庭用の延床面積で新耐震基準を満たした建物であれば控除を利用できることが分かります。
土地部分は固定資産評価額が減額される
土地部分の固定資産税評価額に対する控除の仕方は、建物部分の控除の仕方は異なる計算法になっています。土地部分に関しての控除の計算方法については以下の計算意識になります。
この計算式に用いられる1/2に関しては、令和6年3月31日までに取得した土地部分に関して、固定資産税評価額の2分の1の額になります。不動産取得税はその額に対して税率が課され、控除額を引く仕組みになります。
控除額は以下の2パターンの内、高い金額が適用されます。
- 控除額:45,000円(計算した税額が45,000円未満の場合はその金額が控除額になる)
- 以下の計算式で算出される金額
※令和6年3月31日までに取得したときは、価格を2分の1にした後の額から1平方メートル当たりの価格を計算します。
不動産取得税の計算式に、上記のいずれかの控除額を引いた金額が不動産所得税になります。
土地部分の不動産取得税を減額させる条件
土地部分の控除を適用する条件は、建物部分とは異なり以下の2点になります。
- 土地と建物の所有者が同じであること
- 取得した中古住宅が前述した軽減の要件に該当しており、なおかつ土地の取得が住宅取得の前後1年以内であること
上記の条件から読み取れるように、不動産所得税の控除の対象になる中古住宅を土地部分と一緒に購入することで、土地部分も条件に該当することになります。
不動産取得税を減額させる手続き
不動産所得税の減税を受けるためには、期限内に必要書類を用意して提出する必要があります。申請先や期限、必要書類について表にまとめましたので参考に一覧ください。
| 申請先 | 住居の管轄する税事務所へ窓口か郵送にて提出 |
| 申請期限 | 中古住宅の取得から60日以内に申請が必要 |
| 必要書類 |
|
上記の表のように、提出期限が重要ポイントになります。新生活が始まれば慌ただしくなることから、申請のことを忘れがちになってしまいます。引越し後は早々に手続きすることを忘れないためにも、あらかじめ準備するよう心掛けておきましょう。
中古住宅の不動産取得税の計算例
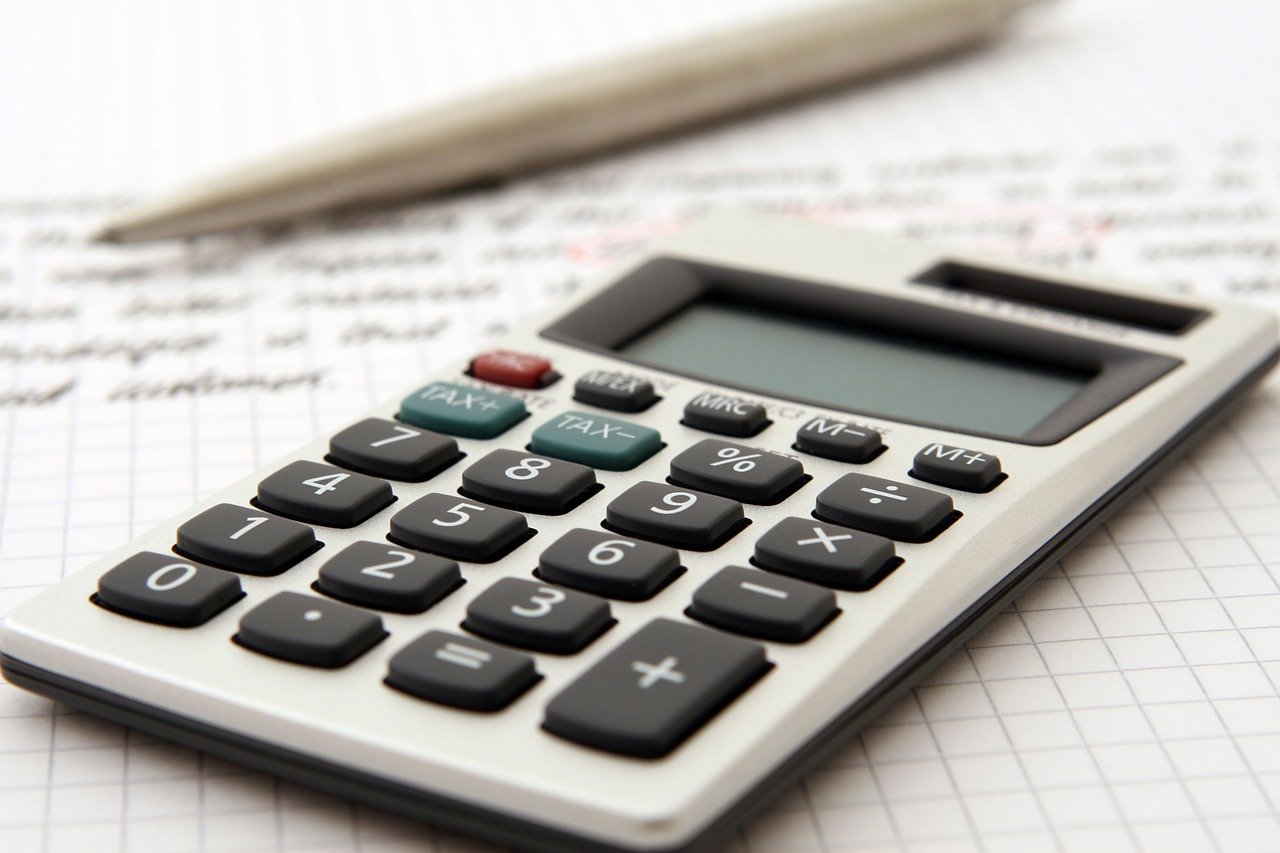
ここまで減額方法にて計算式や提出方法について解説してきましたが、ここからは実際の具体例を交えてパターン別に紹介していきます。
建物と土地で減額できた場合
以下の中古住宅の建物部分と土地部分の状態を、前述で解説した表と式を用いて計算していきます。
新築時期が平成9年5月1のマイホームで、家屋に1,000万円の固定資産税評価額、土地2,000万円(100平米)の固定資産税評価額の物件、価格3,000万円の中古住宅とします。不動産取得税の税率は土地及び住宅は3%(2024年[令和6年]3月31日まで)となっています。
| 不動産取得税が軽減できた場合 | 不動産取得税が軽減できなかった場合 |
| 建物部分は(1,000万円-1,200万円)x3%=0円 | 建物部分1,000万円x4%=40万円 |
| 土地部分は2,000万円x1/2×3%-30万円=0万円 | 土地部分2,000万円x1/2×4%-30万円=10万円 |
不動産投資目的で中古住宅を購入した場合
不動産投資目的で中古住宅を購入する場合は、申請者自身がマイホームとして住む前提ではなくなることから、控除の対象になりません。そのため、計算式で控除額部分をなくした状態での計算になります。
上記の内容と同じ条件で計算してみましょう。新築時期が平成9年5月1のマイホームで、家屋に1,000万円の固定資産税評価額、土地2,000万円(100平米)の固定資産税評価額の物件、価格3,000万円の中古住宅とします。不動産取得税の税率は土地及び住宅は3%(2024年[令和6年]3月31日まで)となっています。
建物部分と土地部分の計算式にそれぞれ当てはめてみます。
| 不動産取得税が軽減できた場合 | 不動産取得税が軽減できなかった場合 |
| 建物部分(1,000万円-1,200万円)x3%=0円 | 建物部分建物部分1,000万円x3%=30万円 |
| 土地部分2,000万円x1/2×3%-30万円=0万円 | 土地部分土地部分2,000万円x1/2×3%=30万円 |
住み替えの場合の不動産取得税の減税例

住み替えた場合にも、ある条件下で不動産所得税が減税されるケースが有ります。今回は住み替えで減税が適用される2つのケースを紹介します。
公共事業で家を収用された場合
公共事業を行うために、その土地や建物を収用され、その代替えとして不動産を取得した場合にも、不動産取得税が下記のような条件付きで減税されます。
その際の軽減の要件や計算式、申請方法については以下の通りです。
適用条件
減税が適用される場合、以下のいずれかの条件が満たされている必要があります。
1. 不動産の取得方法が以下のどちらかを満たす
- 公共事業として利用するために、公共事業を行う人に土地や建物を譲渡した方
- 公共事業として利用するために、公共事業を行う人に譲渡をした土地の上に、建築されていた建物について移転補償金を受けた方
2. 被収用不動産等の譲渡日(移転補償契約を締結した場合は、その締結日)と、代替えの不動産の取得日の期間が次のいずれかであること
- 不動産の譲渡等を行った日(移転補償契約の締結日)から、2年以内に代替えの不動産を取得していること
- 代替えの不動産を取得してから、1年以内に不動産の譲渡等(移転補償契約を締結)を行っていること
計算方法
税率は、土地、建物は3%、家屋(非住宅)は4%で計算されます(令和6年3月31日までの税率)それぞれで計算方法が異なるので、当てはまる方で計算を行いましょう。
- 譲渡等を行ってから2年以内に代替えの不動産を取得した場合の計算方法
(代替えの不動産の評価額-収用された不動産の評価額)×税率=不動産取得税
- 代替えの不動産を取得してから1年以内に譲渡を行った場合の計算方法
(代替えの不動産の評価額×税率)-(収用された不動産等の評価額×税率)=不動産取得税
申告方法
取得した不動産の所在地を管轄する税事務所に提出する必要があります。必要書類は以下の通りです。
- 記入した不動産取得税申告書
【収用される不動産について分かる書類】
- 売買(交換)契約書、物件移転補償契約書
- (公共事業の内容が不明な場合)買取証明書 又は 収用証明書
- 固定資産評価証明書
【代替え不動産の取得が分かる書類】
- 売買契約書及び最終代金領収書
- (家屋を新築した場合) 検査済証 又は 登記事項証明書(建物)
参考文献:東京都主税局「公共事業と不動産取得税の軽減制度について」
災害で家を失った場合
天災や火災による災害で家屋や土地を滅失・損壊した方を対象に、各自治体の条件を満たして代替え不動産を取得することで減免が適用されます。
また、建物部分は災害による倒壊度合いによって減免率が変動し、土地部分に関しては被災した面積で減免額が決まります。必要書類や申告先、期限に関しても各自治体によって異なります。被災による代替え不動産の取得の際は、管轄の自治体のHPや復興窓口などで確認してみましょう。
固定資産税についても理解しておこう

住宅を購入すると、固定資産税も不動産取得税と同じく支払う必要があります。中古住宅を取得する際は、この2つの税金を支払う算定で資金計画を立てておきましょう。
ここでは、固定資産税についての解説と計算方法、支払時期と支払用紙紛失時の対応について解説していきます。
中古住宅にかかる固定資産税とは
固定資産税の基準は1月1日時点で中古住宅を所有している所有者に対し、5月から6月を目安に納税通知書が届けられます。もし中古住宅を購入した1月1日以降で会った場合、売主(前の所有者)に固定資産税の納税通知書が届けられます。
一般的に、売買契約の際にこの固定資産税の扱いについて折半する流れを契約の際に取り決めます。引渡し日以前と引渡し日以降を基に日割りして、引渡し日以降の納付分を売主に支払うことになるため、あらかじめ固定資産税については用意しておきましょう。
不動産取得税のケースと同じく固定資産税は土地部分と建物部分に分けて算出されます。固定資産税の額は、対象となる不動産の課税標準額に税率1.4%を乗じた額になります。
建物部分の控除額の計算方法は、「建築後の経過年数に応じた減価率」が考慮されます。式は以下の通りです。
土地部分の控除額に関しては、新築住宅も中古住宅も同様の条件になります。
- 土地の面積が200平米以下の部分については、評価額に1/6を乗じた額が課税標準額とされます。
- 土地の面積が200平米を超える部分については、評価額に1/3を乗じた額が課税標準額とされます。
土地部分の固定資産税の計算式は以下の通りです。
固定資産税を支払う時期
上記で解説したように、1月1日時点で所有している所有者に納税通知書が届く仕組みになっています。自身で固定資産税を支払うようになるのは、1月1日に所有している年からの納付になります。この固定資産税は、年4回(4期)に分けての支払いが一般的ですが、1回で全額支払うことも可能です。このことを全納と言います。
固定資産税の支払いは不動産取得税とは異なり、不動産を所有している限り毎年支払う税金となります。支払方法は納付書での支払いになります。多くの自治体は口座振替にすることも可能です。
紛失した振込用紙は再発行
全部で4回支払いがある固定資産税ですが、5月や6月に納税通知書という支払い用紙で届くため、3回目や4回目になると用紙を紛失しがちです。
この振込用紙は最寄りの役所の税務課で再発行してもらえます。たとえ紛失したとしても納付期限がその分延長されることはありませんので、あらかじめスケジュールで支払いの管理をしておくなど注意しておきましょう。
また、固定資産税についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
https://news.mynavi.jp/fudosan-satei/3985
中古住宅の不動産取得税でよくある疑問

最後に、よくある不動産取得税の代表的な5つの疑問点について触れていきます。状況に合わせて参考にしてください。
- 中古住宅を解体したら、不動産取得税の扱いはどうなるのか
- 中古住宅の贈与や相続する場合は納税する必要があるのか
- 購入後のリノベーションは不動産取得税の支払い義務があるのか
- 不動産取得税を滞納するとどうなってしまうか
- 現行の耐震基準に適合しない場合は?
中古住宅を解体した場合の支払いについて
中古住宅を購入して建物を取り壊して更地に、建替えをしたいという方も少なくありません。では取り壊しを前提にした中古住宅の取得には、不動産取得税はかかるのでしょうか。
答えは、以下の条件すべて該当する場合は課税対象にならないということです。
- 取り壊すことを条件として家屋を取得したこと
- 取得後使用していないこと
- 取得後直ちに取り壊したこと
条件に当てはまった場合、不動産取得税調査申請書と必要書類を準備して、管轄する税事務所に取得してから60日以内に提出できるように準備しておきましょう。
必要書類は以下の通りです。
- 不動産売買契約書
- 最終代金領収書
- 建築確認済証、工程表等の取り壊した後の土地の利用状況が分かるもの
- 登記申請書及び登記完了証、もしくは解体証明書及び解体業者の印鑑証明書(原本)
条件に当てはまらない場合は、取り壊した建物部分の不産取得税も支払う必要がありますので注意しましょう。
更地に関する費用も併せて知りたい方はこちらの記事もチェックしてみて下さい。
https://news.mynavi.jp/fudosan-satei/5425
中古住宅の贈与や相続でも納税義務はあるか
中古住宅を贈与で取得した場合は、通常通り、前述で解説した通りに不動産取得税は課税されます。しかし、相続や相続人への遺贈で中古住宅を取得した場合は課税されません。
課税されないケースを下記にて紹介します。参考に一覧ください。
- 公共用、公益目的の不動産を取得した場合は課税なし
- 公共事業など地方自治体の事情による不動産の取得は課税なし
公共事業にかかわる事情の場合は、課税を免除されるケースが有ります。その場合はあらかじめ納税課の窓口で確認しておくと安心です。
取得税は非課税でも相続の時にかかる税金がある?詳しくはこちらの記事を参考にして下さい。
https://news.mynavi.jp/fudosan-satei/199
購入後リノベーションした場合の支払いについて
不動産を取得した際に、不動産取得税がかかることは解説した通りですが、中古住宅を購入し、築年数が古かったりバリアフリーを考えたときに、リノベーションを検討されることかと思います。
しかし、リノベーションによって増改築した場合にはその時に新たに不動産取得税が課税されることになります。増築や改築によって登記に記載のない新たな不動産が発生したり、不動産の価値が高まったりすると、同様に不動産取得税がかかります。
その際は上記で解説した減額方法が利用できますので、リノベーションの工事が完了次第、条件が当てはまる場合は早急に申請することをおすすめします。
中古住宅の不動産取得税を滞納した場合の支払いについて
万が一、支払いが遅れてしまった場合は延滞税を含めて支払う必要があります。期日の翌日から2カ月以内は原則年7.3%、2カ月以降は原則年14.6%となります。支払いを無視すると最終的には財産の差し押さえまで至ります。その流れを以下にてご紹介します。
- 督促状による催促の通知
- 電話や訪問による催促の通知
- 滞納者の財産調査が行われる
- 財産の差し押さえ、捜査
- 登記や通知案内
- 公売や取り立てによる換価が行われる
- 滞納した税金への充当が行われる
この流れは最短2ヶ月程度で差し押さえられる可能性があります。不動産取得税の滞納によって、せっかく購入したマイホームを失うことになりかねません。必ず納付期日までに支払うようにしましょう。
現行の耐震基準に適合しない場合は?
不動産取得税を減額させる条件として現行の耐震基準に適合しない場合は、一定の手続きを取ることで減額されることになります。手続きの流れは以下のとおりです。
- 住宅取得税の申請猶予を申請する
- 建物の耐震改修工事を行う
- 耐震基準適合証明書もしくは住宅性能評価書の証明を受ける
中古住宅を購入後に耐震改修工事を行うことを考えている方は、この手続きをしてみて下さい。
まとめ

ここまで中古住宅の不動産取得税について解説しましたが、不動産取得税は中古住宅を取得した際に課税されるとともに、条件によってはリノベーションした際にも課税されることになります。中には課税対象にならなかったり、控除されることで0円になるケースもあります。購入する際はその点を踏まえ、不動産取得税の分も資金計画に入れて備えておきましょう。
また、この不動産取得税の控除については申請期間が定められているため、あらかじめ申請の準備を行い、新生活後は早々に申請手続きを行ってください。不動産取得税を節税することで費用の負担が大幅に軽減されます。この記事で得た知識を参考に、中古住宅の節税に活かして下さい。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。


