不動産の購入には、住宅や土地の購入費用だけでなく、不動産取得税という税金もかかります。また、手続き費用や新生活の用意にも費用がかさむため、できるだけ掛かる費用を抑えたいですよね。なんと、今回紹介する不動産取得税は一定の条件を満たすことで、支払額を大幅に抑えることが可能になるのです。
この記事で、新築不動産を取得した人が不動産取得税の控除をうまく活用して節約ができるよう、基礎知識から計算方法、控除の内容、申請の仕方から注意点まで解説していきます。記事で得た知識を参考に、購入後の節税方法を身につけていきましょう。
※LIFULL HOME'S 住まいの窓口来場者(390組)を対象とした調査(集計期間:2019年4月~2020年3月)より
そもそも不動産取得税とは

新築住宅を取得すると掛かる税金であると先に解説しましたが、ここでは以下のような内容を解説していきます。
- 不動産取得税の基礎知識
- 何に対して課税されるか
- どのように計算されるか
- 不動産取得税が課税されないケースとは
不動産取得税はどういう税金になるのか、計算方法や課税されないケースについても解説していきます。
不動産を取得した際に課せられる地方税
マイホームを購入すると、毎年支払う義務が発生する固定資産税・都市計画税とは異なり、不動産取得税の場合は、不動産を取得した際に一度だけ課せられる地方税です。中古・新築に限らず、以下のような不動産を取得した人全てに納税の義務が発生します。
- 新築、中古戸建住宅
- 新築、中古マンション
- 無償譲渡の不動産
- 改築工事を行い、価値を高めた住宅
これら上記に課税された不動産取得税の支払先は国ではなく、購入した家の地域にある都道府県です。
不動産取得税を計算する際に用いられる不動産の評価額は自治体によって異なります。また、詳細は後述しますが、計算に用いられる税率は購入した年によってパーセンテージが変わる可能性もあります。
建物と土地それぞれにかかる
不動産取得税は、購入した不動産という括りに対してかかるのではなく、戸建ての場合は購入した土地と住宅の両方にかかります。これは国の基準により、土地や建物に対してそれぞれ評価されて決められます。詳しくは後述しますが、それによって計算方法、控除の適用条件も異なる仕組みになっていることを留意しておきましょう。
また、マンションの場合は戸建てと異なり、延床面積の扱いや土地部分に関して特殊になるため、以下の項目で詳細を解説していきます。
マンションの場合
上述した通り、マンションを取得したことで発生する不動産取得税は、一戸の居住スペースを専有部分、マンションの共有部を住宅部分、敷地利用権を土地部分として双方にかかります。
土地部分として計算する敷地利用権とは、マンションが建つ土地を利用する権利を戸数分で割った権利を指します。この敷地利用権は専有する床面積によって割合が異なります。
また、共有部分に関しては以下のようなスペースが共有部分となります。
- エントランス
- ロビー
- 廊下
- 階段
- エレベーター など
上記のように、居住スペース以外のマンションの床面積が共有スペースの対象になります。共有スペース全ての面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積が、一戸の住宅面積になります。
不動産取得税の算出方法
不動産取得税は、土地と建物で別々に発生する旨は前項でも解説しましたが、算出方法は共通して以下の内容で計算されます。
土地部分と建物部分をそれぞれ上記の式に当てはめ、計算した額が不動産取得税の金額になります。この式に使用されている各用語について、以下の項目で解説していきます。
2021年3月31日までは税率は3%
原則として、固定資産税評価額の4%が税率になります。しかし、2021年3月31日までに不動産を取得した場合は、土地部分と建物部分が特例によって3%で計算される仕組みになっています。そのため、新築住宅を取得した時期によって計算される税率が異なるので、取得時期がいつ頃になるのかあらかじめ確認しておきましょう。
また、建物部分が住宅としての目的を満たしていない場合はこの特例が使用されず、4%での計算となりますので注意が必要です。
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額は、不動産取得税の算出方法として使用されるだけではなく、登録免許税の計算方法や固定資産税、都市計画税などの計算にも用いられます。
この基準は各自治体の担当者が固定資産評価基準を基に、土地や建物の条件を綿密に調査したうえで決定しており、3年に一度は見直しが行われているのでその地域の評価として適正に調整されています。
一般的に新築住宅の固定資産税評価額の目安としては以下のような目安で判断されます。
- 建物部分:建築費用の約40%~60%
- 土地部分:土地の時価の60%~70%
これらの目安は、土地の形状や面積によって評価が変動します。建物部分に関しても住宅の規模や構造などによって評価額が変わってくるため、あくまで目安として参考にしてみてください。
不動産取得税が課税されない場合がある
ここまで不動産取得税について解説してきましたが、控除などの適用以前に、そもそも不動産取得税が課税されないケースもあります。
課税されないケースについては以下のような内容の不動産が対象になります。
| 不動産の条件 | 課税対象にならない金額目安 |
| 土地 | 10万円未満 |
| 家屋部分(新築または増改築) | 23万円未満 |
| 家屋部分(売買または贈与) | 12万円未満 |
また、以下は金額条件以外の課税されないケースです。
- 相続による不動産の取得
- 法人による不動産の合併、もしくは法令によって不動産を分割して取得
- 離婚などで共有物分割による不動産の取得
- 債権の消失により、担保設定後の2年以内に譲渡担保財産の所有権が設定者に移転した場合
- 土地区画整理事業等での換地にて得た不動産
- 公共用のために取得した道路
- 宗教法人の活動を目的とした不動産の取得
- 学校法人が保育もしくは教育を目的とした不動産の取得 など
以上のようなケースはあくまで一部分になり、このほかにも課税されないケースがありますので、気になる方は管轄の自治体へ確認してみましょう。また、非課税の申告は原則として自身で申告する必要があるため、非課税の対象として当てはまる場合は管轄の税事務所へ申告しに行きましょう。
新築住宅購入時に利用できる不動産取得税の軽減制度

これまでの内容を踏まえたうえで、新築住宅に使える不動産取得税の控除方法について紹介していきます。土地部分と建物部分で軽減措置の条件が異なることは前述でも少し触れましたが、ここではその制度についての解説と、軽減措置の有り無しでどれだけ節税ができるかを検討できるよう、実際のシミュレーションも紹介していきます。
実際に不動産取得税はかからないのでしょうか?以下の内容を参考に、自身の不動産が当てはまるかどうか見ていきましょう。
新築住宅の軽減制度
新築の住宅部分の軽減内容は、固定資産税評価額に対して1,200万円を控除します。もし固定資産税評価額が控除額未満の場合は、その金額が控除の金額になります。
この控除が適用された場合の軽減された不動産取得税の計算方法は以下の通りです。
この通り、高額な控除を受けることで、税金への出費を大きく抑えられることが分かります。
しかし、全ての住宅が対象というわけではなく、戸建て・マンション(共有部分を按分した面積も含む)ともに延床面積が50㎡以上240㎡以下の建物であることが適用要件となります。
この面積の判断として、現況の面積から判断されるため、登記で登録された面積と相違が出る可能性があることを留意しておきましょう。
土地の軽減制度
土地部分の軽減措置は、下記のいずれかのうちの大きい方の金額が控除額として適用されます。
- 45,000円(控除前の税額が45,000円未満の場合はその金額)
- 土地の1㎡に対する固定資産税評価額×1/2(※)×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率3%
この軽減措置を踏まえ、以下のような計算式で控除後の不動産取得税額を算出します。金額を当てはめて計算にご利用ください。
※2022年3月31日までに取得した場合には、1/2で計算した後の額で計算します。
この軽減措置を受けるための適用要件は以下の内容になります。
- 新築住宅部分が軽減措置の要件を満たしていること。
- 下記3つのいずれかの内容を満たしていること。
- 土地取得後から3年以内にその土地に住宅を新築し、なおかつ住宅が新築されるまでその土地を継続して所有している。
- 住宅を新築する前の土地を譲渡した場合、譲渡してから3年以内に受け取った側がその土地に住宅を新築している。
- 住宅を新築してから1年以内にその場所の土地を取得している。
土地と建物で取得のタイミングが異なる場合
新築住宅の場合、土地と住宅を同時に購入するケースだけでなく、土地の購入後に新築住宅を建てるケースや、新築住宅購入後に土地を正式に取得するケースなど、購入手段は様々です。
土地購入が先なのか住宅購入が先なのかで控除の適用条件が異なります。ここではその内容について解説しますので、自身のケースに合わせて参考にしてみてください。
| 土地取得タイプ | 適用条件 |
| 住宅と同時に取得 | 新築未使用の住宅を築1年以内に取得している |
| 住宅より前に取得 | 敷地取得から3年以内に住宅を新築している |
| 住宅建築より後に取得 | 敷地取得以前の1年以内に住宅を新築している |
取得を基準に期限を設けているので、土地取得が後になる場合は早めに土地取得の手続きをする必要があることが分かります。
軽減制度のシミュレーション
では実際に軽減税率が適用されるとどれだけの恩恵を受けることができるか、軽減される前と、軽減後の不動産取得税の違いを土地と住宅部分で比較してみましょう。
モデルケースは以下の内容を使用します。
- 住宅部分:延床面積120㎡、取得価格2,200万円、固定資産税評価額1,100万円
- 土地部分:現況面積180㎡、取得価格1,800万円、固定資産税評価額1,300万円
モデルケースを前述した計算式に当てはめ、軽減前と軽減後を表で比較してみましょう。
| 種別 | 軽減前 | 軽減後 |
| 住宅部分 | 330,000円=1,100万円×3% | 0円=(1,100万円-1,200万円)×3% |
| 土地部分 | 195,000円=(1,300万円×1/2)×3% | 0円=(1,300万円×1/2)×3%-軽減額216,000円 |
| 不動産取得税の金額 | 525,000円 | 0円 |
※上記の税率は、2021年3月31日以前の取得を想定しています。
上記のシミュレーションからも読み取れるように、軽減措置を利用することで合計525,000円分の税金を軽減することが可能になります。軽減措置の計算は固定資産税評価額を知る手間だけで把握できる情報のため、自身の新築住宅のケースにも当てはめて、実際にどれだけの軽減措置が受けられるかを確認しておきましょう。
不動産取得税の控除の申請方法

不動産取得税の場合、原則として軽減措置を申告するための期限が設けられています。申請するタイミングを逃した場合の救済措置などもありますが、新築住宅取得のタイミングに合わせて申請ができるよう、ここでは申請期限や申請場所について紹介していきます。
軽減措置の申請時期は取得してから60日以内
申請期間は管轄する都道府県の税事務所により異なります。一般的に20日~60日以内の申告を期限とするところが多い傾向にありますが、実際は管轄する税事務所によっては提出期日が異なるため、不動産の担当者もしくは税事務所へ確認しておきましょう。
また、あらかじめ軽減措置の条件をクリアしていることを証明する必要書類を用意したうえで、税事務所に申告しておくと、控除を受けた納税が可能になります。
不動産取得から5年以内ならさかのぼって申請可能
書類準備の段取りや申請の期限などの関係、軽減措置の申告を忘れたなどの理由により申告が期限内に間に合わず、通知書通りに納税した場合でも、後から控除の差額分の還付金を受けられる可能性があります。不動産を取得してから5年以内に還付請求を行うことができ、支払った税金の一部が戻ってくるため欠かさず申告するようにしましょう。
とは言え、不動産取得税の支払いは新築住宅取得後の出費に大きな影響を与えるため、あらかじめ申告しておいたほうが得策です。引越しなどの忙しさから申告を忘れることがないよう、あらかじめ用意できるものは用意しておき、申請できるよう準備しておくことをおすすめします。
申請時の必要書類は税事務所により異なる
軽減措置の申請に必要になる書類は、以下の内容になります。
- 住民票(マイナンバーの記載のないもの)
- 印鑑
- 不動産取得税申告書(管轄の都道府県税事務所のHPで入手可能)
- 不動産取得税減額申請書(管轄の都道府県税事務所のHPで入手可能)
- 不動産売買契約書と最終代金領収書(金額証明のため)
- 建設工事請負契約書
- 建築確認済証
- 平面図(※共同住宅や二世帯住宅、併用住宅の場合)
- 長期優良住宅認定通知書(※長期優良住宅として軽減の場合)
- 分合筆の経過が確認できる書類(※土地の分筆で軽減の場合)
- 証明日が住宅完成日以降の土地の登記事項証明書
- 新築建物に関する証明など(※検査済証や建物部分の登記事項証明書、建物引渡証明+請負業者の印鑑証明書のいずれか)
また、契約書などコピーで対応できる書類もあれば、原本で提出が必要な書類もあるため、管轄する税事務所の指定に合わせて用意する必要があります。
申請場所は不動産を取得した場所の管轄の税事務所
上記でも解説した通り、申請場所は新築住宅を取得した場所を管轄する都道府県(東京23区の場合は区)税事務所へ申請する必要があります。担当する税事務所がどこにあたるかは不動産会社やハウスメーカーの担当者が把握している場合もあるので、確認してみるのもおすすめです。
申請して6ヶ月〜1年後に税事務所から納税通知書が送られてきます。軽減措置の申請を行い、結果的に税額が発生しない場合は通知書が届かないこともあります。なかには0円でも通知書として送られてくるケースもありますので、臨機応変に対応しましょう。
届いた通知書には不動産取得税の支払額が記載されており、支払期限が設定されているので、期限までに納税するようにしましょう。一般的には、税事務所が発送した当月末までの期限を設定されます。支払方法に関しては管轄の税事務所や金融機関窓口、コンビニで現金での納税、もしくはオンライン決済などで納税しましょう。
不動産取得税の軽減制度を利用する際の注意点
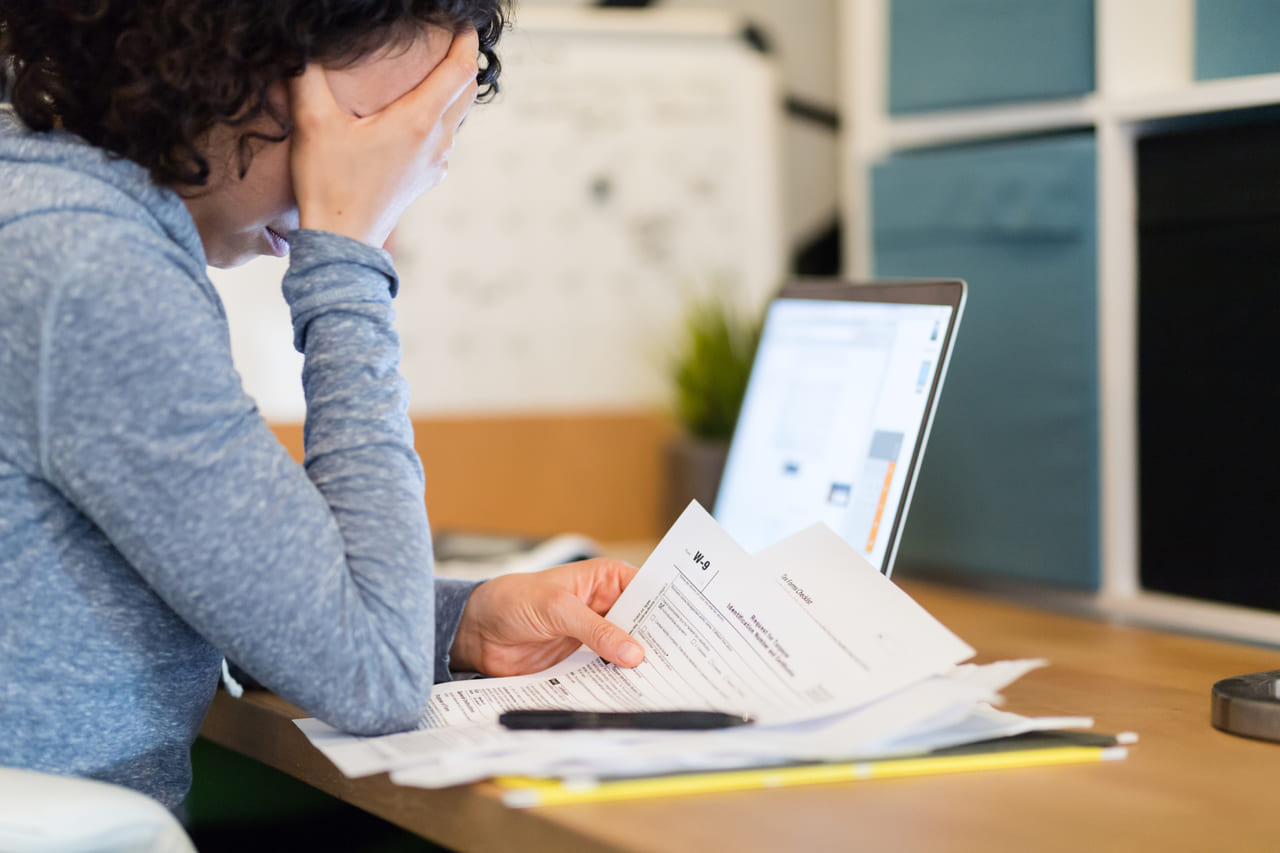
最後に、控除を受けるための申請の際の注意点について解説していきます。申請する前に知っておくことで時間を短縮、または不利益を軽減することができるでしょう。
ポイントは以下のような内容です。
- 申請についての詳細は全て管轄する税事務所
- 控除申請は自発的に行う必要がある
- 課税内容について不服がある場合
順に解説していきますので、必要に合わせて見ていきましょう。
控除の申請についての詳細は各税事務所に確認する
各税事務所によって以下のような内容が異なります。
- 手続き方法
- 申請期限
- 必要書類
- 支払い方法
実際に、上記で紹介した必要書類は一概にすべてが必要になるわけではありません。また、支払方法に関して全税事務所が現金以外の納税に対応しているわけではありません。
管轄する都道府県の税事務所によって必要な書類が異なり、支払方法や申請期限も異なります。必要書類を求めて何度も足を運ぶことを防ぐためにも、申請する前に窓口やHPなどで確認しておきましょう。
控除の申請は自分で行う必要がある
控除の申請は、税事務所の判断で軽減措置の適用を行ってくれるわけではありません。当然、取得した不動産が軽減措置の対象物件になるかを知らせる便りが届くことはなく、自身で軽減措置の条件を満たしているか確認したうえで、管轄している税事務所へ申請を行う必要があります。
申請内容に不安がある場合などは税事務所に問い合わせるなど、申請の手続きにミスが生じて時間を取られることがないよう、準備を万端にしておくことをおすすめします。
課税内容に不服がある場合
不動産取得税の課税内容に不服が生じるケースもあります。代表的な例は計算に用いられる課税評価額の基準などです。違和感を感じたり、納得いかない点などあれば、内容をそのまま享受して支払うことは大変損になります。
そのような場合には、納税通知書が届いた翌日から3ヶ月以内に各都道府県の知事に対して、もしくは管轄の税事務所へ不服申し立ての審査請求を行うことができます。不服申し立てに使用する書式は各都道府県税事務所に備え付けてあるため、申し立ての際は備え付けの書類を利用して審査請求を行うようにしましょう。
まとめ

ここまで、新築住宅を取得した際に発生する不動産取得税について解説してきましたが、軽減措置が利用できる場合は大幅な節税が期待できることが分かりました。中には、まるごと控除されて不動産取得税がかからないケースもあります。
しかし、軽減措置の恩恵を受けるためには、住宅部分と土地部分で一定の条件を満たす必要があります。申請は自身で行う必要があることから、控除の対象物件かどうかをあらかじめ確認しておき、必要になる書類や申請期限について管轄する税事務所へ確認しておきましょう。
事前準備の手間がそのまま節税効果に繋がります。利用できる控除を有効に活用して、新生活にゆとりが出るよう、事前に備えておきましょう。
新居の購入に関する悩みを専門家に相談できる「HOME’S住まいの窓口」

家づくり・住まい選びで悩んでいるならHOME’S 住まいの窓口に相談するのがおすすめです。HOME’S 住まいの窓口がおすすめな理由を以下にまとめています。
- 家づくりの進め方のアドバイスや、自分に合う建築会社・不動産会社を紹介してもらえる
- 日本最大級の不動産・住宅情報サイトのLIFULL HOME’Sが運営。利用満足度99.5%(※)
- 住宅ローンや費用に関しても相談可能。ファイナンシャルプランナーの無料紹介も
- 不動産会社・建築会社とのスケジュール調整や断りの連絡を代行
※LIFULL HOME'S 住まいの窓口来場者(390組)を対象とした調査(集計期間:2019年4月~2020年3月)より
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。


