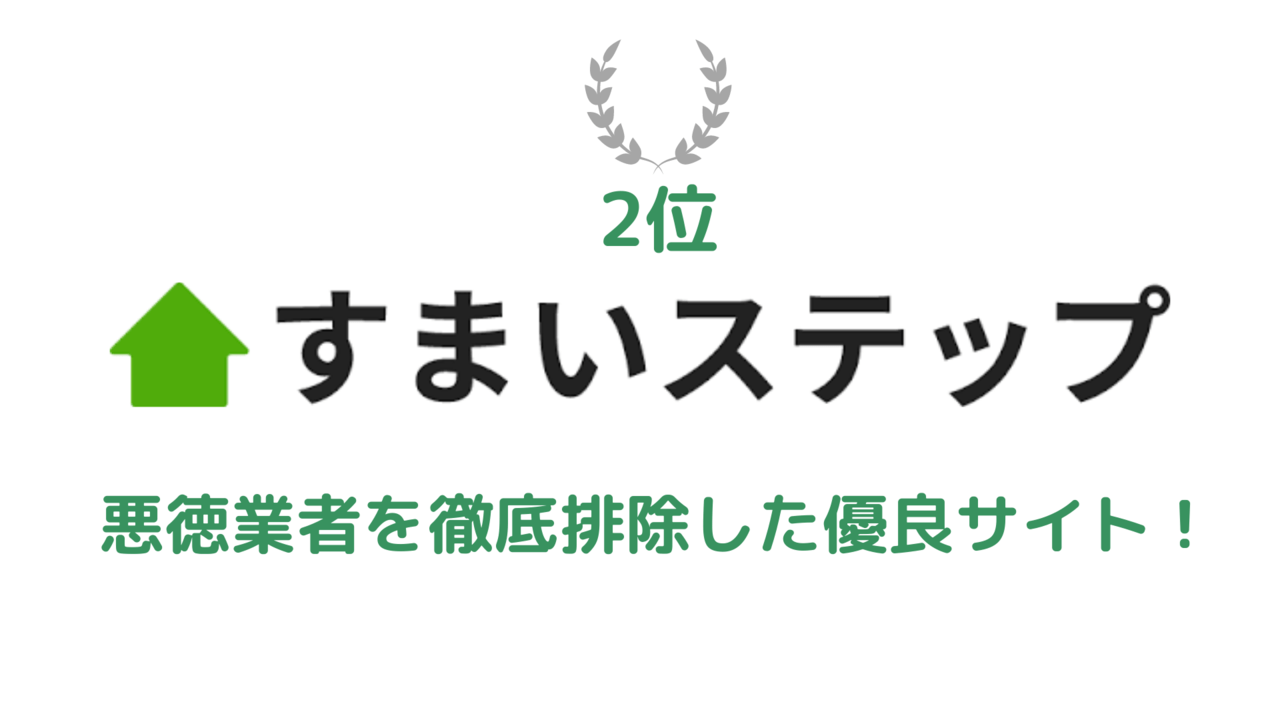「土地を売却しようと土地の権利書を探したが見つからない」「紛失してしまった土地の権利書は悪用されるのか心配」などと困っていませんか?
土地の権利書を紛失しても悪用されるリスクは高くありませんが、状況によっては所有権を勝手に移転される場合もあります。そのため紛失時の対処法を把握して、悪用に備えた行動をとる必要があります。
この記事では、土地の権利書を紛失したときの対処法や、再発行について詳しく解説します。土地の権利書とはどんなものなのかや悪用されるリスク、よくある質問などについても細かく見ていきましょう。本ページを読んでいただければ、権利書がない場合の対処法を把握でき、土地売買や相続などのシーンでも役立ちます。
不動産一括査定サイト利用者が選んだおすすめサービスTOP3
この記事を読まずに、先におすすめの査定サービスを知りたい人におすすめなのが、以下の3サービスです。 マイナビ編集部で実施した独自アンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声と編集部の知見が合わさってできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)
土地の権利書とは

土地の権利書は名義人であることを証明する書類で、効力を持つものは2種類あります。ここでは、土地の権利書とはどのようなものなのかを詳細に解説します。以下のような項目を理解しておきましょう。
- 名義人であることを証明するもの
- 効力を持つものは2種類ある
- 紛失しても所有権はなくならない
- 所有者が死亡すると相続人名義で発行される
一つずつ具体的に説明します。
名義人であることを証明するもの
土地の権利書は、法務局から土地の所有権を取得した際に発行されるもので、土地の登記名義人ということを証明できる書類で、正式名称は「権利書」ではなく「登記識別情報」です。
登記識別情報には12桁の番号があり、土地所有者が登記名義人だということが証明できるようになっています。また登記識別情報は、不動産関連のさまざまなシーンにおいて使われるもので、非常に重要なものといっても過言ではありません。
効力を持つものは2種類ある
名義人であることを証明する書類は、登記識別情報と登記済権利証の2種類あります。登記済権利書とは、平成17年まで発行されていた「登記済」と押印された紙の書類のことで、現在はパスワードが記載されている登記識別情報に変更されました。
名称は異なるものの、登記識別情報と登記済権利証どちらも土地の権利書として、同じ効力を持っています。
紛失しても所有権はなくならない
登記識別情報や登記済権利証といった土地の権利書は、土地の所有権を証明するための書類であり、紛失しても所有権そのものはなくなりません。登記情報が変更されるなどのトラブルに見舞われた際は、所有権を失うことになりますが、紛失が所有権の放棄にはつながりません。他に所有権を証明できるものがあれば、土地の登記名義人であることを証明できるでしょう。
所有者が死亡すると相続人名義で発行される
土地の所有者が死亡した場合は土地の権利書の効力はなくなりますが、相続の手続きを行えば、相続人の名義で新しく土地の権利書が発行されます。
また登記識別情報は、複数いる相続人の1人が申請人となって登記申請を行うと、他の相続人には登記識別情報が通知されないため注意が必要です。元の権利書は使用するシーンがゼロではないため、しっかりと保管しておきましょう。
土地の権利書が悪用されるリスク

土地の権利書が悪用されることはほとんどありません。しかし、状況によっては所有権を勝手に移転されるケースもあります。ここでは、土地の権利書が悪用されるリスクなどについてまとめました。
悪用される可能性は低い
まず、土地の権利書のみで名義変更をされたり、勝手に土地を売却されたりするリスクはありません。名義変更する際は権利書だけではなく、印鑑や3ヶ月以内に発行された印鑑証明書なども必要です。売却する場合も、さまざまな書類を準備しなければならないため、すぐに焦る必要はないでしょう。
さらに登記は司法書士に依頼することが一般的で、必ず本人確認が行われます。そのため、土地の権利書が悪用されるリスクはほとんどないと認識しておきましょう。
また、土地売買の際に必要な手続きや書類について詳しく知りたい人は、以下の記事もおすすめです。

状況によっては所有権を勝手に移転される場合もある
悪用される可能性は低いものの、勝手に土地の所有権を移転されてしまう場合もあります。以下のようなケースには注意しましょう。
- 印鑑や土地の権利書、印鑑証明書をセットで紛失
- 各種書類の偽造
- 司法書士の裏切り
可能性は高くありませんが、これらのケースにおいては所有権を移転されてしまうリスクがあるでしょう。不正な登記は、裁判によって無効にすることも可能ですが、費用・時間・手間がかかるため、権利書を含め大切な書類を紛失しないように、しっかりと保管しておくことが重要です。
土地の権利書を紛失した場合の対処法

万が一、権利書をなくしてしまった際は以下のような対処法があります。
- 管轄の登記所に相談する
- 不正登記防止の申出を行う
- 登記識別情報の失効申出を行う
これらの対処によって、紛失後のトラブルを回避できる可能性が高まります。各対処法の詳細を知り、紛失時に備えておきましょう。
管轄の登記所に相談する
土地の権利書を紛失した場合は、すぐに最寄りの登記所にその旨を伝えるようにしましょう。登記の申請や登記関連書類の発行を行っている登記所(法務局)に相談すれば、この対応を怠った場合よりも、他者が勝手に所有権移転登記などを行うリスクを防止できます。
管轄の法務局の住所や連絡先は、法務局の公式サイトから調べましょう。公式サイトでは、法務局の一覧が掲載されているだけではなく、日本地図からも場所を見つけられます。土地の権利書を紛失して、何をすべきか焦っても問題は解決しないため、すみやかに管轄の登記所に相談しましょう。
不正登記防止の申出を行う
法務局に申し出た日から3ヶ月以内に登記の申請があった場合は、名義人に通知してもらえる「不正登記防止申出」という制度があり、土地の権利書を紛失したときの対処としておすすめです。不正登記防止申出で準備する書類は次の通りです。
- 印鑑証明書
- 登記事項証明書
管轄の法務局に直接出向き、これらの書類とともに提出します。3ヶ月と期限が定められていますが、何者かが登記しようとしている場合には、申請者に連絡が来るため安心できるでしょう。必要書類や手続きでわからない部分があった際は、法務局の担当者に聞いてみてください。
登記識別情報の失効申出を行う
登記識別情報の失効申出を利用すれば、登記識別情報を無効にすることが可能です。この制度は、土地の権利書を紛失した場合だけではなく、パスワードを盗み見されてしまったケースにおいても役立つでしょう。
また不正登記防止申出のように期間の制限はなく、登記識別情報の効力が永久に失われることも特長です。この方法であれば、不正利用を確実に防止できます。
土地の権利書をなくした場合の再発行について

権利書を紛失した場合は再発行ができません。しかし、名義人であることを証明できる制度はいくつかあります。ここでは、土地の権利書をなくした場合の対応策について紹介します。
基本的に再発行はできない
その他の多くの書類とは異なり、登記済証や登記識別情報をなくしても、再発行には対応していません。ただし権利書を紛失しても、名義人であることを証明する方法はいくつかあります。
しかし登記済証や登記識別情報以外で、名義人であることを証明するためには手続きや費用が必要なので、権利証をなくさないようにすることが大前提と考えておきましょう。
再発行しなくても名義人であることは証明できる
登記済証や登記識別情報を再発行せずに、名義人であることを証明する方法は以下の3つです。
- 事前通知制度
- 専門家に本人確認を依頼する方法
- 公証役場を活用する方法
これらの方法を利用すれば、売却や名義変更を行うことも可能です。各方法の詳細を見ていきましょう。
事前通知の方法
事前通知制度は、権利書の紛失などの事情を説明することで土地所有者であることを証明でき、特別な費用はかかりません。事前通知制度を利用する際の流れは、以下の通りです。
- 権利書を添付せずに登記申請(紛失などの理由も明記)
- 法務局から申請内容の確認を行う通知(本人限定受取郵便)が届く
- 必要項目を記入し返送する
- 土地の所有者であることを証明可能
手軽に利用できる制度ではあるものの、2週間以内に返送を行わなかった場合は申請を認めてくれません。海外に住んでいる場合は4週間以内です。
また、登記を完了するまでに時間がかかることもデメリットに挙げられます。「できるだけ費用をかけたくない」「急いで登記することを考えていない」という場合は、事前通知制度を活用しましょう。
専門家による本人確認の方法
土地家屋調査士や司法書士などの専門家による本人確認によって、権利書がない場合でも登記を進められます。専門家による本人確認では、以下の対応が必要です。
- 本人確認できる書類の提示
- 有資格者による面談
専門家に依頼するため手数料はかかるものの、事前通知制度のような手続きは不要です。「自分で手続きする時間を作れない」「面倒な手続きは専門家に任せてしまいたい」という場合は、専門家による本人確認の方法を採用しましょう。
公証役場を活用する方法
実印や印鑑証明書、委任状などを持って公証役場に行き、公証人の立ち合いのもとで手続きを行えば、委任状を土地の権利書代わりにできる方法もあります。公証役場を活用する方法は、専門家に依頼するよりも費用を抑えられることがメリットですが、公証役場に行くための時間が必要なことはデメリットです。
公証役場は全国に設置されているため、ホームページで場所を確認しておきましょう。また必要書類については、身分証明書などが求められるケースもあるため、事前に問い合わせておくと安心です。
土地の権利書を紛失した場合にかかる費用と期間
事前通知や専門家による本人確認、公証役場の活用にかかる費用と期間の目安は以下の通りです。
| 名義人であることを証明する方法 | 費用 | 期間 |
| 事前通知 | 無料 | 2~4週間 |
| 専門家による本人確認 | 50,000~10万円程度 | 専門家次第 |
| 公証役場の活用 | 3,500~10,000円程度 | 本人次第 |
費用面を考慮した場合は事前通知を、できるだけ早く手続きを済ませたい場合は、その他の方法をおすすめします。
土地の権利書に関するQ&A

土地の権利書について、よくある質問は次の通りです。
- どんな場面で必要となるのか?
- いつ届くのか?
- 登記簿との違いは?
- 最適な保管方法は?
それぞれの回答を紹介するので、より権利書について理解を深めたい方は参考にしてください。
どんな場面で必要となるのか?
土地の権利書が必要になる場面は、土地を売買するときだけではなく、相続や譲渡、住宅ローンの借り換え、寄付するケースなども含まれます。不動産売買においては、次のようなシーンで土地の権利書が必要です。
- 不動産会社に仲介を依頼する際は、不動産所有者の確認時に権利書を提示
- 売却契約後に買い主に所有権が渡るときも権利書が必要
基本的には、土地の名義人を明確にするシーンにおいて、必要になると認識しておきましょう。
土地を売買するときの流れや費用
土地の権利書が必要になる売却の流れや必要書類、費用について知っておいても損はありません。仲介での売却を参考にした場合の流れや、かかる税金などは以下の通りです。
| 流れ |
|
| 必要書類 |
|
| 費用・税金 |
|
ただし、売却する方法によって流れや必要書類は異なるため、スムーズに手続きを進めるために、仲介する不動産会社に直接確認しておきましょう。また、土地売却のコツも以下で提示するので、納得のいく取引を成功させるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
| 土地売却のコツ | 詳細 |
| 相場を調べるときや不動産会社を選ぶときは不動産一括査定サイトを利用する |
|
| 不動産会社の担当者の人柄・実力を確認する |
|
| 状況に合った媒介契約を結ぶ |
|
| 土地をきれいな状態にしておく |
|
おすすめの一括査定サイトは「すまいステップ」

- 初めてで不安だから実績のあるエース級の担当者に出会いたい
- 厳選された優良不動産会社のみに査定を依頼したい
- 悪徳業者が徹底的に排除された査定サイトを使いたい
\ 厳選した優良会社に査定依頼 /
すまいステップで一括査定する
その他の一括査定サイトや選び方について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

土地の売却で困ったときの相談先
土地の売却に悩んだときは、どこに相談したらよいのか把握しておくと安心して進められます。また、以下のように状況や内容によって相談先は異なります。
| 状況 | 相談先 |
| 売買全般 | 不動産会社 |
| 早めに売却したい | 買取専門不動産会社 |
| 売却後も使いたい | リースバック提供の不動産会社 |
| ローン関連 | 金融機関 |
| 借金問題 | 法テラス |
| 遺産分与で揉めた場合 | 弁護士 |
| 登記変更 | 司法書士 |
| 税金関連 | 税理士 |
土地の売却には複雑な問題が多く、相談する機関を誤ると不要な費用がかかる可能性があります。自分の状況をしっかりと整理して、どの悩みをどの専門家に相談するのかを見極めましょう。
不動産相続時の流れや費用
土地の権利書が必要になる相続時の流れや費用、税金は以下の通りです。
| 流れ |
|
| 必要書類 |
|
| 費用・税金 |
|
遺言書があれば上記よりも必要書類は多くなく、遺言書や戸籍謄本、住民票などを準備するだけです。また書類の取得費用もそれほどかからないでしょう。相続の手続きでわからないことがあったときは、司法書士や弁護士などの専門家に相談してみましょう。
相続や売却で利用できる特例
土地を相続したり相続した土地を売却したりする場合は、税金を納める必要がありますが、以下のように節税できる特例はたくさんあります。
| 特例 | 内容 |
| 農地相続税の納税猶予 |
|
| 小規模宅地等の特例 |
|
| おしどり贈与 |
|
| 配偶者控除 |
|
| 取得費加算の特例 |
|
| 10年超所有不動産の特例 |
|
| 3,000万円特別控除 |
|
こうした特例を活用すれば、納税はほとんど必要ない可能性も考えられます。各特例の条件は細かく設定されているため、軽減税率を含めてしっかりと確認しながら上手に利用しましょう。また適用を受けるためには、確定申告が必須な特例もあるので、不明点は税務署や税理士に相談することをおすすめします。
いつ届くのか?
土地の権利書は、土地を購入したり相続したりした場合に、所有権移転登記をした時点で交付されます。このようにすぐに届くため、時間がたつと忘れてしまうかもしれません。
土地の権利書を紛失してしまうと手間も費用もかかるため、なくさないように十分注意しましょう。登記を司法書士に依頼している場合は、いつ届くのかを問い合わせてみるとよいでしょう。
登記簿との違いは?
土地の権利書は土地の所有者を証明するものであり、登記簿は土地の権利が誰にあるのかがわかるものです。さらに登記簿は法務局が管轄しているもので、手数料を支払えば誰でも閲覧できます。
また登記簿は法務局で保管されているため、土地の権利書と保管場所が違うことも認識しておきましょう。土地の権利書は個人で保管するものです。
登記や登記事項証明書・登記簿謄本の違いについて
土地売買や相続などを進める際は、登記について理解を深めておくことも重要です。登記とは不動産の権利情報のことで、登記の主な内容は次の通りです。
- 土地面積
- 所在地
- 所有者
- 住宅などの種類
- 木造などの構造
- 床面積などの状態
どのような不動産なのかが明確に記されていて、不動産売買などに必要になりますが、この登記の内容が記された書類を登記事項証明書といいます。登記簿謄本という書類も同様の内容が記載されていますが、それぞれの違いは以下の通りです。
- 登記簿謄本:紙をコピー
- 登記事項証明書:コンピュータ内のデータを印刷
また登記事項証明書の種類は、以下のような5つの種類があることも認識しておきましょう。
| 登記事項証明書の種類 | 記載事項 |
| 全部事項証明書 |
|
| 現在事項証明書 |
|
| 一部事項証明書 |
|
| 閉鎖事項証明書 |
|
| 登記事項要約書 |
|
こうした登記事項証明書は、登記・供託オンライン申請システム、あるいは申請用総合ソフトを使用して取得可能です。全国各地にある法務局の窓口で申請を行ったり、郵送で請求したりすることもできます。
最適な保管方法は?
勝手に所有権を移転されるなどの悪用を防止するためにも、土地の権利書の保管場所は、誰にも見られないところを選びましょう。もちろんパスワードは誰にも見せないようにして、印鑑や印鑑証明書と一緒に保管しないように意識してください。
悪用されないためにも、他の人には分からない場所に保管するようにしましょう。さらに他の種類と混ざらないように、ファイルなどに入れて整理しておくことも重要です。
まとめ

土地の権利書は、不動産関連のさまざまなシーンにおいて使われるもので、12桁の番号がある「登記識別情報」と紙の書類の「登記済権利証」の2種類あります。どちらも土地の権利書として同じ効力を持っており、万が一紛失したとしても、所有権そのものはなくなりません。
権利書が悪用されるリスクは低いものの、印鑑や印鑑証明書をセットでなくした場合は、所有権を勝手に移転されるケースも考えられるため、紛失した際はすみやかに管轄の登記所に相談しましょう。権利書は再発行できませんが、事前通知制度や専門家に本人確認を依頼する方法などを利用すれば、売却や名義変更を行うことも可能です。土地の権利書を紛失しても慌てずに対処して、スムーズに土地売買や相続の手続きを済ませましょう。
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。