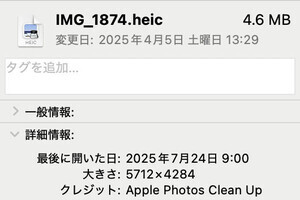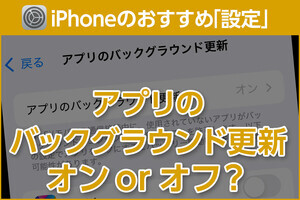2018年第3四半期決算におけるiPhoneの販売台数および売上の数字は、2017年9月以降のAppleのiPhone戦略の成功を印象づける内容となった。
同時に、端末の販売台数からアクティブユーザーベースの成長へ、またそれを背景にしたサブスクリプションサービスの成長へという、指標の移行についての筋道を立てつつあり、評価基準の在り方を変えていこうとしている。こちらも、サービス部門の急成長を背景に、投資家に認められていくことになるだろう。
Cook氏はiPhoneについて、「生活のあらゆる物事の格納庫となる。ごく一部ではなく、全ての物事を目指している」と語り、ホーム、ビジネス、ヘルスケアなど全方位の中心にiPhoneを据えていく考えを打ち出した。
同時に、Apple Watchを理由にiPhoneを選ぶユーザーの存在にも触れ、成長が続くウェアラブルデバイスとiPhoneの相互作用によって、ロイヤリティを高めていくこと、またエコシステムにユーザーを取り込んでいく戦略を推進するとアピールしている。
今回の決算においては、人工知能や拡張現実に関する指摘は特に目立ったものはなかった。6月に開催されたWWDC 2018では、秋に配信予定の新OSについて触れたが、iPhoneやサービス部門などにおけるソフトウェアに関する指摘が少なかった点が気になる。
サービス部門の発展は自社、あるいはApp Store向けアプリの開発者によるソフトウェアと、エンターテインメントや生産性に関連するサービスのサブスクリプションによって構成される。この部門に関してはハード以上にソフト面での功績が大きいが、完全にサードパーティの開発者任せというのではなく、Apple自身の戦略と業績の影響も少なからず依るところがあるので、筆者は、もう少し具体的に考察を進めるべきだと考える。それに加えて、iPhoneのアクティブユーザーベースの数字は、販売台数とともに指標の数字として発表していくべきではないだろうか、とも。

|
松村太郎(まつむらたろう)
1980年生まれ・米国カリフォルニア州バークレー在住のジャーナリスト・著者。慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了。慶應義塾大学SFC研究所上席所員(訪問)、キャスタリア株式会社取締役研究責任者、ビジネス・ブレークスルー大学講師。近著に「LinkedInスタートブック」(日経BP刊)、「スマートフォン新時代」(NTT出版刊)、「ソーシャルラーニング入門」(日経BP刊)など。ウェブサイトはこちら / Twitter @taromatsumura