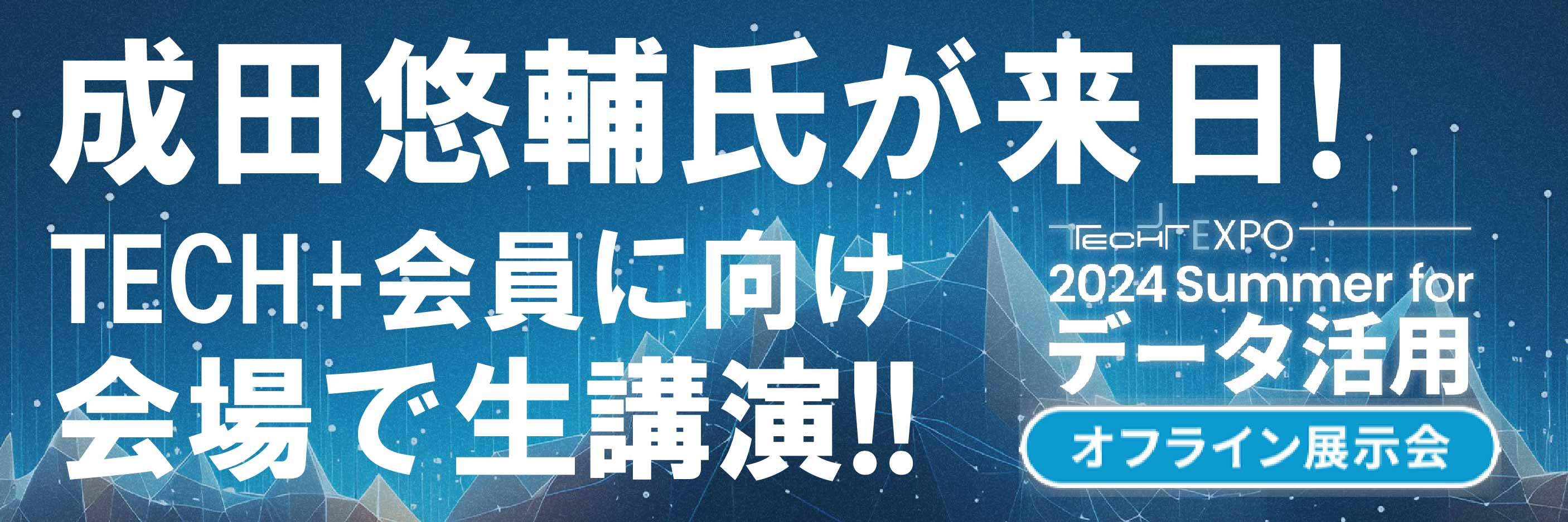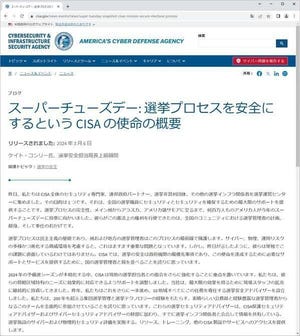急速な市場変化やニーズの多様化に柔軟に対応する上で、DXは避けて通ることができない課題である。
2019年にDX Agendaを制定し、その推進に取り組む日本電気株式会社(NEC)は、以前のデータ統合での課題の表出を受け、DXの前提となる新たな全社規模のデータプラットフォームの構築を開始。
利用状況に応じてクラウド上で柔軟に運用でき、ベンダーフリーで多様なツールとの連携に開かれたSnowflakeの特長は、ソリューションとしての外販も視野に入れて構築が進む、同社の次世代データプラットフォームに重要な役割を果たしている。
課題:費用対効果に見合うことが共通データプラットフォームの大きな課題
[PR]提供:Snowflake