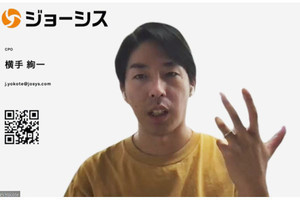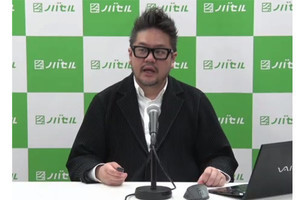チーム・コミュニケーションを円滑にするビジネスのサポートツール「Slack(スラック)」。コロナ禍におけるリモートワーク文化が進んだことも相まり、近年は多くの企業が導入を始めている。では、Slackはどのように企業のコミュニケーションを円滑にしているのだろうか。今回はSlackの全社導入以降、グループ会社全体でプロプランからEnterprise Gridに移行したラクスルの事例を紹介する。→過去の「Slackで始める新しいオフィス様式」回はこちらを参照。
Enterprise Grid移行の背景にあった「セキュリティ強化とコミュニケーション整備」
ラクスルがSlackを全社導入したのは2014年。プロプランを経て、今年4月からEnterprise Gridの契約を開始した。2カ月もの移行期間を経て、7月からは「ノバセル」や「ハコベル」といった各事業を展開するグループ会社ごとに、異なるワークスペースを作成。現在はトータルで約800アカウントが登録されている。
同社がプロプランからEnterprise Gridに契約変更した背景は大きく2つある。1つは情報セキュリティのリスクを解消させるためだ。全グループの情報システムの管理・運用を行うラクスル VP of Corporate Technologyの佐藤友厚氏は、Enterprise Grid契約以前の状況を次のように語る。
「弊社ではラクスル、ノバセル、ハコベルとプロダクトごとに事業部門や会社が分かれています。それぞれでクローズドにやりとりすべき情報も存在しますし、オープンに周知させたい情報の中にも『これは他の事業部には見えないようにすべき』というデータもありました。そういった情報漏えい防止の観点からも、1つのワークスペースを複数の事業会社が利用する運用方式に限界を感じていました」(佐藤氏)
また、従業員数が増えたことで、コミュニケーションにも課題を抱えていたラクスル。Enterprise Gridへの移行には、オンライン上でのやりとりを活性化するという目的もあったようだ。
「従業員数が増えつつあるなかでの、コロナ禍によるリモートワークへのシフト。グループ内でも各部署にどんな人がいるかが分かりにくく、雑多にチャンネルが散らばってました。現場の社員にとって、どこで誰に何を話せばいいかが不明瞭だったんです。情報セキュリティを強化しながらも、円滑にコミュニケーションを取れるようにする。ワークスペースを分割できるEnterprise Gridに移行し、組織ごとに既存のチャンネルを整理してオープンな環境を作ることで、これら2つの課題がクリアできる、という結論に至りました」(佐藤氏)
移行期間で気づいた「導入前にこうしておけばよかった」という反省
現在、ラクスルでは組織ごとにZoomやTeams、Google Workspaceなどのツールを併用しつつも、メインのコミュニケーションツールとしてSlackを活用している。佐藤氏をはじめとする情報システムを統括するチームではじめに行ったのは、プライベートチャンネルを含む7000もの既存チャンネルを整理することだった。
実際の作業に関わったラクスル CCO / Manager of Strategic Communicationの松本藍氏は次のように振り返る。
「日ごろから整理しておくべきだったと後悔するほどには、骨の折れる作業でした(笑)。各チャンネルの役割や必要性を確認するためにも、現場の皆さんに都度チェックしてもらって。中にはチャンネルオーナーがすでに退職していて、管理者が不在になったチャンネルもありました。最終的には半分以下の3,000チャンネルまで削りました」(松本氏)
また、運用開始期間までに検討する点はもう1つあった。それは認証システムの仕組みづくりだ。ラクスルではAzure AD(Microsoft Azure Active Directory)をユーザー認証の基盤として使用。事業部の担当者グループごとにアカウントを分け、各ワークスペースへ自動的に振り分ける仕組みを検討していたが、リハーサルは難航した。
従来から従業員台帳のような内製のシステムからAzure ADへユーザー登録連携を行なっていたことから、その台帳システムをもとにSlackのアカウントも管理していたという。
「プロプランの時もユーザーが台帳システムに追加された場合は、都度Slackアカウントへの登録やワークスペースへの追加を手作業で行っていました。Enterprise Gridに移行するにあたり、SAML認証を用いて自動的に台帳システムとAzure AD、Slackアカウントを紐づけるような設計を検討していました。しかし、Slackアカウントを手作業で都度判断により追加・管理していたため、自動的に判定するためのルールが明確ではありませんでした」(佐藤氏)
導入前の仕組みにまつわる反省として「誰がどういう根拠でどのグループに所属しているかを明確にすべきだった」と佐藤氏。特に業務委託で複数の部署に関わるスタッフの扱いなど、イレギュラーなアカウントをどのように判定するかで躓いた。「あらかじめ、具体的なユーザーの管理ルールを用意しておく」ということが、アカウント移行の鍵になっていたようだ。
「現在、予定していなかったワークスペースに追加で登録をしたり、外部からのゲストを呼んだりする時は、手作業で管理していますが、基本的には台帳システムに登録したら、Slackにもユーザー登録がされるような仕組みで運用しています。イレギュラーな部分だけは、今後も手作業が残ると思います」(佐藤氏)
透明性の高いコミュニケーションを推進していく
「BE TRUSTED」というグループ全体のテーマを掲げ「従業員同士が信頼しつつ、生産性の高い業務を行う」ためのガイドラインを敷きながらSlackを運用するラクスル。
パブリックとプライベートを使い分けながら情報制御を行うことで、「アクセスが制御された環境下で活発に情報交換がなされる」という目標が達成された。
各社をまたいだ情報のやり取りなども激減し、セキュリティ面のリスクも軽くなった。Botを活用することで、ユーザービリティの向上も図っている。
「2年前にインドとベトナムにもサテライトオフィスを作ったことで、全社的な発信は英語表記を併記するようになりました。ポストに特定の絵文字を押すとBotが英語訳・ベトナム語訳をしてくれるようなアプリを搭載するなど、コミュニケーションをとりやすくなるようなBotは実装しています」(松本氏)
“情報は保護しながらも透明性は高く”という設計のもと、Enterprise Gridで組織ごとにクローズドな環境を作り、その中でオープンなコミュニケーションを行うことで「オープンチャンネルも徐々に本来の意味での『オープンさ』が出てきた」という松本氏。なんと、パブリックチャンネル(制限なく誰でも参加できるチャンネル)とプライベートチャンネル(特定のアカウントのみ参加できるチャンネル)の比率も大きく変化した。
「パブリック率は2020年7月時点でわずか12%。ほとんどがプライベートでやりとりを行っており、情報のオープン化が難しい状況でした。しかし、事業ごとにクローズドなワークスペースを作り、パブリックチャンネルでのやりとりへの移行を推進したことで、現在は半数近くがパブリックチャンネルに。一時期に比べると情報の流通度は向上しました」(松本氏)
Enterprise Gridに完全移行してから約3カ月が経過した現在。今後の方針について、2人は次のように語る。
「ワークスペースを複数持つことは、Enterprise Gridにのみ許された機能・特徴になります。支社ごとにワークスペースを分けて運用することで、オープンなコミュニケーションとセキュアな情報共有の両立がしやすくなりました。今後の運用について、ユーザー管理はヘルプデスクが行いつつ、ガバナンスやルールづくりは各社ごとに運用を委ねていく予定です。集中管理から分散管理へと移行していくことが、大きなロードマップ。アプリとの連携なども現在は申請制にしていますが、今後は組織ごとに判断を委ねていきたいと考えています」(佐藤氏)
「Enterprise Gridに移行する前の、膨大な量のチャンネルが並ぶ状態に、われわれは慣れてしまっていました。現在は、まだまだEnterprise Gridを使いこなせていない状態のように思います。Enterprise Gridならではの機能を活用し、業務内のやりとりと業務外のやりとりの棲み分けを行うことで、必要な情報にアクセスできる透明性の高い状態を確保しつつも、社員間のコミュニケーションの活性化を図っていきたいと思っています」(松本氏)