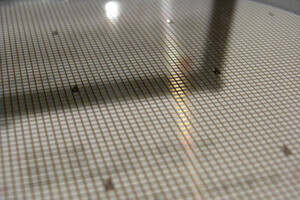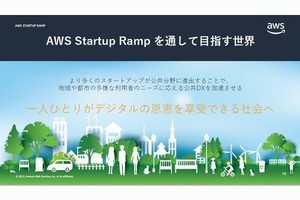チーム・コミュニケーションを円滑にするビジネスのコラボレーションプラットフォーム「Slack(スラック)」。コロナ禍におけるリモートワーク文化が進んだことも相まり、近年は多くの企業が導入を始めている。では、Slackはどのように企業のコミュニケーションを円滑にしているのだろうか。今回は一般社団法人 コード・フォー・ジャパン(CfJ)の事例を紹介する。→過去の「Slackで始める新しいオフィス様式」の回はこちらを参照。
「誰でも参加OK」なオープンソースコミュニティ
まず、CfJは2013年に発足したIT技術による地域課題の解決(シビックテック)を推進する非営利団体である。市民が主体となった地域のコミュニティ作りをサポートするほか、自治体DX(デジタルトランスフォーメーション)やオープンデータを支援する活動などを行っている。
現在、CfJではオープン・コミュニティのプラットフォームとして、Slackのワークスペースを開放している。
シビックテックに興味のある人であれば誰でも参加でき、現在は約7000人がワークスペースに参加。エンジニアを中心に、社会人から学生まで、さまざまなスキルをもったメンバー同士が情報交換を行う。月間アクティブユーザー(MAU)も600~700人前後をキープし続けており、非常に活発な状況だ。
こういった「オープンな情報交換の場」としてのSlack運用がCfJで始まったのは、2016年からだった。Slack全体の企画・運用を行うコード・フォー・ジャパン 副代表理事・陣内一樹氏は導入当初の状況について次のように振り返る。
「導入した2016年の段階では、FacebookのMessengerとグループ機能を活用していました。というのも導入当初は日本語版もなく、エンジニア以外、特にインターンに参加する学生などには、Slackの知名度がまだ低かったんです。2017年以降、日本語版が提供開始されてから、じわじわとSlackへと移行していきました」(陣内氏、以下同)
参加メンバー数が爆発的に伸びたのは、2020年3月。CfJが発表した「新型コロナウイルス感染症対策のためのデータ公開支援」が、SNSを中心に拡散された。東京都の新型コロナウイルス感染症対策サイトと聞けば、思い出す方もいるだろう。
この取り組みをきっかけに「CfJの運営するSlackに、誰でも参加できる」という情報も一気に広まったのだ。なんと、1日の参加申請が数百人にのぼる日もあったという。
「ルールに沿えば誰でもチャンネルを作成できるのですが、基本的にはプロジェクトごとにパブリックチャンネルを立ててもらい、プライバシーやセキュリティに関わるやりとり以外は『誰でも参加OK』な状態でコミュニケーションを取ってもらいます。その結果、チャンネル数も今現在では100以上に増えました。誰でも閲覧・参加できるパブリックチャンネルは、そのうち7割以上。なかには休眠しているプライベートチャンネルもあるため、実質9割以上がパブリック、と言えるかもしれません」
クローズドなワークスペースを追加し情報を整理
しかし、オープン・コミュニティが活性化していくことで、生じる課題もあった。それは、チャンネル数の増加による「情報の乱雑化」と「セキュリティ」である。
「メンバーは毎日、イベントの告知や質疑応答、プロジェクトにまつわる議論をSlackに投げ続けます。そのため、ちょっとでも目を離せばプライベートチャンネルでやりとりしている情報がすぐ埋もれてしまうんです。何より、一歩操作を間違えれば機密情報を大勢のユーザーに誤送信してしまいます。リスクと隣り合わせの状態だからこそ、早急に解決すべき課題だと感じていました」
2021年4月、CfJではSlackが提供するNPO支援プログラムを活用し、有料のプロプランを契約。CfJを運営する20人ほどの職員に向けた業務用ワークスペースを新たに設立した。
そして、一般社団法人として進めるビジネス関連のコミュニケーションや、他社とのやりとりを、すべて業務用ワークスペースに移管したのである。中にはSlackコネクトを活用し、外部ユーザーを招待しコミュニケーションを取るチャンネルもある。
「Slackコネクトで外部とコミュニケーションを行なっているチャンネルは、業務用のワークスペースで20ほどありますね。IT企業が中心ですが、最近ではSlackを導入している行政機関や研究機関などともSlack上でやりとりすることがあります。ちなみにコミュニティ用のワークスペースに入れるメンバーは『誰でもOK、制限ナシ』ですが、業務用ワークスペースに入れるのは我々が招待したメンバーだけ。いずれも他社の事例を参考にしながら運用を行なっています」
新規メンバーが動きやすくなるための仕組みづくり
また、CfJではメンバーのアクセシビリティを高めるための工夫も行う。現在、特定のチャンネルに投稿された情報を全員に通知するための機能も導入する。
「10数人しか入っていないチャンネル内で投稿された内容を、チャンネル外にも知らせたい時のために『リアク字チャネラー』というアプリを導入しました。『リアク字(リアクション文字)』専用の絵文字を押すと、ユーザー全員が入っている“random”チャンネルに投稿が転送される、というシステムなんです」
一方、ストック情報についてはドキュメントやデータベースを一元管理できるクラウドツールである「Notion」を導入し、情報管理を実施。途中からプロジェクトに参加した人が状況を把握しやすくなるよう整備を行なっている。
「今でも少しずつメンバーが増えているからこそ、新規メンバーが長いやりとりを遡って進捗を把握したり、会話へ参加しにくくなったり、ということは避けたいと考えています。今後はメンバー参加後のワークフローや、プロジェクトの議事録などもNotionに集約し、Slackと併用できるのが理想。Notionに職員や理事からのお知らせを書き込んだら、ユーザー全員にSlack上で通知が届くような仕組みを検討中です」
さらに、2023年に一般公開を予定しているドキュメンテーション機能「Slack canvas」の実装にも期待している、という陣内氏。
「あくまでイメージではあるのですが、あらゆるプロジェクトにも通じるような情報の集約はSlack canvas、細かいプロジェクトに関するタスク管理をNotion、と使い分けができると嬉しいです。良くも悪くも情報過多な状態だからこそ、ユーザビリティを高める工夫は今後も続けていければと思います」
Slackがないと業務が回らなくなってしまう
現在、プロジェクトによってはDiscordをはじめ他のツールを活用するなど「コミュニティのプロジェクトメンバーの判断に委ねつつ、柔軟な運用を目指している」という陣内氏。相手に応じ複数のコミュニケーションツールを使いつつも、情報共有の中心となるのはSlackだ。
「他団体とのやりとりなどでSlack以外のコミュニケーションを利用することもあるのですが、やっぱり使い心地が良いなと感じるのはSlack。リアクション文字を使った感情表現など『単なる情報共有』以上のことができるこが魅力だと思います。自然とCfJ内でも『Slackが中心だよね』という流れにはなっていますね」
また、CfJの業務を進めるうえで「Slackじゃないと実現できないこともある」と陣内氏。というのも、同社はフルフレックス、フルリモートのため、基本的にはオンラインですべてのやりとりが完結しているという。
陣内氏は「副業をしているメンバーも多いので、打ち合わせを除けば非同期のコミュニケーションが中心です。Slackがないと業務自体が回らなくなってしまいますし、コミュニティも継続ができなくなってしまう。もはや必要不可欠な存在なんです」と話す。
そして、最後に「だからこそ、目下の課題は『情報にアクセスしやすくすること』です。多くの人がSlackに参加するからこそ、入ってすぐ積極的にやりとりを始めてもらうことにハードルはあると思っています。また、今後も徐々に新規プロジェクトが増え、関係者も複雑化していくはず。フローとストックの情報の使い分けをしながら、アクティブではないチャンネルはアーカイブ化し、外からでは中身がわかりにくいチャンネルはNotionなどで説明を加えるなど、積極的に『居心地の良い環境』へと整えていきたいです」と同氏は述べていた。