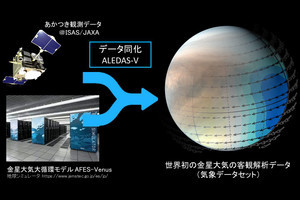東京大学(東大)と神戸大学の両者は3月7日、火星の大気大循環において、これまでスケールの小ささから全球での観測やモデルの再現が難しく、その寄与を定量的に調べることができていなかった「大気重力波」(浮力を復元力とする時空間スケールの小さな波動)の役割を明らかにしたと共同で発表した。
同成果は、東大大学院 理学系研究科の阿隅杏珠大学院生、同・佐藤薫教授、同・高麗正史助教、神戸大大学院 理学研究科の林祥介特命教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国地球物理学連合が刊行する惑星科学を扱う学術誌「Journal of Geophysical Research:Planets」に掲載された。
火星には、6ヘクトパスカル(地球の約6/1000)という薄さだが大気があり、気象現象も存在している。火星の大気大循環はこれまで、軌道上から複数の衛星が観測した温度データや、大気大循環モデルを用いて研究が進められてきた。しかし、それらの研究は特定の期間のみにとどまっており、長期間の観測データに基づく季節平均的描像はまだ十分に解明されていない。
大気重力波は、浮力を復元力とする時空間スケールの小さな波動のことで、大気の主要波動の1つだが、気候モデルでは通常解像できない。ただ近年の火星の大気大循環モデルを用いた研究においては、解像度を上げると大気重力波による大気大循環の駆動力がより大きくなるという指摘がなされていた。しかし、これまでのところ定量的な解明には至っていなかった。
火星はこれまで、人類が最も多くの観測衛星や着陸機、ローバーなどを送り込んできた惑星だ。衛星による火星の大気観測も今では10火星年(地球年で約18年9か月半)以上となり、最近になってその蓄積されたデータを用いた大気再解析データ「EMARS」が公開された。大気再解析データとは、観測データを数値モデルに統合し、現実に近い大気状態を再現する技術を用いて作成されたさまざまな物理量を含む全球一様の四次元グリッドデータセットのことだ。
EMARSの課題は、その解像度が大気重力波を表現するほど高くないという点にある。そこで研究チームは今回、重力波そのものを表現できないとしても、地球の大気の研究において考案された、重力波の役割を定量的に解析することが可能な診断的手法を用いたとのこと。この手法を用いて火星の大気大循環の駆動メカニズムを解析し、地球と火星との比較惑星学的視点からその特徴を明らかにすることを目指したという。
火星の大気大循環は従来、大気角運動量を保存するような「ハドレー循環」が支配的であると考えられてきた。ハドレー循環とは、主に太陽放射で駆動される大気角運動量を保存するような大気大循環のことを指す。地球大気では、主に高度10km以下の対流圏において、赤道域で加熱されて上昇した空気塊が亜熱帯で下降する経度方向に一様な循環のことをいう。しかし、火星の大気大循環に沿って大気角運動量の値が保たれているのは、南北緯約30度より低緯度かつ高度40km以下の領域のみだった。つまり、ハドレー循環は全球で支配的ではなく、この領域に限られることが判明したのである。
そこで次に、ハドレー循環を除く領域における火星の大気大循環の駆動メカニズムが調べられた。まず北半球冬季には、高度約60~80km、北緯50~80度にかけて、地球と比べて4倍も強い北極向きの流れが存在していることが判明。さらに、ここでの大気波動に伴う熱フラックスは小さいことも明らかにされた。これは地球の成層圏循環とは異なり、火星の大気大循環は「ロスビー波」では駆動されていないことを示すという。なおロスビー波とは、大気重力波と並ぶ大気の主要波動の1つで、地球の自転による見かけの力である「コリオリの力」は同一の風速に対しても、高緯度ほど強いことから現れる波動である。また時空間スケールが大きいので気候モデルで解像できる点が、大気重力波とは大きく異なる点だ。
-

北半球冬季における火星大気質量流線関数Ψの緯度高度断面。赤は時計回り、青は反時計回りの循環を表す。(a)全流線関数。(b)大気大循環モデルで解像される潮汐波・ロスビー波の流線関数への寄与。 (c)大気大循環モデルで解像されない大気重力波の流線関数への寄与(出所:東大Webサイト)
そこで、地球大気の研究で提案された手法を用いたモデルで、解像できない大気重力波による駆動力を間接的に推定したとのこと。その結果、特に高度60km以上の中高緯度において、大気重力波が主な駆動源であることが確かめられた。これは、地球の中間圏循環の駆動メカニズムと類似しているという。
-

地球の1月の気温(左)と火星の北半球冬季の気温(右)の緯度高度断面の比較。黒い矢印付き曲線は、大気大循環の構造が模式的に表されたもの。ロスビー波、潮汐波はどちらも大気大循環モデルで解像されるが、大気重力波は解像されない(出所:東大Webサイト)
研究チームは今回の研究成果について、火星大気大循環モデルの検証・改善につながるとし、より現実に近い火星大気の全球規模の変動が解明されることが期待されるとする。また、今回明らかにされた火星中層大気の描像は、火星電離圏を含む上層大気との相互作用の解明にも寄与するという。これらは、火星全大気の包括的な理解の進展につながることから、探査機の着陸時期における火星の大気現象予測など、将来の探査計画に役立つ可能性があるとしている。