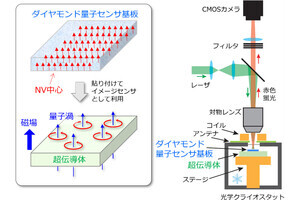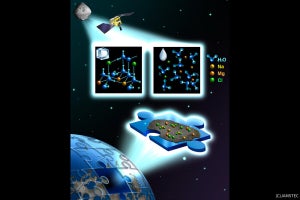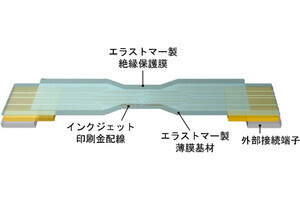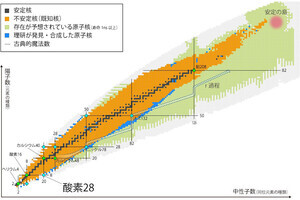東京工業大学(東工大)、大阪大学(阪大)、科学技術振興機構(JST)、富山大学、静岡大学、分子科学研究所(分子研)の6者は9月20日、1.5Vの乾電池1本をつなぐだけで光る青色有機ELの開発に成功したことを発表した。
同成果は、東工大 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所/阪大 接合科学研究所の伊澤誠一郎准教授(JSTさきがけ研究者兼任)、富山大の森本勝大准教授、静岡大の藤本圭佑助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。
OLED、つまり有機ELはすでに大型テレビやスマートフォンなどに用いられるなど産業化に成功しているが、青色の有機EL発光素子に関しては、いまだに駆動電圧が高く消費電力が大きいことや素子の長期安定性が低いなど課題を抱えている。さらに青色発光は光エネルギーとしては3eV程度と高いため、低エネルギーの赤、緑の発光と比較して、有機分子の分解による有機EL素子の劣化を引き起こしやすい。今後、有機ELが中型ディスプレイや白色照明などに応用範囲を拡大するためには、青色発光素子の電圧ならびに消費電力の低減、安定性の向上は解決すべき課題である。
そこで研究チームは今回、2種類の有機分子の界面を使った独自の発光原理を用いて、乾電池1本(1.5V)という低電圧で光る青色有機ELを開発することにしたという。その発光メカニズムは、まず電子と正孔(ホール)がデバイスに注入された後で、2種類の電子ドナー/アクセプター分子の層の界面で再結合を起こし、電荷移動「CT状態」という励起状態を形成する。次に、CT状態からエネルギー移動が起こり、ドナー層中で「三重項励起状態」(T1)を生成。その後、ドナー層中で2つの三重項励起状態から、三重項-三重項消滅により高エネルギーの「一重項励起状態」(S1)を作り出す「アップコンバージョン過程」を経て、青色発光は実現される。
この発光メカニズムを実現するドナー/アクセプター分子の組み合わせを明らかにするため、青色発光を示すドナー分子として5種類の「アントラセン誘導体」を、アクセプター分子として14種類の「ナフタレンジイミド誘導体」を探索することにしたという。
これらのドナー/アクセプター分子から最適な組み合わせを用いて、有機ELデバイスを作製。462nmに最大発光強度を持つ青色発光(光エネルギーで2.68eVの青色の発光)が観測されたとする。印加電圧に対する発光輝度の立ち上がりが測定されたところ、青色発光が1.26Vという低電圧から認められ、スマートフォンディスプレイ程度の発光輝度である100cd/m2には1.97Vで到達したという。このように1.26Vという低電圧で青色の発光が認められたことから、1.5V乾電池1本をつなげるだけで青色光が実現された。
今回のような超低電圧での青色発光は無機材料の青色LEDでも不可能であるため、有機、無機材料、双方を含めても世界最小電圧で発光する青色LEDの開発に成功したといえるとする。
また、今回開発された素子の安定性を検証するため、発光輝度が1000cd/m2の状態で連続駆動した際の輝度の低下に関して、従来報告されている青色りん光の有機EL素子との比較が行われた。その結果、従来の青色りん光素子と比較して90倍程度、素子寿命が長いことが確認されたという。
青色光は光エネルギーが大きいため、発光する有機分子の分解を引き起こしやすく、安定性が低いという問題が指摘されているが、今回の発光メカニズムは低エネルギーの三重項励起子から青色発光を導くため安定性に関しても有利であることが明らかとなった。
これにより、有機ELの課題だった青色発光にかかる電圧を低減することが実現された。今後、さらに研究を進展させれば、大画面テレビやスマートフォンディスプレイなどの機器の消費電力を低減できる可能性があるとしている。
なお研究チームは今後、今回の技術をディスプレイ機器へ応用するため、より色純度が高いスペクトル幅が狭線な青色発光を低電圧で実現することを目指すという。さらに、今回のメカニズムの発光効率を向上させることで、従来技術よりも消費電力の低減を達成するとした。また発光色を白色化することで、超低電圧で光る白色有機EL照明の開発にもつながるとしている。