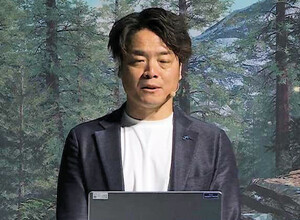ハイフライヤーズは、キートスチャイルドケアやキートスベビーケアの名称で、千葉県内で11の認可保育園の設置・運営を行っている。現在、合計550名ほどの園児を約170名の職員で預かっている。
そして同社はさまざまなITツールを駆使して、職員間のコミュニケーションを活性化し、業務の効率化を行っている。本稿では、同社が取り組む保育園におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)についてお届けする。
ITサービスの活用で離職率を低下
同社が活用しているITサービスの一つがコミュニケーションサービスだ。導入のきっかけは離職率の高さだったという。
同社では2019年ごろ、相次ぐ職員の退職に悩んでいた。当時の状況について、ハイフライヤーズ 保育運営本部 本部長 キートス統括園長の日向 美奈子氏は次のように語る。
「退職理由を聞くと、人間関係は良いという回答がもらえるのですが、本当の理由は、正直分かりませんでした。そこで、給与面や有給などの福利厚生を整えることを検討しました。ただ当時、マンションを借り上げ無償で提供、初任給は実質30万円、有給も100%消化している状況でした。そのため、給与や福利厚生を充実させても、職員をつなぎ止めることには結びつかないという実感がありました」
-

ハイフライヤーズ 保育運営本部 本部長 キートス統括園長の日向 美奈子氏。右はハイフライヤーズ 事業企画本部 広報部 部長 石井渚氏。左は、システム開発を担当するハイフライヤーズ 事業企画本部 渡久地翔氏
そこで同社は、新たに表彰制度を取り入れ、毎週1回、園長が集まってミーティングを行い、頑張っている人を表彰する仕組みを導入した。それでも表彰された人が辞めていくという状況が続き、効果は得られなかったという。
何をしたらいいのかわからない状況だった時、介護施設を回っている企業の人に、「サンキューカード」を職員間で送り合っているという話を聞き、これを実践した。ただ、手書きのカードは保管が難しい上、1対1のコミュニケーションになり、全体には広がらないという課題もあった。そこで、たまたま広告で知った「Unipos(ユニポス)」というコミュニケーションサービスを知り、導入したという。
「Unipos」は、仲間同士に感謝称賛のメッセージと「ピアボーナスR」という少額のボーナスを送り合えるITサービス。その書き込みを見た人がそれを称賛する拍手を送ることができる「いいね!」のような機能を持つ。
「当社は2010年に創立してから、園数を急拡大してきたので新卒採用が多く、職員は20代前半が大半です。その職員たちが惹かれるものを考えたとき、SNS世代ということに着目しました。普段、自撮りしてそれをアップして、『いいね!』を送り合っているのを垣間見る中で、上司からの表彰という評価ではなく、一緒に働く人たちからの承認やありがとうという感謝がほしいのではないかというところにたどり着きました」(日向氏)
投稿内容は、園をまたいだすべての職員が閲覧できる。年間を通して毎月95%の職員が利用しているという。
また同社は、早退・遅刻・欠勤がなく、月の投稿数が30を超えた職員には、有給を与える制度も導入した。これにより毎月、職員の半数ほどが有給を取得しているという。これらの取り組みの結果、離職率は徐々に低下したという。
なお、同社は職員間の事務連絡用ツールとして、Slackも利用している。
デジタル連絡帳「きーとすのーと」で登園確認を確実に
そのほか、保護者との連絡帳の代わりに「きーとすのーと」というサービスを自社開発し、利用している。「きーとすのーと」では、保護者からの出席・欠席、お迎え時間の連絡、保育園からの連絡やお知らせ、フォト機能、成長記録などの機能を持つ。
「きーとすのーと」は、保護者から先生に対して「ありがとう」という感謝のメッセージを伝える機能を持っており、職員のモチベーションアップにつながっているという。
加えて、同社はSalesforceをデータベースとして活用しており、「きーとすのーと」のデータもSalesforceに保存されている。「きーとすのーと」には、欠席だけではなく、出席を連絡する機能もあり、欠席の連絡がなく、朝9時30分までに登園が確認できない場合は、自動的にSlackにメッセージが流れ、職員が保護者に電話して確認することになっている。
過去に関西の保育園で起きた保護者が園児を登園させたつもりが、実際には登園しておらず、園児が車の中で熱中症で死亡とするといった事故を受け、このような事態を防ぐための仕組みを構築したという。
「きーとすのーと」には職員が1日あったできごとを園児一人ずつ入力しているが、以前は手書きのノートだったため座って記入する必要があり、昼寝の時間にまとめて行っており、手間がかかっていた。
「きーとすのーと」を導入してからは空き時間を見つけて入力することができるようになり、子どもと触れあう時間を増やすことができたという。現在は、各保育士が空き時間を見つけて園が用意したiPhoneを用いてデータを入力しているため、作業の軽減が図られているという。
サービスを自社開発する理由について、ハイフライヤーズ 事業企画本部 広報部 部長 石井渚氏は、次のように説明した。
「既存のアプリの場合、ほしい機能がなかったり、カスタマイズが思うようにできなかったりします。しかし自社開発であれば、保育園として必要なことや保護者が求めていることをどんどんアップデートできます。いろいろなアプリを使いこなすのは大変ですが、Salesforceの画面からどこにでも飛べるようなっているところは工夫しています」