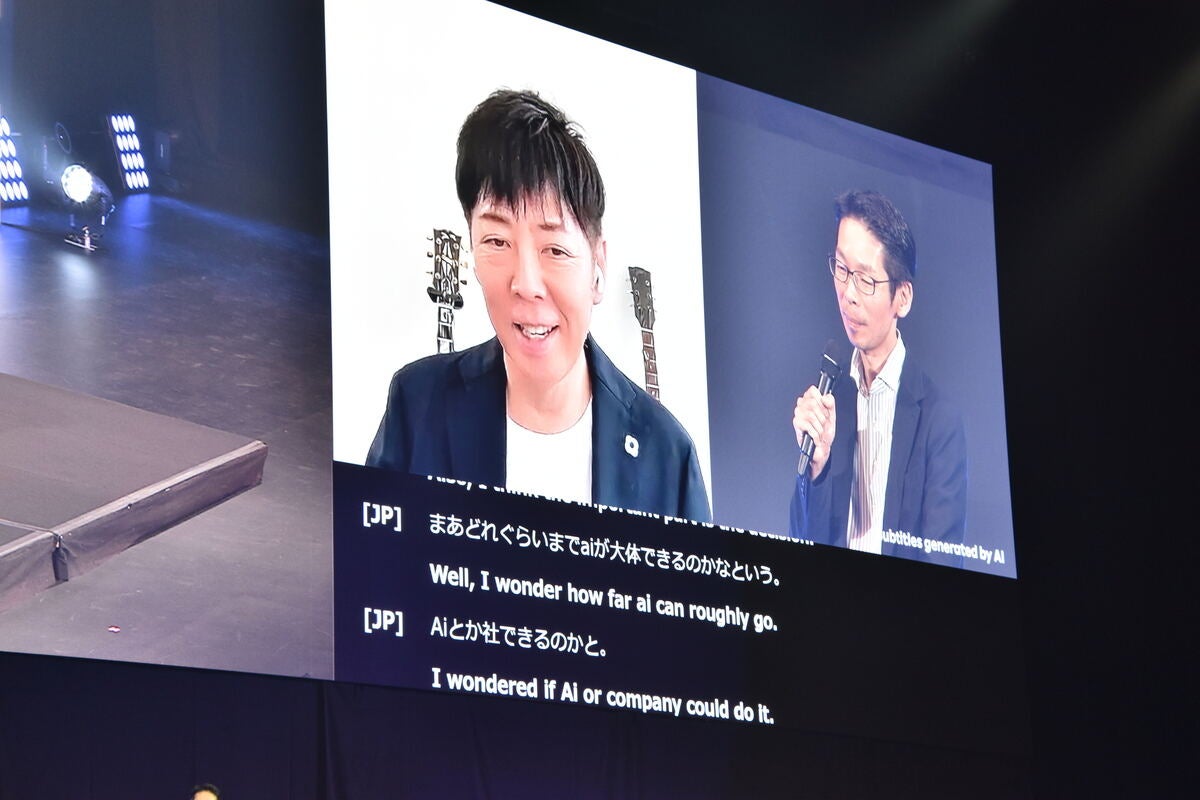楽天は8月2日~4日に自社イベント「RAKUTEN OPTIMISM2023 ビジネスカンファレンス」を開催した。同イベントでは、同社の三木谷浩史社長から楽天×OpenAI社の協業が発表されるなど、「AI」をテーマとしたセッションが数多く実施された。
その中から本稿では、3日に開催された「AI × クリエイティブ:未来を拓くイノベーションの可能性」についてレポートする。同セッションには楽天グループ 副社長執行役員CMOの河野奈保氏、京都大学大学院 理学研究科教授 物理学者の橋本幸士氏、そしてクリエイティブスタジオSAMURAI 代表の佐藤可士和氏が登壇。AIとクリエイティブの関係性について議論した。
橋本教授「ここ5年でAIは大きく進化した」
橋本氏は、同氏が提唱する独自の学問「学習物理学」の権威として知られる。学習物理学とは、機械学習と物理学の理論を統合して、物理学の課題解決を目指す考え方である。
学習物理学者の立場から、橋本氏は「ここ5年でAIは大きく進化した」と切り出した。同氏曰く、かつてAIは物理学において「興味のある物理学者のみが追い求めている研究だった」が、今ではどの物理学者も常に動向を追う“必修科目”に変わっているという。
橋本氏の研究にもAIは活用されており、人間が認識できない物理現象をAIに実証させたり、現象解明のための方程式を解かせたりしているそうだ。
「物質や事象を判断する際に、人間であれば実際に実験をしてみないと解明ができないものも、AIが人間の知能を超えて助けてくれるようになりました」(橋本氏)
“AI佐藤可士和”は生まれるのか? クリエイティブ×AIの行く末
河野氏によれば、冒頭で紹介した今回のセッションタイトルも、ChatGPTによって生成された複数の候補から、議論を重ねて採用されたものだそう。キャッチコピーなども含め、クリエイティブ領域でもAIの活用が進んでいることがうかがえる。
セッションのタイトルについては佐藤氏も「外さない答えは出てきているが、驚くようなモノはない」と評価した。
人間のアイデアを凌駕するようなタイトルにはならなかったが、こうしたAIが人間を超越する「シンギュラリティ」について、佐藤氏はその“現在地”に興味を持っていると語る。
「10年前はまだシンギュラリティの実現は難しいという話でした。遠い未来、クリエイティブディレクションやアイデアの着想、判断が、どれほどAIに代替されるのかに興味があります。シンギュラリティが起きて、“AI佐藤可士和”は生まれるのかどうかが知りたいですね」(佐藤氏)
これに対し、橋本氏は「まだシンギュラリティには達していないが、段階を踏んでいる」との見解を示す。
「ChatGPTのような生成AIなど、汎用的な人工知能が登場しました。これによってシンギュラリティ実現に向けた大きな段階をクリアしたと思います」(橋本氏)
続いて橋本氏から佐藤氏へ「AI佐藤可士和に登場してほしいと思いますか?」との問いが投げかけられた。ここで佐藤氏はライバルの登場に好奇心をのぞかせる。
「僕は登場してほしいと思います。AIから刺激を受けたいですね。自分自身が周囲から刺激を受ける、ということがクリエイティブにとっては大事だと思っています。新たなアイデアの見取り図を見た時に、自分の価値観が壊れて、新しいものを生み出せるのではないかと思いますね」(佐藤氏)
佐藤氏「AIをガンガン使いたい」
生成AIの発展により、橋本氏は「言葉の定義が変わってくる可能性がある」と予想する。例えば数学は、古き時代からさまざまな定義が証明されてきた。その中で“自動数学”の登場が現実味を帯びているという。
これは、AIが数学の新たな定義を予想し、その定義を人間の行動なしに証明できる可能性があるということだ。実現された場合、自動数学を旧来扱ってきた「数学」として認めていくのか、といった、これまでの常識を覆すような議論がなされることも考えられる。
では、本セッションのテーマ「クリエイティブ」はどう定義されるのだろうか。橋本氏は「感じるもの」と表現した。
「たくさんのアイデアを自由に試せる環境や、間違いを許容する文化を作っていく必要があると思います。そういった失敗や経験を積み重ねて、一握りのものすごいアイデアが生まれてくるのではないでしょうか」(橋本氏)
佐藤氏も、今回のセッションでAIに対する知見が広がったと話す。
「橋本先生のお話を聞いて、モヤっとしていた部分が少しクリアになりました。僕は変化に対して積極的な人間ですので、AIをガンガン使っていきたいと思います」(佐藤氏)
最後に、河野氏も「楽天では皆さまをあっと驚かせるようなアイデアや新サービスを、AIを使って生み出していきたい」と意気込みを語り、講演を締めくくった。