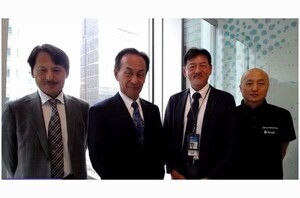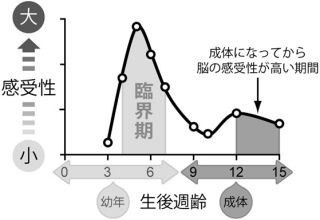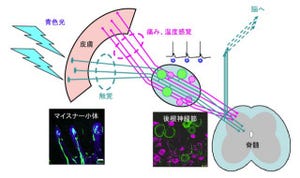京都大学は8月17日、全世界で利用されている実験用ラットの「シロネズミ」117系統のDNAを調べ、すべての系統が共通してたった1つの「アルビノ突然変異」を持っていることを突き止め、そのアルビノ変異は、まだら模様を持ったラット「まだらネズミ」に生じた可能性が高いことを判明したと発表した。
このことは、ラットが実験動物化された19世紀後半、あるいはそれ以前に、まだら模様のラットがまず利用され、その繁殖の過程でシロネズミが出現したと考えられるという。そのシロネズミ(アダムあるいはイブ)の子孫たちは、性質が温順で人にもよく慣れたことから、実験動物として広く用いられるようになったという推測だ。
成果は、京大 医学研究科の庫本高志准教授、同・芹川忠夫教授、同・中西聡技術専門職員らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間8月16日付けで米オンライン科学誌「PLoS ONE(Public Library of Science One)」に掲載された。
実験用ラットとは、正式な学名は「Rattus norvegicus」、和名は「ドブネズミ」で、世界中で広く用いられている代表的な実験動物だ。野生のドブネズミを長い間かけて家畜化し、動物実験に用いるために実験動物化したものである。成熟体重は雌で200~400g、雄で300~700g。鼻先から尾の根元までの体長は20~25cm、尾長は15~25cmという体格だ。
ラットは1850年ごろから学術研究に用いられた。ラットを利用したもっとも古い学術論文は、栄養学に関するもので、1863年にLancetに公表されている。1885年にはドイツ人Crampeが、ラットを用いた交配実験を行ってメンデルの「遺伝の法則」が哺乳動物でも成り立つことを示している。
現在でも、ラットは、医学、生物学、生理学、薬理学、神経科学、栄養学、遺伝学などのさまざまな分野で利用されている重要な実験動物だ。その利用数は年間数百万頭規模だ。日本では、平成22年度で約190万頭のラットの販売実績があった(日本実験動物協会調べ)。
19世紀半ばから現在まで、主に利用されているラットはシロネズミと「まだらネズミ」だ。特にシロネズミは広く用いられている。そのため、シロネズミはラットの代名詞ともなったほどだ。現在でこそ、ラットという言葉が用いられているが、古くは、シロネズミ、ダイコクネズミ、ラッテなどと呼ばれていた。
なお、日本では、ラットをライフサイエンスの進展に不可欠な資源(リソース)としてとらえ、その収集・保存・提供体制を整備するために、2002年よりナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」が実施されている。
そして実験用シロネズミ(画像1)だが、これはラットのアルビノ変異体だ。メラニン合成に必須の酵素「チロシナーゼ」活性を先天的に欠損しているため、メラニン色素を作り出すことができず、白い毛色となる。また、眼球のメラニン色素も作り出すことができないので、眼底の血流が外から見え、赤い眼をしている(フィクションなどではアルビノの眼は白目の部分がきれいに描かれることが多いが、それは間違い)。
もう一方の実験用まだらネズミとは、ラットの「Hooded(頭巾斑)変異体」。Hooded変異をホモに持つことで、体毛の色素分布が変わり、胸部から臀部が白くなる。頭部から上腕部にのみ色素が分布し、あたかも「頭巾」をかぶったかのような模様になるのが特徴だ。そのため、このような模様を「頭巾斑」と呼ぶ。頭巾斑変異体では、背骨にそって色素がドット上に分布するのも特徴である。
|
|
|
|
画像1。実験用シロネズミ。先天的にメラニン色素が合成できないために、白い毛色、赤い眼となる(ナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」より転載) |
画像2。実験用まだらネズミ。Hooded変異をホモに持つと、特徴的な模様となる。これを「頭巾斑」模様と呼ぶ(ナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」より転載) |
現在、シロネズミ系統は100系統以上存在し、少なくとも年間数百万頭が利用されている。これらのラットが、すべて同一のアルビノ変異を持つのか、あるいは特定のシロネズミ系統ごとに別々のアルビノ変異を持つのか定かではなかった。
また、シロネズミとまだらネズミはどちらが、先に発見、家畜化されたのかも不明だった。
古い文献でも、シロネズミとまだらネズミが併記されており、その起源は明確に書かれていない。例えば、ウィスター研究所初代所長のDonaldson(1915)は、「ラットは、野生または飼い馴らされたものを入手できた。後者は、アルビノか、まだらが主であった。アルビノの由来は、1つなのか複数なのかわからなかった。ヨーロッパのコロニーに関係しているのかもわからなかった。」と記していることがわかっている。
そこで研究チームは今回、最新の遺伝子解析技術を使って、シロネズミの起源を探ることにした次第だ。ナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」を通じて世界各国から集められた117系統のシロネズミ系統を対象に、シロネズミの原因遺伝子であるアルビノ変異の有無が調べられた。
その結果、すべての系統が同一のアルビノ変異を持っていることがわかったのである。つまり、世界中で用いられている数百万頭のシロネズミには、起源となるシロネズミがいたことがわかったのだ。
さらに研究チームは、まだらネズミの原因遺伝子が「Kit遺伝子」の変異であることを見つけ、この変異の有無を117系統のシロネズミ系統で調べた。その結果、すべてのシロネズミ系統が、Kit遺伝子の変異を持っていることが判明したのである。
以上の結果から、(1)シロネズミの起源となる一頭のネズミ(アダムあるいはイブ)がいた、(2)そのシロネズミは、まだらネズミから出現した、という2点が推測された。
つまり、最初に野生ネズミにHooded変異が生じてまだらネズミが出現し、次いでまだらネズミにアルビノ変異が生じシロネズミが出現したと考えると説明がつきやすいというわけだ。
今回の研究は、シロネズミの起源を明らかにしたと同時に、新たな謎として「まだらネズミの起源は?」を生み出すきっかけとなった。
これにこ耐える1つのアプローチが、ゲノムの比較研究だ。Kit変異の近傍のゲノム領域には、Kit変異が生じたラットのゲノム情報が残されている可能性がある。この領域を対象に、世界中の実験用ラット、愛玩用ラット、あるいは野生ラットのゲノムを比較することで、Kit変異がどのようなラットに生じたのかがわかるかも知れないという。
また別のアプローチとして、古い文献調査という手段もある。例えば、ハーバード大学教授のCastleは、1914年The American Naturalistに、「まだらネズミは、1900年ごろJapanese ratと呼ばれていた」という報告などだ。
また、日本では江戸時代、ネズミを飼い馴らしてペットとして飼うという文化があった。ネズミを飼うガイドブックとして、「養鼠玉のかけはし」(1775年)や「珍玩鼠育草」(1787年)が出版されていた。
もしかしたら、日本のまだらネズミが欧州、米国へと渡り、実験用ラットのアダムあるいはイブになったのかも知れない。21世紀のナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」事業とあわせて、「日本はラットを用いた科学研究を支えている」と思いを巡らせることができると、研究グループはコメントしている。