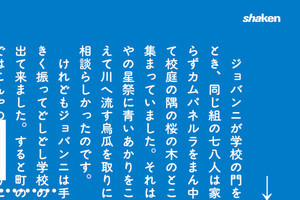フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
ぶらぶらする仕事
1923年 (大正12) 3月、森澤信夫は大阪から上京し、星製薬に入社した。社長の星一から直々に誘われてのことだった。
信夫は上京すると、前回同様、星製薬商業学校の職員室に泊まりこんだ。驚いたのは工場長の星三郎だ。なにしろ信夫は、職員室に住みつく気でいる。
「困ったやつが来たぞ。いいかげん、出ていってくれ。だれか、森澤に下宿を見つけてやってくれ」
こうして信夫は、代々木の素人下宿に入ることになった。
入社して工場勤めがはじまったものの、信夫には決まった仕事がなかった。特定の部署に籍を置いたわけでもなく、所属もはっきりしない。星には、「きみはどこにも所属しなくてよい。工場内を自由にまわって、なにかと見てくれればよい。なにか気づいたことがあったら、私のところに直接言ってきたまえ」と言われた。職工でもない、機械のオペレーターでもない。社長直属のような立場だが、もちろん秘書でもない。決まった仕事がないにもかかわらず、信夫の初任給は月給80円だった。当時、大学卒でも初任給は50円もらえれば上等で、ふつうは3、40円が相場という時代。信夫の給料は破格ともいえる金額だった。
しかたがないので信夫は、星の言いつけどおり、工場のなかをぶらぶらと歩きまわって過ごした。工場には、若い女性工員が多かった。信夫はいつしか、彼女たちの注目の的になった。
「あのひと、なんだろう? 毎日工場のなかを歩きまわっているだけで、なにも仕事をしていないみたいだけど」
「わからないけど、ちょっといい男じゃない?」
彼女たちはやがて信夫に「八幡様」というあだ名をつけた。信夫の姿を見るたびに、
「八幡様がまわっておみえだよ」
とささやきあうのだった。
おもしろくないのは男性社員たちだ。自分たちよりも高い給料をもらって、ただ工場のなかをぶらぶらと歩きまわっている。彼らは信夫をやっかみ、その高給にむらがった。信夫の下宿には絶えず悪友が訪ねてきて、給料の大半は彼らの飲みしろに化けてしまった。
星は信夫に高給を与えただけでなく、オートバイも貸してくれた。「オートバイにでも乗って遊んでいろ」と言うのだった。
車中の講演会
毎日工場を歩きまわっているうちに、信夫にはいろいろなことが見えてきた。工場のシステムや、作業現場のこまかなことが理解できるようになったのである。
たとえばある現場で、女性工員が包装作業をおこなっているところを見て「ここをこう変えたら、もっと能率が上がるかもしれないぞ」と気がつく。また、ある機械を見て「このレバーは使いにくそうだ。ここを改良するとずいぶん使いやすくなるぞ」といった意見が思い浮かぶようになってきた。信夫は機会あるごとに、そうした意見を星に伝えた。星はいつも「うん、そうか、そうか」と耳を傾けてくれた。
星はことあるごとに、信夫を車に同席させた。先方に到着するまでのあいだ、ひとしきり信夫に講義をする。そして用事が済むまで信夫を車中に待たせ、帰途、ふたたび講義の続きをはじめた。星は信夫が入社した1923年 (大正12) 3月に、『科学的経営の真諦』(星製薬商業学校)というテキストをまとめている。これは自己発見、自己開発、健康、意志、思考、努力、親切、礼儀、知識、能率、組織、広告……といった多岐にわたる項目について、全1000条で要点をまとめた本で、1922年 (大正11) の欧米外遊を経て、星製薬商業学校の学生や特約店の店主たちに説く必要があると感じた内容を記述している。
社会経済から人生論まで、きっと『科学的経営の真諦』にまとめたような内容も、星は信夫に説いて聞かせただろう。星は自身が1922年 (大正11) にアメリカでエジソンからもらった〈成功しない人があるとすれば、それは努力と思考をおこたるからである〉という言葉を愛し、この言葉をしょっちゅう引用した。また、〈文明の最大問題は人間の能率である〉〈商品をして活動せしめよ〉〈思考は生産なり〉といった言葉も好んで口にしたという。[注1] 信夫は星のことを「社長」ではなく「先生、先生」と呼んで慕った。
一方で星は、信夫を人に紹介するとき、「これは私の社の小エジソンです」「発明家です」と言ったという。
「発明」は、星製薬のモットーとしている「親切第一」と同じく、星が大事にしていることのひとつだった。星は、特約店と社員教育のためにみずから執筆した「星製薬本領」にも〈改良発明は永遠無窮なることを知り、絶えずそれに向って企図を怠る勿れ〉という項目を掲げていた。[注2]
-
五反田のTOCビル屋上には、星製薬五反田工場にあった「親切第一稲荷」の社がいまでもある。ただし現在の名称は「氷川神社」となっている (1990年頃は「孫太郎稲荷」だった。この写真は、2023年1月撮影) [注4]
入社して半年が過ぎた1923年 (大正12) の8月末、信夫は星から命じられ、大阪出張におもむいた。戻って星に出張の報告ができるのは、9月1日の予定だった。
(つづく)
[注1] 馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974 p.87
[注2]大山恵佐『努力と新年の世界人 星一評伝』大空社、1997 p.155
[注3]〈稲荷信仰の篤い福島で生まれた星一は、強羅に主殿を置く「親切第一神社」を工場や営業所に祭っていた。しかも稲荷は潰すと祟られるというので、ビルの屋上に移されるケースが多い。〉荒俣宏『大東亜科学奇譚』ちくま文庫、1996 p.136/初出は筑摩書房、1991
ちなみに、SF作家、ショートショートの神様として知られる星新一(星一の長男/1926-1997)の本名は「親一」で、星製薬のモットー「親切第一」からとられたという
[注4] 現在の氷川神社の撮影は筆者。キャプション内容は、荒俣宏『大東亜科学奇譚』ちくま文庫、1996 p.140/初出は筑摩書房、1991 より
【おもな参考文献】
馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974
沢田玩治『写植に生きる 森澤信夫』モリサワ、2000
産業研究所編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代(1) 』産業研究所、1968 pp.185-245
「写植に生きる 森沢信夫」『男の軌跡 第五集』日刊工業新聞編集局 編、にっかん書房 発行、1987 pp.169-204
星新一『明治・父・アメリカ』新潮文庫、1978/初出は筑摩書房、1975/電子版は新潮社、2011(25刷改版、2007が底本)
星新一『人民は弱し 官吏は強し』新潮文庫、1978/初出は文藝春秋、1967
大山恵佐『努力と信念の世界人 星一評伝』大空社、1997/初出は共和書房、1949
荒俣宏『大東亜科学奇譚』ちくま文庫、1996 p.136/初出は筑摩書房、1991
『家庭医書』105版改訂、星製薬、1924/初版は1910
【資料協力】
株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影