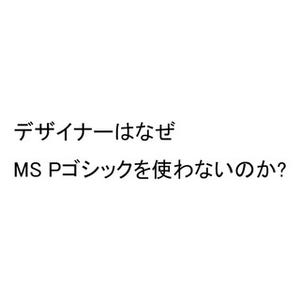種字彫刻師から書体デザイナーへ
モトヤのデザイン部長、のちに技術顧問となった故・太佐源三氏は、橋本さんの最初の師匠だった。
「モダンなひとでした。まだ住みこみの徒弟制度も残っている時代、仕事は師匠の背中を見ておぼえろという職場も多いなかで、太佐さんは言葉でも教えてくれる方でした。神戸の芦屋にお住まいのクリスチャンで、歌がとてもうまかった」(橋本さん)
太佐源三氏は、1897年(明治30)生まれ。
太佐氏の父はもともと東京・牛込の印判屋に生まれ、大阪でも印判彫刻を手がけていたが、明治初年には銅板の彫刻師として紙幣版製作などに従事し、その後、活字のもとになる種字の彫刻をおこなうようになった。父の友人に築地活版製造所の種字彫刻師・竹口芳五郎氏がおり、太佐氏の彫る明朝体は、その流れをくんでいる。(*1)
太佐氏自身は、父の仕事に接するうちにおぼえたのが、種字彫刻の道に入るきっかけとなった。1920年(大正9)、大阪工業専修学校高等部機械科を卒業すると、大阪三有社に入って種字彫刻に従事し、三有社丸ゴシックを完成させた。
1929年(昭和4)には種字彫刻師として独立し、朝日新聞社などの種字を彫刻した。現在でもそうだが、新聞社は、各社が独自の書体をもっている。朝日新聞社の本文用明朝体を彫ったのは太佐氏である。
この時代、活字デザインは「描くもの」ではなく「彫るもの」だった。使用サイズ原寸の種字を、鏡文字の状態で凸状に彫ることによって、活字のデザインは表されたのだ。種字を彫るのは、活字の大きさの鉛合金の角柱だ。
〈彫刻者は活字になる文字のレイアウト、デザインから、他の活字と並んだときのバランスを考えて彫刻刀を振わねばならない。その上、この文字面は印刷された時正像になるが、彫刻する時には逆像即ち左文字である。この左文字の状態で、組版にした時の字並びに狂いないものをと、いわゆるヨリ、ヒキ、上り、下りまでを考えながら刻むのだから、その苦心…というよりは高度の技術と熟練が要求されるのである。〉(*2)
これは、太佐氏が種字彫刻師の仕事について書いた文章だ。手で彫刻するいちばん小さいサイズは7号活字だったという。7号とは5.25ポイント=約1.8mm。一辺2mmにも満たない活字材の表面に、左右逆像の文字を彫刻していたのだ。太佐氏は、あらかじめ筆で文字を朱で下書きして彫っていたという。(*1)
1940年(昭和15)、朝日新聞社活版部に入社して種字彫刻に従事。しばらくして一度活版部を離れるものの、1949年(昭和24)に国産ベントン彫刻機を朝日新聞社が導入したことにともない、再び活版部に配属され、母型係長となった。
このとき太佐氏は「活字彫刻のための刀を筆に持ちかえた」。それまでの種字彫刻から、方眼の入った原字用紙に鉛筆や筆で文字をデザインする仕事に変わったのだ。そこで太佐氏が心がけたのは、「読みやすい新聞文字」だった。漢字の画数の多い少ないによって極端に印刷面の黒みが変わることなく、明るくて読みやすい文字にしたい。その思いで、朝日新聞の原字デザインに打ちこんだ。
一方モトヤは、1949年(昭和24)に国産ベントン彫刻機が発売されるやいち早く導入したものの、あらたな原字の描き手が見つからず困っていた。
〈そういうデザインをやる人がほとんどいないので、凸版印刷とか、いろいろ大手の印刷会社でデザインをしているような人、あるいは有名な書家に頼みまして、とにかく明朝体を書いて出発したのですけれども、なかなか思い通りのものが書けない。その当時の金で1枚50円から100円ぐらい、いまの時価にしたら何千円(1万円近いか?)もするような代金を出して書いて、いろいろ母型を彫ってみると、目も当てられないような文字になるということがありまして、つくっては捨て、つくっては捨てという時代が2年ぐらい続きました。〉(*1)
当時のモトヤ社長・古門正夫氏は、ベントン用の原字デザインの苦労についてこう語っている。
古門氏は結局、デザインが一番大切と考え、自分自身で古い活字の印刷物を引き伸ばしたりして、なにがデザインのポイントなのか、3年ほどかけて研究した。さらに、朝日新聞社の彫刻師だった太佐源三氏の腕に目をつけ、1953年(昭和28)、太佐氏が同社を56歳で定年退職になるのを待って、デザイン部長としてモトヤに招いた。
〈太佐は明朝体・ゴシック体が得意で、一番最初にいまも評判のよい明朝を手がけたのであります〉(古門氏)(*1)
モトヤでの太佐氏の最初の仕事は、モトヤ明朝のベントン用原字デザインだった。
1958年(昭和33)にモトヤが発行した書体見本帳がある。ベントン彫刻機による彫刻母型がある程度、普及した時期のもので、すでに12台ものベントン彫刻機を導入し(国産ベントン彫刻機は当時1台80~100万円だった)その母型の質に自信をもっていたモトヤは、見本帳の序文で〈「美しい印刷は書体の良いベントン活字を用いなければ出来ない」とゆうことは今や印刷業者の常識となった〉と高らかに宣言している。(*3)さらにこの見本帳のおもしろいのは、書体の組見本の文章が、同社の活字にまつわる内容になっていることだ。
新聞用13段(9ポイント)扁平明朝の組見本は、美しい印刷には優秀な書体の母型が大事だということを語った文章になっており、そのなかに「餅は餅屋」という小見出しで始まる一文がある。
〈活字の書体にしても生かじりでデザインしたところでロクな物は出来ないに決っている。それよりも充分研究を重ねた優秀な書体を吟味して買った方が利口ではないか。如何に大印刷所、大新聞社と雖も書体の研究となると単なるこの一部分にそう大きな費用もかけられないし、又立派な書体を作ることは天才的技術を持った一部の人々の独占であるといっても過言ではない。実はそれ程困難な仕事だと言える。その人を得るには「運」と「根気」と「金」がかかる。弊社もこのデザイナーの獲得には心血をそそいだのである〉(*3)
「その人」とは太佐源三氏のことだろう。古門社長がどれほど太佐氏の入社を熱望したかが想像できる。
読みやすい文字 デザインのポイント
太佐源三氏がモトヤに入社したのは1953年(昭和28)1月のこと。古門社長からの依頼は「可読性が他社の文字よりはるかによい漢字、モトヤ明朝体の完成」だった。
その当時、世間で見かける印刷物で、太佐氏が満足に思う書体は皆無だったという。太佐氏は視線が流れるようにスラスラと読める、安定感のある文字をつくりたいと考えた。そうして試行錯誤をくりかえしたのち、次のような方針にたどりついた。
〈文字の外郭を結ぶと種々の字形ができる。例えば、国は四角、上は三角、今は菱形というように。これらが文字の大小や、字並びを悪くする原因で、この場合、国は大きく、今は小さく見え、上は下って見える。種々の字形から起る可読性障害を防ぐため〉(*2) 、太佐氏が掲げたポイントは次の通りだ。
〈①字形の面積が大きいものは、字面一杯でなく、内側に少し小さくデザインする。
②重心が下にある文字は、稍上げてデザインする。
③右寄りの傾向の文字は少し左へ寄せてデザインする。
④左寄の傾向の文字は少し右へ寄せてデザインする。
⑤文字の画数が極端に多いものは、画線の中可能な線を細めて全体に明るさを保つようにする。〉(*2)
これらのポイントに留意して完成したのが、当時の「モトヤ明朝体M1」。できるかぎり文字のフトコロ(線で囲まれた空間)を広くし、空間のバランスがよく、明るく見えるようデザインした。
古門社長は太佐氏のデザインについて、〈太佐はクリスチャンで、人柄もよく、音楽を好み、終戦直後NHKの音楽の審査員をやったくらいですから、ピアノは弾けますし、声楽も達者で、なかなかの音楽家なんですね。そういう人が当社の文字を書いたのです。書体にはその制作者の人格が出るものですね。非常に円滑な、あきないすぐれた字です〉と語っている。(*1)
太佐氏の没年は不明だが、1976年(昭和51)1月の『印刷とモトヤ』No.5に寄稿し「しごく健康でいまだ眼鏡なしで新聞が読めるし、あふれるほど元気」と述べており、80歳前後までは存命だったと確認できる。
77歳で『季刊タイポグラフィ』(*4)に掲載されたときには、「主食はさつまいもをふかしてスキムミルクをたくさんまぶしたもの。卵を1日に6~10個。野菜と果物はなんでもたくさん食べることにしている」と若さの秘訣を、「今後も若い世代と交流し、読みやすい、すぐれた書体をデザインしていきたい」と夢を語った。その言葉からは、80歳近いとは思えないみずみずしい情熱が伝わってくる。
「ぼくは師との出会いに恵まれた。自分のこれからの道を教えてもらった。『活字とは、空気か水のようなもの』という太佐さんの言葉は、いまも脳裏から離れません」
そう語る橋本和夫さんの最初の師・太佐源三氏は、読みやすい文字へのこだわりを生涯持ち続けたひとだった。
(つづく)
(注)
*1:「中垣信夫連載対談 第4回――モトヤ活字の設計思想 印刷と印刷の彼岸 ゲスト:古門正夫 特別ゲスト:太佐源三」『デザイン』No.5(美術出版社、1978年7月)
*2:太佐源三「文字とともに70年」『印刷とモトヤ』No.5(モトヤ、1976年1月)
*3:「書体」(モトヤ、1958年)
*4:『季刊タイポグラフィ』3月号(日本タイポグラフィ協会編・柏書房発行、1974年)
話し手 プロフィール
橋本和夫(はしもと・かずお)
書体設計士。イワタ顧問。1935年2月、大阪生まれ。1954年6月、活字製造販売会社・モトヤに入社。太佐源三氏のもと、ベントン彫刻機用の原字制作にたずさわる。1959年5月、写真植字機の大手メーカー・写研に入社。創業者・石井茂吉氏監修のもと、石井宋朝体の原字を制作。1963年に石井氏が亡くなった後は同社文字部のチーフとして、1990年代まで写研で制作発売されたほとんどすべての書体の監修にあたる。1995年8月、写研を退職。フリーランス期間を経て、1998年頃よりフォントメーカー・イワタにおいてデジタルフォントの書体監修・デザインにたずさわるようになり、同社顧問に。現在に至る。
著者 プロフィール
雪 朱里(ゆき・あかり)
ライター、編集者。1971年生まれ。写植からDTPへの移行期に印刷会社に在籍後、ビジネス系専門誌の編集長を経て、2000年よりフリーランス。文字、デザイン、印刷、手仕事などの分野で取材執筆活動をおこなう。著書に『描き文字のデザイン』『もじ部 書体デザイナーに聞くデザインの背景・フォント選びと使い方のコツ』(グラフィック社)、『文字をつくる 9人の書体デザイナー』(誠文堂新光社)、『活字地金彫刻師 清水金之助』(清水金之助の本をつくる会)、編集担当書籍に『ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン』(小塚昌彦著、グラフィック社)ほか多数。『デザインのひきだし』誌(グラフィック社)レギュラー編集者もつとめる。
■本連載は隔週掲載です。