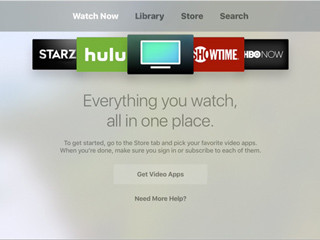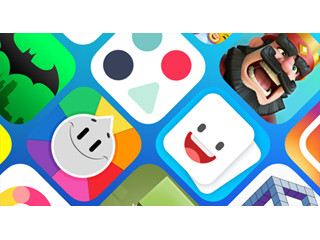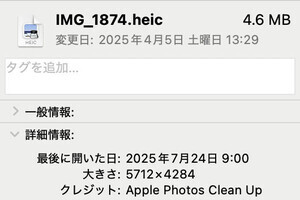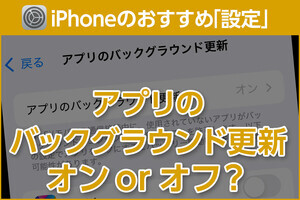筆者が2007年に、米国ニューヨークで初めて初代iPhoneを試したころの体験を振り返ると、最も印象的だったのは地図だった。当時は東京に住んでおり、ニューヨークは旅先だったわけだが、慣れない土地での地図を頼りにした移動において、iPhoneの地図アプリは画期的だった。それまで地図と言えば、大きな1枚の紙か、地図帳、もしくは旅行ガイドのような紙ベースの情報を入手するという形態だった。そのため、自分が地図の中でどこにいるか、どちらの方向を向いているか、目的地はどこにあるか、といったことは、ある程度の慣れが必要だった。
しかしiPhoneの地図では、GPSによって、自分が地図の中でどこにいるのかを的確に示してくれるし、今では電子コンパスでどちらを向いているのかも分かる。加えて、通るべき道順もきちんと地図上に線を引いて示してくれる。そのとき、「地図に弱い人」や「方向音痴」は、地図のユーザビリティで解決可能なことだ、と感じたものだった。
iOS 6から、独自の地図へと移行し、しばらくはその充実度の面でGoogleマップ に見劣りする面も多かったが、現在では、複雑な東京の乗り換えも含めて、Apple製の地図のみで迷わず移動することができるようになっている。
地図に関して、紙からスマホへ、という変化のメリットはいろいろある。
紙の地図を持ち歩かなくても、あるいは行く予定がない場所に行っても、きちんとその場所や周辺の様子を見つけ出すことができ、加えて地図に付随する情報を含めて利用することができるようになる。これから行く、あるいは行く予定のある場所をプリントしたり、その都度、購入したりする必要はない。
周辺にある街の情報は、レビューや写真を含めて、地図アプリから見つけることができるし、もし移動する場合には、UberやLyftといったライドシェアサービスで車の手配をすることもできるようになった。
スマホの地図によって、自分が今いる場所、これから行く場所を知るという利用の方法から、より積極的な活用の道が開けた。そこには、交通情報などのリアルタイムの情報も反映されており、行動の可能性をより正確に予測するツールになっている。
iPhone登場以降の10年で「地図」の世界で起きたことをまとめると、「場所を知るという問題解決から、場所での問題解決の手段へ進化した」と結論づけることができる。